【2025年最新版】土地家屋調査士試験におすすめの関数電卓は?選び方などを徹底解説!

土地家屋調査士試験では、専門的な知識とともに、複雑な計算を迅速かつ正確に進める能力が求められます。
その計算を支える重要なツールが関数電卓です。
適切な関数電卓を選ぶことは、試験の合否を左右する要素の一つとも言えるでしょう。
本コラムでは、土地家屋調査士試験におすすめの関数電卓や選び方を解説します。
土地家屋調査士・測量士補試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?


約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度土地家屋調査士試験記述式の模範解答・解説講義がもらえる!
『合格総合講義 民法テキスト』をまるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
土地家屋調査士試験の関数電卓とは?一般的な電卓との違いは?
関数電卓は、一般的な四則計算に特化した電卓とは異なり、多くの計算機能を備えた高度な専門ツールです。
外見上も、通常の電卓に比べてボタンの数が多く、その多くは「ファンクション機能」と呼ばれる特定の操作を実行します。
この機能により、一つのボタンで複数の入力をまとめて行うことができ、計算効率を大幅に向上させます。
関数電卓の大きな特徴は、三角関数(sin、cos、tan)を内蔵している点。
三角関数表を参照することなく直接数値を入力し、複雑な図形計算を可能にします。さらに、「°′″」ボタンと組み合わせることで、角度計算も容易に行えます。
また、方向キーが備わっていることも関数電卓の利点です。
入力中の計算式を修正したり、過去に入力した計算式を再利用したりすることが可能です。
土地家屋調査士試験では、限られた時間内に多くの計算をこなす必要があり、計算式の再利用は必須のテクニックとなります。
一般的な電卓と比べて、より多くのメモリ(記憶機能)を備えている点も重要です。
座標値や辺長、方向角など、頻繁に使う数値をメモリに記憶させることで、毎回手入力する手間が省け、計算時間を大幅に短縮し、入力ミスも減らすことができます。
土地家屋調査士試験では、これらの機能が不可欠であり、関数電卓の活用は試験合格への鍵を握ります。
土地家屋調査士試験における電卓の持ち込みルールと禁止事項
土地家屋調査士試験では、電卓の使用が特定の条件下で認められています。
試験に持ち込める電卓には明確なルールがあり、遵守しなければ受験の中止を命じられる可能性があります。
持ち込み可能な電卓の基準と型番リスト
試験で使用できる電卓は、法務省が定める基準を満たすものに限られます。
具体的には、以下のキーを通常備えている電卓が使用可能です。
- 置数キー: 1, 2, …, 9, 0, 00, 000
- クリアーキー: C, AC
- 計算命令キー: +, -, ×, ÷, =
- 独立メモリーキー: MC, MR, M+, M-
- 関数計算機能キー: sin⁻¹, cos⁻¹, tan⁻¹, sin, cos, tan
法務省の公式ウェブサイトでは、毎年、試験で使用できる電卓の型番リストが公表されています。
試験前に自身の電卓がこのリストに含まれているかを必ず確認しましょう。
使用することができない電卓は?
以下のいずれかの条件に該当する電卓は、試験での使用が禁止されています。
- プログラム機能があるもの: 「RUN」「ENTER」「PRO」「PROG」「EXE」「COMP」「P1~P4」「PF1~PF4」などのキーがある電卓は、プログラム機能を有しているため使用できません。
- プリント機能があるもの。
- アルファベットやカナ文字が入力できるもの。
- 電池式(太陽電池・乾電池等)以外のもの。
上記以外にも、電子辞書や電子手帳、特定のポケットコンピューターなど、他の機能を持つ電卓も使用が禁止されています。
禁止事項に違反した場合、試験の中止を命じられる可能性がありますので、細心の注意が必要です。
電卓は2台持ちがおすすめ
土地家屋調査士試験では、予備機を含めて電卓を2台まで携行することが認められています。
「2台持ち」は、単なる予備ではなく、試験対策上の大きなメリットがあります。
2台持ちをおすすめする理由は以下の通りです。
- 試験中における故障への備え
万が一、試験中に電卓が故障した場合でも、もう一台があれば計算を中断することなく試験を続行できます。 - 計算の効率化とミス防止
土地家屋調査士試験の計算は、通常の計算設定と交点計算などの特殊な計算設定で異なる場合があります。設定を頻繁に切り替えることはミスにつながりやすく、また、設定変更時に記録したメモリが消える可能性もあります。
2台の電卓を「通常の計算用」と「交点計算用」に使い分けることで、設定変更の手間を省き、計算ミスを減らし、時間を短縮することができます。 - 用途に応じた使い分け
複素数計算用と交点計算用で2台を使い分ける方法や、土地の問題用と建物の問題用で電卓の種類を変える方法など、受験者自身の使いやすいように工夫することで、操作時間の短縮と得点アップにつなげられます。
電卓を2台持ち込むことは、効率と正確性を追求し、合格の可能性を大きく高めるための戦略的な選択と言えるでしょう。
土地家屋調査士試験におすすめの関数電卓
土地家屋調査士試験には、特定の機能を持つ関数電卓が適しています。
ここでは、特におすすめの2つの機種について、それぞれの特徴とメリットを紹介します。
- キヤノン「F-789SG」の特徴とメリット
- カシオ「fx-JP500」の特徴とメリット
キヤノン「F-789SG」の特徴とメリット
キヤノン「F-789SG」は、土地家屋調査士試験の受験生に高く評価され、一押しの機種として推奨されることが多い関数電卓です。
メリット:
- 豊富なメモリ数
最大の特長は、19個ものメモリを搭載している点です。一般的な関数電卓のメモリと比べて倍以上であり、多数の計算結果や座標値を記憶させる際に、メモリ不足を気にすることなく利用できます。特に、座標値が多い問題では、上書きを気にせず個別に管理できる点が大きなメリットです。 - コストパフォーマンス
機能性と操作性に優れながらも、比較的安価で入手可能です。 - 多様な計算機能
複素数計算や交点計算など、試験で求められる高度な計算機能が充実しており、時間短縮に貢献します。 - 頻繁に使うキーへのアクセス
「Abs」と「∠」キーは1ストロークで入力できます。 - 予備校での推奨
アガルートアカデミーの「[中山式]複素数計算」講座など、多くの試験対策講座でこの機種をベースに操作方法が解説されています。講座と連動して学習を進めたい場合には、非常に効率的です。
ただし、画面表示が日本語に対応していないため、関数電卓の操作に慣れていない初心者には、使い方を覚えるまでに時間がかかる可能性があります。
カシオ「fx-JP500」の特徴とメリット
カシオ「fx-JP500」も、土地家屋調査士試験で多くの受験生が利用する人気の機種です。
メリット:
- 日本語表示対応
関数電卓としては珍しく日本語表示に対応しており、メニューがアイコンで表示されるため、直感的な操作が可能です。
関数電卓に不慣れな初心者でも、使いやすさを感じやすいでしょう。 - 視認性の高い表示
桁数の多い数値も折り返してすべての桁を表示してくれるため、スクロール不要で値を一目で確認できます。そのため、入力ミスに気づきやすく、正確性の向上につながります。 - 頻繁に使うキーへのアクセス
「STO」キーは1ストロークで入力できます。
しかし、「fx-JP500」は現在生産終了しており、入手困難です。
後継機種として「fx-JP500CW」が試験に対応しています。
以上の特性を踏まえると、メモリ数を重視するならばキヤノン「F-789SG」、日本語表示や直感的な操作性を重視するならばカシオ「fx-JP500」(または後継機種)を選ぶのが良いでしょう。
土地家屋調査士試験用関数電卓の選び方5つのポイント
土地家屋調査士試験で使用する関数電卓を選ぶ際には、以下の5つのポイントに着目することが重要です。
- 試験に持ち込みできる指定電卓を選ぶ
- 複素数モード搭載の電卓を選ぶ
- メモリ数が多い電卓を選ぶ
- 使いたい機能にすぐたどり着けるものを選ぶ
- 画面表示が見やすい電卓を選ぶ
試験に持ち込みできる指定電卓を選ぶ
何よりもまず、試験の規定で持ち込みが認められている機種であるかを確認することが最重要です。
法務省は毎年、使用可能な電卓の型番リストを公表しており、プログラム機能や文字入力機能など、不正使用につながる可能性のある機能を持つ電卓は厳しく制限されています。
不適切な機種を使用した場合、受験自体が認められなくなるため、購入前に必ず最新の公式リストを確認し、指定されたモデルの中から選択しましょう。
複素数モード搭載の電卓を選ぶ
土地家屋調査士試験の記述式問題、特に土地に関する問題では、多くの座標計算が求められます。
複素数計算モードを搭載した電卓は、複雑な計算を迅速かつ正確に行うために極めて有効です。
複素数モードを使用することで、X座標とY座標の2つの数値を1つのメモリで効率的に管理でき、計算における打鍵数を減らし、入力ミスを抑制する効果も期待できます。
土地家屋調査士試験において、複素数モードでの計算は絶対的に有利なテクニックとされています。
メモリ数が多い電卓を選ぶ
メモリ数が多い関数電卓は、数値を効率的に管理し、再入力を省くことで計算時間を短縮し、入力ミスを防ぐのに役立ちます。
土地家屋調査士試験では、座標値や方向角、計算の中間結果など、繰り返し使用する数値を多数記憶させる必要があります。
メモリが不足すると、必要な値を上書きしたり、改めて入力したりする手間が発生し、それが時間ロスやミスの原因となる可能性も。
最低でも10個以上のメモリがあると安心して計算に取り組めるでしょう。
使いたい機能にすぐたどり着けるものを選ぶ
よく使う機能に少ないストロークでアクセスできる電卓は、試験中の操作時間を短縮し、操作ミスを減らす上で非常に有利です。
関数電卓の機種によって、特定の機能を呼び出すために必要なキー操作の数(ストローク数)は異なります。
例えば、メモリへの格納(STO)や絶対値(Abs)、角度(∠)の入力など、頻繁に使う操作のストローク数は、全体の計算スピードに影響を与えます。
そのため、機種選びの際には、操作のしやすさも考慮に入れると良いでしょう。
画面表示が見やすい電卓を選ぶ
電卓の画面表示が見やすいことは、計算の正確性を保ち、目の疲労を軽減するためにも重要です。
試験本番は時間が限られ、緊張状態の中で計算を進めることになります。
表示のコントラストがはっきりしていることや、長大な数値や計算式がスクロールせずに1画面で表示されることは、確認作業をスムーズにし、計算ミスを防ぐ上で大きなメリットとなります。
日本語表示に対応した機種は、初心者にとって特に理解しやすく、操作への抵抗感を減らすことにもつながるでしょう。
土地家屋調査士試験における関数電卓の使い方
土地家屋調査士試験における関数電卓の操作方法は、メーカーや機種によって異なります。
同じ機能を使用する場合でも、電卓ごとにボタンの数や押す順序が異なるため、一概に説明することはできません。
例えば、メモリへの格納(STO)や絶対値(Abs)、角度(∠)の入力といった頻繁に使う操作に必要なキー操作の数(ストローク数)は機種ごとに違う場合があります。
そのため、関数電卓の使い方を効率的に習得するには、対策講座やテキストを活用することがおすすめです。
講座やテキストには、使用する電卓の機種をベースにした操作方法の解説が含まれているため、自身が使用する電卓に合わせて学習することで、より効率的な習得が可能です。
独学で関数電卓の使い方をマスターするには、かなりの労力が必要となるでしょう。
複雑な土地に関する問題で求められる座標計算などを、圧倒的な速さと正確さで解くためには、複素数計算モードの習得が不可欠です。
複素数計算は、計算上の打鍵数を減らし、入力ミスを抑制する効果も期待できます。
アガルートアカデミーの「[中山式]複素数計算」講座は、複素数計算を学ぶ上で非常に有効です。
[中山式]複素数計算では、関数電卓の準備から複素数モードのセットアップ、座標値の入出力、座標計算、基準点測量、面積計算といった、本試験で出題されるすべての計算を網羅。
講義はキヤノン「F-789SG」を使用して解説されています。
また、現在生産が終了しているカシオ「fx-JP500」と、その後継機種であるカシオ「fx-JP500CW」についても、詳細な操作方法がテキストに記載されているため、受講者は自身の持つ機種に合わせて学習を進められます。
講座では、キーを打つ回数を減らし、数値をメモする手間をなくすことで、計算ミスを少なくし、正確な答えを導き出すコツを習得できるでしょう。
短時間で関数電卓の具体的な使い方を習熟できるため、試験対策として非常に効率的です。
まとめ
土地家屋調査士試験において、関数電卓は単なる計算道具ではなく、合否を左右する重要な戦略的ツールです。
本コラムで解説した内容をまとめると以下の通りです。
- 土地家屋調査士試験では、高度な計算を効率的かつ正確に行うために関数電卓が必須
- 試験の持ち込み規定を満たした機種を選ぶことが最重要
- 複素数モード・十分なメモリ数・視認性の高い表示などの機能性を重視
- キヤノン「F-789SG」はメモリ数の多さで高評価
- カシオ「fx-JP500(後継機含む)」は日本語表示と操作性に優れる
- 2台持ちや計算内容に応じた使い分けで効率と正確性が向上
- 操作方法は講座やテキストで学ぶことで短期間で習得可能
関数電卓は、ご自身の学習スタイルや重視するポイントに合わせて選択すると良いでしょう。
購入後は、試験までに電卓の操作に習熟し、特に複素数計算の練習を徹底することが合格への鍵となります。
電卓の具体的な使い方を解説する講座やテキストを活用することも、効率的な学習に役立ちます。
適切な関数電卓を選び、その機能を最大限に活かすことで、土地家屋調査士試験の複雑な計算問題を迅速かつ正確に解き進め、合格へと近づくことができるでしょう。
土地家屋調査士・測量士補試験の合格を
目指している方へ
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?


約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度土地家屋調査士試験記述式の模範解答・解説講義がもらえる!
『合格総合講義 民法テキスト』をまるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る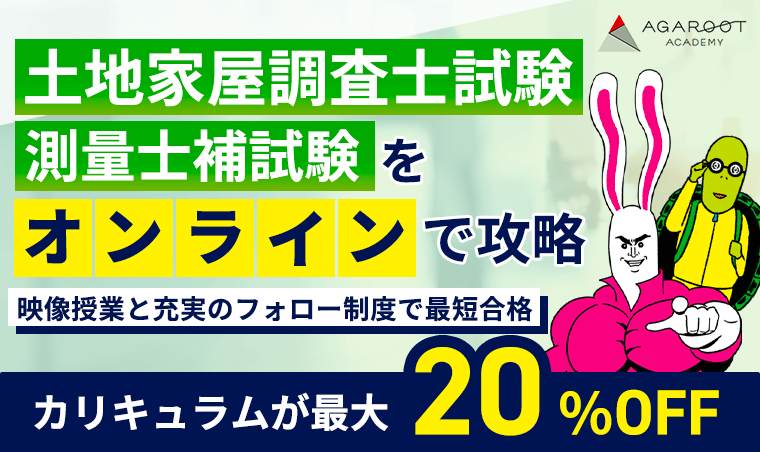
4年連続1位合格者輩出!
令和6年土地家屋調査士講座の
アガルート受講生の合格率63.64%!全国平均の約6倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
▶土地家屋調査士・測量士補試験講座を見る
