土地家屋調査士試験の難易度は?合格率や偏差値なども調査!

土地家屋調査士は、不動産登記の「表示に関する登記」を独占業務とする国家資格。
土地家屋調査士に興味をお持ちの方は、土地家屋調査士試験の難易度について詳しく知りたいと考えているのではないでしょうか。
本コラムでは、土地家屋調査士試験の難易度や難しいと言われる理由について解説します。
ほかの資格との難易度ランキングや、試験の難易度を大学の偏差値に例えた一覧表なども掲載しているため、ぜひ参考にしてください。
土地家屋調査士・測量士補試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?


約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度土地家屋調査士試験記述式の模範解答・解説講義がもらえる!
『合格総合講義 民法テキスト』をまるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
土地家屋調査士の難易度は?
土地家屋調査士は、例年の合格率が約9〜10%の難易度が高い国家資格です。
土地家屋調査士になるためには、土地家屋調査士試験に合格しなければなりません。
毎年約4,000人が土地家屋調査士試験を受験しますが、合格できるのは上位約400人のみ。
また、土地家屋調査士試験に合格するために必要な勉強時間は約1,000時間とされており、簡単に取得できる資格ではないといえるでしょう。
土地家屋調査士試験は、筆記試験と口述試験によって構成されています。
筆記試験は「午前の部」と「午後の部」に分かれており、筆記試験の合格者だけが口述試験を受験できます。
以下のいずれかの資格を有している方は、筆記試験の「午前の部」の免除を受けることが可能です。
- 測量士
- 測量士補
- 一級建築士
- 二級建築士
※参考:土地家屋調査士試験について
筆記試験の「午前の部」では、難解な内容が出題されます。
また、「午前の部」の免除を受けない場合、午前から午後まで一日かけて筆記試験を受けなければなりません。
長時間の試験によって体力や集中力を消耗しやすいため、「午前の部」の免除を受けた受験者よりも不利になる可能性が高いでしょう。
このような事情により、多くの受験者はまず難易度が低い測量士補試験に合格して「午前の部」の免除を受けます。
「午前の部」の免除を前提として考えた場合、「午後の部」の試験対策が合格を左右するといえるでしょう。
また、土地家屋調査士試験が難しいと言われる理由として以下の3つがあげられます。
- 土地家屋調査士試験が難しい理由①計算や作図が必要
- 土地家屋調査士試験が難しい理由②試験時間が短い
- 土地家屋調査士試験が難しい理由③「基準点」と「合格点」がある
土地家屋調査士試験が難しい理由①計算や作図が必要
土地家屋調査士試験が難しいと言われる最大の理由は、作図や計算が必要な問題が出題されることです。
土地家屋調査士試験では、三角関数や複素数の知識が必要な計算問題が出題されます。
高度な計算問題は出題されないものの、数学が苦手な方は注意が必要です。
また、作図が必要な問題では、定規を使った図面の作成が求められます。
このように法令知識だけでは解けない問題が出題されるため、試験対策が難しいと感じるでしょう。
土地家屋調査士試験が難しい理由②試験時間が短い
土地家屋調査士試験が難しいと言われる2つ目の理由は、試験時間が短いことです。
筆記試験の「午後の部」では、2時間半で20問の択一式問題と2問の記述式問題を解かなければなりません。
出題される問題のボリュームに対して試験時間が短いため、図面を最後まで描けずに試験が終了してしまう人も多く見受けられます。
また、図面がズレていたり、未記入の箇所があったりすると減点されるため、素早く正確な図面を描く力が必要です。
限られた時間の中で得点を最大化できるよう、ペース配分を工夫する必要があるでしょう。
土地家屋調査士試験が難しい理由③「基準点」と「合格点」がある
「基準点」と「合格点」が設けられていることも、土地家屋調査士試験が難しいと言われる理由のひとつです。
土地家屋調査士試験では択一式・記述式の両方に基準点が設けられており、いずれか片方の得点が基準点を下回ると足切りされてしまいます。
また、択一式・記述式の点数を合計した得点が合格点に満たない場合も、試験に合格することはできません。
合格点は例年平均よりも高めの点数が設定されるため、一定以上の実力がないと合格は難しいでしょう。
土地家屋調査士の合格率
土地家屋調査士試験の合格率は、例年約9%です。
令和6年度における土地家屋調査士試験の受験者は4,589人・合格者は505人であり、合格率は11%でした。
過去10年の土地家屋調査士試験の受験者数・合格者数・合格率は、以下の通り。
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 平成27年 | 4,568人 | 403人 | 8.82% |
| 平成28年 | 4,506人 | 402人 | 8.92% |
| 平成29年 | 4,600人 | 400人 | 8.70% |
| 平成30年 | 4,380人 | 418人 | 9.54% |
| 令和元年 | 4,198人 | 406人 | 9.67% |
| 令和2年 | 3,785人 | 392人 | 10.36% |
| 令和3年 | 3,859人 | 404人 | 10.47% |
| 令和4年 | 4,404人 | 424人 | 9.63% |
| 令和5年 | 4,429人 | 428人 | 9.66% |
| 令和6年 | 4,589人 | 505人 | 11% |
※出典:法務省:土地家屋調査士試験
過去10年の土地家屋調査士試験の合格率は8.82%〜11%で推移しており、平均合格率は9.68%です。
実施年によって合格率が変動する理由は、受験者数の差にあると考えられます。
上記の表からは、例年の合格者数が約400人で安定しているのに対し、受験者数は約3,800人〜4,600人まで差があることがわかります。
受験者数が4,000人を下回った令和2年と令和3年の合格率は、いずれも10%以上でした。
対して、受験者数が多く、4,500人を上回った平成26年から平成29年までの合格率は、8%台と低めの水準です。
土地家屋調査士試験の合格者数は概ね決まっているため、受験者数が少ないと合格率が上がる傾向がありました。
令和6年は受験者、合格者ともに上昇しています。受験者数は微増に対し、合格者数はここ10年で一番多い500人を超える結果となりました。
受験者のレベルが上がっていることがうかがえるでしょう。
土地家屋調査士の偏差値はどのくらい?
土地家屋調査士試験の難易度を偏差値で例えると、60〜64に該当すると考えられます。
大学のレベルでは、明治大学・青山学院大学などのMARCHと同程度です。
土地家屋調査士試験は、偏差値の観点からも難関であるといえるでしょう。
資格試験の難易度を大学の偏差値で例えた表は、以下の通り。
| 大学 | 偏差値 | 試験 |
|---|---|---|
| 東京大学・京都大学 | 68~ | 司法試験・予備試験 |
| 慶應大学・早稲田大学・上智大学 | 65~67 | 不動産鑑定士・司法書士・弁理士 |
| 明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学 | 60~64 | 土地家屋調査士・中小企業診断士・社労士・行政書士・技術士二次試験・通関士・マンション管理士・ケアマネジャー |
| 日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学 | 55~56 | 技術士一次試験・宅建・測量士・管理業務主任者・社会福祉士・インテリアコーディネーター |
なお、資格試験の難易度を正確な偏差値として算出することはできません。
上記の表はあくまで目安としてお考えください。
土地家屋調査士の難易度ランキング!他の資格と比較すると? 表込
土地家屋調査士とほかの資格の合格率を比較した難易度ランキングは、以下の通り。
| 順位 | 試験種 | 合格率 |
|---|---|---|
| 1位 | 司法書士 | 4~5% |
| 2位 | 不動産鑑定士 | 5~6% ※短答式試験合格率×論文式試験合格率 |
| 3位 | 一級建築士 | 8~9% |
| 4位 | マンション管理士 | 8~9% |
| 5位 | 土地家屋調査士 | 9~10% |
| 6位 | 行政書士 | 11~15% |
| 7位 | 宅建士 | 15~17% |
| 8位 | 管理業務主任者 | 20~23% |
合格率で比較した場合、土地家屋調査士は行政書士よりも難易度が高く、マンション管理士よりもやや難易度が低いといえるでしょう。
難関資格として知られる司法書士や不動産鑑定士よりは難易度が低いものの、宅建士や行政書士よりは難易度が高めです。
このように、合格率の観点からも土地家屋調査士は取得難易度が高い資格であることがわかります。
以下に、土地家屋調査士と比較されやすい3つの資格を取り上げ、それぞれの難易度について解説します。
- 土地家屋調査士と宅建を比較
- 土地家屋調査士と行政書士を比較
- 土地家屋調査士と測量士を比較
土地家屋調査士と宅建を比較
| 合格率 | 勉強時間 | |
| 土地家屋調査士 | 9~10% | 約1,000時間 |
| 宅建 | 15~17% | 約300~400時間 |
土地家屋調査士と宅建を比較した場合、土地家屋調査士の方が難易度が高いといえます。
土地家屋調査士試験の合格率は9〜10%ですが、宅建試験の合格率は15〜17%。
いずれも合格率20%を下回る難関試験ですが、土地家屋調査士の方が合格率が低いことがわかります。
また、合格に必要な勉強時間は、土地家屋調査士試験が約1,000時間・宅建試験は約300〜400時間であるとされています。
宅建の約3倍の勉強時間が必要であると考えれば、土地家屋調査士の難易度の高さが伺えるでしょう。
土地家屋調査士と行政書士を比較
| 合格率 | 勉強時間 | |
| 土地家屋調査士 | 9~10% | 約1,000時間 |
| 行政書士 | 11~15% | 約500~1,000時間 |
土地家屋調査士と行政書士を比較した場合、一般的には土地家屋調査士の方が難易度が高いと言われています。
行政書士試験の合格率は11〜15%であり、土地家屋調査士試験よりもやや高めです。
一方で、合格に必要な勉強時間を比較すると、行政書士試験は受験者の学習レベルによって約500〜1,000時間まで幅があることがわかります。
法律の知識がある方は行政書士試験の勉強時間を短縮できる可能性があるため、土地家屋調査士試験の方がやや難易度が高いといえるでしょう。
土地家屋調査士と測量士を比較
| 合格率 | 勉強時間 | |
| 土地家屋調査士 | 9~10% | 約1,000時間 |
| 測量士 | 約10% | 約300~400時間 |
土地家屋調査士と測量士を比較した場合、土地家屋調査士の方が難易度が高いと考えられるでしょう。
土地家屋調査士の合格率は9〜10%・測量士試験の合格率は約10%であり、一見して大きな差はないように見えます。
しかし、測量士試験は実施回によって問題の難易度が異なるため、毎回合格率が変動します。
最近の測量士試験の合格率は約7〜17%で推移しており、令和6年の合格率は13%でした。
つまり、約10%の合格率はあくまで平均値であり、年によっては合格率が高くなる場合があります。
また、測量士試験に合格するために必要な勉強時間は約300〜400時間であるのに対し、土地家屋調査士試験の場合は約1,000時間の勉強が必要です。
勉強時間の観点からも、測量士よりも土地家屋調査士の方が難易度が高いことがわかります。
まとめ
本コラムでは、土地家屋調査士試験の難易度や、難しいと言われる理由について解説しました。
本コラムのまとめは、以下の通り。
- 土地家屋調査士は取得難易度が高い国家資格である
- 土地家屋調査士試験の合格率は約9〜10%、必要な勉強時間は約1,000時間
- 土地家屋調査士試験の難易度を偏差値で例えると60〜64であり、MARCHレベルに該当する
- 土地家屋調査士試験は試験時間が短く、作図や計算などの問題が出題される
- 土地家屋調査士試験には「基準点」「合格点」の両方が設けられており、基準点による足切りがある
- 土地家屋調査士は、宅建・行政書士・測量士よりも資格試験の難易度が高い
土地家屋調査士試験は合格率が低く、難易度が高い試験です。
効率よく土地家屋調査士試験に合格したい方には、アガルートアカデミーの土地家屋調査士試験・測量士補試験講座がおすすめ。
アガルートの土地家屋調査士講座は合格実績が高く、毎年多くの受講生が合格を勝ち取っています。
興味をお持ちの方は、講座の無料体験を利用して教材との相性を確かめてみてはいかがでしょうか。
土地家屋調査士・測量士補試験の合格を
目指している方へ
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?


約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度土地家屋調査士試験記述式の模範解答・解説講義がもらえる!
『合格総合講義 民法テキスト』をまるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る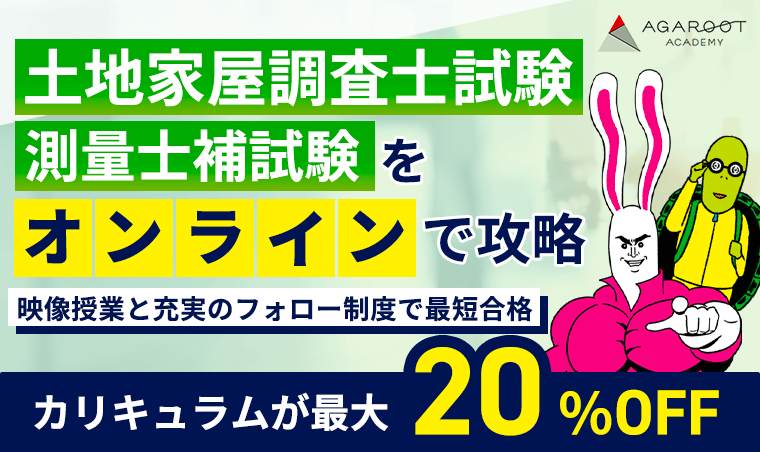
4年連続1位合格者輩出!
令和6年土地家屋調査士講座の
アガルート受講生の合格率63.64%!全国平均の約6倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
▶土地家屋調査士・測量士補試験講座を見る
