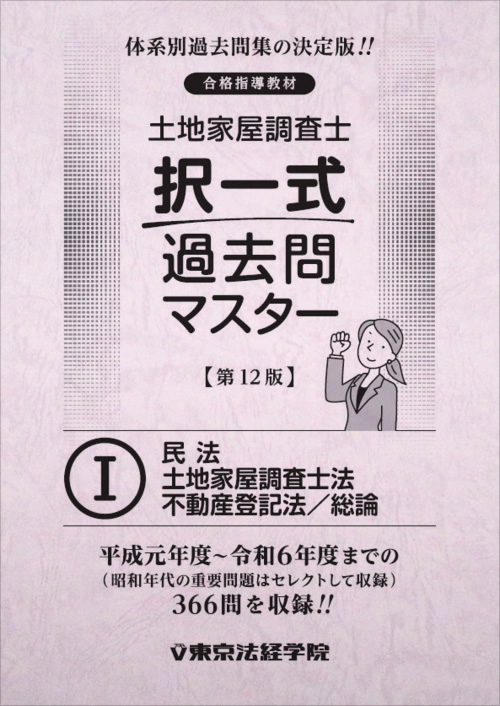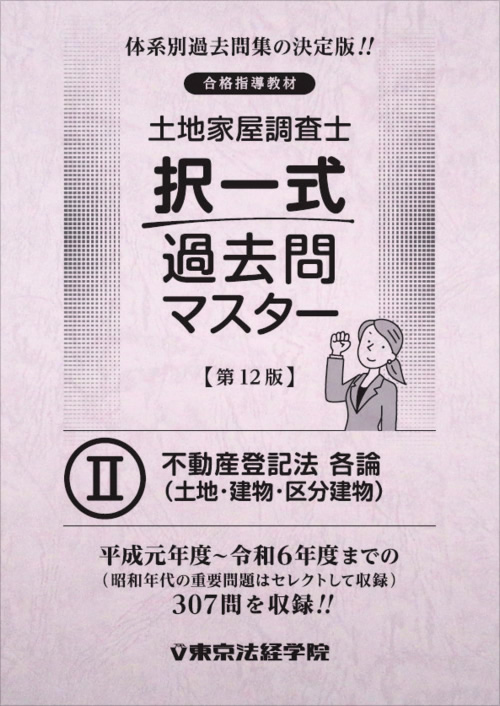土地家屋調査士試験の択一式の勉強法!基準点や対策方法は?
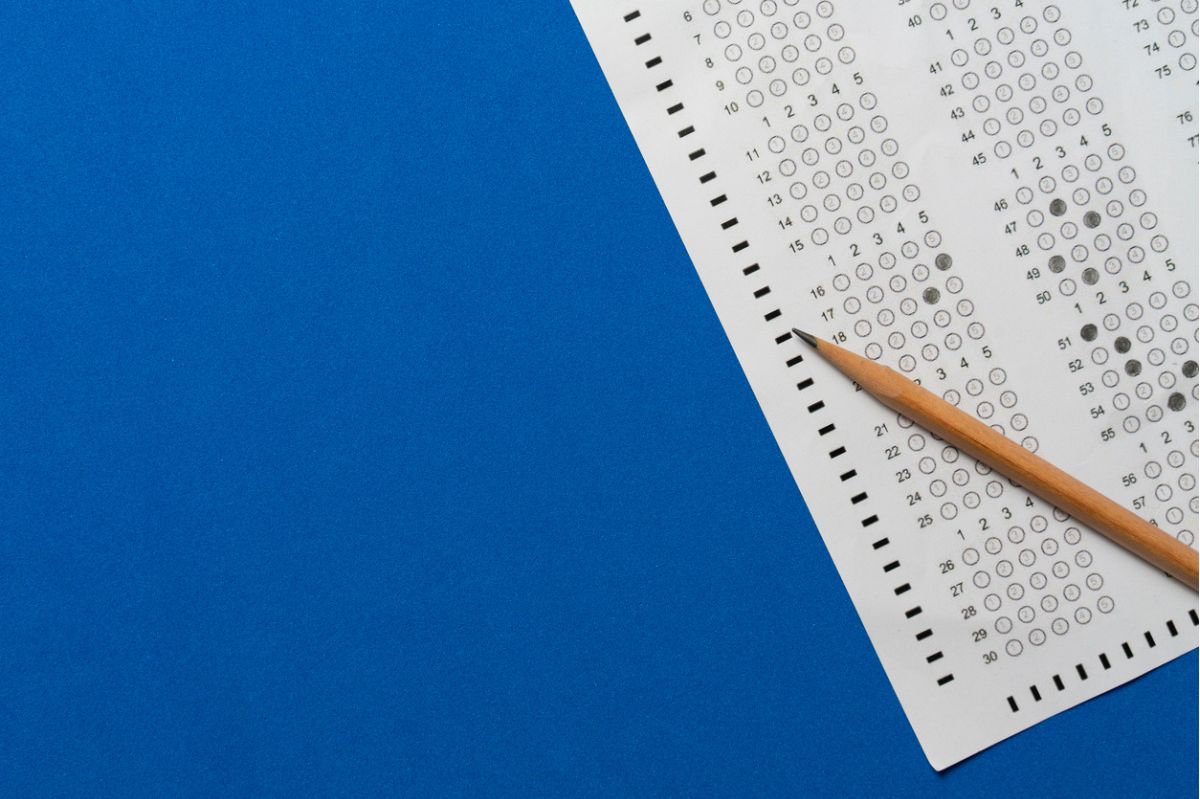
土地家屋調査士試験は、択一式と記述式の2つの形式で構成されている資格取得試験です。
択一式とは、あらかじめ用意された選択肢の中から正しい回答を選ぶ形式です。
土地家屋調査士の試験を受ける人は、択一式の合格点や基準点が気になるところでしょう。
当コラムでは、土地家屋調査士試験の択一式の勉強法について解説します。
択一式の基準点や合格点、おすすめの過去問・テキストも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
土地家屋調査士・測量士補試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?


約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度土地家屋調査士試験記述式の模範解答・解説講義がもらえる!
『合格総合講義 民法テキスト』をまるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
土地家屋調査士試験の択一式とは?
土地家屋調査士試験の午後の部における筆記試験には、「択一式」と「記述式」があります。
午前の部については、測量士や測量士補、一級・二級建築士の資格保有者は免除される測量や作図の試験です。
今回は、択一式の解説になるため、午後の部のみを対象に解説します。
| 択一式 | 記述式 |
|---|---|
| あらかじめ用意された選択肢の中から正しい回答を選ぶ形式 | 土地や建物それぞれについて回答を記述する形式 |
択一式の特徴は、あらかじめ用意された回答の中から回答を選べる点です。
択一式は、記述式と違ってあらかじめ用意された回答の中に正解があります。そのため、自分で回答文を書かなくても、正解を選べる点がメリットです。
また、択一式は選択肢が少なければ正解率が高くなります。
ただし、土地家屋調査士試験の択一式では、1問につき選ぶ対象の回答が5つ用意されています。
そのため、1問につき正解率が20%の確率となるでしょう。
土地家屋調査士試験午後の部の内容は、次の通りです。
| 出題範囲 | 民法に対する知識 登記の申請手続きの知識 登記審査請求の手続きの知識 不動産登記法の筆界に関する知識 土地家屋調査士法第3条第1項第1号~6号までの規定業務知識 |
| 試験時間 | 150分(2時間半) |
| 問題数 | 択一式:20問 記述式:2問(土地:1問・建物:1問) |
| 配点 | 択一式:1問2.5点 記述式:1問25点 |
※参考:法務省:土地家屋調査士試験
土地家屋調査士試験の択一式の勉強法
土地家屋調査士試験の択一式に対して、おすすめの勉強方法は次の通りです。
- 学習計画を立てる
- 出題傾向の分析
- 過去問を繰り返し解く
- 苦手分野の攻略
- 模試の活用
学習計画を立てる
土地家屋調査士試験の択一式の勉強法は、学習計画を立てることから始めましょう。
学習計画を立てることは、どの試験分野においても共通して重要なポイントです。
無計画で試験勉強を始めた場合は、想定外の科目に時間をかけてしまい、結果として勉強時間が足りなくなるかもしれません。
学習計画は、「テキストのどの部分を、いつまでに、どういった進め方で取り組むのか」と、学習スケジュールと取り組む内容を明確にすることが重要です。
例えば、1年単位で学習に取り組むのであれば、1年を3つに分けて計画を立てます。
- 学習開始~4カ月目:テキスト全体の把握・過去問の反復
- 5か月目~8か月目:テキスト問題の理解・時間を意識した回答
- 9か月目~本試験当日:全問正解を目指して反復回答・過去問の正解理由の理解
択一式の学習計画で重要な部分は、表面だけで正解を暗記しないことです。
正解の理由まで理解できるまで繰り返す必要があります。
出題傾向の分析
土地家屋調査士試験の択一式の勉強法では、過去問から出題傾向を分析することも重要です。
択一式は、全20問のうち、多い科目や少ない科目の割合を知っておくのもポイントになるでしょう。
例えば、過去問から出題頻度の多い科目を把握できれば、優先すべき科目も明確になります。
- 民法から3問
- 不動産登記法から16問~17問
- 土地家屋調査士法から0~1問
土地家屋調査士の仕事は、不動産登記関係が主体になるため、択一式では不動産登記法からの出題が全体の3分の2以上を占めている傾向です。
土地家屋調査士の実務や過去問の出題傾向から優先する範囲を判断しましょう。
過去問を繰り返し解く
土地家屋調査士試験の択一式の勉強は、全体の9割(45点)以上の正解を目指しましょう。
択一式20問中18問の正解を目指すことで、後述する基準点をクリアできます。
択一式は、正解を選ぶ回答形式です。
着実に合格点を上げるために欠かせない部分とも考えられます。
過去問を徹底して繰り返し解くことは、結果的に合格への近道になるかもしれません。
また、過去問を解くうえで重要なポイントは年度ごとに解くという点です。
例えば、民法だけを解いたり、不動産登記法だけに集中したりするのではなく、本試験を想定して年度単位をセットに過去問を解くことをおすすめします。
年度単位で解く学習方法は、出題範囲の全体を学習する意味でも有効な方法です。
苦手分野の攻略
土地家屋調査士試験の出題範囲には、得意不得意の分野もあるでしょう。
苦手な分野に関しては、そのまま放置するのではなく、「不正解だった問題」として記録することが大事です。
解けなかった問題を本試験当日まで放置したままでは、その分野の出題によって基準点に到達できないかもしれません。
苦手分野の攻略では、その都度メモに記録し、不正解だった問題だけに集中した自主テストも対策のひとつになります。
模試の活用
土地家屋調査士試験の択一式では、模擬試験の活用がおすすめです。
模擬試験は、本番の試験を想定した試験の経験値を上げる機会となります。
日頃の学習では、正解出来ていても本試験で実力を発揮できない人は少なくありません。
そのため、本試験を想定した模擬試験は、試験に場慣れする意味でも活用することをおすすめします。
土地家屋調査士試験の択一式の基準点と合格点
土地家屋調査士試験の択一式や記述式は、先述した配点に対して、基準点が存在します。
その基準点によって合格点が決まる仕組みです。
土地家屋調査士試験は、相対評価(他者との比較で評価する方法)の仕組みになるため、合格点が決まっておらず毎年変動します。
土地家屋調査士試験の合格を目指すには、択一式基準点・記述式基準点・合格点それぞれの点数を超える必要があります。
ここでは、土地家屋調査士試験の択一式及び記述式の基準点と合格点の推移を紹介します。
| 年度 | 対象の試験 | 択一式の基準点 | 記述式の基準点 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 午前の部 | 30.0点 | 34.0点 | 70.0点以上 |
| 午後の部 | 32.5点 | 33.0点 | 76.5点以上 | |
| 令和2年 | 午前の部 | 30.0点 | 32.5点 | 70.5点以上 |
| 午後の部 | 32.5点 | 30.0点 | 71.0点以上 | |
| 令和3年 | 午前の部 | 30.0点 | 30.5点 | 64.0点以上 |
| 午後の部 | 32.0点 | 30.5点 | 73.5点以上 | |
| 令和4年 | 午前の部 | 30.0点 | 32.0点 | 68.0点以上 |
| 午後の部 | 37.5点 | 34.0点 | 79.5点以上 | |
| 令和5年 | 午前の部 | 30.0点 | 28.0点 | 70.0点以上 |
| 午後の部 | 35.0点 | 29.0点 | 72.0点以上 | |
| 令和6年 | 午前の部 | 30.0点 | 28.0点 | 70.0点以上 |
| 午後の部 | 37.5点 | 31.5点 | 78.0点以上 |
※午前の部:択一式60点満点中、記述式40点満点中
※午後の部:択一式50点満点中、記述式50点満点中
※引用:法務省「土地家屋調査士試験」
択一式の基準点は、午前の部においては大きく変動していません。
午後の部に関しては、令和元年〜令和3年の基準点よりも、令和4年~令和6年の基準点が若干高くなっている傾向です。
土地家屋調査士試験の択一式対策におすすめのテキスト・過去問題集
土地家屋調査士試験の択一式の試験対策には、以下のテキスト・過去問題集がおすすめです。
- 土地家屋調査士受験100講
- 土地家屋調査士 択一攻略要点整理ノート
- 土地家屋調査士 択一式過去問 令和7年度版
- 土地家屋調査士 択一式過去問マスター
土地家屋調査士受験100講
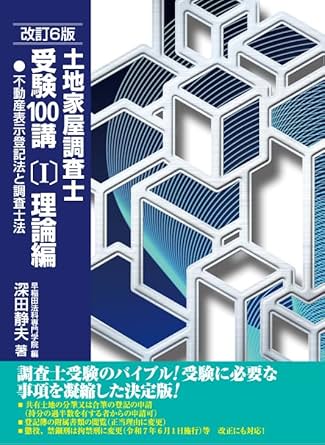
引用:Amazon
『土地家屋調査士受験100講』は、試験午後の部の択一式で出題される不動産登記法や調査士法の理論について解説しているテキストです。
午後の部だけではなく、午前の部の図面作成における規則なども取り扱っています。
『土地家屋調査士受験100講』は、6度の改訂のもと根強く活用されています。
早稲田大学大学院法学研究科を卒業した深田静夫氏による全487ページに及ぶ理論をまとめたテキストです。
択一式の出題範囲となる不動産登記法と土地家屋調査士法に特化した学習におすすめします。
土地家屋調査士 択一攻略要点整理ノート
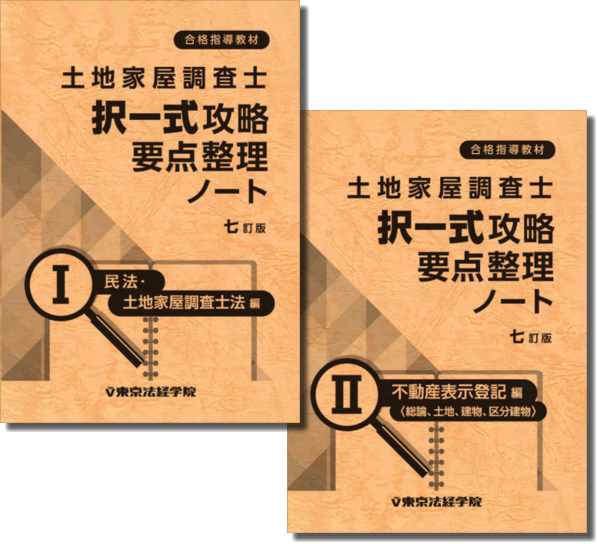
引用:東京法経学院
『土地家屋調査士 択一攻略要点整理ノート』は、択一式の問題を2冊のノートに分類して段階的に学ぶテキスト・問題集。
1冊目の1講では、択一式で出題される科目の基本力を理解し、練習問題で定着させる流れで進めます。
土地家屋調査士など法律専門の資格取得を支援する東京法経学院が2冊セットで発行しています。
『土地家屋調査士 択一攻略要点整理ノート』は、択一式で出題される部分の要点を理解したうえで過去問の練習問題に取り組む人におすすめです。
1講が全672ページ、2講が836ページの2冊構成のテキストになります。
土地家屋調査士 択一式過去問 令和7年度版
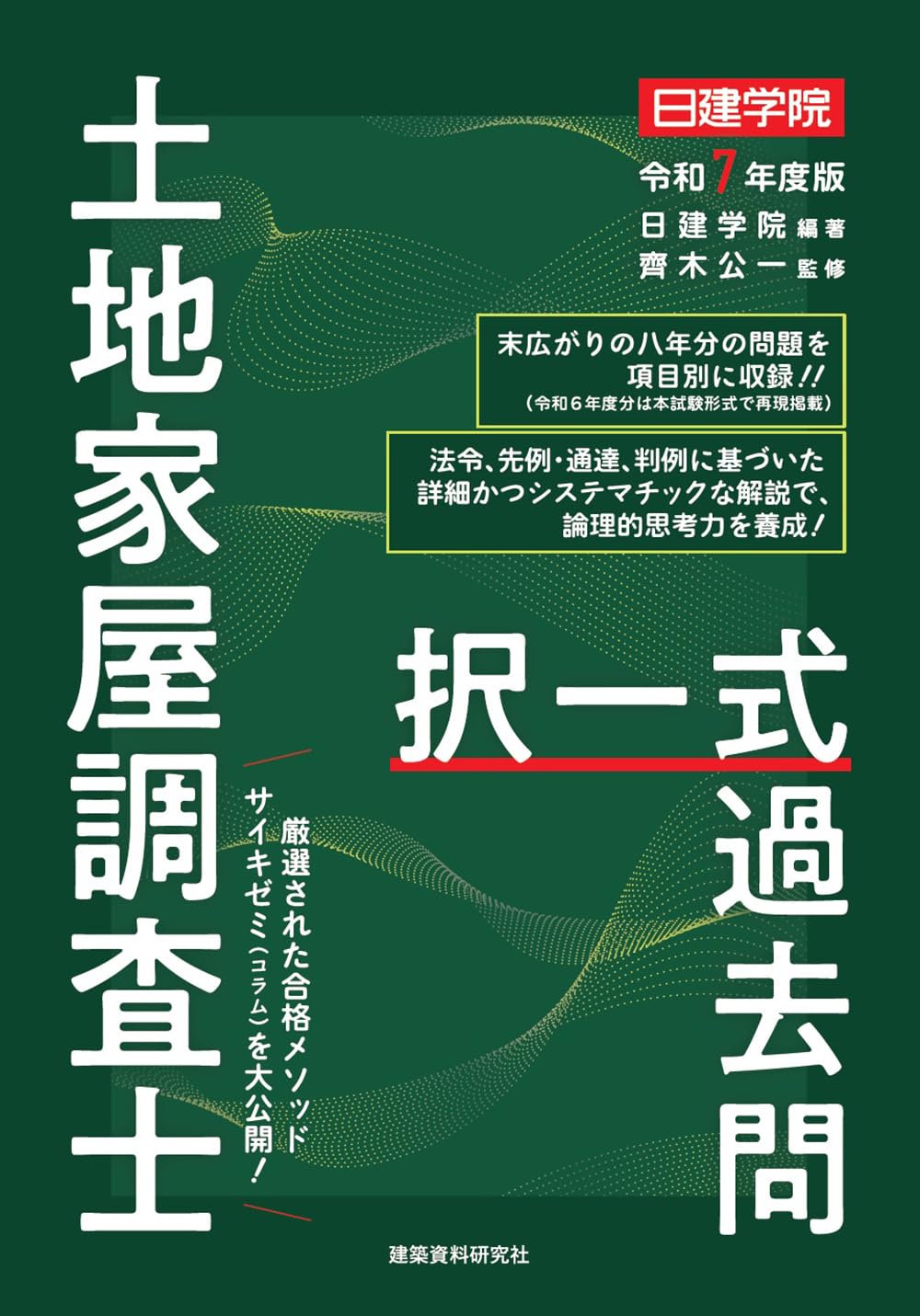
引用:Amazon
『土地家屋調査士 択一式過去問 令和7年度版』は、択一式の過去問に特化した過去問題集。
令和7年版は、過去8年分の過去問を掲載しているため、年度別で過去問に取り組む人におすすめできます。
『土地家屋調査士 択一式過去問 令和7年度版』は、漫画雑誌によく使われるB5サイズになるため、携帯性も期待できるでしょう。
建築資料研究社が発刊する全592ページの書籍です。
土地家屋調査士 択一式過去問マスター
『土地家屋調査士 択一式過去問マスター』は、択一式の出題傾向として指摘される「民法や不動産登記法、土地家屋調査士法の過去問をマスターするための問題集。
マスター1とマスター2と2冊構成で過去問が掲載されています。
マスター1では、択一式全般の科目を対象に平成元年~令和6年までの計366問の過去問が収録されています。
マスター2では、択一式のおもな出題範囲となる不動産登記法について特化した307の過去問に挑戦できるでしょう。
マスター1とマスター2の2冊に繰り返し取り組むことにより、択一式の出題範囲への理解が高まるでしょう。
まとめ
土地家屋調査士試験の択一式は、あらかじめ用意された5択の回答から正しい回答を選ぶ形式です。
記述式と比べて文章を書き込む必要がないため、表面的な理解のままで進めてしまう可能性があります。
そのため、過去問を繰り返し解きながら、「なぜ、正解なのか」という理由についてもインプットできるレベルまで理解度を高めましょう。
今回紹介したテキストや過去問の問題集は、買っただけで使わなければ意味がありません。
アガルートの土地家屋調査士試験講座では、土地家屋調査士試験で最高得点を獲得した講師がテキストや問題集の効果的な使い方、試験勉強のコツなどを学べます。
実績のある講師から学び、着実に力をつけましょう。
土地家屋調査士・測量士補試験の合格を
目指している方へ
- 土地家屋調査士・測量士補試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの土地家屋調査士・測量士補試験講座を
無料体験してみませんか?


約10.5時間分の土地家屋調査士&約2時間分の測量士補の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!土地家屋調査士・測量士補試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!
土地家屋調査士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
2024年度土地家屋調査士試験記述式の模範解答・解説講義がもらえる!
『合格総合講義 民法テキスト』をまるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く!
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る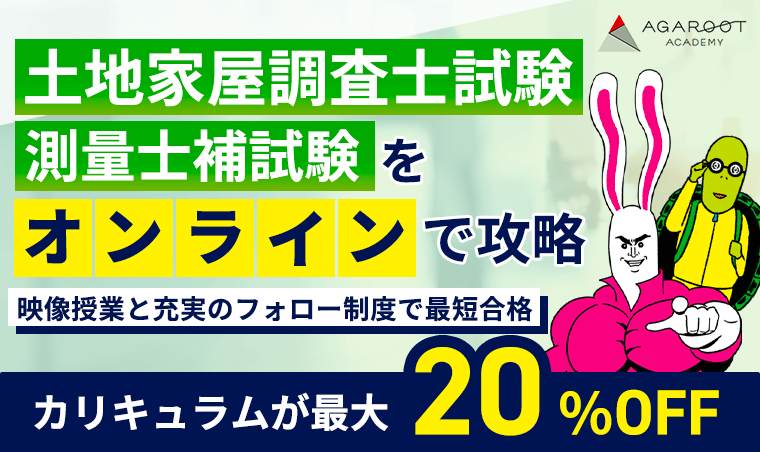
4年連続1位合格者輩出!
令和6年土地家屋調査士講座の
アガルート受講生の合格率63.64%!全国平均の約6倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
▶土地家屋調査士・測量士補試験講座を見る