
トップに訊く
「人」が創るミツウロコ法務の変革 100年企業に息づくベンチャースピリット
株式会社ミツウロコグループホールディングス
上席執行役員 兼 ジェネラルカウンセル
大竹 宏枝
エネルギー事業を主軸に多角的な事業を展開し、創立100周年を間近に控える株式会社ミツウロコグループホールディングス(以下、ミツウロコ)。歴史ある企業の中で、法務組織は大きな変革期を迎えています。
2024年4月に独立部門として新たなスタートを切ったミツウロコ法務は、単なるリスク管理ではなく、「事業の実現を共に推進する」ことをミッションに掲げ、経営の一角を担う戦略部門へと進化を遂げようとしています。
本記事では同社の上席執行役員 兼 ジェネラルカウンセルの大竹様へのインタビューを通じ、法務組織の挑戦と魅力、そして多様な事業を支えながら、未来を切り拓く法務パーソンに求められる本質に迫ります。
ミツウロコ入社の決め手

株式会社ミツウロコグループホールディングス 上席執行役員 ジェネラルカウンセル 大竹 宏枝 様
まずは自己紹介を兼ねて、これまでのキャリアと現在の役割についてお聞かせいただけますでしょうか。
新卒で大手電気メーカーに就職し、以来ずっと法務畑で経験を積んできました。メーカーを3社経験した後にミツウロコに入社しました。
入社当初は法務のポジションではなく、グループ会社経営支援を担当していたのですが、社内で法務機能の強化の議論が進み、2024年4月1日付で法務ヘッド、そして2025年4月1日付でジェネラルカウンセル法務ヘッドという職位に就いています。
2024年までは取締役の法務担当者が私の上におりましたが、2025年からは社長に直接レポートする形になり、少し役割が変わった状況です。
前職から現職への転職のきっかけや入社の決め手は何ですか。
私のキャリアでは法務のポジションをご案内いただくことが圧倒的に多かったのですが、そうではないポジションでのご案内だったので「面白そうだな、話だけでも聞いてみよう」という気持ちでカジュアル面談を受けました。
それが初対面にもかかわらず、その日のうちに社長とも面談し、気づくとトータルで2時間半ほど経っていたというくらい話が盛り上がり、その日のうちに内定をいただいたんです。不思議な縁を感じ、直感的に「この人たちと一緒に働いてみたいな」と思ったのが入社の決め手です。
転職を繰り返して思うのは、やはり最終的には「人」が決め手になるということです。どのような方々と一緒に、どのような気持ちで働けるかが非常に重要だと感じています。
プロパンガスからボウリング場運営まで、多様な事業を展開
貴社はエネルギー会社のイメージが強いですが、他にも多岐にわたる事業を展開されていますね。
おっしゃるとおり、主力の事業はエネルギーで、中でもプロパンガスがもともとの柱です。現在では電力事業も大きな柱の一つになっています。
その他にミネラルウォーター等の製造販売、「麻布十番モンタボー」というスクラッチベーカリーや、「元町珈琲」というカフェを経営するフーズ事業も展開しています。
不動産関係では賃貸物件の経営も行っていますし、横浜駅近くの温浴施設「SPA EAS(スパ イアス)」やボウリング場の「Hamabowl(ハマボール)」などリビング&ウェルネス事業も手掛けています。
もともとは運送業から始まったと伺いました。
はい、ご理解のとおり、創業は運送業から始まり、その後煉炭や豆炭の製造をするようになりました。世の中の流れでそれらが使われなくなると、プロパンガスへと事業を切り替えてきました。
時代の変化に合わせて柔軟に事業を変えてきた会社で、次の10年を見据え、現在も多様な事業を展開しています。
独立した法務体制とミッション
多岐にわたる事業を展開される中で、法務組織はどのような体制になっているのでしょうか。
法務組織は、もとは総務部門の一部でした。法務機能を強化していこうという方針のもと、2024年4月1日付で部門として独立しました。
2025年5月現在は8名が在籍しており、私を含めて管理職が4人、主任が4人という体制です。
まだ新しい部門なのですね。法務部が掲げるミッションについてはいかがでしょうか。
明文化しているほどではないのですが、「事業の実現を共に推進していく」という点は重視しています。
これまでは法務部門が独立していなかったため、まだ法務からの指摘に慣れていない社員が抵抗を感じることもあります。そのため我々が考える法務の役割をお伝えし、理解を深めてもらうためのコミュニケーションが重要だと感じています。
法務はどうしてもゲートキーパー的な役割を担う場面で「ノー」と言うこともありますが、その際に「だからダメ」と言うのではなく、「こうすればできるのではないでしょうか」と代替案を提示することを心がけています。
もちろん、どうしても「ノー」と言わざるを得ない場合もありますが、普段から「イエス」を追求することで、その「ノー」の重みが伝わると思っています。
総務部から独立した背景には、どのような考えがあったのでしょうか。
総務部の一部として少人数で業務を行っていた時は他の業務も兼務する必要があり、正直、迅速なビジネスサポートは困難でした。
そこで私の考える法務の本来の姿をもとに問題提起したところ、経営者が考えている「こうあってほしい法務」の姿と近いことが分かりました。
特にコンプライアンスが重要視される現代において、しっかりと法務の体制を築かないと、コンプライアンス推進も難しいという認識を共有でき、部門の立ち上げと人員拡大に同意してもらえたのです。
多様な事業と提案が形になる醍醐味:ミツウロコ法務の特徴

多岐にわたる事業を抱えるミツウロコでの法務は「飽きることがない」という。
大竹様ご自身もニューヨーク州の弁護士資格をお持ちですが、弁護士の有資格者の方は多いのでしょうか。
そうですね、弁護士が多い部門です。2025年5月現在、日本の弁護士資格を持つメンバーが管理職に1人、主任に3人、そして弁理士資格を持つ者が1人という状況です。
8名中6名が有資格者となりますので、割合は大きいですね。
これだけ多様な事業を展開されていると、法務として大変なこともあれば、やりがいや面白みもあるのではないでしょうか。
様々な事業に携わるということは、それに伴う多岐にわたる法律を理解する必要があります。特に電力事業法のような特殊な業法については、法務の人間よりも実務に携わるビジネスの人間の方が詳しいことも多いため、ビジネスと連携しながら進めています。
また、今の人数でできることには限りがあるため、外部の弁護士の先生方への相談も非常に重要です。
しかし、多岐にわたる事業とそれに関わる法律が多い分、「飽きることはない」と言えると思います。
常に新しいことを勉強し、新しいことに挑戦していくことが必要な環境ですので、法務の仕事に飽きてきて、新しいことに挑戦してみたいという方には、いくらでも新しい経験ができる面白味のある職場だと思います。
法務部門が独立してまだ1年少しの会社なので、これから整備していくべき部分も少なくありません。そのため、「こういうことをやってみてはどうか」という提案が求められ、歓迎される環境です。
自分たちで提案したことが形になっていく過程を見られるのも、今のフェーズの醍醐味です。全てが整った環境を好む方には難しいかもしれませんが、新しいものを創り上げていくことや、自ら考え提案することが好きな方には、非常に面白い環境だと思います。
全社のコンプライアンス推進は法務の重要な役割
コンプライアンスも非常に重視されていると伺いました。具体的な取り組みについて教えていただけますでしょうか。
以前から全社員向けのコンプライアンスハンドブックの配布や、月に一度の小集団活動でコンプライアンスの徹底を図るなど、長年継続してきた取り組みはあります。
法務組織が立ち上がってから新たに取り組んでいることとしては、これまであまり研修テーマになっていなかった基本的な法律に関するeラーニングやオンラインセミナーの実施です。
まずは「実はあなたの業務にも関係しますよ」と、社員に一般的な法律と業務との関連性に気づいてもらうための活動を昨年度から始めています。
研修は全社向けと事業領域に特化したものがあるのでしょうか。
現在は全グループ向けの一般的な法律の研修から始めています。
事業特有の業法と呼ばれる分野については、現場の実務に直結しており、現場の人間のほうが詳しいことも珍しくありません。現在はまだ法務が業法をすべて把握するには至っていないこともあり、業法については研修を行っていません。
現在、グループ会社はどのくらいあるのでしょうか。
約40社です。そのグループ会社をホールディングスの法務8名で割り振って見ている形です。事業も多様で数も多いため、現場に法務の声が届きにくいと感じることもあります。
そこで、主要な事業会社には法務と現場の従業員をつなぐ「法務担当」を置いてもらうよう調整し、密に連携を取っています。
ホールディングスから直接伝えるよりも、現場に近い法務担当から伝えてもらう方が効果的なことも少なくないからです。
ミツウロコ法務部のユニークな魅力と今後の展望
様々な会社を見てこられた大竹様から見て、ミツウロコグループホールディングスの法務にはどのようなユニークさがありますか。
2026年5月で創立100周年を迎える歴史ある会社でありながら、法務は「これから作っていくぞ」というベンチャーのようなフェーズにあるところが、他社さんにはあまりない特色かもしれません。
そして、本当に多様な事業を展開しているので、幅広い経験を積めるという点も特徴です。
一つの分野で道を極めたい方には向かないかもしれませんが、様々なことに挑戦したい方には良い環境だと思います。
グローバル法務についてはどうでしょうか。
現在は国内が中心ですが、海外事業も進めています。
シンガポールに子会社があり、香港やマレーシアにも展開していますし、先日シンガポールでの業務提携も発表しました。
国内が圧倒的に多いですが、海外事業もこれから拡大していく段階です。
法務部のメンバーに共通するマインドセットはありますか。
個性はバラバラですね。
ただ、職場全体は非常に和気あいあいとしており、話しやすい雰囲気があります。
弁護士事務所出身の弁護士が4人居て、弁護士が多いということは言えると思いますが、一人ひとり個性は全く違います。
当社の法務組織にフィットする方としては、新しい挑戦や多様な経験を面白いと思える方、そして事業部の人とのコミュニケーションを苦にしない方が挙げられます。
電話や対面での問い合わせも多いので、黙々と書面と向き合うスタイルを好むタイプの方よりは、話すことが好きな方が向いていると思います。
働き方についてはどうですか。
リモートワークの頻度はいかがでしょうか。
法務の業務はリモートでも対応できることが多いので、対面でのミーティングが必要なければ、週に1〜2回の出社で、あとはリモートという働き方が一般的です。
時代の変化が速い中で、法務組織や法務パーソンに求められるものはどのように変化していくとお考えでしょうか。
リスクマネジメントが非常に難しくなっている現代において、法務は経営の一角を担う重要な部門と位置づける会社が増えていると感じます。
将来的にはより組織を大きくし、経営の一角を担える戦略的・能動的な部門になっていくことが非常に重要です。
昔は管理部門というと経理や人事のような部門が重視され、法務の最高責任者が取締役にいることは稀でした。しかし今は、コンプライアンスやガバナンスが社会的に重視され、法務の重要性が高まっています。
何か問題が起きた際に、会社が事前に対策を講じていたかどうかで会社が受ける影響は全く異なります。
法務は言われた仕事をするだけでなく、問題がそもそも起きないようにするための仕組みを考えたり、社員への研修を行ったりと、戦略部門として会社の経営に貢献していく役割を担うようになっていくでしょう。
今後、貴社の法務組織として、特に強化したいポイントはありますか。
まだ数は少ないのですが、海外案件に対応できる人材を育成していきたいと考えています。また、組織としてもグループ会社の法務としてはまだ人数が足りていないので、もう少し大きくしていきたいです。
そうすることで、重要な契約の交渉に法務が同席するなど、より踏み込んだ役割を果たせるようになると考えています。
現場の事業会社としても、法務が交渉に加わることで法的な側面からサポートが得られ、交渉を進めやすくなるでしょうし、法務部員にとっても交渉経験を通じてスキルを身につけられるという、皆にとって良い効果が生まれる組織にしていきたいと考えています。
法務パーソンに求められる「人間力」

大竹様は生成AIの活用が広がる時代の法務パーソンに求められるのは「人間力」だと語る。ステークホルダーとの信頼関係構築も、法務の重要な役割だ。
法務の重要度が増す時代において、法務パーソンにはどのような資質が求められるのでしょうか。
法務の作業のうち契約書の作成やレビューといった業務の多くは、2~3年後には生成AIによって置き換えが進む可能性があります。
そうなると、AIに任せられることはAIに任せ、人間でなければできないことが法務パーソンとして非常に重要になってくると思います。
突き詰めると、結局は事業会社の人々や社内外のステークホルダーと「信頼関係を築ける人」であることが最も重要なのではないでしょうか。
信頼関係の構築には時間がかかりますし、地道な努力が求められます。コミュニケーション能力を含めて、いわゆる「人間力」が重要になってくると思います。
大竹様ご自身のキャリアを振り返ってみて、今に繋がっていると感じる経験はありますか。
色々とありますが、キャリアのスタート時にひたすら秘密保持契約書を見る日々を送っていて、当時は「もうお腹いっぱい」と思っていましたが、今になってみればそれが財産です。
スポーツの名門チームが基礎練習を徹底するように、基礎がしっかりしていれば応用が利きます。地道に基礎を固めることが何事においても重要だと感じています。
また、私は運が良いのか悪いのか、本当に様々な経験をさせてもらいました。
それらの多様な経験が、一分野しか経験していない人では気づけないことに気づいたり、多角的な視点を持てたりするなど、仕事をする上で大きな財産になっています。
大変だと思っていても、後から振り返るとそれが財産になっていると強く感じます。
その時、頑張り続けることができた要因は何でしょうか。
職場の人間関係が非常に良好で、「この会社を辞めてやる」というような環境では全くなかったということが大きかったと思います。
ひたすら秘密保持契約書を見る日々で「これに意味があるのだろうか」と思う状況でも、人間関係が良好だと「ここにいたい」という気持ちが働くものです。
上司や先輩、同僚に恵まれたことが、困難を乗り越えられた最大の要因だと感じています。
最後に、キャリアの情報収集をされている弁護士や法務部にお勤めの方々に向けてメッセージをお願いします。
ミツウロコグループホールディングスの法務は、まだこれから様々な施策を打ち、組織拡大も考えています。
新しいことに挑戦したい方、多様な経験を積みたい方は、ぜひ話だけでも聞きに来ていただければと思います。
動画:ミツウロコ法務トップが考える法務人材に求められるもの
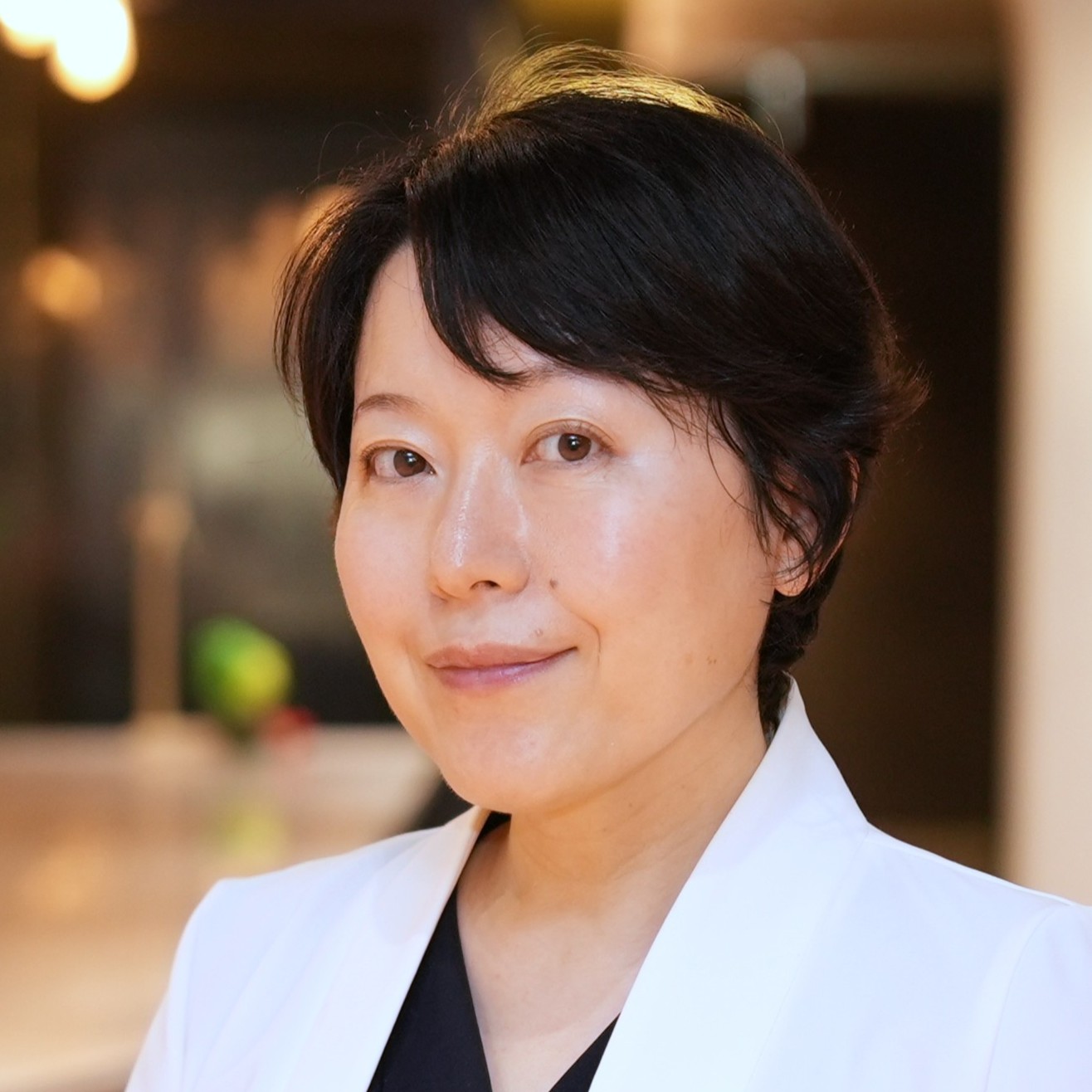
Recommend
おすすめ記事
-

- トップに訊く
QVCジャパン法務トップが語る「優れた法律家であり続ける」ためのキャリア戦略
株式会社 QVCジャパン ジェネラル・カウンセル
西岡 志貴
- 企業内弁護士
- 企業法務
-

- トップに訊く
沖縄から世界へ広がる琉球スフィア 「法の護り」を広げるカギは「人間力」にあり
弁護士法人琉球スフィア 代表弁護士
久保 以明
- パートナー・代表
- グローバル
- 一般民事
- 企業法務
-

- 事務所を知る
東京スタートアップ法律事務所が考える、新時代を生き残る新しい弁護士像
東京スタートアップ法律事務所 代表社員弁護士
中川 浩秀
- パートナー・代表
- リモートワーク
- 刑事事件
- 一般民事
- 若手弁護士
-

- 事務所を知る
国内から海外まで幅広いネットワークで多様な法務領域を支えるベリーベスト法律事務所
ベリーベスト法律事務所 代表弁護士/パートナー弁護士
浅野 健太郎/折田 忠仁
- パートナー・代表
- M&A
- グローバル
- 一般民事
- 企業法務
-

- インハウスの実態
「マジ価値」を支える法務の力。freeeで働く楽しさとやりがいとは
フリー株式会社 リスク管理部 法務チームマネージャー
中島 一精
- SaaS
- リスクマネジメント
- 企業内弁護士
- 若手弁護士
- スタートアップ
-

- インハウスの実態
法律事務所からインハウスへ。QVCジャパンで広がる法務パーソンとしての経験
株式会社 QVCジャパン シニアカウンセル/カウンセル
小嶋 潔/新沼 奏之介
- 企業内弁護士
- 企業法務




