
トップに訊く
「業務時間は9時~19時」大企業顧問中心でもワークライフバランスを実現する香川総合法律事務所
香川総合法律事務所
代表弁護士
香川 希理
弁護士としてのキャリアを追求する中で、専門性を高めながら個人の生活も充実させることは、多くの法律家が抱える普遍的な課題の一つです。特に企業法務の分野においては、その多忙さゆえに「ワークライフバランスは困難」という認識が一般的かもしれません。
しかし、東京に拠点を置く香川総合法律事務所は、この常識を覆す新たな働き方を提示しています。
本記事では、創設者である香川先生へのインタビューを通じて、同事務所がどのようにして土日祝日休みや19時退勤といった働き方を実現しながら、企業法務、特にマンション・不動産やカスハラ(カスタマーハラスメント)といった専門性の高い領域で顧問業務を展開しているのかに迫ります。
香川先生のキャリアパスと独立への道のり

香川総合法律事務所 代表弁護士 香川 希理 様
香川先生の簡単な自己紹介からお願いできますでしょうか。
香川と申します。私は2010年(63期)に弁護士になりました。
3年間、都内の一人のベテランの先生が経営されている事務所で経験を積ませていただき、2013年に独立しました。
現在、弁護士7名の事務所を経営しております。
独立される前のファーストキャリアとして、別の法律事務所にいらっしゃったということですよね。その事務所を選ばれた理由と、どのような業務をされていたのか教えていただけますか。
就職活動が厳しい時期でしたが、その中で選んだ基準は、都内であることと、企業法務を扱う事務所であることでした。
なるべく伝統的な、いわゆる「古き良き事務所」のようなところで、弁護士としての「型」をしっかりと作りたいと考えていました。
将来的な独立を当初から考えていたため、法律事務所の概念や仕事の仕方の基礎を学びたいという観点から、その事務所を選びました。
それは、規模が非常に大きな事務所というよりは、一人の先生について基礎から学べるような場所を求めていたということでしょうか。
その通りです。
一人のベテランの先生のもとで、まさに師匠と弟子の関係で修行させていただきました。
いわゆる「一見さんお断り」の完全紹介制で、ホームページもないような事務所でしたね。
修習中の就職活動で、どのようにしてそのような事務所を見つけられたのですか。
それはもう本当に、修習の先生や活動している中のご縁でお会いさせていただきました。
その先生は35期の大ベテランで、今も尊敬しております。
その事務所でも企業法務案件を幅広く扱っていたと伺いました。
はい。
昔ながらの都内のちゃんとした先生の事務所という感じで、優良顧問を中心に、ご紹介があれば一般民事も受けるという事務所でした。
最初の事務所に入られてから3年ほどで独立されたとのことですが、この3年という期間に何か理由があったのでしょうか。
ある程度のことはできるようになったと感じたのと、当時2013年という時期は、まさに弁護士が非常に増え、過当競争が今後さらに激化していく段階でした。
その中で、独立するならここが「ラストチャンス」だと考えましたね。
体力と世間の潮流を考慮しての判断でした。
香川総合法律事務所独自の強みと成長戦略

質の高いサービスを提供できないと判断すれば、紹介なしの相談は引き受けないことも多いという。
香川先生が経営されてらっしゃる香川総合法律事務所の概要について伺います。現在、どのくらいの人数規模で、主にどのような領域を扱っていらっしゃるのでしょうか。
現在、弁護士は7名です。
ご依頼いただく案件の99%がご紹介です。案件領域としては企業法務が中心で、以前の事務所と同様に企業の顧問業務を主としていますが、経営者のご家族からの相談や従業員の交通事故など、ご紹介があれば一般民事も引き受けることがあります。
ご自身のファーストキャリアでの経験を基盤に展開されているのですね。弁護士の皆さんの修習期はどのような層が多いのでしょうか。
私の修習同期である63期の弁護士がもう一人おります。
あとは、70期以降の比較的若手の弁護士が5名います。
私以外の弁護士6名のうち、4名が修習を終えてそのまま入所した方々で、2名が中途採用です。
顧問業務の中でも、特に強みである領域があれば教えていただけますか。
一番強いのはマンション・不動産です。
この分野が強みとなった背景はどのようなものですか。
これは最初の事務所の先生のおかげです。先生がマンション業界の企業の顧問をされていて、私が独立した後も下請け的に手伝わせていただいていたのですが、その企業から「香川先生に顧問になってほしい」という提案をいただきました。
大先生の了解を得て顧問に就任したところ、若手でその業界の顧問を務める弁護士は珍しかったため、その繋がりでどんどんご紹介が増えていきました。
なるほど、そこからご紹介で顧客が増えていったのですね。ご紹介なしの「一見さん」の案件はお断りされることも多いのですか。
ご紹介いただく機会はかなりあります。
ただ私たちの強みが活かせない案件や、医療過誤のように他の専門の先生の方が確実にうまくやれる案件は他の事務所をご紹介しています。
何でも引き受けるのではなく、質の高いサービスを提供できる分野に特化しています。
ホームページを拝見して、いわゆる「カスハラ(カスタマーハラスメント)」の領域も強みの一つだと感じたのですが、いかがでしょうか。
その通りです。特にここ2、3年で相談がかなり増えています。
これも以前の先生がその分野の日本における第一人者だったため、弁護士登録直後から修行させていただきました。
当時は「カスハラ」という言葉はなく、「クレーム」や「不当要求」の分野として行政や大企業に対する不当要求などを扱ってきました。
地道に続けてきた分野が最近になってカスハラとしてクローズアップされ、条例や法律が整備されたことでさらに案件が増えています。
マンションや不動産、カスハラといった強み領域で、特に印象的だった事例や案件があれば教えていただけますか。
マンションに関しては、法律論的にまだ固まっていない分野が多いんです。
区分所有法という民法の特別法なのですが、この分野で先進的な裁判例を獲得したことはありますね。
法的に明確な答えがない分野だと、一審の結果が二審で逆転することもあるのでしょうか。
そうなんです。裁判官すら答えがない分野で書籍にもどこにも決まった考えが載っていないため、学者の先生方を招いて月1回勉強会を開いています。
そこで疑問を出し合い、みんなで意見交換しながら「こういう考え方もあるのではないか」とご指導いただいています。
強みである領域においても、常に最先端を行くために努力されているのですね。
ええ、そこは徹底してやっています。
オンライン顧問サービスとメディア活動
「オンライン顧問サービス」も始められたと拝見しました。どのようなサービスなのかご説明いただけますでしょうか。
これまでの法律顧問サービスは、基本的に対面での打ち合わせが中心でしたが、これをオンラインで同様のサービスを提供できるようにしました。
このメリットは大きく、大企業になるほど支社が複数ある場合、東京本社だけでなく、大阪支社や名古屋支社といった方々にも、全国統一のリーガルサービスを提供できる点にあります。
以前はどのように対応されていたのですか。
東京本社は東京の先生に、大阪支社は大阪の先生に頼むといった形でした。もちろん、裁判や交渉で相手方と対面する際はそれが良いのですが、法律的な見解がバラバラになってしまうことが問題でした。
私たちがチェックすると、全く違う見解が上がってきて「これは先日お伝えいただいた内容と違うのですが」と聞くと、「それは別の地域の先生の見解です」という状況になることがありました。
このような不都合があったため、全国統一のリーガルサービス提供を目指しました。
見解の統一は非常に重要ですよね。
加えて、地方の先生方は非常に優秀で何でもこなしますが、一方で専門特化が難しい局面があります。
例えば、マンションの建設数は東京が圧倒的に多数で、専門とする弁護士の数や経験値もそれに伴って高まります。しかし地方の先生は他の一般民事をこなしながら顧問業務としてマンションを扱うため、最新の事情が伝わっていないことがあるのです。
地域に本社を構える不動産会社なども、オンラインで顧問サービスを受けられるということですね。
その通りです。むしろ地方に本社がある企業からの問い合わせが多く来ますね。
香川先生はメディアにも出演されていますよね。情報番組や漫画「正直不動産」の制作協力などもされていますが、メディア露出で得られているものは何でしょうか。
露出をすることによって、逆に情報が集まってくるという点です。
例えば情報番組で「こういう問題があるんです」と取り上げると、「実はその問題にはこういう側面もあって、こういう問題もあるんです」といった情報が寄せられることがあります。
専門分野の知識がさらに集積されていくというメリットがあると思います。
ワークライフバランスを実現する働き方

業務時間は9時から19時が基本。「弁護士は長時間労働が当たり前」というイメージを覆すワークライフバランスの取れた職場環境が実現されている。
アソシエイトの弁護士の方々の執務時間や働き方はどのような感じなのでしょうか。
基本的にはアソシエイトを含め、全員が朝9時には出社してもらっています。これは、顧問業務が多いため、9時からメールや電話が来る会社があるからです。
お昼休憩は1時間自由に取ってよく、帰りは19時までとしています。
ただし、1年目の先生など、まだ仕事に慣れておらず時間がかかる場合は、プラス1時間後ろ倒し(20時まで)でも良いとしています。2年目ではまだ30分ほど早い帰宅ですが、4年目くらいの先生は皆19時には帰っていますね。
緊急的な対応で突発的に忙しくなることはありますか。
それはどうしようもない時は残ってもらうこともありますが、業種的に、いわゆる一般民事の先生に比べて「ガーッと忙しい」というよりは、ある程度ならすことができる分野なので、そこまで多くはないです。
法律事務所の先生方のお話を聞く中で、貴事務所のように19時頃に帰るというのは非常に珍しい印象です。
「本当にこんなに少ないんですか」と非常に驚かれます。面接の時でも疑われますね(笑)。
なぜこのような働き方をされているのでしょうか。
社会が変わってきたということが一つと、遅くまでやったからといって効率が良くなるわけではないからです。
1日睡眠時間4時間や5時間でずっとやっても、その分仕事ができるかというと、やはり効率は落ちてしまいます。
土日祝日も仕事はないのですか。
アソシエイトは土日の業務は行いません。企業に勤める従業員の方と同じです。
雇用契約なのですか。
雇用契約と業務委託を選べるのですが、最近入所した方は雇用契約を選ぶ方が多いです。
リモートワークはいかがでしょうか。
リモートワークはやっていません。
私も彼らが何をやってるかを把握できなくなりますし、実際に可能なのかと今も思うところがあり、一貫してずっと出社スタイルでやっています。
クライアント企業に対するリーガルサービスの品質担保のためでもあります。皆が出所することで、何かあったらすぐに相談できるような体制を構築しています。
個人事件の受任は可能ですか。
個人事件は3割負担ですが、受任は可能です。ただし、その分、事務所案件に支障が出ないよう、自分で調整して補ってもらう形です。
事務所案件に従事する時間が過度に長くはないため、個人事件を受任している弁護士も多いですね。
自分で顧問を持っている弁護士もいますし、うまく事務所業務後に打ち合わせを入れたりしています。
未来を見据えた採用と人材育成
採用について伺います。司法試験に受かって法的知識を持っていることは前提として、一緒に働く方を見極める際に、どんなポイントを重視されていますか。
責任感があって真面目な人です。顧問業務が中心なので、クライアントとの信頼関係が最も重要な仕事だと考えています。
能力というよりは、人間性を重視されているということですね。
そうですね。
面接は何回くらいされていますか。
3回から4回ほどです。私だけでなく、他の弁護士にも面接に入ってもらうようにしています。
私だけだと偏りが出てしまう可能性があるので、なるべく多くの人に見てもらうためです。
食事をすることも多いですね。大体1回は食事をしています。
それは素の姿を見るためですか。
そうですね。逆に事務所側を知ってもらうのも重要だと思います。お互いのミスマッチは避けたいですから。
経験の有無は重視されますか。
正直、あまりないです。入ってから勉強してもらえれば良いと思っています。
むしろ、経験のある弁護士の場合は今までの「辞め方」や「キャリアの作り方」といった点に目がいく気がしますね。
どんな仕事であれきちんと筋を通して真面目にやってきたのかという点が重要だと感じます。
香川総合法律事務所に入所することのメリットはどのような点でしょうか。
やはり一番多くの方に驚かれるのは、都内で企業法務を扱いながらワークライフバランスを実現できることです。私の知る限り、このような事務所はそう多くないのではないでしょうか。
急成長というわけではありませんが、独立してから10年以上、着実に少しずつ伸びていますので、長く働きたいと考えている方にとっては、将来設計しやすいと思います。
ワークライフバランスと専門性を高めて長く働きたい方には、非常に向いているということですね。
そうですね。そのため、お給料も初年度に一気に高く出すというよりは、ずっと右肩上がりに昇給していく仕組みです。
昇給は年に一度ですか。
はい、年に一度、1月に行います。
担当案件に応じたインセンティブ制度はありますか。
今のところは設けていません。本来はどこかで設けるべきなのかとも思う一方で、それを公平に作るのが非常に難しいと感じています。
顧問中心の事務所だと、インセンティブ制度は馴染みにくいかもしれませんね。
その通りです。私としては、目先のお金を稼ぐことよりも、きちんと仕事をして目に見えない信頼を積み重ねることを評価しています。
顧問の担当体制はどのようになっていますか。
企業によって違います。
事務所全体で対応する企業や、これまでの継続的な知識が必要となる企業は、主担当と副担当を置く形にしています。
新しく入られた方は、まず副担当として入る形でしょうか。
はい、そうです。
最初は副担当としてサポートする形で入ってもらい、ある程度自分でしっかりと業務をこなせるようになったら主担当に入ってもらいます。
弁護士業界の展望と若手弁護士へのメッセージ

「これから伸びるだろう」と思われる領域を見極め、専門性を高めることが「求められる弁護士」になる方法だという。
今後の事務所の展望についてお聞かせください。
まずはやはり基本的なことをしっかりとし、現在の得意分野であるマンション、不動産、カスハラといった領域をしっかりとやっていくことです。
同時に、少しずつではありますが、色々な分野に対応できるようになりたいと考えています。
都内には「この事務所はしっかりしているよね」と言われるような企業法務の事務所がいくつかありますが、そういった伝統的でしっかりとした事務所という評価を受けられるようになるのが次の目標です。
弁護士に求められるものも時代とともに変化していると思いますが、香川先生の見解はいかがでしょうか。
特にここ2、3年、コンプライアンスが非常に重視されています。
これは世の中的にも弁護士業界的にも良いことであり、チャンスだと捉えています。
弁護士が提供できる価値があることを、もっと提案できるのではないかと以前から思っていました。
コンサルやシンクタンク、会計監査事務所なども行っていますが、本当はコンプライアンスの部分は弁護士がもっと積極的に担うべき分野だと思います。
私も含め、弁護士会全体としてもっとそういった分野に取り組んでいくべきでしょう。
また、例えば社外取締役の分野もそうですね。タレントが増えているといった話もありますが、本当にそれで良いのかと疑問に感じます。
社外取締役を置く趣旨からすると、コンプライアンスやガバナンスをきちんと理解しているべきです。
そういった分野も今後増えていくのではないでしょうか。
若手の弁護士の方から「何でもやれます」というのも一つだが、器用貧乏になってしまうという相談も多いと聞きます。そのような方へアドバイスをお願いします。
私自身はマンションとカスハラという今後伸びていくだろうと予想した分野を選びましたが、やはり「伸びるだろう」という分野に取り組むのが良いと思います。
やりたくてもニーズがなければ力を発揮する場がないですからね。ニュースや本を読んでいれば、なんとなくどこが伸びるかは分かるものです。
例えば、以前はなかったカスハラという言葉を頻繁に聞くようになったように、統計を見れば「ここは確実に増えていく分野だ」ということが、流行する前から分かる場合もあります。
今はそうでもないけれど、今後増えるであろう分野を選ぶのが良いのではないでしょうか。
また、若手の先生方はエンタメ系の分野を好む傾向もありますが、エンタメは競争も激しいので、何か一工夫した方が良いと思いますね。
キャリアについて検討している弁護士の皆さんに向けてメッセージをお願いします。
当事務所の強みは、ワークライフバランスを実現しながら、安定的に長期に働けることだと考えています。
これまで、ワークライフバランスを実現するためにはインハウスになるしかない、と考えていた方も多くいらっしゃいました。
インハウスという選択肢も素晴らしいものですが、当事務所は「ワークライフバランスを実現しながら、都内で企業法務に携わり、共に大きくなっていきたい」と考える方々にとって、新しい選択肢となると信じています。
もしそのような方がいらっしゃいましたら、ぜひご応募いただけると非常に嬉しいです。
動画:大企業顧問×ワークライフバランスを保てる法律事務所/土日祝休み・19時退勤

Recommend
おすすめ記事
-

- 法務部インサイド
変革期の企業を支えるユーザベースの法務組織のあり方
株式会社ユーザベース 執行役員 General Counsel 兼 NewsPicks事業CLO
吉田 真実
- CLO
- メディア
- SaaS
- リーガルテック
- 企業内弁護士
- スタートアップ
- 企業法務
-

- トップに訊く
あらゆるフェーズのベンチャー・スタートアップを支援するAZX Professionals Group
AZX Professionals group マネージングパートナー COO
菅原 稔
- 出向
- パートナー・代表
- 若手弁護士
- スタートアップ
- 企業法務
-

- 事務所を知る
東京スタートアップ法律事務所が考える、新時代を生き残る新しい弁護士像
東京スタートアップ法律事務所 代表社員弁護士
中川 浩秀
- パートナー・代表
- リモートワーク
- 刑事事件
- 一般民事
- 若手弁護士
-
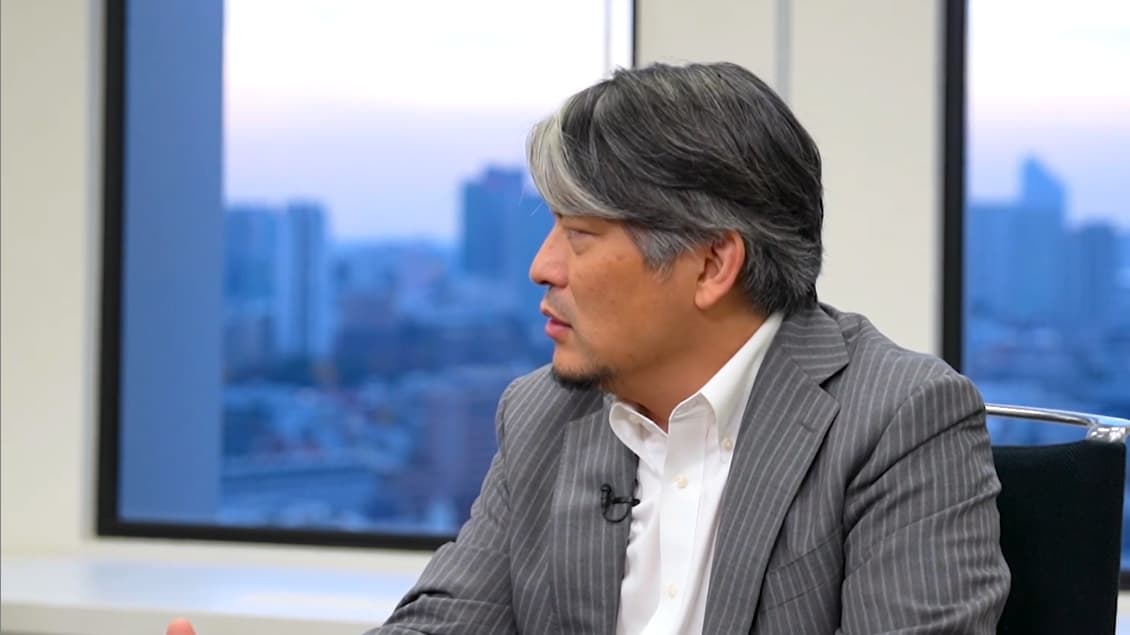
- トップに訊く
真のグローバルトップファームを目指す東京国際法律事務所
東京国際法律事務所 代表弁護士
山田 広毅
- パートナー・代表
- 留学
- LL.M.
- シンガポール
- 紛争解決
- M&A
- グローバル
- 企業法務
-

- 事務所を知る
アジア各国の商習慣や法務環境に明るいOneAsia法律事務所だから提供できる価値と求める人物像
OneAsia法律事務所 シンガポール/タイ/ベトナム オフィス
鴫原 洋平/千葉 広康/松谷 亮
- シンガポール
- グローバル
- 若手弁護士
- 企業法務
-

- 事務所を知る
アトム法律事務所が「刑事・交通・離婚・相続」にこだわる理由
アトム法律事務所 代表弁護士
岡野 武志
- 刑事事件
- 一般民事




