
ヤメ検・ヤメ判録
キャリア12年の元検事に聞いた検察官の仕事内容
アガルート法律会計事務所
弁護士・アガルートアカデミー講師
江原 佐和
今回はアガルート法律会計事務所の江原弁護士にインタビューをおこないました。
江原弁護士は12年間検事としてキャリアを積まれたのち、アガルート法律会計事務所に転職。現在はクライアント様の法律事務や、企業・個人を対象とした講師業務などを主に担当されています。
法曹界に興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。
12年の検事生活ののち、法律事務所へ転職

アガルート法律会計事務所 弁護士・アガルートアカデミー講師 江原 佐和様
本日はアガルート法律会計事務所の江原先生にお越しいただきました。検事から法律事務所へ転職された経緯をはじめ、さまざまなお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは簡単に自己紹介をお願いします。
アガルート法律会計事務所の弁護士およびアガルートアカデミー講師の江原 佐和と申します。
私は千葉大学を卒業し、上智大学法科大学院を経て司法試験に合格。1年間の司法修習を経て、2010年12月に検事に任官されました。
その後2022年の年末に検事を辞職し、翌年よりアガルート法律会計事務所で弁護士を、またアガルートアカデミーで企業様や個人を対象とした講師業もおこなっております。
本日はどうぞよろしくお願いします。
法曹への興味が湧いたのは大学入学後
実は江原先生も、弊社の弁護士の先生方に特化した転職エージェントをご利用いただいて転職されたと伺っています。早速ですが、なぜ法曹の道を目指そうと思われたのでしょうか。
実は、私が法曹の道を志すようになった「目覚め」というのは割と遅いほうでした。
もともと公務員のような、女性が一生食べられるような仕事をしようと思っていたんですね。そうしますと「じゃあ法学部かな」ということで、大学では法学部を選びました。
入学してみたら何やら法科大学院というすごいものができるらしいという流れになり、実際に法科大学院に進学した先輩の姿も見ていたんです。
法学部にも入ったし、大学院もできるということで、だったら入ってみようかなと。それで法科大学院に入るからにはやはり司法試験を受けて、法曹になってみたいなと思うに至ったわけです。
ですからもう法曹を志したのは大学に入ってからという感じでしたね。
法学部に入学した当初は、法曹になろうとまでは思っていなかったということでしょうか。
そうですね。はっきりと法曹とまでは決めていませんでした。
法曹にも「弁護士」「検事」「裁判官」とありますが、その中でも検事になろうと思っていたんですか?
実はですね、私は最初は裁判官を志望していました。
というのも、なにか争いが起こった時に一方の話だけではなく、なるべく広く関わった人の話を聞いて公平に判断したいなと思っていたんですね。
そうすると、中立な立場で両者の言い分を聞く裁判官が一番向いているのではないかなと思って。
両者から話を聞いてしっかり判断するということで、裁判官というイメージを持たれていたということなんですね。
検察修習で大きく印象が変わった
実際は裁判官ではなく検事になられたということで、お考えが変化するタイミングやきっかけなどは、どのようなものがありましたか?
考えが変わったのは司法試験に合格して、司法修習に入ってからでした。
検察修習の際、実際に指導係検事が関係者からお話を聞いたり、さまざまな事件の記録を読んだりするのに接する機会があります。
その中で、実は刑事事件は検察官の手元で不起訴になる事件が非常に多いということや、検察官も裁判官と同様に、疑いがかかっている方と被害に遭ったとして届を出している方の両方からお話を聞いて判断を下しているんだということがわかりました。
そうするとむしろ検事のほうが自分に合っているかもしれないと思いを改めた次第です。
そうだったんですね。知識として裁判官と検事の違いはご存知だったと思うのですが、実際の現場を見て感じたことに大きな差はありましたか?
そうですね、やはり修習で感じた感覚であったり、実際に体験したことは非常に大きいものでした。
例えば「検察官は被疑者の取り調べをするよ」とか、「裁判官は法廷で裁判を主催するよ」だとか、あるいはどれぐらいの事件が不起訴になり公判請求されるかというデータを学習してはいました。
しかし、それが実際どれだけ自分の身になっていたかというと、あまり意識してはいなかったと。自分事としてとらえ、実際に働いたらこういうことになるんだなとはっきり分かったのは、やはり修習のときだったなと感じます。
都市部と地方では任官数にも大きな差が
どこの修習に参加されたんでしたっけ。
私は東京修習でした。
東京修習は人数が多いんですか?
はい。私が受験したのは今の司法試験がまだ「新司法試験」と言われていた時代で、新63期という世代なのですが、3000人近い合格者がいました。
その世代は多いですね。直近だと1700人ぐらいでしたか?
そうですね、2000人に満たないくらいです。現在と比べるとかなり多いですね。東京修習は80人が4班で320人参加していました。
そういう状況だと、やはり東京修習に参加している方から任官される人数が多くなる傾向があったりもするんでしょうか?
まさに私が修習地を決める際にはそのことも考えました。検事や裁判官の任官は人数が無制限ではないだろうと。
やはり修習生の人数に比例して大体これぐらい任官できるというのが決まっているんじゃないかなと推測しました。20人4班で80人の地方修習地と、80人4班320人の東京修習では、東京のほうが4倍近い枠があると予想したんです(※江原先生のご推測です)。
それなら実力で1番がとれなくても「面白枠採用」とか、勉強があまりできなくても「キャラで採用してやろう」とか、そういう望みがあるかもしれないという若干の打算もあって東京修習に参加することにしたんです(笑)。
修習地はそういう選び方もあるんですね。
一般企業や法律事務所の内定は「取っておけ」と言われる
検察官を第一志望に進めていったと思うのですが、100%受かる保証があるわけではありませんよね。志望を変更して法律事務所や一般企業のインハウスローヤーのポジションとか、そういったものも見てはいたのでしょうか。
やはり検察長官からも裁判長官からも、任官を希望する場合でも内定は取っておくべきだということははっきり言われるんですね。私も弁護士としての就職活動をおこなっていました。
どのようなところを受けたんですか? やはり法律事務所がメインだったのでしょうか。
法律事務所の選考も受けましたし、ちょっと珍しいところでは企業のインハウスローヤーにも申し込みました。
なるほど。昔に比べればインハウスローヤーもかなり一般化してきたと思いますが、当時はまだまだ多くはなかったですよね。
そうですね、特に初就職先としては本当に珍しかったと思います。
現時点でもファーストキャリアでインハウスローヤーを選ぶ方は、おそらく全体の数%ほどじゃないかと思います。そんな中で、最終的に検察官の道が開けて、そちらへ進まれたということですよね。
そうですね。
2年おきに地方を転々と異動

検事は基本的に2年で異動。江原先生もさまざまな部署で経験を積んだ。
ここからは検察官になってからのお話をお聞きしようと思います。まずはどのような業務に携わっていたのか、また最初の配属地からどのように転勤していったのかなどを教えてください。
私の場合、2010年末に任官されたあと、新任検事ということで研修と実践をかねて1年間は東京地検に勤めていました。その後、広島地検と京都地検に2年ずつ勤めたのち、横浜地検小田原支部に行きました。
産休・育休を経て同じく横浜地検小田原支部に復帰後、次の異動で東京地検に戻ったんですね。東京地検に籍を置いている間に、日本サイバー犯罪対策センターへ出向も経験しています。出向から東京地検に戻り、そこで辞職しました。
やはりというか、全国を転々とされるんですね。おおよそ2年ごとに転勤するものなのでしょうか?
そうですね。基本的には2年ごとに転勤となります。
お仕事の内容としては、東京地検のようないわゆる大都市の検察と地方の検察とでは違いがありそうに思いますが、実感されたことはありますか?
これは一般企業でも同じかもしれませんが、東京地検は非常に規模が大きいので、部署の細分化がかなり進んでいます。
例えば捜査や公判というだけでなく、その中でも「このジャンルはこっち、あのジャンルはあっち」というように分かれています。「縦割り」と言ってしまうとちょっとネガティブかもしれませんが……。
一方、地方の検察では検事の人数自体に限りがありますので、東京のように細かく組織を分けることなく、来た仕事はその場にいる人がなんでも一生懸命やるという形です。
地方ごとに組織の体制は様々ですが、場所によっては起訴されるまでの捜査部門と、起訴されてからの公判部門を同じ検事が受け持つようなところが今でもありますよ。
個人の意向を伝える機会は定期的にある
「都市部がいい」とか「あの地方に行きたい」とか、多少なり個人の希望を出したり通したりはできるものなのでしょうか?
異動の意向は毎回尋ねられます。どこそこの地検がよいとか、これこれの高検管内がよいというように個別に希望を出すこともできますし、「お任せします」でももちろんOKです。
ただ100%希望が叶うわけではありませんが、それでもやはり各人の要望を踏まえてできる限り配慮しようという対応をしてくださいます。私も、特に産後はかなりご配慮いただいたなと感じています。
さまざまな働き方改革とか世相もあると思いますが、組織としての柔軟さが増してきていると感じますか?
それはまさしくあると思います。
それこそ、かつては男性が検事としてバリバリ働いて、専業主婦として家事に専念しているパートナーを伴ってあちこちに……という形が多かったと思うのですが、いま女性検事の割合がとても増えていて、パートナーを持った場合、その女性検事のほとんどが共働きになるんですよね。
そうするとずっと離れたままというのはなかなか大変です。
そのため、ご家族がなるべく一緒にいられるような形であるとか、家事育児の都合上あまり無理はできない場合に対応できるような配置を考えるだとか、そのような配慮がかなりなされていると感じます。
事案の専門性は次第に高まる傾向
江原先生が実際に検事として産休・育休含めて12年勤めていらっしゃった中で、担当する事案の種類は専門的になっていったりするのでしょうか。
まず実働ができる女性検事の任官者が増えているとはいえまだまだ少数派ですので、女性や小さな子どもが被害に遭った事件は、赴任地を問わずかなり多くお任せいただいたなと思います。
小さな子どもや、自分ではいろいろと話をしにくい事情がある方に対して、ありのままにお話いただくための「司法面接」という特別な話の聞き方の研修を受ける機会があったので、私がそのような事件を自ら担当したり、また若い検事にアドバイスしたりということをしていました。
東京に戻ってからは「生活安全部門」という生活に即した事案を取り扱う部門に配属されたため特殊詐欺の事件をかなり多く扱っていたのと、こちらでも同じように性犯罪の事案を担当していましたね。
さらにその後は日本サイバー犯罪対策センターに出向したので、国内外を問わずサイバー犯罪の動向について調査をしたり、海外のカウンターパートの機関とやり取りをしたりしていました。
そのような経験を踏まえてか、東京に戻って辞職するまでの短い期間ではありましたが、サイバー係検事ということで関連犯罪のご相談を受けたりもしていました。
検事がもっとも忙しいのは4、5年目
けっこう並行して複数事案の対応を行うことになると思いますが、どのくらいの数を並行して進めることになるものなのでしょうか。
その時の繁忙度やポジションによってもかなり違いますが、私の場合は京都地検にいた時期が一番忙しかったなと思います。
検事としては4、5年目を終えたころには一人前の検事として一通りの事件を一人で担当できないといけないというのが暗黙の了解になっておりますので、その時期は仕上げということでかなりいろいろな事案を担当させていただきましたね。
逮捕・勾留……つまり身柄を拘束されていて、法律で定められた期日までに起訴・不起訴の判断をすることが強く求められる事件(身柄事件)が14、5件ほど並行してありました。事件としても相応に重大な事件ばかりで。
それにプラスして、在宅で身柄拘束を受けていない、いわゆる書類送検の形で来ているものが別に30件ぐらい常にあるというような状況が、京都地検ではありました。
やはりかなりお忙しかったのですね。
当時はそうですね。かなり仕事に打ち込んだなという記憶があります。
逆に小田原支部に復帰してからは、当時の上司と常に「今ちょっと余裕があります」とか「ちょっとコロナで保育園が休園になってしまったんです」というような相談をしあっていましたね。
時には身柄事件をゼロにしてもらい他の検事に任せたり、他の検事に事情がある時は逆にこちらが受け持ったりという調整をして、身柄事件が多くても5件ぐらいを超えないように差配していただいていたという感じです。
素人からすると、検事と聞くとやはりドラマの「HERO」を見て検事になりたいと思う方も多かったのかなと思うのですが、あんな風に1事案にチーム全員で戦っていくということはないものなんですね。
そうですね、現役検事の中にもやはり「HERO」にあこがれて任官を受けたという方はいますね。
さっき申し上げたように、同時にいくつもの事件を回していかなければいけませんので、実は「HERO」のように1事案だけに集中するわけにはいきません。
ただその中でも「この方からは直接お話を聞かないと」とか、「この現場にはぜひとも直接行かないと」とか必要なことをしっかり見て、やらなきゃいけないことはちゃんとやるという感じです。
検事は「世の中になくてはならない」職業だと思う
検事のお仕事を振り返ってみると、大変なことももちろんあったかと思います。その一方で、大きな「やりがい」を感じる部分もあったのでしょうか。
はい。辞めてしまったいまでも、やはり検事は世の中になくてはならない、非常に意味のある仕事だと私は思っています。
私自身、司法のシステムをきちんと回していくんだという気持ちを持ってずっと勤めていましたし、今でも本当によい仕事だと思います。
お話しぶりからも、仕事とそのような向き合い方をされてきたんだろうなと感じます。
ありがとうございます。
転職を考えたきっかけ
前回に引き続き、アガルート法律会計事務所の江原先生にお越しいただき、転職のきっかけや経緯などを伺います。まずは率直に、なぜ転職をお考えになったのでしょうか?
検事の仕事に大きな魅力を感じていたのはずっと変わりませんでしたし、私の育児や家事の事情にも配慮していただいてはいました。
しかし検事の仕事はどうしても紙の書類や証拠物を検察庁内でしっかり検討することが大切で、リモートワークには向きません。子どものお迎えに帰ってしまうと、その後職場に戻って仕事をすることがどうしてもできないんですよね。
他方で、身柄拘束されている事件(身柄事件)は法律上の時間制限があるので、大規模な事件が起こると能力の高い検察官が時間制限いっぱいにフルコミットして解決に導きます。
でも私のような事情があると、そういった事案にはアサインできないということになってしまいます。
それは配慮していただいた結果の表れでもあるのですが……私としては歯がゆい気持ちをどうしても覚えてしまって。誰も悪くはないんですが、ちょっと悔しいなと思っていました。
あとは私の子どもが環境の変化にあまり強くなかったというのも理由のひとつです。
私自身は仕事上転勤があることはやむを得ないと思っていたんですが、子どもには2年おきに学校や病院を変えることを繰り返すのは合っていなさそうだなと思ったんです。
それに夫も転勤族だったので、夫婦どちらか片方だけでも、特定の土地に軸足を置く働き方を考えたほうがいいんじゃないかなと考えました。
複合的な理由があったんですね。それは個人でどうこうできるものではないですよね。
そうですね。
やはり女性の割合が増えると同時に共働きの割合もどんどん増えています。
また刑事手続きのIT化が進んでいるところなので、そういった部分もカバーできるようになればいいなと、ちょっと未来に期待という感じです。
そういった期待はありつつも、まだまだ時間はかかるだろうということで、当時の江原先生としては「やはり別の環境を」というご決断をされたと。
そうですね。
出向先の自由な労働環境に「こういうのもあるのか」
転職活動を始めた際、情報収集はどのように行っていましたか?
はじめは「弁護士 転職」で検索するとか、本当にそういうところから始めた記憶があります。
日本サイバー犯罪センター(JC3)という機関に出向していたんですが、そこには民間企業でリクルーティング事業をされている方もいらっしゃったので、そのつながりで転職サイトを見てみたこともあります。
少し話が逸れてしまうのですが、JC3では民間企業の方がかなりのびのび働いていました。
フルリモートでお子さんを膝に乗せてミーティングに出席するみたいな方もいて、「なるほど、こういう働き方もあるのか」と思わされて、今でも印象に残っています。
それで転職サイトをインターネットで調べて、子どもがいることを前提とした働き方でも問題ない職場を探していましたね。
「絶対ここに入る」と思い1社だけ応募

「人に自分の経験を話す」というアガルートの講師業に、ご自身の適正を見出したそう。
なるほど。転職サイト経由で応募した職場は、企業のインハウスローヤーが多かったですか? 法律事務所などにも応募されたのでしょうか。
ご紹介を受けた求人にはインハウスも法律事務所もどちらもたくさんありましたが、実質的に選考に進んだのは現在のアガルートが最初で最後でした。
というのも、アガルートが第一希望で「私、絶対ここに入る!」と思って、実際受かったので。
カジュアル面談ぐらいのことは他社でもやりましたが、選考にちゃんと進んだのは実はここだけなんです。
そうだったんですか。それは何故だったのでしょうか?
アガルートが司法試験の予備校として名を馳せていたのですが、アガルート代表の岩崎と私が実質同期なので私はアガルートを受講することはできなかったんですよ。
でも検事を辞める前の数年間、新任や若手の検事から「アガルート」という名前をやたら聞くなと思っていたんです。
とてもありがたい話です。
それでアガルートのサイトを見てみると「講師ができる弁護士を募集していますよ」と書いてありまして。そういった求人をしている事務所が他には全くなかったんです。
実は検事は仕事のかたわらさまざまな団体や警察を対象に研修というか講義を行うことがあるんです。
特に、私はJC3に出向している間、全国の警察幹部の方に向けてたくさんの講義をしていました。講義を褒めていただけることもたまにあり、それがとても嬉しかったんですね。
人にお話をして理解してもらうということにやりがいを感じていたので、アガルートの求人はピッタリだなと。しかも「リモートもできる」と書いてあったので、ますます合っているなと思いました。
理想の環境で成長し続けたい
一般的な法律事務所だとクライアント様の法律事務に対応するのがメイン業務だと思いますが、アガルート法律事務所だとアカデミー講師業務もあれば、企業向けの講習や講師業務も今行っているんでしょうか?
そうですね、検事の時は企業よりは非営利の団体が多かったんですが、現在非常に多くの一般企業様からお問い合わせいただいています。
企業規模の大小を問わず、法律や諸官庁の見解を踏まえてコンプライアンスやハラスメント研修を行ってほしいというお問い合わせが多く、実施も多数行っています。
アガルートグループにはグループ企業が12社(2024年7月時点)あるので、1事務所で多くの企業のインハウス法務を経験できるというのは珍しいですよね。
そう思います。
私はアガルート法律会計事務所に興味を持ったあとで、「アガルートって転職エージェントもやっているんだ」と気づいて問い合わせまして。当時の担当エージェントの方には本当に親身にご対応いただきました。
ご紹介いただいた求人もアガルートグループだけではなくて、一番私のニーズに即した求人票のラインナップを質・量ともにバーンと揃えてくださったんですね。
他にもやり取りをしていたエージェントさんが複数いた中で、「一番私のことを分かってくれているな」と思えた、ベストなエージェントがアガルートキャリアでした。
担当業務は人によって異なる
弊社サービスをご利用いただいて入所されたということですが、現在担当されている業務の比率はどのくらいですか?
企業様への研修や司法試験予備試験を目指している個人への指導がだいたい6割~7割くらい。
また今年度から弁護士チーム、アソシエイト弁護士全員のマネジメント業務をしてまして、それが3割くらい。
残りの1割で外部の顧問先からのご相談であったり、アガルートやその関連会社の内部のご相談を扱ったりという、いわゆる企業法務を行っています。
私のイメージですと、先生によって業務割合がバラバラなイメージがあります。これはどのように決めているのでしょうか。
おっしゃる通り、弁護士ごとに仕事の割合はさまざまですが、第一に本人に出してもらった希望にしたがって差配をします。
その上で基本的には各アソシエイトの自主性に任せてはいます。
ただ誰か忙しくなりすぎている人がいないかを見て、「これ危ないな」という時には私がマネジメントという形で巻き取ったり介入したりして、みんなで仕事をしています。
江原先生が「調整弁」のような役割で、状況を見ながら差配しているんですね。
そうですね。
アソシエイト間で不公平感が出てしまわないように、ちょっと引いた目で差配できる人間がいたほうがかえって自由度が高まるんじゃないかという考えで、今年度からのチャレンジとしてマネジメント役を一人おいて運用しています。
新しいチャレンジということですが、アガルート法律会計事務所はスピーディーに変化していく組織なのでしょうか。
会社自体がまだ若いということもあって、「こうしたほうがいいんじゃないか、ああしたほうがいいんじゃないか」というのはどんどんやってみようと。
意思決定やよりよくするための動きは非常にスピーディーだと思います。
クライアントの希望優先だが、リモートワークが8割
今はどのくらいの頻度でリモートワークをされているんですか?
私は8割が在宅で、残りの2割がお取引先の企業様への往訪だったり対面での指導だったりという形です。
他の先生方も江原先生と同様に8割ぐらいなのでしょうか。
そうですね、皆さんかなりリモートワークを活用しています。
たとえばちょっと本を見たいというときなんかに出勤されている先生もいますが、ふだんの相談などはチャットやWeb会議でやり取りをしています。
なるほど。クライアント様のご要望があるときには行くものの、それ以外はリモートで仕事できるなら全然リモートで問題ないよということなんですね。
クライアント様のご都合が私どもの優先事項ですので、対面のご希望であったり、何日にここに来てくださいというご要望があれば絶対に承ります。
自分自身でスケジュールを決められる業務は、自宅で自分のペースで行えばよいという形です。
クライアント様のご都合が最優先ということですが、ちなみに最近はクライアント様もWeb会議などオンラインでのやり取りが主流になってきているのでしょうか?
Webでお願いしますとか、通常の連絡でも電話よりメールでという方は非常に多いです。
ただ、私の場合、ハラスメント研修やコンプライアンス研修ですとワークやグループディスカッションをすることが多いので、内容がセンシティブなこともあって対面を希望される企業様も少なくありません。
研修の質としても、顔を合わせて自分の手で問題点を書き出してみたり、リアルタイムで複数のグループでディスカッションをしていただくとなると、対面の便利さや内容の浸透力が高いかなと。
そのあたりをどうするかは本当にクライアント様によるという感じですね。
2年目には検事時代と同様の報酬水準に
ちょっと聞きにくいお話ですが、転職してみて報酬面はいかがでしょう。正直、水準的には同じくらいなのか下がったのか、そのあたりは。
転職して1年目は少し下がりましたが、2年目の現在は東京で働く検察官と遜色ないような報酬をいただいています。
私としては非常にありがたいです。「今日も米が買えます」という感じで(笑)。
個人事件の経費自己負担はゼロ
アガルート法律会計事務所は個人事件が自由と伺っています。一般的な法律事務所だと、経費の自己負担が3割かかるというところが多いかなと思うのですが、アガルート法律会計事務所は自己負担ゼロなんですよね?
そうです。
個人事件を結構受けている先生方も多いのでしょうか。
かなり精力的に個人事件を受任されてバリバリやってらっしゃる先生方もいらっしゃいます。
私は家庭の事情があったり、まだまだ勉強することがあったりするので個人事件を受けていません。
そういう部分もやる・やらない含めて「個人の裁量で自由にどうぞ」という考え方が根底にあるということですね。
はい、そのとおりです。
自分が提供できる「バリュー」を意図して転職活動を行った
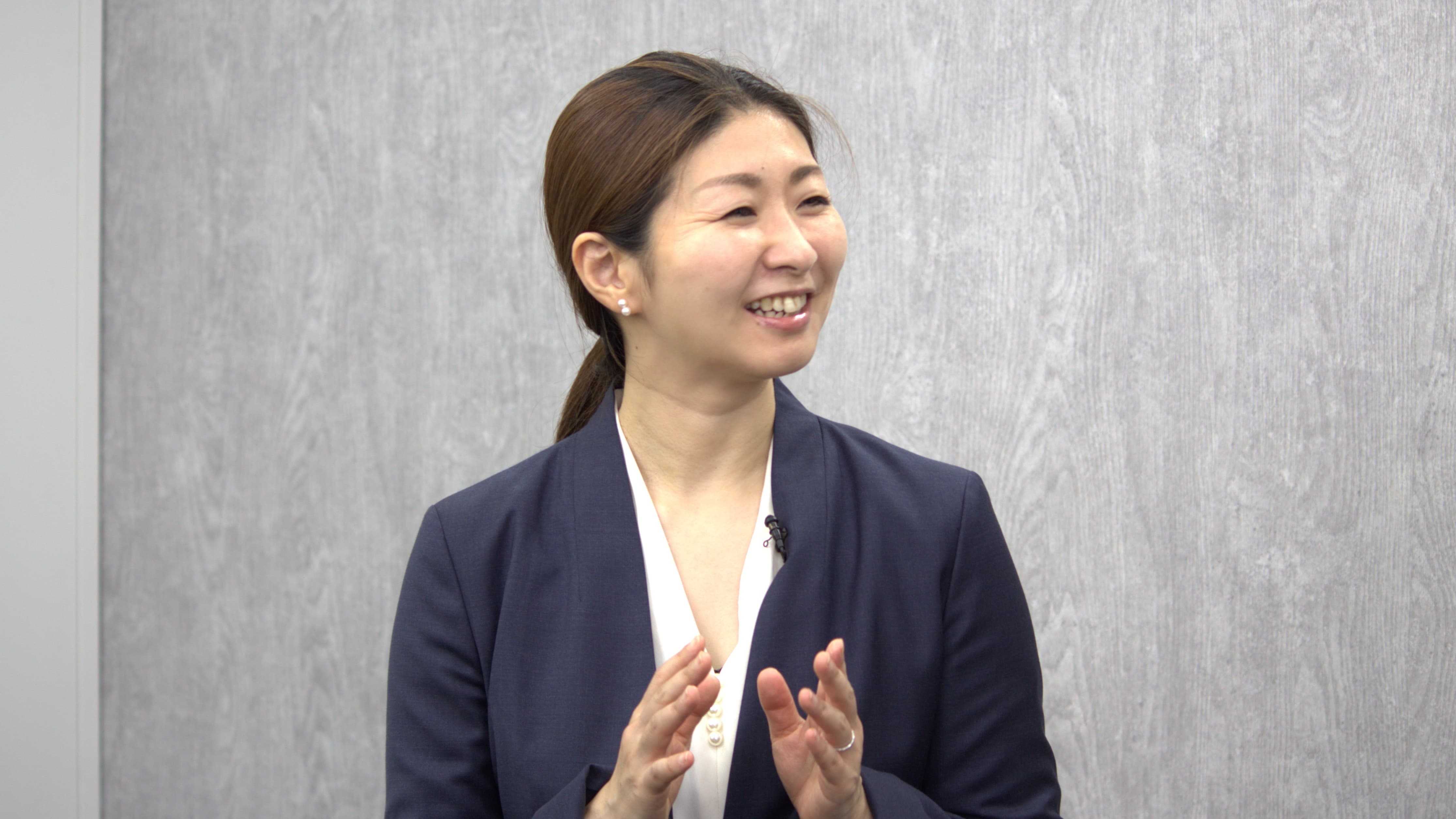
あえて「ヤメ検」のいない職場を選び、自身の経験を最大限活かした転職を意識したという。
あんまりご入所前のイメージとギャップはありませんか?
そうですね、失望するとか、こんなはずではなかったということはまったくありませんでした。
転職の際ここに決めた理由として元裁判官の先生はおられたんですが、いわゆる「ヤメ検」がいなかったことがあるんです。
一人目の元検事で、なおかつ司法、予備試験の指導を行う講師陣にも企業法務等を行う法律会計事務所のアソシエイト弁護士にも女性がほとんどいなかったので、ちょっと違う属性の人が入ることでバリューを提供できるんじゃないかという期待もあって入所しました。
一人目ということが逆に悪く働いてしまう可能性もあり得ると思っていたのですが、皆さんその部分をとても汲んでくださって、むしろ思っていたよりずっと楽しくやれているなと日々感じています。
意識的にそういった環境の職場を探したという感じでしょうか。
「ヤメ検」の方が大勢いらっしゃって、ルートがある程度できている弁護士事務所のご紹介も受けました。
それはそれで非常に魅力的ではありました。
しかし、むしろまだ「ヤメ検」がいないところに一人目として入ることで「検事ってこうだよ」とか「実は刑事事務ってこうなんだよ」と、アガルートに対して価値を提供できるかなと意図したところはありましたね。
アガルートグループ全体をつらぬく「横串」がほしい
せっかくの機会なので、逆に今ある課題についてもお聞きしたいなと思います。そういった観点でお感じになる点はありますか?
法律会計事務所だけでなく予備校事業も行っているアガルートという企業全体で言うと、とても短期間でワーッと勢いよく走ってすごい勢いで成長していった会社だと思うんですね。
そういう勢いで成長していった会社には付き物かなと思うのですが、各自の良識に任せてなんとかなっている部分だとか、統制をする部分についてはまだまだ改善すべきところはあるように感じます。
これはまさに法律家である私たちがしっかり考えていかなければならないところですね。
それから例えば「アガルート」と検索してみるとびっくりされると思うんですが、関連会社が非常に多いですよね。
各社グループ会社になったあともすごく強い個性で輝きを放っていて、それぞれの自由な形できちんと利益を実現されています。
でも全体を貫くようなポリシーというか「横串」のようなものがもしかしたらあってもいいのかもと考えてはいます。
欲しいのは「自走できる人」。でも「独走」ではない
アガルート法律会計事務所は現在も仲間を募集していますよね。江原先生の個人的な観点からでも構いませんので、どういう方がマッチしていそうとか、どんな人と一緒に働けたらよいとか、逆にこんな人には合わないかもといったことがあれば、ぜひお教えください。
非常に自由な働き方ができる会社ですので、自分のことは自分で責任を持って決めることができ、当事者として自走できる方が望ましいかなと思います。
裏を返せば、当事者意識が持てないとか自走できない方、すべて人に委ねてしまう方というのは、弊社・弊所で働くのは難しい面がありますね。
でも、自走というのは何もかも一人でやらなければならないということではありませんよ。困ったときにスピーディーに人に相談するとか、問題点を共有するということです。
リモートワークが多いとコミュニケーションを取らなくていいんだと考えてしまうかもしれませんが、むしろリモートだからこそ必要なコミュニケーションはしっかり真剣に行わなければなりません。
そのように皆と協調するということも含めて自走できる方なら、困らず一生懸命働いて成長できるのではないかなと思います。
弁護士の転職活動は情報収集からアガルートキャリアで
分かりました、ありがとうございます。ここまで色々とお聞きしてきましたが、最後に法曹を目指している方や、今まさに弁護士としてのキャリアの情報収集をされている方へのメッセージを一言お願いします。
違う道もあるかもしれないなと思っていたり、自分の欲しいものや欲しい人生ってこういうものだったかしらと悩んでいる方がいたら、自分が今後進みたい道がどういったものかよくお考えになって、よかったらお気軽にご相談ください。
いつでも待っています。
前編:元検事に聞いたキャリア選択と働き方
後編:元検事に聞いた転職活動の進め方と理想の働き方

Recommend
おすすめ記事
-

- 事務所を知る
東京スタートアップ法律事務所が考える、新時代を生き残る新しい弁護士像
東京スタートアップ法律事務所 代表社員弁護士
中川 浩秀
- パートナー・代表
- リモートワーク
- 刑事事件
- 一般民事
- 若手弁護士
-

- インハウスの実態
四大法律事務所からアクセンチュア、そしてテスラへ――多様な経験が導いたキャリア像
Tesla Japan合同会社/松下法律事務所 弁護士
稲井 宏紀
- 大手企業
- 企業内弁護士
- 企業法務
-
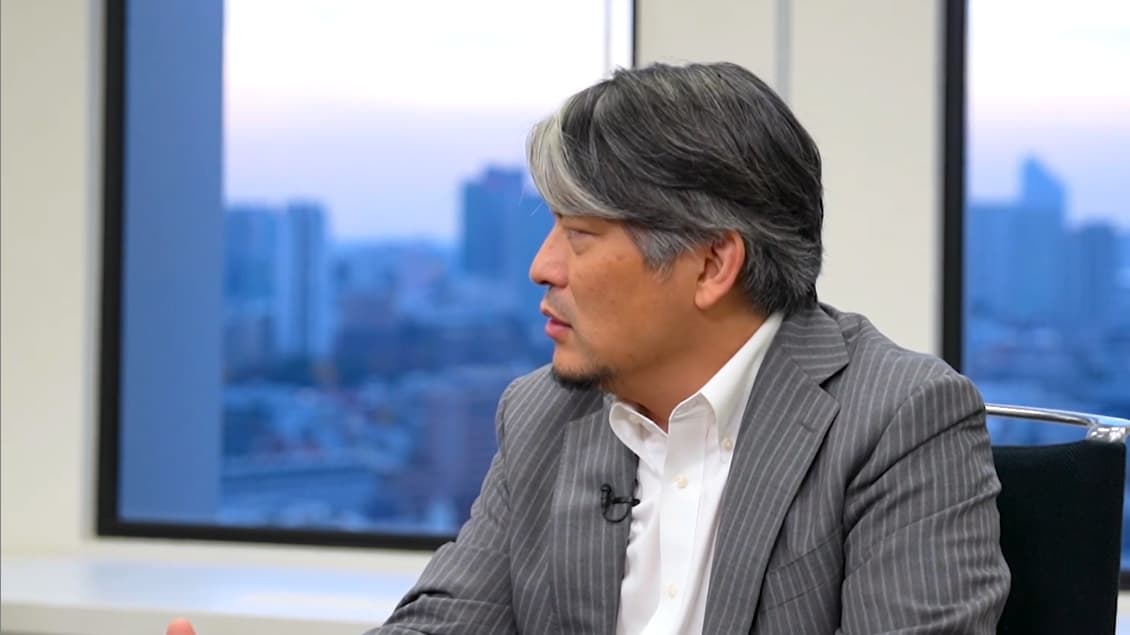
- トップに訊く
真のグローバルトップファームを目指す東京国際法律事務所
東京国際法律事務所 代表弁護士
山田 広毅
- パートナー・代表
- 留学
- LL.M.
- シンガポール
- 紛争解決
- M&A
- グローバル
- 企業法務
-

- 法務部インサイド
法務部は多様な事業をともに推進する戦略的パートナー
レバレジーズ株式会社 法務部マネージャー/法務部 メンバー
合田 武司/廣澤 沙織
- 人材業界
- スタートアップ
- 企業法務
-

- 事務所を知る
アジア各国の商習慣や法務環境に明るいOneAsia法律事務所だから提供できる価値と求める人物像
OneAsia法律事務所 シンガポール/タイ/ベトナム オフィス
鴫原 洋平/千葉 広康/松谷 亮
- シンガポール
- グローバル
- 若手弁護士
- 企業法務
-

- キャリア羅針盤
大手法律事務所との協業で実現する法務人材の未来の姿
MNTSQ株式会社 CEO 兼 長島・大野・常松法律事務所 弁護士
板谷 隆平
- リーガルテック
- 若手弁護士
- 四大法律事務所
- スタートアップ




