
キャリア羅針盤
大手法律事務所との協業で実現する法務人材の未来の姿
MNTSQ株式会社
CEO 兼 長島・大野・常松法律事務所 弁護士
板谷 隆平
四大法律事務所で“留学より起業”を選び、いま注目を集めるリーガルテック企業を率いているのは、MNTSQ株式会社CEOであり、長島・大野・常松法律事務所で現職の弁護士を務める板谷隆平先生。
MNTSQ株式会社は“すべての合意をフェアにする”というビジョンを掲げ、ビジネスの要である「契約」の世界にどんな変化をもたらそうとしているのでしょうか。板谷先生へのインタビューを通じ、“法務×テクノロジー”が切り開く新しいキャリア像に迫ります。
ぜひ最後までご覧ください。
四大法律事務所に入所も前代未聞の「留学より起業させて」

MNTSQ株式会社CEO 兼 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 板谷隆平様
本日は、今注目のリーガルテック企業MNTSQ(モンテスキュー)株式会社さまにお邪魔し、代表取締役の板谷さまにお話をうかがいます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はじめに自己紹介をお願いします。
皆さん初めまして。MNTSQ代表、また長島・大野・常松法律事務所で弁護士をしております、板谷と申します。東京大学法学部から予備試験のルートで入所しました。
四大法律事務所の弁護士は留学に行くのですが、私は入所して5年ほど経った際に留学の代わりに「起業させてくれ」と言ったんですね。前代未聞かもしれませんが(笑)。
そういったお願いをしたところ「じゃあちょっとやってこい」ということで8億円もやると言われたので、じゃあやりますということで、このMNTSQという会社を創業して5年ほどになります。
本日は楽しみにしておりました。よろしくお願いします。
弁護士は想像以上に面白い
よろしくお願いします。今お話しいただいたように、留学の代わりに起業させてくれというのはなかなか聞いたことがありませんね。「起業」というあたりに、板谷さんが感じていた課題があるのかなと推察していますが、長島・大野・常松法律事務所で弁護士を勤める中で強く感じた課題があったのでしょうか。
長島・大野・常松法律事務所に入ったときに「なんて面白いんだ」って思ったんですよね。変な話ですが、「弁護士って想像してたより全然面白いじゃん」と思って。
特に事務所の空気も僕に合っていたのか、淡々とお客様にとっての最高のクオリティとは何かということをひたすら考えて、それを契約という一つのアウトプットに落とし込むという作業がめっちゃ面白いぞと。すごく楽しんで弁護士をしていました。
そうなんですね。
「しょうもないことずっとやってる」の一言に衝撃
ただ正直、「契約」に対する問題意識を感じるシーンはかなりありました。
僕たちの資本主義社会では契約がないところにビジネスはありません。契約しないとビジネスを前に進められないし、非常に重要な血液とか血管のようなものだと思うんです。他方で、契約を交わすのにめちゃくちゃ時間がかかるんだなと驚きました。
時間をかけるだけの付加価値を、ビジネスサイドは多分感じていないなと思ってしまったんですよね。
たとえば、弁護士時代、高層ビルの屋上階の、ガラス張りで丸の内全部見渡せますみたいな部屋で、クライアントの社長と膝を突き合わせて交渉してたんです。僕が契約書をめくって「この『重大な』という文言を削除させてください」と言うと、社長に「君、なんでかね?」とか言われて。長々と交渉して。めちゃくちゃ面白いんですよ。
でもある日、依頼者の事業部長の方が「社長から電話です」と言って会議室から出る瞬間、社長に報告した一言が僕の耳にも漏れ聞こえてしまって。
その方「いやー、なんかしょうもないことでずっとやってますね」と。
ふぅーっと言っていて。
それは耳に残りますね。
そうなんです。もう後ろからガーンとレンガで殴られたような、そういう衝撃で。
「契約」は本質的にアンフェアなもの
その時にしたかったビジネスは非常に社会的意義のあるビジネスだったのですが、そのビジネスを一刻も早く前に進めるのではなく、この「重大な」という文言がいるのかいらないのかっていうようなことを200か所くらいずっとやっている状態でした。
これって本当に社会に貢献できているんだろうか。時間がかかりすぎているのではないかというのが、まず一つ感じていた課題です。
時間をかけてよい契約になるならよいんですよ。でも実際はそうではない。そもそも契約というのは本質的にフェアじゃないなと僕は思っています。
なるほど。
締結までに時間がかかるし、結果的に締結されるものはフェアじゃない。
契約というものは本来は信頼関係の表現であるにもかかわらず、一体正しいことなのだろうかというのが辛い部分でした。
法律に限らないかもしれませんが、専門性の非常に高い領域には情報の非対称性がありますよね。持っているところは情報をめちゃくちゃ持っているといいますか。ベンチャーのスタートアップの経営者や若い経営者が、大手企業と何かで提携するような時は、経験もリーガルの専門性も何もない中ではもう「言われた通りにお願いします」となってしまいますよね。これがフェアではないということでしょうか。
そうです。本当にそう思います。
契約というのは約束をするためのツールですから、ある意味もっと無色透明で、誰もが一瞬で通り過ぎることができて、そこでつまずくことがあってはいけないものだと僕は思っているんですよ。
テクノロジーならそれが実現できるんじゃないかという仮説をもって、僕はこのMNTSQという会社を始めました。
目の前の案件だけフェアにしても解決にはならない

「契約の本質的な『アンフェア』をなくしたい」と語る板谷さんは、常に笑顔だ。
フェアではないという部分への課題感をお持ちだったということですが、たとえばリーガルテック企業に入社するだとか、他にも解決手段はあると思います。なぜご自身で起業しようと思ったのですか?
僕自身は弁護士生活が本当に楽しかったのですが、やはりアンフェアさや契約にすごく時間がかかるという課題は、僕が一人の弁護士として目の前の契約だけどうにかしようとしても本質的には解決できません。
日本では年間5億件ほど契約が締結されているらしいんですね。そうなると僕が1件契約を作っている間にもう数百万件契約ができているわけです。
それって広い海からコップ一杯分の海水をすくって、きれいな水に蒸留して戻したら、また海水に戻っちゃうみたいな。「これなんだ?」みたいな(笑)。
はい、はい(笑)。
すべての合意をフェアにする
これをAIの文脈で考え直してみると、「ガーベージイン・ガーベージアウト」といって「ゴミを入れてもゴミしか出てこない」。つまり、学習用のデータの質が低いとまともなAIにならないんですね。
いつか契約交渉の簡単な部分のプレイヤーが人間からAIに移っていくとしたら、そのAIがダメダメな教師から教わったダメダメなAIではなくて、長島・大野・常松法律事務所のような最高のクオリティやノウハウをAIが再現できるようにしたい。
そのための承継の「ハブ」に自分がならないといけないなと思ったんです。ちょっと大げさな話ですけどね。
最高品質のAIを使わなければ、人間からテクノロジーにプレイヤーが変わっても合意がフェアになりませんから。
貴社の「すべての合意をフェアにする」というビジョンは、まさにそこに出発点があるのですか?
そうです。
目の前の合意ひとつだけをよくする、あるいは交渉に勝たせるということであれば僕は事務所で弁護士をしていればよかったので。
個々の企業に眠るナレッジを活用する
そういった世界を実現するために、どのようなプロダクトを今展開されているのでしょうか。
先ほど、フェアな契約のための長島・大野・常松法律事務所のノウハウやナレッジが必要と申し上げました。
我々のプロダクトのコアコンセプトは、創業以来ずっと「ナレッジマネジメント」なんです。だれもが最高品質のナレッジにアクセスできる世界を作ろうというのが、我々のコンセプト。
5年前の「黎明期」と言われていたころのリーガルテックは「AIレビュー」というものが非常に流行っていました。これは定型的な契約に対して、定型的なリスクポイントをすべて指摘するというサービスでした。これはこれで素晴らしいサービスだと思ってはいます。
しかし長島・大野・常松法律事務所のナレッジと同じように、実は企業ごとにベストプラクティスが蓄積されているんですよね。日本の各社ごとに最高のナレッジがありますから、これらを誰でもうまく扱えるような形に変えたかったんです。
個々の企業のすべてのナレッジと、長島・大野・常松法律事務所なり四大法律事務所なりのナレッジを融合させて、そのうちベストなものに誰もがアクセスできるデータベースを作ることが、僕が最初にやりたかったことです。
MNTSQは「プラットフォーム」を目指している
次に気づくのは、ナレッジのデータベースを作るなら、そもそも業務システムが全部統合されなければいけないよね、ということです。
やり取りはメールで、案件管理はエクセルで、他にもストレージがあって、電子契約も別にあって、契約管理はまた別の仕組みがありますというように業務システムがバラバラだと、結局データもバラバラになってしまうんです。
それならばもう契約の作成も案件の受付もアサインもレビューも管理も、すべてひとつのソフトウェアでできるようにすれば、ナレッジが全部一か所に集まるじゃないかと。これがCLM(Contract Lifecycle Management = 契約のライフサイクルマネジメント)というコンセプト。一気通貫ですべてを実行するということですね。
これをやるぞとなったのが2年前です。さらにそこから、ナレッジが貯まって法務部の業務はMNTSQ一本で大丈夫となったら、法務部から出て事業部門だぞと。事業部門のように法律のリテラシーが高くない部署でも、契約を作って交渉できるようにしようというのが次のチャレンジです。
どうしても「いわゆるリーガルテック」ということで一括りにされがちだと思うのですが、一気通貫で完結するという部分がポイントだということでしょうか。
そうですね。
電子契約やAIレビューというものは、さまざまな業務からワンポイントを行うサービスが日本では多いのですが、MNTSQが目指しているのはそれだけで業務が完結するプラットフォームです。
大企業への導入、言うは易し行うは難し
大企業からMNTSQを導入していくことで、日本企業のノウハウがどんどんMNTSQに集まってきます。
これをあえてドライにビジネス的に言えば、先行者利益が一番高い組織からデータを集めるというのが我々の戦略ですね。
なるほど。その戦略には非常に納得感がある一方で、非常に難しかったのではないでしょうか。
いやあ、難しかったですよ。
トヨタなど大手のグローバルメーカーやメガバンクなどに導入されていますが、導入企業へも板谷さんが営業されたのでしょうか。
そうですね、僕もかなり営業に出ました。
現在、法務部員が30名以上いるようなメガクラスの企業さまのシェアが40%ほどあります。ドミナント戦略に近くなってきましたが、「大企業から導入していく」というのは、言うは易し行うはめちゃくちゃ難しです。
まあ難しいんですが、ここはやはり法務領域の特殊性として、長島・大野・常松法律事務所というブランドがめちゃくちゃ効いたところでもありました。
「長島・大野・常松ブランド」が信頼を勝ち取る助けに
結局、なぜベンチャー企業が大企業に営業できないかというと、与信がないんですよね。信頼されないわけです。
それはそうですよね。
自分たちの大事な契約データを、こんな「MNTSQ」とか読み方もよくわからないような会社に預けていいのかって必ずなるわけです。
でもそこで「長島・大野・常松法律事務所の板谷です。長島・大野・常松法律事務所と一緒に法務をこういう風に変えていきたいと思っています。だからこのチャレンジを一緒にやっていってくれませんか」と言うと、部長の方でも「ああそうなんだ、こういう風に業界が変わっていくんだね」とすごく賛同していただけました。
これはあまり再現性がないというか、ユニークな戦略だったかなと思います。
業界ではライバルでも志は同じ

「四大法律事務所の看板」が営業の大きな武器になったという。
さっそくですが、西村あさひ法律事務所との戦略的協業についてお聞きします。板谷さま自身が長島・大野・常松法律事務所のご出身ということで「まさか西村あさひ法律事務所と協業されるとは」という印象です。協業にあたって大変だったことや、それでも成し遂げたかった板谷さまの思いをお聞かせください。
もうめちゃくちゃ大変でしたね。
ただ四大法律事務所同士、世の中の法務をもっと良くしていこうというモチベーションや、ノウハウは共通しているんです。
海外のリーガルテックの品質にも負けないサービスを作らなければいけませんし、それをもって日本の国際的な法務競争力を上げていかなければ、日本の法務業界そのものがどんどん尻すぼみになってしまいます。
だから最高のテクノロジーを一緒に作って、オープンなプラットフォームとして手を組もうという話になっていきました。
でも本当にたくさんの方から「まさか」と言われましたね。
大げさかもしれませんが、海外を見たときに「チーム日本」として共通の課題感や問題意識があったということでしょうか?
おっしゃる通りです。
トップローファームのマネジメントの方ともなるとやはり非常に視座が高く、テクノロジーに対する感度も高いので、私自身もお話をしていてすごく刺激を受けました。
学ぶところも多いですし、ある意味その方々の思いを我々が受け継いで、しっかりとよいプロダクトを作ろうと身が引き締まる思いがしますね。
法務人材は「文書を作る人」ではなくなる
リーガルテックがどんどん成長してよいサービス・よいプロダクトができることで、弁護士や法務人材の価値が変わっていくと思います。このことについて、板谷さまはどのようにお考えでしょうか。
AIは間違いなくまだまだ進化していきます。
ただ本質的にAIが統計技術であることは変わりません。いろいろな個々の事例から「統計的に標準なものはこうだよ」というのがAI技術です。
ここで面白いのは、すべての取引は必ずどこかしらユニークなものだということですね。完全に標準的なビジネスだとしたら利益はあげられないので、何かしら「ゆらぎ」があるんですよ。
法務でも標準的でプレーンな契約を作るところはAIに任せつつ、ビジネスを進めようとしている事業部ともっと深くコラボレーションをすることが求められています。
そうすることで、この事業で何をしたいかとか、どんなリスクは取ってよくてどんなリスクは取っちゃいけないかといったことが分かってくる。
「この事業部の皆さんがやりたいことを実現するために、実はこのリスクはとってもいいですね」とか、法務人材はビジネスごとのユニークネスにもっと寄り添うようになっていくと思います。
これまでの法務は、書類のフォントサイズを10.5に直して、明朝体に変えて、インデントを直して……というように文書を作る仕事でした。でもこれからは、事業部の横に並んで事業を作る人になっていくと思うんです。
これってやっぱり面白いことだと思うんですよね。
面白いですね。
そこに前向きになれるかどうかが、ひょっとしたら法務人材の分水嶺になるかもしれないなと思うときはありますね。
キャリアも一緒だなと思います。AIが最適な仕事を提案してくれるような世の中にこれからどんどんなっていくと思うのですが、全く同じ人生、人、キャリアというのは絶対にありえません。どこかしらにユニークな「ゆらぎ」があるというのは同様ですし、そのご支援をするという業務には、きっとAIに取って代わられない部分が残っているのでしょうね。
まさに一緒ですよね。
レジュメを見て客観的に「この人はこういう企業に行ったらいいんじゃないか」ということではない。
その方の人生観なりライフストーリーに応じて、「実はこの人はこういう企業に行くとハッピーなんじゃないか」と提案するのがリクルーターとしての価値だと思うと、めちゃくちゃ納得感があります。
一番の課題は「医者の不養生」

より強いMNTSQとなるために、必要な人材を採用したいと意気込む。
「すべての合意をフェアにする」というビジョンを実現していくにあたって、現在の課題はどのようなことでしょうか?
我々の「すべての合意をフェアにする」というビジョンは、世の中にあるありとあらゆる契約という約束事を、テクノロジーの力ですべてフェアにしたいということです。
契約というものの小難しさにだまされずに、誰もが本当に納得した状態で合意することができる世界を実現したいと。
そのための「座組」として長島・大野・常松法律事務所や西村あさひ法律事務所にご支援をいただき、トヨタさまのようなお客様がたくさんついてきてくださっているという状況です。
良くも悪くも我々はここ2年ほどでかなり急激に成長してしまったという面があります。「医者の不養生」で恥ずかしい話なのですが、現在100人の社員がいるのに実は法務の専任者がいません。
それはちょっと驚きですね。
これはだいぶまずい。
弊社はたとえばお客様との対面のコンサルタントだとか、プロダクトマネージャーだとか、法務人材がいろんなところにいるんですよ。
これまでは私も含め、彼らが横目で法務も見ながらなんとかしてきたのですが、もはやそんなことをしていていい規模ではないので……。
ギリギリなんとかしてきたという。
そうですね。
最後の最後は僕も見るからなんとかなるかなと思っていたんですが、法務の専任の方が1人入ってきて「MNTSQの法務は任せろ」と言っていただけたらだいぶ強くなるはずです。
ビジネスをより成長させて、ビジョンとミッションをつなげていくための人手が足りていないと。
おっしゃる通りです。
我々はよいプロダクトが作れると思っていますし、サービスを売ってサクセスする力も非常に高いと思っています。実はまだ解約されたことが一度もないんですよ。
すごいことですよね。
すごいですよね(笑)。
でもやはりそれを支える法務・採用といった部分は、より強化していかなければいけないと思います。
「テクノロジーで業界をどう変えるか」の面白さが味わえる
MNTSQさまの法務は、一般的な事業会社の法務よりも面白そうですよね。
正直、めちゃくちゃ面白いと思いますよ!
業界がみるみるうちに変わっていくんです。
法律事務所だけではなくて、法務部長クラスの方が話す内容やテクノロジーに期待されること、さらにはテクノロジーができることも変わっていきます。
大規模言語モデルなんかはまさにそうですが、どんどんテクノロジーが増えていきます。
それらを使って業界をどう変えていくかという、この肌触りに勝る面白さは多分ないんじゃないでしょうか。法務の方から見たら、本当にめちゃくちゃ面白いのではないかと。
また面白さだけではなくて、法務人材がリスペクトされやすい社内の状況もあります。
お客様と向き合う際も法務の話をしますし、プロダクトにしても当然法務のプロダクトですから、法務の専門家がとても貴重なんです。
「お客様にこんなこと言われたんだけど実際どうなの、●●さん?」って聞きたいんですよ。「こんなプロダクト作ってみたいんだけど、●●さんの意見ちょうだい」って言いたいんですよね。
いわゆるバックオフィス的な法務だけではなくて、もっとビジネスサイド、いわゆる「Go to market」に関わっていくことができます。
このようにお客様にも関わるし、プロダクトにも関わるし、法務として仕事もするので絶対に他社ではできない経験ができるはずです。だからめちゃくちゃ面白いと思うんですよね。
テクノロジーへの感度が法務部の明暗を分ける時代になった
そうですね、プレゼンスがとても高いと思います。私たちもクライアントさまとお話をしていても社内プレゼンスが高くない法務部がたくさんあるように感じます。それと比べると、MNTSQさまは非常に魅力的な環境ではないでしょうか。
これまでは法務部ごとの差がつきにくい環境でした。
しかしテクノロジーが出てきたことによって、テクノロジーを導入する先進性や使いこなす力に応じて、ある種「よい法務部」と「ちょっと伸び悩む法務部」が明確になってきたように思います。
さらに法務部人材市場の流動性が上がっているので、人が流れて行ってしまう。新しく採用することが非常に難しいので、今は各社の法務部の危機意識がグングン高まっています。
だからお話をすると「このままじゃまずい」という熱量が非常に高いんですよね。
これも面白いところだなと思います。
「自由と責任」の文化を受け入れられるか
逆に貴社のカルチャー的な部分で、「こういう方にはマッチしにくいよ」という部分はありますか?
我々の社内は一言で言うと「自由と責任」の文化です。
自由とは「その人のポテンシャルや能力が十全に実現されている状態」と定義しています。
この「自由」を発揮できる環境を会社としてはお渡しするので、「すべての合意をフェアにする」というビジョンに向かって最大限を尽くしてくれということですね。
社員一人ひとりに裁量と情報とコラボレーションのための人間関係を渡していって、「あとはよろしく!」というような。そういう文化です。こういう文化だと明確に合わないタイプが出てきます。
ひとつは受動的な方ですね。
もちろん「僕、何すればよいですか」と聞いていただいてもいいんですよ。でもMNTSQはまだやはりベンチャービジネスであって、個人の職域を明確に定義できず、グレーな部分が残っています。
その中で「自分は今なにをすれば一番MNTSQをビジョンに近づけられるんだろう」ということを主体的に考えて仕事できる方が、合っていると思いますね。
「自分、浮いてる?」くらいがちょうどいい
もうひとつはセクショナリスティックな方です。
「法務としてはこうです。以上」という言い方は法務の世界ではまかり通りやすいのですが、ベンチャービジネスではおしまいなんです。
ビジネスサイドやプロダクトサイドと一緒になって課題を解決するということが非常に重要です。
境界を超えて色々なものを吸収して問題解決できる方が、MNTSQには合っていると思います。
ひょっとしたら、法務部にいても自身の職域以外にも積極的に手を伸ばす、「自分ちょっと浮いてるかもな……」と感じるぐらいの方が合うのかもしれません(笑)。
また、リーガルテック企業でさまざまなオペレーション業務の経験を積むと、法務部門に戻った時に「法務部のオペレーションをどうしよう」だとか「法務部においてテクノロジーをどう活用していきましょうか」といった、より視座の高い議論を自分がリードできるようになります。
ですから、法務部の経験はリーガルテック企業で活きますし、リーガルテック企業の経験は法務部で活きると思いますね。
MNTSQは自分たちが業界を動かしていく面白さを肌で感じられる会社

エントランスにて
非常に面白いお話が聞けました。最後にキャリアの情報収集をしているリーガルパーソンの方に対し、板谷さまからメッセージをお願いします。
楽しめる方ならこれ以上ないくらい面白いんじゃないかなと思います。
自分たちの業界がどんどん変わっていくこと、それを自分たちが動かしていく面白さがありますよ。
その中で自分も伝統的な法務部らしさから、もっとコラボレーティブに、もっとプロアクティブに、もっとビジネスに近いところで業務をしていくこと。
業界も変わる、自分も変わる、その肌感覚というか肌ざわりみたいなものを味わい尽くせるような場所なんじゃないかなと思っています。
血気盛んに面白いことをやるぞという法務の方にめっちゃオススメです。
ぜひ一緒に仕事をしましょう!
前編:「すべての合意をフェアにする」トヨタ等大企業が導入
後編:西村あさひ法律事務所との戦略的協業を実現|MNTSQが考えるこれからの法務人材

Recommend
おすすめ記事
-

- 事務所を知る
クライアントのビジネス成長に真に貢献できる弁護士へ
弁護士法人スフィア東京 弁護士、日本プロ野球(NPB)選手会公認選手代理人
久世 圭之介
- M&A
- グローバル
- 若手弁護士
- 企業法務
-
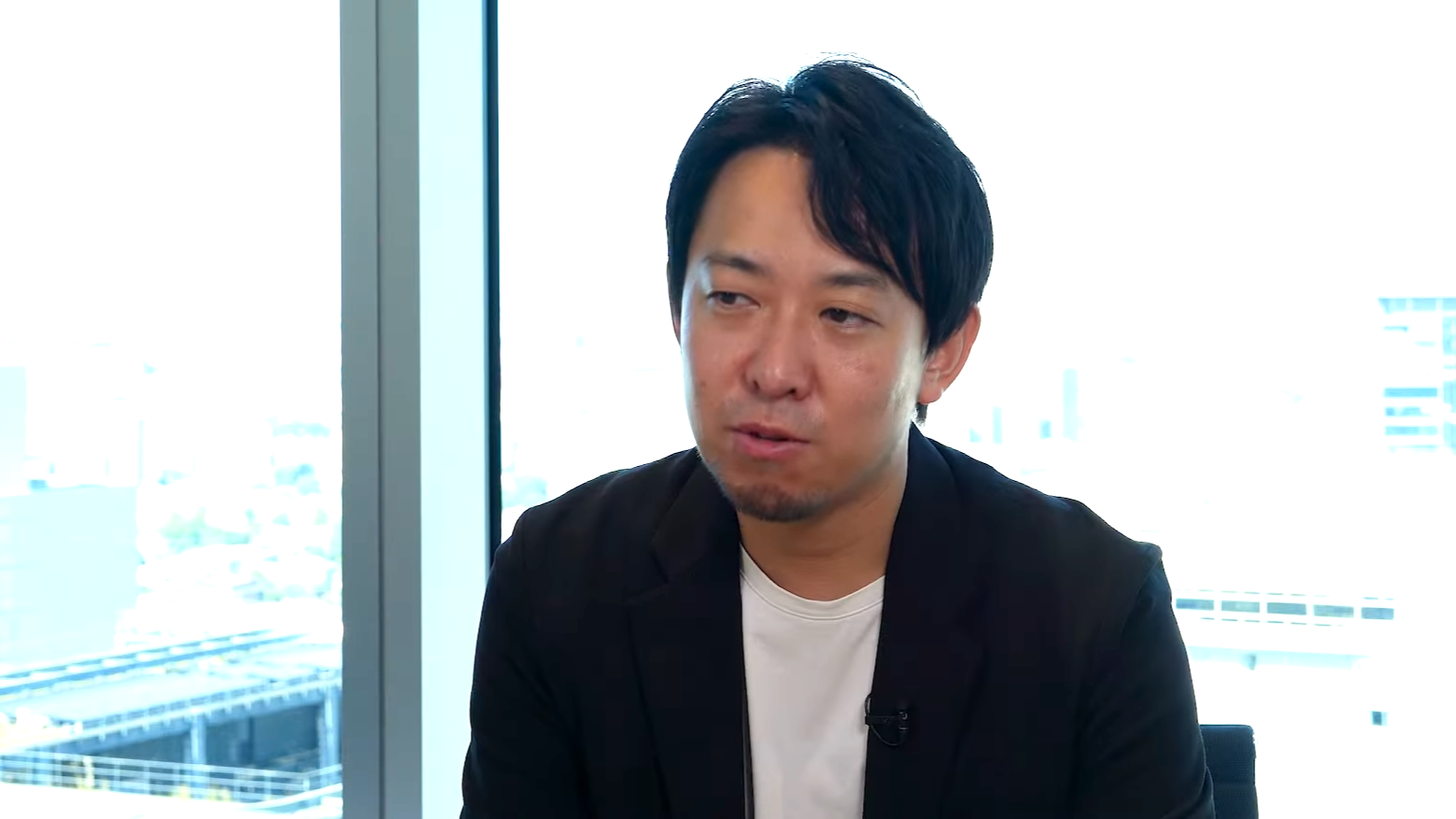
- 法務部インサイド
法務のスペシャリストの存在が、事業成長の力になる
レバレジーズ株式会社 執行役員
森口 敬
- M&A
- 企業内弁護士
- スタートアップ
- 企業法務
-

- キャリア羅針盤
人事労務問題の専門性を高められる杜若経営法律事務所
杜若経営法律事務所 所属弁護士
中村 景子
- 社員弁護士
- 労務問題
- 一般民事
- 若手弁護士
- 企業法務
-

- トップに訊く
四大法律事務所弁護士が選んだLegalOn Technologiesでの「法務開発」という道
株式会社LegalOn Technologies 執行役員 CCO
奥村 友宏
- 留学
- SaaS
- リーガルテック
- 企業内弁護士
- 四大法律事務所
- スタートアップ
-

- キャリア羅針盤
四大法律事務所から独立 若手弁護士のキャリア戦略
ホウガイド法律事務所 代表弁護士
福澤 寛人
- 出向
- 企業内弁護士
- 若手弁護士
- 四大法律事務所
- 企業法務
-

- インハウスの実態
自分の仕事が「スタンダード」になる モビリティ業界をリードするパーク24法務が取り組む「正解のない課題」
株式会社パーク24 グループ法務・知的財産部 次長
堀 真知子
- コンプライアンス
- 企業内弁護士




