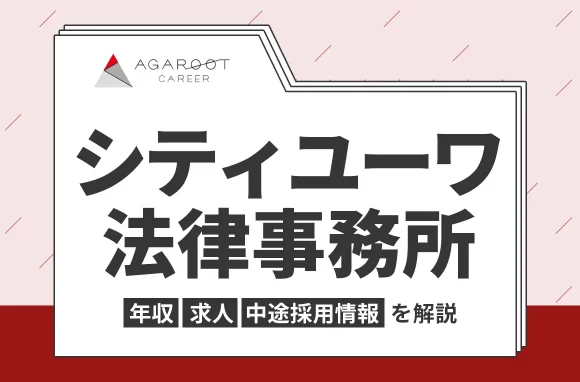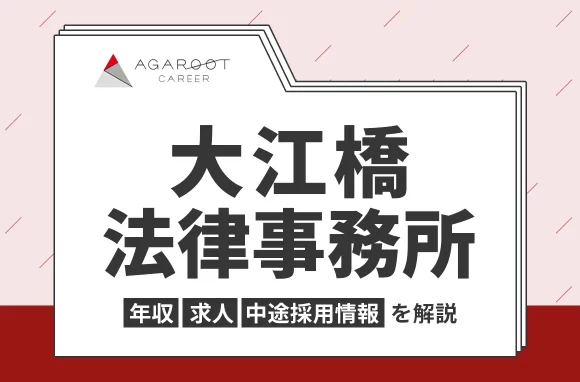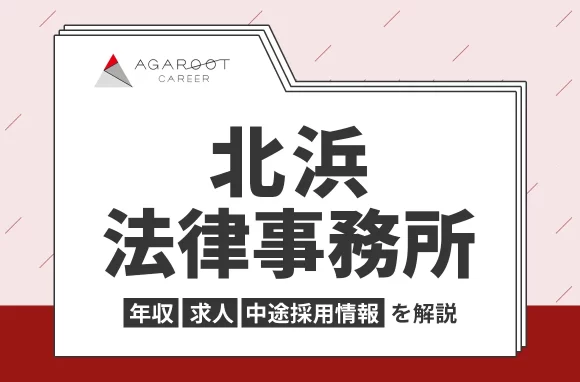弁護士が独立するメリットと失敗しないために考えるべきこと
- 更新日:2024.12.26
弁護士の中には独立を目標として活動している方もいるでしょう。
弁護士として活動していると他人から独立を勧められたり、同期の弁護士から共同独立の誘いを受けたりすることもあると思います。
この記事では弁護士が独立するメリットとデメリットや弁護士が独立する前に考えるべきことなど、弁護士が独立する際に参考となる事項を解説します。
→ 弁護士の求人一覧はこちら
PEファンド、有名企業、事務所などの アガルートキャリアは弁護士専門の転職エージェントです。弊社独自の求人をご経歴に応じて個別に紹介しております。求人の情報収集をお考えの方はお気軽にメールマガジンにご登録ください。
非公開求人を最速で受け取れるメルマガ配信中
INDEX
弁護士が独立するメリットとデメリット
まず弁護士が独立するメリットとデメリットを挙げていきます。
弁護士が独立する方法には弁護士1人の場合と複数の弁護士による共同の場合がありますが、以下では特に1人で独立する場合に該当するものを挙げます。
メリット
弁護士が独立するメリットは、以下のものが挙げられます。
- 事務所の場所を選ぶことができる
- 受任する事件を選ぶことができる
- 業務スタイル(業務時間や曜日など)を選ぶことができる
- 自分のスタイルで事件処理をすることができる
- 収入が増える可能性がある
デメリット
弁護士が独立するデメリットは、以下のものが挙げられます。
- 独立するための初期費用が掛かる
- 事務所の経費を負担する必要がある
- 事件の依頼を受けるための営業に割く時間が増える
- 事件処理の相談をする弁護士がいない
- 収入が減ったり不安定になったりする可能性がある
▶弁護士のキャリアパスをリーガル専門の転職エージェントが解説
弁護士が独立する前に考えるべきこと
弁護士が独立する前に考えるべきこととして、
- 独立のタイミングと平均年齢
- 資金面
- 売上予測
- 事務所の場所
- 事務職員の採用
の5点を解説します。
弁護士が独立する状況としては、法律事務所に所属している場合と企業勤務弁護士(インハウスローヤー)の場合が考えられますが、ここでは特に法律事務所に所属している場合に考えるべきことを中心に挙げています。
独立のタイミングと平均年齢
最初に弁護士が独立する場合の独立のタイミングと平均年齢についてです。
弁護士が独立する場合のタイミングと平均年齢は様々です。
日本弁護士連合会の「統計・調査(弁護士白書等)」によると、弁護士全体のうち経営者弁護士の割合は以下となっています。
- 弁護士経験5年未満:13.9%
- 弁護士経験5年以上10年未満:51.3%
- 弁護士経験10年以上15年未満:75.9%
- 弁護士経験15年以上20年未満:83.3%
- 弁護士経験20年以上25年未満:86.7%
- 弁護士経験25年以上30年未満:93.2%
これより「弁護士が独立するタイミングは弁護士経験5年前後の時期が最も多い」と言えます。
弁護士が独立する年齢に関しては、20代半ばで弁護士になれば数年勤務弁護士を経験した後でも20代で独立となりますし、50代で弁護士になれば即独しても独立は50代です。
特に、司法制度改革によって法科大学院制度となって以降、社会人経験者や30代以降の方が弁護士になるようになってからは即独する弁護士や弁護士活動1~2年という比較的早いタイミングで独立するケースが増えた傾向にあるようです。
もっとも弁護士の独立のタイミングを弁護士経験5年とし、司法試験合格の平均年齢が約29歳(参考:法務省「令和元年司法試験の結果について」)であることから「弁護士が独立する平均年齢は35歳前後」と言えるでしょう。
法律事務所に所属している弁護士にとって、現在担当している事件の処理や依頼者をどうするのかという点は独立のタイミングに影響する場合があります。
独立しても事件や依頼者を担当できるかどうかは事務所や依頼者の意向によりますので、独立を決めた場合は早めに準備をする必要があります。
資金面
弁護士の独立をする・しないの判断において、大きな問題となるのが資金面でしょう。
資金面で特に考慮すべき内容として、
- 開業資金
- 資金調達の方法
の2つがあります。
開業資金
弁護士が独立する場合の開業資金は「最低でも200万円は掛かる」と考えておきましょう。
これは事務所を賃貸した場合に係る敷金や事務所設備といったあくまで初期費用です。
したがって、独立直後は相談や依頼が少ない傾向にあることを踏まえると独立後数か月~6か月程度の運転資金として別途200~300万円程度の余剰資金は必要と言えます。
なお、弁護士の独立形態には弁護士1人の場合と複数の弁護士による共同の場合がありますが、「最低でも200万円は掛かる」という試算は最もオーソドックスな形態といえる弁護士1人の場合についての額です。
参考:東京 独立開業 独立開業 東弁版 第2版 33頁「事務所全体・初期費用・中間値」
資金調達の方法
資金調達の方法としては、
- 金融機関(銀行や日本政策金融公庫など)や公的機関(地方自治体や弁護士共同組合など)からの借入れ
- 親族や知人から借入れ
- 自己資金
などが考えられます。
金融機関や公的機関からの借入れは利息が掛かる点が負担となります。
したがって自己資金を貯めてから独立する方法が最も負担の少ない資金調達の方法です。
親族や知人から借入れが出来るようであれば、基本的には利息が掛からないでしょうし返済方法も融通が利きやすいため、比較的負担の少ない資金調達の方法と言えます。
売上予測
売上予測は、弁護士に限らずあらゆる事業者が独立する場合に必要です。
絶対的に必要な売上は、毎月の固定費用を超える額です。
毎月の固定費用を超える額の売上がなければ事務所を継続できません。
したがって、売上予測を立てることが事務所の場所(賃料)や事務員の採用の有無や人数といった独立の方法に影響します。
売上予測は、
- 顧問料×顧問先の数
- 着手金×受任事件の数
で大まかに算出します。
例えば、顧問料月3万円で顧問先10件、着手金20万円で受任事件月4件(1週間に1件)だとすると、1か月の売上予測は110万円になります。
すなわち、独立の際に顧問先の数が多ければ多い程事務所の経営は安定します。
事務所の固定費用が毎月40万円とした場合、弁護士の収入は単純計算で月70万円となり年収にすると840万円になります。
※事務所の固定費参考:東京 独立開業 独立開業 東弁版 第2版:33頁「事務所全体・運営費用・中間値」
事務所の場所
続いて、事務所の場所です。
弁護士が独立する場合、
- 弁護士会や裁判所の近く
- 交通の便が良い場所
- 自宅兼事務所
等が事務所の場所の主な候補地となります。
事務所の場所が弁護士会や裁判所の近くであれば、弁護士活動における移動コストを軽減できます。
交通の便が良い場所であれば、相談や受任の数が増えることを期待できます。
自宅兼事務所であれば、賃料や光熱費等の固定費用を軽減できます。
事務所の場所は、相談内容や依頼者の層にも影響しますので賃料や移動に掛かるコスト等を考慮して決める必要があります。
事務職員の採用
弁護士が独立する場合の事務職員の採用について解説します。
事務職員の採用にはメリットとデメリットがありますので「段階的採用」が1つのモデルケースです。
弁護士が独立する場合に事務職員を採用するメリットは、
- 独立準備の負担が軽減する
- 外出時の電話や来客対応が可能
- 郵便物の受取や発送等、弁護士自身がやらなくてもできる業務をお願いできる
- 事務職員がいるだけで相談者や依頼者等、対外的信頼が上がる
があります。デメリットとしては、
- 人件費が掛かる
- 雇用の維持に関する問題
があります。
事務職員を採用するメリットとデメリットを踏まえると、何らかの形で事務職員は採用しつつ、人件費をいかに抑えるかがポイントとなります。
そこで、独立直後の段階では、
- アルバイトとして採用する
- 親族や知人に頼む
- 時間や日数を制限する
といった方法で人件費を抑え、売上が伸び収入が安定してきたら、
- 正社員として雇用する
- 事務職員を増やす
- 時間や日数を増やす
といった段階的採用を行うのも選択肢の1つです。
弁護士独立の成功例
弁護士独立の成功例は独立後半年以内に黒字化し、以降黒字経営となることです。
独立後数カ月間の赤字経営は弁護士に限らずやむを得ません。
したがって、独立の際に
- 顧問先(顧問収入)を出来るだけ多くする
- 余剰資金を出来るだけ確保する
といった対策をとることが理想です。
弁護士独立の失敗例
弁護士独立の失敗例は独立後黒字化できずに廃業することです。
独立時の費用を掛けすぎると黒字化する前に資金が尽きてしまいます。
したがって、独立の際に
- 家賃
- 人件費
- 事務所設備費や広告費
は、できるだけ抑えることを意識しましょう。
弁護士独立に伴う手続き
弁護士事務所開業に伴う手続きは細かいため、今回は
- 独立計画
- 退所準備・手続
- 独立準備・手続き
の順に大まかな流れを解説します。
独立計画
まずは、独立の有無を含め、独立計画を検討します。
- 弁護士1人か複数人か
- 事務所の場所はどこにするのか
- 予算の見積もり
- 資金準備 など
できるだけ具体的に検討しましょう。
特に事務所の場所は地元に帰る等により所属弁護士会の変更を伴う場合、新たな所属弁護士会の入会資格や手続きも確認する必要があります。
退所準備・手続き
独立計画を定めたら、所属法律事務所(勤務先)の退所準備・手続きをします。
弁護士事務所の勤務年数が長い程抱えている事件や依頼者が増えるので、退所まで数か月から1年程度の期間は要するつもりで所属法律事務所の代表弁護士等に退所の相談をしましょう。
退所の時期が決まれば、独立後も取引をする依頼者や取引先等には独立する旨の報告と共に新たな連絡先を報告します。
インハウスローヤーの場合、個別の事件や依頼者を抱えているケースは少ないので法律事務所所属の弁護士より退所の準備・手続きは容易と言えます。
独立準備・手続き
退所の時期が決まれば、
- 事務所の賃貸借契約
- 事務所設備の購入やリース契約
- 事務職員の採用
- 税金や保険手続き
- 弁護士会への届出
- 事務所HPの作成
などを独立の時期に合わせて準備・手続きしましょう。
まとめ
弁護士の独立にはメリットがある反面、デメリットもあります。
弁護士の職務の責任の大きさからすると廃業という結末は出来るだけ回避すべきですので、デメリットには十分配慮すべきでしょう。
独立に際しては所属する弁護士会が作成しているマニュアルを確認したり、独立した弁護士の先輩や知り合いがいる場合には注意点を確認したりする等、慎重に準備・手続きを進めましょう。
弁護士の転職でアガルートキャリアを活用するメリット
アガルートキャリアは、弁護士や法務などのリーガル領域を中心とした管理部門専門の転職エージェントです。
多くの司法試験合格者を輩出している「アガルートアカデミー」のグループ会社が運営しています。
リーガル領域の人材の資格取得~キャリア形成までサポートを行っています。
転職活動において、弊社を活用いただくメリットをご紹介します。
独自の求人をご紹介可能
弁護士や法務などのリーガル領域に強い転職エージェントだからこそ、大手弁護士事務所、多様な弁護士事務所、国内外大手企業(メーカー、IT、商社、金融)の企業内弁護士・インハウス、スタートアップなど豊富な求人や機会をご紹介可能です。
- 大手法律事務所
- 企業内弁護士/インハウスローヤーへの転身
- スタートアップの幹部、CLOなど
- 一般民事から企業法務への転身
など経験やご希望年収、働き方など様々な要望に応じた求人をご紹介しています。
豊富な実績をもとにした書類作成・選考対策のサポート
弁護士の募集は、専門性が高く、一般的な書類作成のノウハウが適用できないこともあります。
専門性の高い職種だからこそ抑えるべきポイントやコツがあります。
そうした書類の作成や選考対策を領域専門のアドバイザーがサポートしています。
中長期のキャリアに関してもご相談ください
プロジェクトや案件の状況、求人の内容次第で転職を考えたいという方もいるでしょう。
弁護士の中途採用(大手事務所/インハウスローヤー)などはポジションが少なく、魅力的な求人ほどすぐに埋まってしまうことがあります。
すぐにではなくとも、ご希望や条件を一度面談でお伝えいただければ、ご要望にあった求人や機会を都度ご紹介します(個別連絡やメルマガ)。
相談は無料です
弊社との面談はすべて無料です。面談を行って頂いたからといって、すぐに求人に応募しなければいけないわけではありません。
ご要望やタイミングに合わせて転職活動の開始時期等もアドバイスさせて頂き支援しております。
転職活動は事前準備が成功のカギ!枠数限定で面談を行っています
納得でき、条件面でも恵まれた転職を実現するには、
- 情報収集
- 選考対策
の2つが必要不可欠です。
弊社の感覚値ですが、90%以上の方の準備が不足しています。
- 良い機会(求人)があるのにその情報にアクセスできなかった
- レジュメ、選考の準備が不足しており見送りになってしまう
といった方々を多く見てきています。
常に転職サイトを見るようなことは非常に手間ですので、弊社のような特化型エージェントをうまく活用いただければと思います。
少数精鋭の専門アドバイザーが面談を行うため、面談数は限定で行っています。
面談ご希望の方は、お早めにご相談ください。
弁護士・法務人材向けにYouTubeでも情報を発信しています
アガルートキャリアでは、You Tubeチャンネルも運営しています。
ぜひ一度ご覧いただき、転職活動を進めるうえでの情報源としてお役立てください。
PEファンド、有名企業、事務所などの アガルートキャリアは弁護士専門の転職エージェントです。弊社独自の求人をご経歴に応じて個別に紹介しております。求人の情報収集をお考えの方はお気軽にメールマガジンにご登録ください。
非公開求人を最速で受け取れるメルマガ配信中
この記事の監修者
リーガル専門コンサルタントとして、弁護士・法務人材を中心に転職支援を行う。中国発大手テクノロジー企業の日本法人にて創業メンバーとして事業開発・推進に従事。スタートアップ〜大手事業会社での事業開発、マネジメント経験を有していることから、様々な角度からの俯瞰したアドバイスを強みとする。
自身では探せない非公開求人をご提案
アガルートグループが運営する
多数の非公開求人を保有