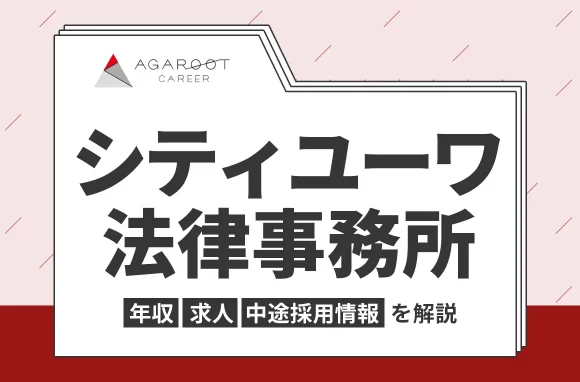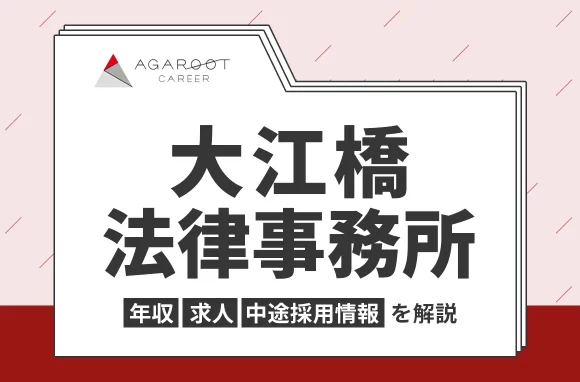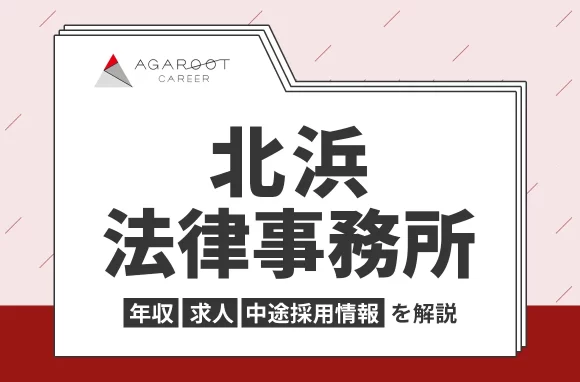士業とは語尾に「士」が付く専門的な職業の俗称
- 更新日:2024.12.26
士業とは、弁護士や司法書士など語尾に「士」が付く専門的職業のことです。
士業には様々なものがあり、弁護士や司法書士など個人の日常生活においても関わる可能性があるものから、公認会計士や弁理士など企業でないと関わることがないものもあります。
この記事では士業の意味や主な士業の業務内容を解説します。
→ 弁護士の求人一覧はこちら
PEファンド、有名企業、事務所などの アガルートキャリアは弁護士専門の転職エージェントです。弊社独自の求人をご経歴に応じて個別に紹介しております。求人の情報収集をお考えの方はお気軽にメールマガジンにご登録ください。
非公開求人を最速で受け取れるメルマガ配信中
INDEX
士業とは語尾に「士」が付くことが多い専門的な職業の俗称
士業とは弁護士や司法書士など、語尾に「士」が付く専門的職業の俗称で、サムライ業と言われることもあります。
以降で士業の意味やサムライ業といわれる由来を説明します。
「士業」の意味
士業の意味は語尾に「士」付く専門的な職業の俗称で、通常資格を必要とします。
士業の資格には国家資格と民間資格があります。
国家資格は資格の認定に加えて業務の独占性が法的に認められます(一部、業務の独占性が認められない資格もあります)。
民間資格は資格の認定や業務の独占性が法的に認められておらず、特定の分野における専門的知識を有することを証明する資格にとどまります。
サムライ業ともいわれる
士業はサムライ業とも言われます。これは「士」に「サムライ」という意味があることが由来です。
8士業の業務内容

8士業と言われる8つの士業の業務内容を解説します。
「8士業」とは、
- 弁護士
- 弁理士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 土地家屋調査士
- 海事代理士
の8つのことです。
8士業はいずれも専門的業務を対象とした国家資格です。
8士業には戸籍謄本や住民票などの公的書類を職務上請求できる権限が付与されています。
弁護士
弁護士の業務内容は、訴訟事件の代理など法律事務全般です。※1
弁護士になるには、通常、司法試験に合格し司法修習を終え入会する弁護士会を通じて日本弁護士連合会への登録が必要です。※2
弁護士は、弁護士業務についての独占性が認められています。※3
※1 弁護士法第3条1項
※2 弁護士法第4条、第9条
※3 弁護士法第72条本文
弁理士
弁理士の業務内容は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得するための手続や書類作成の代理です。※1
弁理士になるには、通常、弁理士試験に合格し日本弁理士会への登録が必要です。※2
税理士は、弁理士業務について独占性が認められています。※3
なお、弁護士は、実務修習(4か月程度)を行うことにより弁理士資格を取得でき(弁理士法第7条2号)、弁理士の業務も行うことができます。※4
※1 弁理士法第4条
※2 弁理士法第7条1号、第17条
※3 弁理士法第75条
※4 弁理士法第7条2号、弁護士法第3条2項
司法書士
司法書士の業務内容は、登記又は供託に関する手続や書類作成の代理などです。※1
認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)になると、簡易裁判所(訴額140万円以下)における訴訟手続きの代理なども行うことができます。※2
司法書士になるには、通常、司法書士試験に合格し入会する司法書士会を通じて日本司法書士連合会への登録が必要です。※3
司法書士は、司法書士業務について独占性が認められています。※4
なお、弁護士は、司法書士業務についても法律事務として行うことができます。※5
※1 司法書士法第3条第1項1号~5号
※2 司法書士法第3条第1項6~8号
※3 司法書士法第4条1号、第8条、第9条1項
※4 司法書士法第73条1項本文
※5 司法書士法第73条1項但書、弁護士法第3条1項
行政書士
行政書士の業務内容は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成代理です。※1
行政書士になるには、通常、行政書士試験に合格し入会する行政書士会を通じて日本行政書士会連合会への登録が必要です。※2
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士は、登録により行政書士になることができます。※3
行政書士は、行政書士業務について独占性が認められています。※4
なお、弁護士は、行政書士業務についても法律事務として行うことができます。※5
※1 行政書士法第1条の2第1項
※2 行政書士法第2条1号、第6条1項
※3 行政書士法第2条2~5号
※4 行政書士法第19条1項本文
※5 行政書士法第19条1項但書、弁護士法第3条1項
税理士
税理士の業務内容は、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類の作成代理です。※1
税理士になるには、通常、税理士試験に合格及び2年以上の実務経験を経て日本税理士連合会への登録が必要です。※2
弁護士及び公認会計士は、登録により税理士になることができます。※3
税理士は、税理士業務について独占性が認められています。※4
なお、弁護士は、所属弁護士会を通じて国税局長に通知することにより税理士業務を行うことができます。※5
※1 税理士法第2条、同条の2
※2 税理士法第3条1項1号、18条
※3 税理士法第3条1項3号、4号
※4 税理士法第52条
※5 税理士法第51条1項
社会保険労務士(社労士)
社労士の業務内容は、労働社会保険業務に関する行政機関に提出する書類や申請書の作成代理等です。※1
社労士になるには、通常社会保険労務士試験に合格及び2年以上の実務経験を経て社会保険労務士連合会への登録が必要です。※2
弁護士は、登録により社労士になることができます。※3
社労士は、社労士業務について独占性が認められています。※4
なお、弁護士は、社労士業務について法律事務として行うことができます。※5
※1 社会保険労務士法第2条、同条の2
※2 社会保険労務士法第3条1項1号、14条の2
※3 社会保険労務士法第3条2項
※4 社会保険労務士法第27条本文
※5 社会保険労務士法第27条但書、弁護士法3条1項
土地家屋調査士
土地家屋調査士の業務内容は、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量等の代理です。※1
土地家屋調査士になるには、通常土地家屋士試験に合格し、入会する土地家屋調査士会を通じて日本土地家屋調査士会連合会への登録が必要です。※2
土地家屋調査士は、土地家屋調査士業務について独占性が認められています。※3
なお、弁護士及び司法書士は、土地家屋調査士業務の一部を行うことができます。※4
※1 土地家屋調査士法第3条1項各号
※2 土地家屋調査士法第4条1号、8条1項
※3 土地家屋調査士法第68条1項本文
※4 土地家屋調査士法第68条1項但書
海事代理士
海事代理士の業務内容は、海事に関する行政機関への申請や届出の手続や書類作成の代理等です。※1
海事代理士になるには、通常海事代理士試験に合格し、地方運輸局(国土交通省)への登録が必要です。※2
海事代理士は、海事代理士業務について独占性が認められています。※3
なお、弁護士は海事代理士業務について法律事務として行うことができ※4、司法書士・行政書士・税理士は海事代理士業務の一部を行うことができます。※5
※1 海事代理士法第1条
※2 海事代理士法第2条1号、9条
※3 海事代理士法第17条1項本文
※4 海事代理士法第17条1項但書、弁護士法第3条1項
※5 海事代理士法第17条1項但書
10士業の業務内容
続いて、10士業と言われる10の士業の業務内容を解説します。
10士業とは、先に紹介した8士業のうち海事代理士を除いた7士業に、
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 不動産鑑定士
の3士業を加えたものです。
10士業は地方公共団体が開催する士業合同相談会等の相談役になる等、中小企業や個人に関する問題と密接関連する専門家で、全て国家資格です。
既に紹介した8士業を除く3士業の業務内容を解説します。
公認会計士
公認会計士の業務内容は、個人事業主を含む企業の財務書類の監査又は証明等です。※1
公認会計士になるには、公認会計士試験に合格及び2年以上の所定業務補助経験を経て実務補習を修了し、公認会計士協会への登録が必要です。※2
公認会計士は、公認会計士業務について独占性が認められています。※3
※1 公認会計士法第2条
※2 公認会計士法第3条、17条
※3 公認会計士法47条の2
中小企業診断士
中小企業診断士の業務内容は、中小企業支援事業における経営診断や助言です。※1
中小企業診断士になるには、通常、中小企業診断士試験(第1次及び第2次)に合格し、実務補習を修了する必要があります。※2
中小企業診断士は、中小企業診断士業務について法的独占性は認められていません。
もっとも、中小企業診断士教会へ登録することで国や都道府県等が行う公的な経営支援業務に加わることができる等のメリットが得られます。
※1 中小企業支援法第13条第2項
※2 中小企業支援法第11条
不動産鑑定士
不動産鑑定士の業務内容は、不動産の鑑定評価等です。※1
不動産鑑定士になるには、不動産鑑定士試験に合格後、実務修習を修了し、不動産鑑定士協会連合会への登録が必要です。※2
不動産鑑定士は、不動産鑑定士業務について独占性が認められています。※3
※1 不動産の鑑定評価に関する法律第3条1項、2項本文
※2 不動産の鑑定評価に関する法律第4条、22条1項
※3 不動産の鑑定評価に関する法律第36条
まとめ
士業は企業や個人に生じた問題の解決に向けたアドバイス等をしてくれる専門家です。
もっとも、士業にはそれぞれ専門分野があり、他の士業ではできない業務もあります。
問題を相談しても、その士業では対応できない業務である場合や他により適切な対応ができる士業がある可能性も踏まえて相談するのが良いでしょう。
弁護士・法務人材向けにYouTubeでも情報を発信しています
アガルートキャリアでは、You Tubeチャンネルも運営しています。
ぜひ一度ご覧いただき、転職活動を進めるうえでの情報源としてお役立てください。
PEファンド、有名企業、事務所などの アガルートキャリアは弁護士専門の転職エージェントです。弊社独自の求人をご経歴に応じて個別に紹介しております。求人の情報収集をお考えの方はお気軽にメールマガジンにご登録ください。
非公開求人を最速で受け取れるメルマガ配信中
この記事の監修者
リーガル専門コンサルタントとして、弁護士・法務人材を中心に転職支援を行う。中国発大手テクノロジー企業の日本法人にて創業メンバーとして事業開発・推進に従事。スタートアップ〜大手事業会社での事業開発、マネジメント経験を有していることから、様々な角度からの俯瞰したアドバイスを強みとする。
自身では探せない非公開求人をご提案
アガルートグループが運営する
多数の非公開求人を保有