司法試験・予備試験に受かる行政法の勉強法!短答と論文それぞれ解説

行政法は何となくつかみどころがない科目という印象があり、苦手意識を持っている受験生も多いのではないでしょうか?
実際、令和4年度予備試験の短答式試験における行政法の平均点は30点中12.8点とかなり低い点数になっています。
しかし、裏を返せば、行政法で高得点を取ることができれば、他の受験生と大きな差を付けることができるということです。
そこで、本コラムでは、行政法の短答式試験・論文式試験それぞれの出題内容や勉強方法、勉強に当たっての注意点などについて解説していきます。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変
- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?
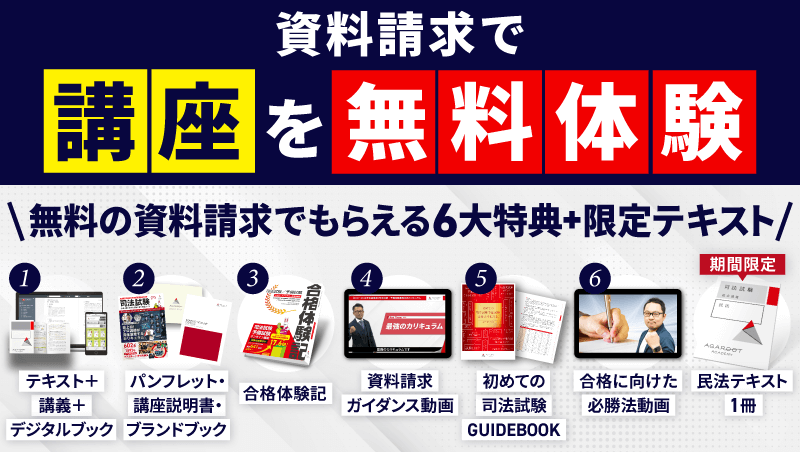
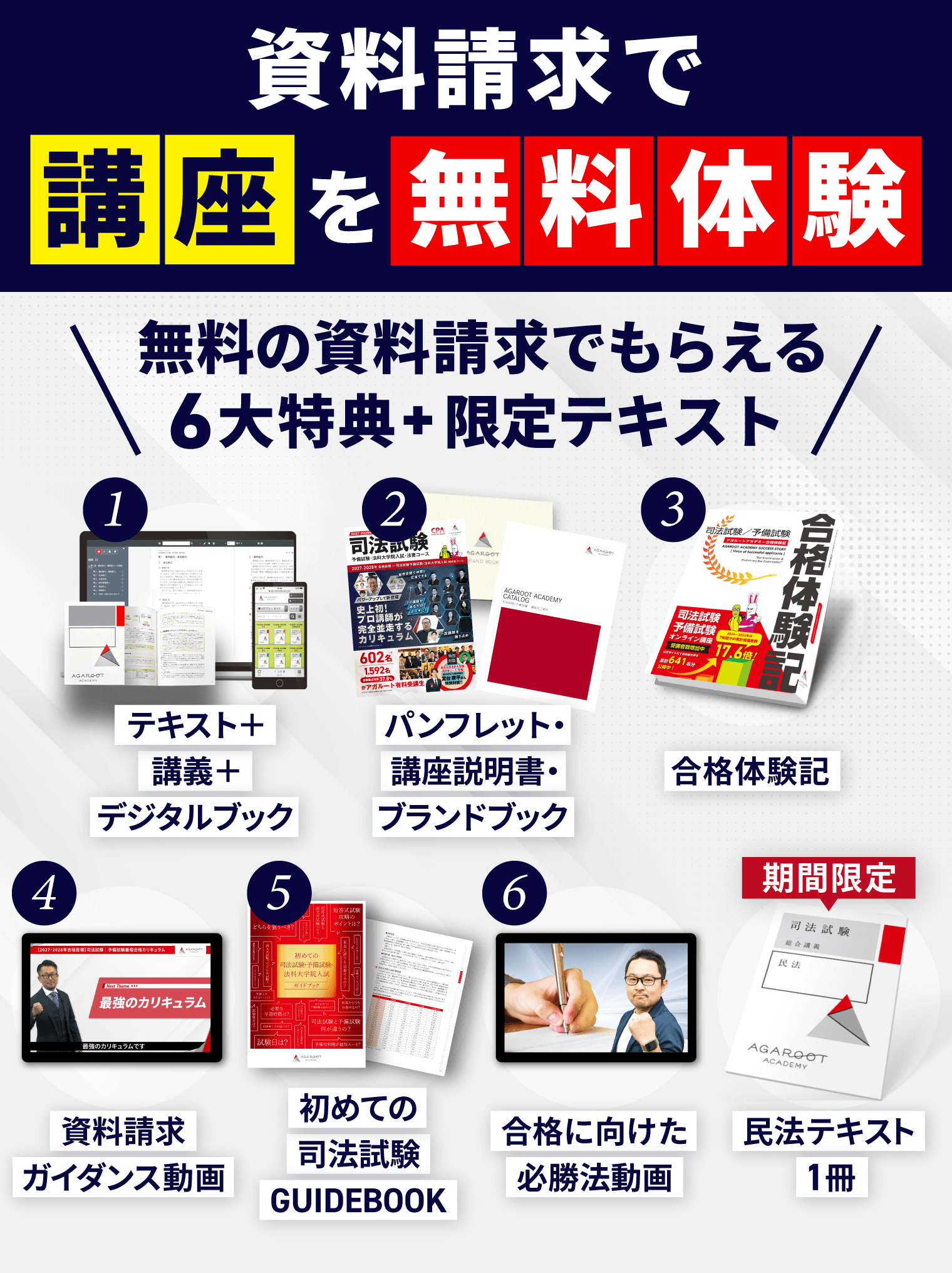
約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
司法試験・予備試験における行政法の重要性と難易度
行政法は、他の法律科目と比べて独特の性質を持っています。
多くの抽象的な概念を取り扱う上、憲法や刑法のように「行政法」という明確な法律が存在しないため、学習初期には具体的なイメージを持ちにくいと感じる受験生も多いでしょう。
さらに、行政法の問題解決には、特定の法律の条文の構造やその背後にある趣旨を深く理解し、それを基にして個別の法律を解釈する能力が求められます。
このようなアプローチは、他の法律科目ではあまり要求されない特有のものであり、行政法の学習の難易度を一層高めています。
このような背景を踏まえると、行政法を効果的に学ぶためには、この科目独自の特性や構造を理解し、それに適した学習方法を採用することが不可欠です。
一般的な法律学習の方法だけでなく、行政法特有のアプローチを習得することで、より深い理解と実践的な応用能力を身につけることができるでしょう。
短答式試験に合格するために必要な行政法の勉強法
この章では、短答式試験に合格するために必要な行政法の勉強法について下記の4点を説明します。
- 行政法の短答式試験で問われること
- 判例を比較検討し、正確な判例知識を身に付ける
- 行政手続法や行政事件訴訟法の素読を行う
- 短答プロパーの分野について集中的に勉強する
行政法の短答式試験で問われること
まず、司法試験の短答式試験においては、憲法・民法・刑法の3科目のみしか出題されないため、行政法の短答式試験はありません。
一方で、司法試験予備試験の短答式試験においては、行政法を含め法律基本7科目(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)全てが出題範囲となるため、行政法科目の対策が必要です。
行政法の短答式試験においては、判例知識を中心に、行政手続法や行政事件訴訟法などの条文知識も多く問われます。
そこで、以下では、これらの幅広い出題に対応するために必要な行政法の短答式試験の勉強方法を説明していきたいと思います。
判例を比較検討し、正確な判例知識を身に付ける
行政法の短答式試験においては、判例についての知識が非常に多く問われます。
というのも、「行政法」という名前の法律は存在しておらず、行政手続法や行政事件訴訟法などの行政に関わる法律やそれに関する判例全体が行政法科目として、1つの科目を構成しているからです。
そのため、行政法の短答式試験においては、判例知識の占める比重が他の科目と比較しても高く、特に重要となります。
また、行政法の短答式試験においては、3つの肢の正誤の組み合わせを問う形式の問題がよく出題されます。
この形式の問題の場合、3つのうち1つでも正誤を間違えてしまうと不正解になってしまうため、より正確な知識が要求されることになります。
判例知識のインプットの際におすすめの方法は、分野ごとに判例を比較して情報を整理していくことです。
行政法の場合には、処分性や原告適格などの分野ごとに問題が組まれることが多いため、分野ごとに判例を並べてみて、事案の概要や結論、結論に至る理由などを比較しながら覚えていくのがおすすめです。
行政手続法や行政事件訴訟法の素読を行う
行政法の短答式試験においては、条文知識もよく問われます。
特に、行政手続法や行政事件訴訟法については、ほぼ毎年出題されるうえ、条文が丸ごと抜き出されて正誤問題の肢になっているようなことも多いです。そのため、行政手続法や行政事件訴訟法に関しては、一度条文を素読してみることをおすすめします。
実際に、行政法の短答式試験を解いてみると、行政手続法や行政事件訴訟法の条文については、同じような箇所が何度も出題されていることが分かると思います。
それゆえ、過去問演習の際には頻出条文をピックアップし、それらの条文を特に重点的に素読するのが効率的であるといえるでしょう。
短答プロパーの分野について集中的に勉強する
行政法の短答式試験においては、行政手続法・行政事件訴訟法のほかにも、国家賠償法や行政不服審査法、行政代執行法の条文・判例知識も問われます。
これらの分野は、論文式試験にはあまり出題されないものの、短答式試験には毎年数問は必ず出題される、いわゆる短答プロパーと呼ばれる分野です。
行政手続法・行政事件訴訟法に比べると重要度は落ちるものの、問題自体はそれほど難しくない場合が多いため、きちんと対策すれば得点に結びつきやすいといえます。
短答プロパー分野については、普段の論文対策で身に付けることは難しいため、短答の直前期に集中的に勉強することをおすすめします。
択一六法などの参考書では、これらの短答プロパー知識が表に整理され、解説されていることが多いため、そうした参考書等も上手く活用すると良いでしょう。
論文式試験に合格するために必要な行政法の勉強法
この章では、論文式試験に合格するために必要な行政法の勉強法について下記4点を説明します。
- 行政法の論文式試験で問われること
- 処分性、原告適格、訴えの利益についての書き方をマスターする
- 出題趣旨・採点実感を読み込む
- 過去問演習を行い、合格者の答案を分析する
行政法の論文式試験で問われること
短答式試験とは異なり、論文式試験においては、司法試験・予備試験ともに行政法が出題されるため、どちらを受験する場合であっても、行政法科目の対策を行う必要があります。
現行の司法試験・予備試験においては、基本的に事例問題が出題されます。
行政法の論文式試験では、事例に加えて、それに関連する個別法も読み解く必要があるため、時間配分には特に気を付ける必要があります。
処分性、原告適格、訴えの利益についての書き方をマスターする
行政法の論文式試験においては、司法試験・予備試験ともに、ほぼ毎年のように処分性、原告適格、訴えの利益のいずれかの分野が出題されています。
そのため、これら3つの分野については特に重点的に対策を行う必要があります。
これらの分野には、いわゆる答案の型のようなものが存在しているため、それらの型を抑えることが、論文式試験の対策としては非常に重要になります。
例えば、処分性の有無を問う問題の場合、まずは、「処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるものをいう」というように、処分の定義を論じたうえで、①公権力性、②直接的・個別具体的な法効果性という2つの要件をそれぞれ検討していくこといなります(処分性の要件については、様々な考え方があり、3要件説や4要件説を採る人もいます)。
このように、処分性、原告適格、訴えの利益といった分野には一定の答案の型が存在しており、その処理手順をマスターすることが、行政法の論文式試験得点アップに向けた近道だといえるでしょう。
出題趣旨・採点実感を読み込む
司法試験・予備試験では、毎年試験後に、司法試験委員会から出題趣旨や採点実感というものが発表されています(予備試験では出題趣旨のみが発表されます)。
これらの出題趣旨・採点実感は、いわば司法試験委員会からのメッセージであり、これらを読み込み分析することはどの科目においても重要です。
その中でも、特に行政法については、出題趣旨・採点実感の重要性は非常に高いといえるでしょう。
前述のとおり、行政法の論文式試験では、処分性、原告適格、訴えの利益といった頻出論点が繰り返し出題されています。
また、その他にも、行政裁量に関連する問題などは頻繁に出題されているため、行政法は過去問と似たような問題が再度出題される可能性が高い科目だといえます。
そのため、行政法の論文式試験対策においては、出題趣旨や採点実感の汎用性が高く、それらを読み込むことが試験対策に直結します。
過去問演習を行い、合格者の答案を分析する
行政法の論文式試験においては、過去問演習を行うことも、もちろん重要です。
前述のとおり、行政法の場合には、出題分野がかなり限定されているため、過去問を繰り返し解くことが最も効率的な勉強方法であるといえます。
過去問演習の際には、合格者の再現答案などを合わせて読むのがおすすめです。特に、上位合格答案の場合には、処分性や原告適格などの頻出分野について、当てはめ部分の論述が非常に秀逸であることが多く、とても参考になります。
近年の行政法の論文式試験においては、問題文の中に具体的な事情が多く散りばめられており、当てはめ部分で差がつくといわれているため、合格者の再現答案を参考にして、当てはめ部分の論述力を磨いていきましょう。
行政法の勉強法においてやってはダメなこと
ここまで、司法試験・予備試験における行政法の勉強方法について説明してきました。
そこで、この章では、実際に行政法の勉強法を行う際の注意点について説明していきます。
行政法の勉強法においてやってはいけないことは、「規範を曖昧に暗記すること」、「判例の結論に安易に飛びつくこと」、「インプットに時間をとられすぎて、アウトプットをおろそかにすること」の3つです。
以下では、これら3つについて、詳しく解説します。
規範を曖昧に暗記すること
1つ目は、「規範を曖昧に暗記すること」です。
前の章でも述べた通り、行政法の試験においては、処分性や原告適格に関する問題が多く出題されます。
たしかに、処分性や原告適格については、規範が長いこともあり覚えにくいことは事実なのですが、勝手に規範を省略したり簡略化したりするのはやめておいた方が良いでしょう。
実際に、令和4年度の司法試験採点実感においては、原告適格の規範に関して、以下のような指摘がなされています。
行訴法第9条第1項の「法律上の利益を有する者」の判断基準については、おおむね判例の 一般的な判断基準を示すことができていた。ただし、次のように、正確性を欠くものも少なくなかった。
・ 「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵 .. ... 害されるおそれのある者」とされる点について、「法律上保護された権利」と記載し、ある .. いは、「必然的に」との記載を欠くもの(後者については、「侵害されるおそれ」があれば足 りるかのような印象を与える。)
・ 「当該処分を定めた行政法規が、個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨 を含む」などと記載し、「個々人の個別的利益」として何を保護するのか、明示しないもの (「不特定多数者の具体的利益を」との記載が欠けている。)
このように、規範については細かい記載にまで指摘がなされているので、曖昧な暗記で終わらせるのではなく、正確な規範を暗記することを心がけましょう。
判例の結論に安易に飛びつくこと
2つ目は、「判例の結論に安易に飛びつくこと」です。
行政法の論文式試験においては、判例を題材にした問題がよく出題される一方で、具体的な事案については、判例の事案とは微妙に変えて出題されることもあります。
その際に注意してほしいのは、判例の結論に安易に飛びつかないということです。
元となっている判例では処分性が肯定されている場合でも、事案が微妙に異なるために、違う結論を採りうることは十分に考えられます。
また、判例の結論に安易に飛びつくと、問題の個別具体的な事情を意識しない表層的な論述になりかねません。
そのため、判例をベースにした問題であっても、安易に判例の結論に飛びつくのではなく、個別具体的な事情を拾って、充実した論述を意識する必要があります。
インプットに時間をとられすぎて、アウトプットをおろそかにすること
3つ目は、「インプットに時間をとられすぎて、アウトプットをおろそかにすること」です。
前述のとおり、行政法においては、規範を特に正確に暗記しなければならないこともあり、インプットに時間をとられてしまうかもしれません。
しかし、この際に気を付けて欲しいのはアウトプットをおろそかにしないということです。
前の章でも述べたとおり、近年の論述式試験では、当てはめ部分の論述で差がつく傾向にあります。
この当てはめ部分の論述は、実際に過去問を解いて答案を書かないとなかなか出来るようにはならないので、アウトプットを積極的に行うようにしましょう。
行政法のおすすめ書籍
行政書士の学習におすすめの書籍は、『行政法〔第3版〕』 (有斐閣ストゥディア)と『基本行政法[第4版]』(基本シリーズ)です。
【司法試験】行政法の入門書~行政法 第2版(有斐閣ストゥディア)~

『行政法〔第3版〕』 (有斐閣ストゥディア)は、行政法の入門書として有名な書籍で、一から学ぶ初学者を対象としています。
イメージを持ちにくい行政法について、図解や実際の事例を活用して説明されているため、視覚的に学べ、はじめての方でも理解しやすいという特徴があります。
また、内容は300ページほどで、簡潔にまとまっているため、行政法を本格的に学び始める前に全体の概要イメージを持つ上で最適な入門書となっています。
基本行政法 第4版(日本評論社)

『基本行政法[第4版]』(基本シリーズ)は、司法試験を目指す受験生から熱い支持を集める基本書の一つです。ケースメソッドが採用されており、判例や事例を簡潔にまとめた内容と、それに関連する個別法が紹介されています。事例に関連した論点の解説や解答へのステップが丁寧に示されており、理解が進みやすい構成となっています。基本知識から応用知識まで網羅されており、頻出テーマに対しても対応できる力を養うことができます。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
予備試験合格で全額返金あり!
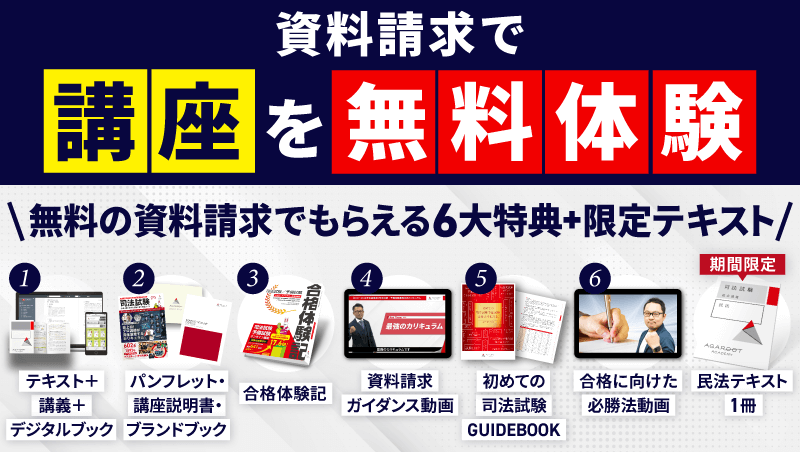
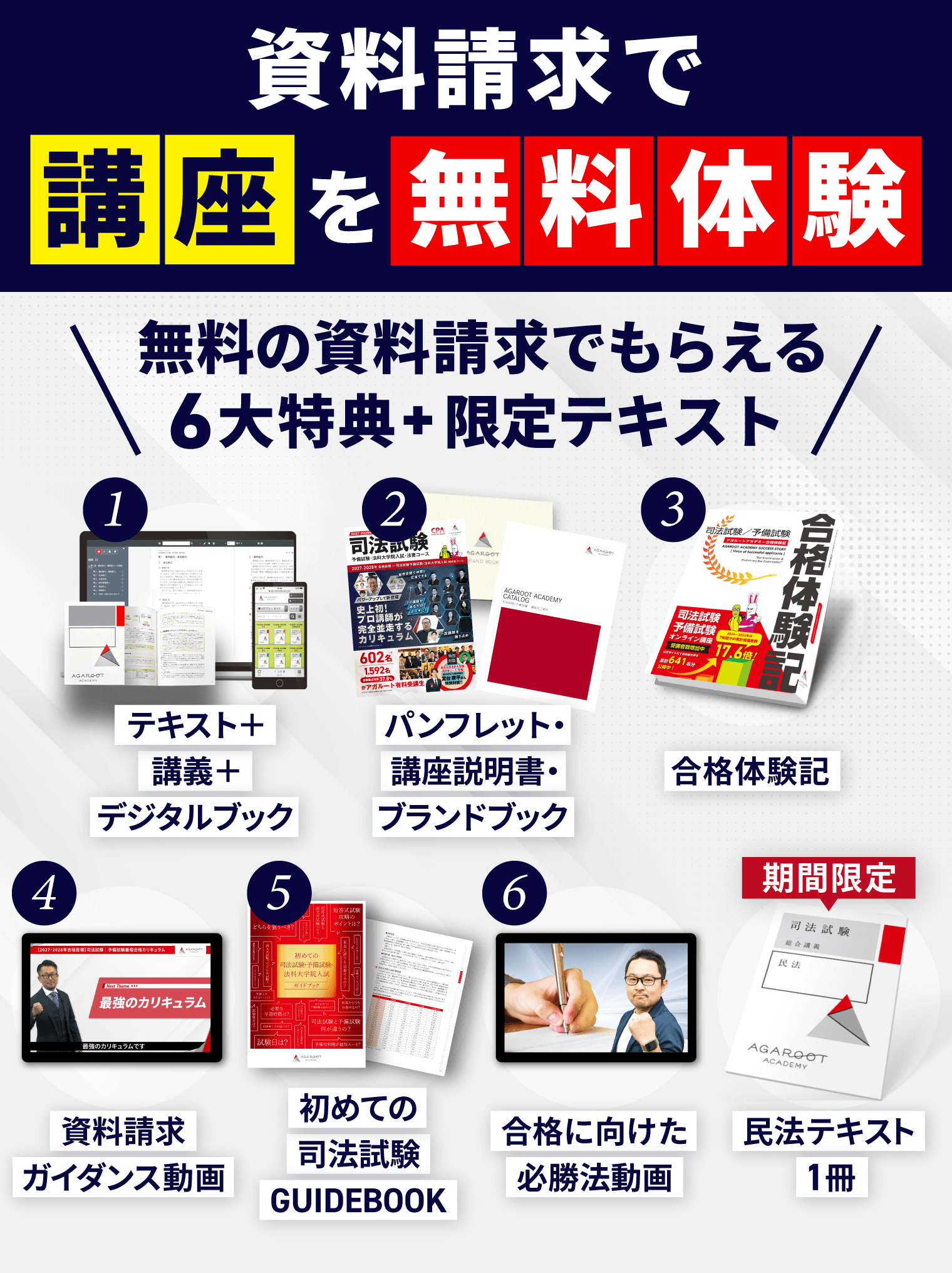
約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る