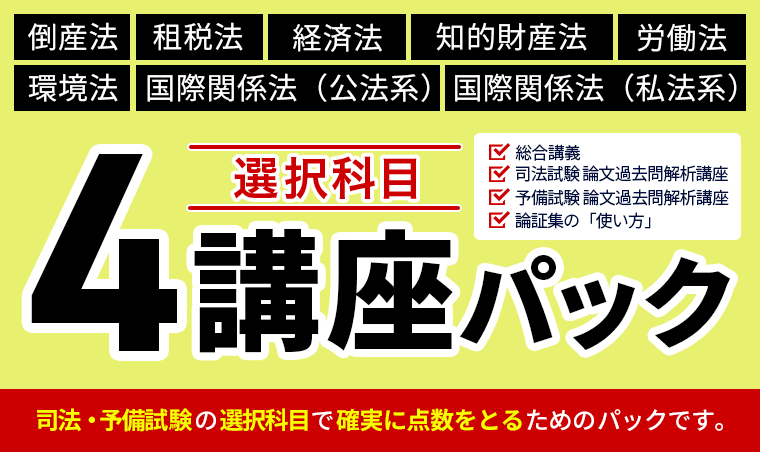司法試験・予備試験の倒産法 勉強法!おすすめの対策法・問題例も紹介

司法試験・予備試験の倒産法の勉強方法について知りたいという方は多いのではないでしょうか。
進め方や勉強すべき範囲など、迷ってしまいますよね。
そこで、このコラムでは、司法試験・予備試験の倒産法の勉強方法について、ポイントや具体的な方法を説明しています。
このコラムを読めば、倒産法の勉強方法がわかりますので、ぜひご一読ください。
<選べる科目別講座!>選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!
これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎
各科目講師による無料ガイダンス公開中!
目次
倒産法とは?特徴とは?
倒産法とは、破産法、会社法上の特別清算、民事再生法、会社更生法の4法の総称です。
そのため、倒産法という法律自体は存在しません。
司法試験では、破産法と民事再生法の各分野から1題ずつ出題されます。
他方で、予備試験の倒産法では、破産法と民事再生法のいずれか、あるいは破産法と民事再生法の比較問題が出題される傾向にあります。
このように、司法試験・予備試験の問題で出題されるのは、破産法と民事再生法になりますので、倒産法の勉強をするにあたっては破産法と民事再生法の学習が中心となります。
また、倒産法の特徴は条文学習が重要です。破産法の基本書それ自体は非常に分厚く、圧倒されることもあるかとは思いますが、司法試験の倒産法で求められる知識はそこまで多くありません。条文の理解さえ丁寧にできれば、合格点に届くことができる科目です。
そのため、倒産法は他の科目と比較しても、学習しやすい科目で、一度理解してしまえば安定した得点を確保することができることから、選択科目の1つとしておすすめすることができる科目の1つです。
倒産法の出題形式や配点、傾向
1 倒産法の出題形式
まず、倒産法の出題形式についてご紹介します。
倒産法の出題形式は、例年、大問が2つ(設問1と設問2)で、各設問には小問が複数出題されている傾向にあります(令和5年度司法試験問題では、大問が2つで設問1には小問が3つ、設問2には小問は特にありませんでした)。問題文の文量はそこまで多くありません。
例年の司法試験では、破産法と民事再生法のいずれも満遍なく出題されていることから、今後も司法試験本試験での出題は破産法及び民事再生法といえるでしょう。
2 倒産法の配点
司法試験での選択科目の配点は100点、予備試験では50点となっています。
各設問の配点については公開されておらず、それぞれの設問にどれくらいの配点がなされているのかは知ることができません。
倒産法の勉強法
ここでは、司法試験科目の1つである倒産法の勉強法について詳しくご紹介します。
1 破産法→民事再生法の順で勉強する
何より破産法と民事再生法の勉強の順序が大切です。
両者は共通点が多いものの、異なる部分も多々あります。
そして、両者を理解するには前提知識として破産法の理解を深めてから、民事再生法の学習をすると非常に効率がよいです。
民事再生法には、破産法の内容及び理解を前提とする知識や論点が数多く存在しますので、破産法の学習なくして民事再生法を先に学習してしまうと、結局のところ、よくわからないことにもなってしまいます。
例えば、令和4年度の司法試験問題(第2問・設問1)を具体例に見ていきます。
この問題で問われていることは、直接的には民事再生法所定の再生手続開始に関する要件及び趣旨を踏まえて、裁判所が再生手続開始の決定をすることができるか否かです。
ですが、裁判所が再生手続開始の決定をすることができるか否かは、再生手続開始の申立てが必要であり、当該申立ては、再生手続開始の原因があれば、申立ての棄却事由がある場合を除いて再生手続開始の決定をすることになっています。
そのため、再生手続開始の原因を具体的に見ていくと、当該原因の根拠となる条文は民事再生法にありますが、実質的な内容は破産法に依拠しています。
このように、民事再生法は破産法の内容を前提とする条文構造になっており、実際の司法試験本試験においても破産法の理解を前提とした民事再生法の問題が出題されています。
したがって、倒産法を勉強するにあたり、まずは破産法を学習し、破産法の全体像を理解したうえで民事再生法の学習に取り掛かることが重要であり、また最も効率がよい学習方法であるといえます。
2 条文を勉強する
次に、倒産法の学習では条文学習が非常に重要です。
当然ながら、他の科目においても条文を理解し、条文操作をすることが何より大切であることは言うまでもありません。
そのうえで特に倒産法においては、条文を意識した勉強が大切です。上記で倒産法の学習は、破産法→民事再生法の順で学習することが最も効率がよい学習であることをご紹介しました。
その際、民事再生法は破産法の理解を前提としているとしましたが、これは条文操作においても同様です。
民事再生法の条文はその内容を実質的には破産法と同一にしていることが多々あります。
そのため、民事再生法の条文を参照しつつ、破産法の条文も同時に参照することが大切です。
両者の条文はリンクしていることがあるため、条文操作を丁寧に行わなければ問われている条文を探しだし、適切に摘示することは困難です。
さらに、本試験という限られた時間内で条文操作を行う必要がある以上、事前準備としての条文操作に慣れておくことは他の受験者との間で差をつけるという意味でも重要なことです。
したがって、(他の科目でもそうですが)条文を意識した勉強をすることが大切であるといえます。
3 判例百選の学習
倒産法の学習をするにあたり、判例百選をもとに学習するとよいです。
近年の司法試験倒産法の問題では判例百選掲載の有名な事例をベースにした問題が出題される傾向にあります。ですので、問題演習をすることも大切ですが、判例百選に掲載されている判例の理解も同様に重要といえます。
判例百選の学習をする際には、判旨だけでなく、当該事例の具体的な内容にも着目しましょう。
多くの受験生は判旨(及びその理由)だけに着目しがちです。ですが、なぜそのような判旨になったのかを理解するには、問題となった事例はいかなる事実関係で、いかなる当事者が、どのような主張をしているのか等を理解しなければいけません。
したがって、判例百選の学習は重要であるとともに、百選掲載の判例学習においては事実関係に着目して勉強をすることも大切であるといます。
4 過去問演習を行う
最後に、過去問演習も必ず行いましょう。倒産法の問題演習書は様々な良書が出版されていますが、問題演習書に手を出す前にまずは過去問演習をすることが肝要です。
過去問演習を行うことで、司法試験出題者がどのような意図で、どのような形式で問題を出題しているのかを知ることが出来ます。出題形式に慣れておくだけで、本試験の際に緊張せず、余裕をもって試験に臨むことができます。
また、過去問演習を行うことでどの論点が出題されているのか、そして論点の出題の仕方として問題文にどのような事実がちりばめられているのかを知ることもできます。
したがって、倒産法の学習では判例百選の学習とともに、過去問の演習も必須です。
倒産法を勉強する上でのポイント
ここでは、倒産法を勉強する上でのポイントについてご紹介します。
1 民法・商法・民訴・民執・民保がベース
まずは倒産法の学習をするうえで、基本科目である民法・商法・民事訴訟法の理解が必須であるということです。
破産法や民事再生法が問題となる場面の背景には、商取引等といった事実関係があり、そのような取引関係を経たうえで破産や民事再生が問題となることが多いです。
そのため、基礎科目としての民法・商法・民訴の理解があると、問題文に現れている事情をより理解しやすくなります。
さらに、民事執行法と民事保全法の理解も重要です。いずれも、執行保全の段階ですが倒産法においても執行保全が関連する場面が多々あります。
したがって、倒産法を勉強する際には、破産法と民事再生法の条文だけでなく、民法・商法・民訴・民執・民保の条文、及び理解を深めることがポイントになります。
2 破産法では条文の当てはめ能力が重要
破産法では条文の当てはめ能力が重要です。
条文操作をすることができたとしても条文に問題文で問われている事実関係の当てはめをしなければいけません。
さらに、問題文の事実関係から逆算して、どの条文が問題になるのかも見つけなければいけません。
そのため、破産法では条文操作だけでなく、条文に当てはめる能力も問われています。ですから、判例百選の学習においても判旨(及びその理由)だけでなく、判例の事実関係にも着目することが大切です。
倒産法の出題例
ここでは、倒産法の過去の出題例をご紹介します。
実際の出題例を見ることで今後倒産法を学習するうえでの到達点を知ることが出来ますのでぜひ目を通して頂ければと思います。
令和5年度予備試験の設問1小問⑴では以下のような問題が出題されています。
その他にも設問1では小問⑵及び⑶が出題されており、小問⑵と⑶は⑴よりも長文です。また各小問は、問題文に指定があるようにそれぞれが独立した問題になっています。
年度によって異なる年もありますが、概ね設問1の小問⑴が非常にベーシックな問題で、小問⑵から⑶に行くに連れてやや応用的な論点が出題されている傾向にあります。下記問題文を見て頂ければわかるように、説明問題(論述問題)が例年出題されています。
〔設問1〕 以下の小問⑴から⑶までに答えなさい(各小問は独立した問題である。)。
⑴ 販売商品の仕入先20社は、A社にとって、いずれも他の仕入先を見付けることも可能な取引 先であり、取引継続の必要性の高い取引先ではない。仕入先20社は、再生手続開始の決定後で ある令和5年3月13日から同月15日までの間にかけて、同年2月末日までに納品した商品に ついての未払売買代金を約定どおりに支払ってほしいとA社に伝えてきている。 A社は、仕入先20社に対し、未払売買代金を約定どおりに支払うことができるか、説明しなさい。
【予備試験】
【司法試験】
まとめ
司法試験の選択科目の1つである倒産法について、具体的な勉強方法や試験内容、出題傾向などについてご紹介しました。
倒産法は司法試験選択科目の中でも比較的受験者が多い科目の1つです。そのため、受験者間でのレベルも高いため、適切に対策を取らなければ合格点を勝ち取ることはできません。
ですので、本コラムを参照して頂き、倒産法の勉強方法や学習ポイントをおさえて頂ければ、より確実に合格点を取ることが出来ます。
ぜひ、本コラムを何度も読んで頂き、司法試験倒産法の学習に役立てて頂ければと思います。
司法・予備試験で確実に点数を取れるように
<選べる科目別講座!>あなたの選択科目対策を集中的にサポート!
選択科目で問われる知識をインプット→過去問解析でベストな解答方法を学べる講座です。
また、「論証集」の使い方を学び、選択科目における重要論点を効率的に理解できます。
選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!
これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎
各科目講師による無料ガイダンス公開中!
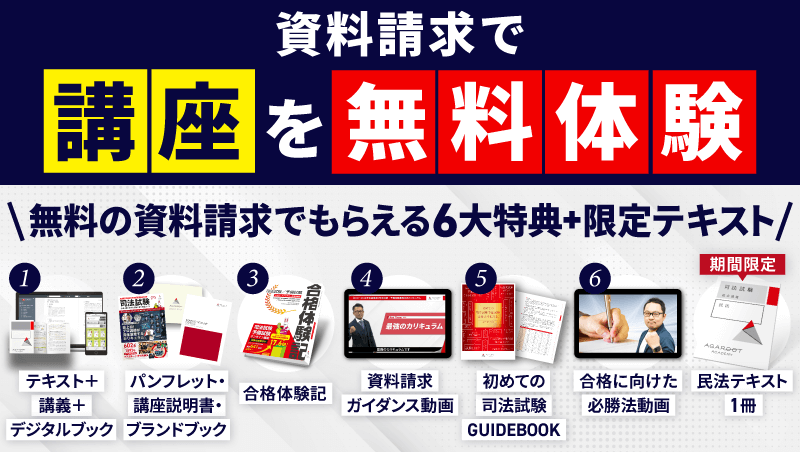
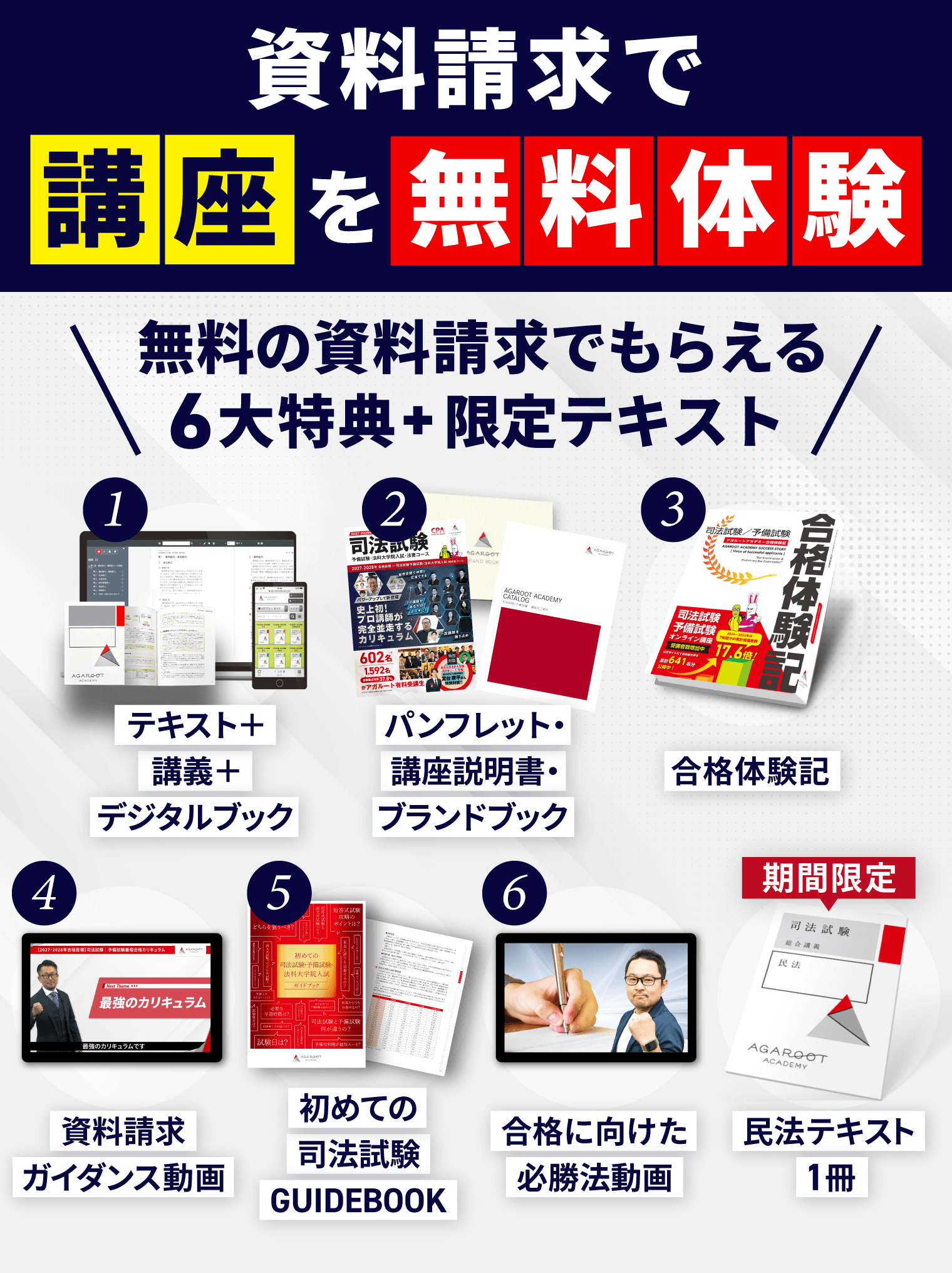
約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る