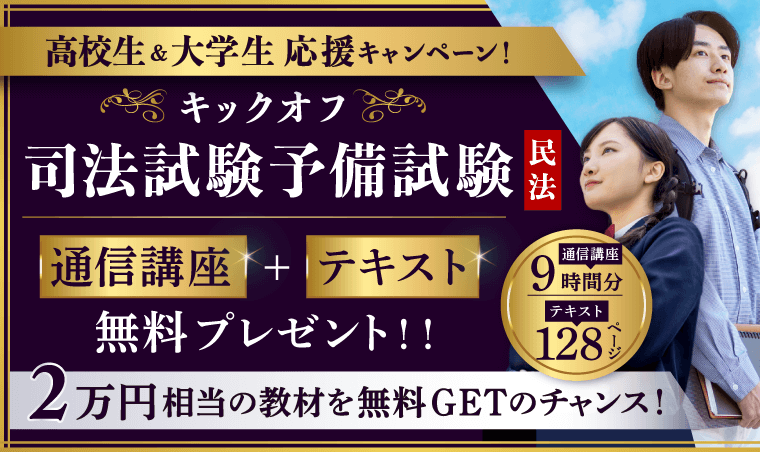司法試験の内容を解説!科目・配点・合格点・足切り・時間割は?どんな問題が出る?【2025年最新情報】

司法試験は、日本の資格試験の中でも最難関試験の1つであると言われています。
最難関と言われている司法試験で、実際にどのような内容の問題が出題されるのか、気になる方も多いのではないでしょうか?
現行の司法試験は、短答式と論文式の2つを受験する必要があるのですが、短答式試験と論文式試験とでは、科目数や足切りなどが大きく異なっているため、受験する際には注意が必要です。
そこで、本コラムでは、司法試験の内容について、科目・配点・合格点・足切り・時間割などを、短答式試験と論文式試験に分けて詳しく解説していきます。
司法試験・予備試験の受験を
検討されている方へ
- 司法試験の勉強についていけるか不安
- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい
- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
このような悩みをお持ちでしたら
アガルートの無料体験を
ご活用ください


サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、
司法試験の勉強についていけるかを試せる!
「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、
司法試験のすべてがわかる!
300名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!
司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
司法試験(短答式)の内容を詳しく解説!科目や配点・合格点・足切り・時間割についても
この章では、司法試験(短答式)の内容について、詳しく解説していきます。
短答式試験の科目・配点・時間割
| 試験科目 | 時間/配点 |
|---|---|
| 憲法 民法 刑法 | 50分/50点 75分/75点 50分/50点 |
短答式試験の試験科目は、憲法、民法、刑法の3科目で、配点は憲法50点、民法が75点、刑法が50点となっています。
また、試験時間は憲法が50分、民法が75分、刑法が50分です。問題数としては、憲法が20問程度、民法が37問程度、刑法が20問程度なので、基本的には1問2〜3分のペースで解いていくことになります。
合格者平均点
| 年度 | 短答式合格者の平均点 |
|---|---|
| 平成30年 | 128.1点 |
| 令和元年 | 129.3点 |
| 令和2年 | 118.1点 |
| 令和3年 | 126.4点 |
| 令和4年 | 123.3点 |
| 令和5年 | 126.1点 |
| 令和6年 | 120.3点 |
短答式試験の合格者の平均点は、年度により多少の差はありますが、概ね120点前後です。短答式試験は3科目で175点満点なので、7割程度得点できれば、短答式試験で周りの受験者から大きく後れを取ってしまうというようなことはないでしょう。
もっとも、短答式試験で7割程度の得点を安定して取るためには、それなりの対策が必要になります。したがって、短答式試験の対策についても手を抜かず、計画的に勉強を行うことが重要です。
足切りライン
次に、短答式試験の足切りラインについて説明します。
短答式試験の足切りは、2段階の基準で判断されます。
まず、1段階目は、短答式試験の各科目において、満点の40%以上の成績を得ることが条件となります。具体的には、憲法で20点以上、民法で30点以上、刑法で20点以上得ることが必要です。
1科目でも40%を下回ってしまうと、足切りとなってしまうため、どの科目もバランスよく勉強することが重要になります。
2段階目の条件は、3科目合計で一定以上の点数を取ることです。3科目合計での足切りラインは、年度によって異なるのですが、平成30年度から令和6年度については、以下のとおりになっています。
| 年度 | 短答式試験の合格に必要な成績 |
|---|---|
| 平成30年 | 108点 |
| 令和元年 | 108点 |
| 令和2年 | 93点 |
| 令和3年 | 99点 |
| 令和4年 | 96点 |
| 令和5年 | 99点 |
| 令和6年 | 93点 |
表からも分かるとおり、3科目合計の足切りラインは、大体100点前後を推移しています。満点が175点なので、足切りラインを超えるためには、6割程度得点する必要があるといえるでしょう。
短答式試験で足切りになってしまうと、論文式試験でどれだけ頑張ったとしても不合格になってしまうため、短答式試験の足切りラインは何としてでも突破したいところです。
令和4年(2022年)に実際に出題された短答式試験の問題例
短答式試験について、大体どの程度得点出来れば司法試験合格に近づくのか、イメージが掴めてきたのではないでしょうか。
そこで、短答式試験では実際にどのような問題が出題されるのか、令和4年の短答式試験を例に挙げて説明していきたいと思います。
憲法

憲法の短答式試験では、このように判例の理解を問う問題が多く出題されます。判例の理解を問う問題の中には、かなり詳細な判例知識が必要になるものもあるため、憲法の短答対策にあたっては、普段から判例をきちんと読み込むことが重要です。
また、統治分野からも一定程度出題されるため、統治分野についても対策を怠らないようにしましょう。
民法

民法の短答式試験では、あるテーマに関して、正しい又は誤っているものの組み合わせを選ぶ問題が多く出題されます。
民法は範囲が膨大で細かい条文知識なども問われるため、苦手意識をもつ受験生も多いのですが、その一方、ほとんどが5択の問題であり、他の科目と比べると選択肢が少ないため、ある程度対策を行うと、得点が安定しやすい科目であることも事実です。
民法は、75点満点と配点も一番大きい科目なので、民法を得意科目にしてしまえば、司法試験合格に大きく近づくことは間違いありません。
刑法

刑法の短答式試験の特徴としては、単純な条文や判例の知識を問う問題以外に、上記のような現場思考型の問題も多く出題されることです。
このような現場思考型の問題は、時間をかけて考えれば解けることが多いため、特に刑法の短答式試験においては、時間配分を上手く行うことが得点アップの鍵だといえます。
司法試験(論文式)の内容を詳しく解説!科目や配点・合格点・足切り・時間割についても
次に、司法試験(論文式)の内容について、詳しく解説していきます。
論文式試験の科目・配点・時間割
| 試験科目 | 時間/配点 |
|---|---|
| 選択科目 憲法 行政法 | 3時間/100点 2時間/100点 2時間/100点 |
| 民法 商法 民事訴訟法 | 2時間/100点 2時間/100点 2時間/100点 |
| 刑法 刑事訴訟法 | 2時間/100点 2時間/100点 |
論文式試験の試験科目は、選択科目、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の8科目で、配点は各科目100点ずつです。もっとも、最終的には、論文式試験の800点満点分が1400点満点に換算され、短答式試験の点数と合計されることになります。
時間は、選択科目が3時間、その他の7科目が各2時間であり、論文式試験自体は3日間にわたって行われます。
合格基準点
論文式試験の得点の配分は、各科目が100点となっており、全体で1400点満点(換算後)です。
算式
短答式試験の得点+(論文式試験の得点×1400/800)
最近の傾向を見ると、総合得点が約820点周辺で合格ラインが設定されています(法務省:司法試験の結果について)。
これを例にとると、短答式試験で120点を獲得した場合、残りの論文式試験で700点以上を得ることで、合格の可能性が見えてきます。つまり、論文式試験で得点全体の約50%以上を獲得すれば、合格の閾値に達する可能性があるということです。
ただし、これは最低合格点が820点と仮定した場合の話です。
例えば、平成28年度のように合格最低点が880点と設定される年もあります。そのような年には、より高い得点が求められ、その場合は、論文式試験で少なくとも約60%の得点が必要になる可能性があります。
それゆえに、もし試験の成功を確実にしたいのであれば、論文式試験においては、約60%以上の得点を目指すことが推奨されます。
すなわち、合格を確実にするためには、各科目を全体的に理解し、それぞれの問題に対して確実に得点を取れるように、十分な準備と練習を行うことが重要です。
さらに、試験の難易度や合格基準は年度によって変動しますので、その点を考慮に入れて、自身の勉強計画を立てることも重要です。
このような考慮事項を抑えつつ、適切な準備を行い、確実な理解と適用能力を身につけることが、司法試験の成功への鍵となります。
足切りライン
論文式試験の足切りラインは、選択科目、公法系科目、民事系科目、刑事系科目それぞれにおいて、素点の25%となっています。
したがって、足切りラインを突破するには、選択科目で25点以上、公法系科目で50点以上、民事系科目で75点以上、刑事系科目で50点以上を得る必要があります。
令和4年(2022年)に実際に出題された論文式試験の問題例
では、実際に論文式試験ではどのような問題が出題されるのでしょうか。
以下では、令和4年の論文式試験を例に、各科目の特徴を説明していきます。
公法系科目

憲法においては、①Xの立場からの主張、②Yからの反論、③私見といったように、様々な立場からの検討が求められる問題が出題されることもあります。このような問題に対応するためには、日頃から、多角的な視点で物事を考えることが重要です。
また、公法系科目においては、上記のように判例への言及が求められることがあります。普段問題演習を行う際、どの判例を参考にするべきなのかを常に意識しておくと、このような出題にも難なく対応できるようになるはずです。
民事系科目

民事系科目においては、このような現場思考型の問題も出題されることが多いです。
司法試験本番で未知の問題が出題されると、焦ってしまうかもしれませんが、それは他の受験生でも同じです。基本的には、法的三段論法を守って論述すれば、周りの受験生に大きく差を付けられることはないはずなので、普段から、法的三段論法を意識して論文式試験の対策を行うようにしましょう。
刑事系科目

刑事系科目については、近年、複数の学説を比較検討させるような問題が出題されることが多いです。そのため、判例・通説の結論だけを暗記する学習では不十分であり、判例・通説の根拠となる考え方や、それらとは異なる学説・見解についても、学習しておく必要があります。
令和8年より司法試験がパソコン受験に
2026年から、今まで紙で解答していたものを、パソコンで受験する形式に変えることが決まりました。手書きで論文問題を書くのは大変なので負担を減らすための取り組みであり、デジタル社会に適応した取り組みとなります。今後、実際の詳しいやり方を考えることになります。
国家公務員や公認会計士、税理士といった人たちが受ける国家資格の試験では、今まで紙で受験していました。これに対して、司法試験がデジタル化することで、国家資格試験で先駆的な試みとなることが期待されます。
試験会場でパソコンを操作する方式を使い、自宅で受験することはできません。
システム内で試験を受けるため、インターネット経由で問題が漏洩することを防げるとのことです。
司法試験に合格する力を身につけるには
ここまで、司法試験の短答式試験、論文式試験の内容についてそれぞれ説明してきました。
司法試験の合格基準点自体は、それほど高いとはいえないかもしれませんが、短答式試験と論文式試験のいずれについても、各科目ごとに足切りラインが設定されているため、それぞれの科目についてまんべんなく対策を行う必要があります。
また、出題される問題についても、決して易しいものではなく、特に近年では、幅広い出題に対応できる学力をつけていかなければなりません。
このように、最難関といわれる司法試験に合格するには、多くの試験科目について膨大な勉強量をこなしていく必要があるため、効率的な勉強方法を知ることが何よりも重要です。
そこで、司法試験の効率的な勉強方法を知りたい方は、ぜひ一度アガルートに相談してみてください。アガルートでは、目的に合わせた多数の講座が用意されているため、自分にあった効率的な勉強方法を見つけることができるはずです。
司法試験・予備試験の受験を
検討されている方へ
- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?
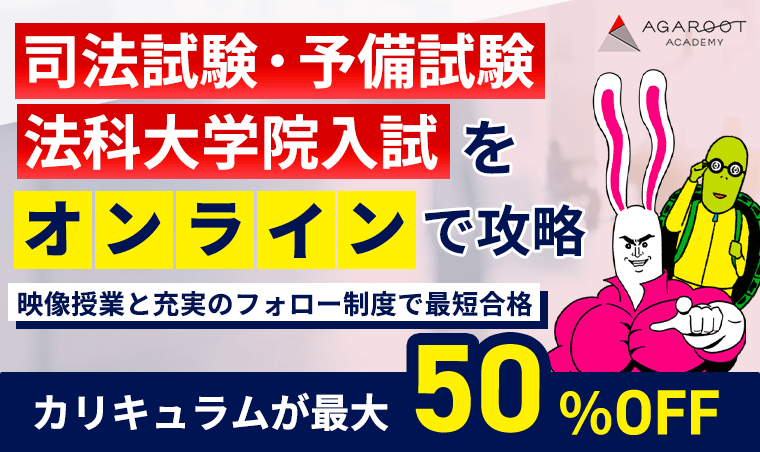
合格者の声の累計981名!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
予備試験合格で全額返金あり!!


サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、
司法試験の勉強についていけるかを試せる!
「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!
300名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!
司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る