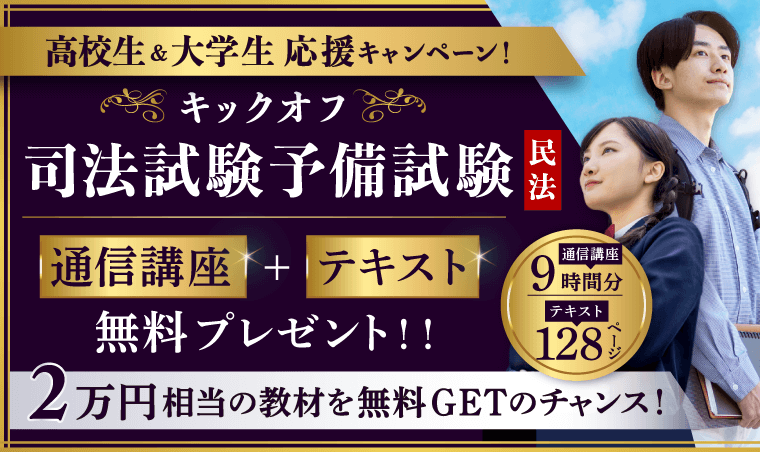【無理ゲー?】司法試験の難易度を解説!難しさは東大とどっちが上?
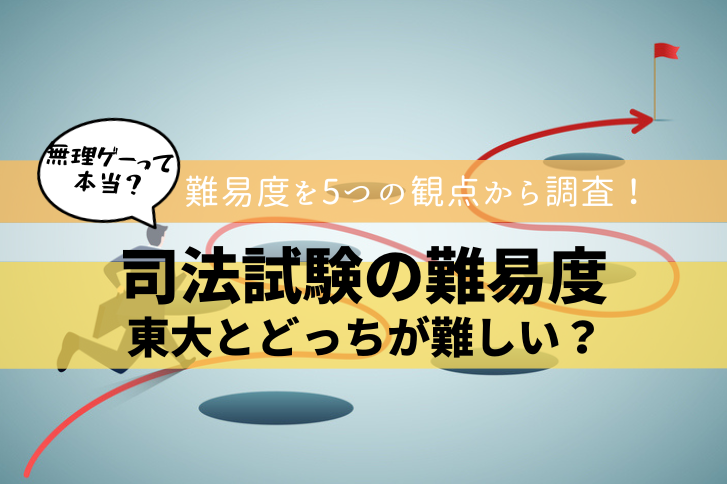
司法試験は最難関の国家資格のひとつといわれることがあります。
「裁判官、検察官、弁護士になりたいが、試験科目が多く、試験問題自体の難易度が高いため、やめておこう」と考えている方や、「司法試験に向けて勉強を始めたものの、自分には合格は不可能だ」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このコラムでは、司法試験・予備試験の難易度を解説し、合格が決して不可能な試験ではないことがわかります。
司法試験・予備試験の受験を
検討されている方へ
- 司法試験の勉強についていけるか不安
- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい
- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
このような悩みをお持ちでしたら
アガルートの無料体験を
ご活用ください


サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、
司法試験の勉強についていけるかを試せる!
「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、
司法試験のすべてがわかる!
300名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!
司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る【結論】司法試験は無理ゲーではない
「無理ゲー」とは困難すぎて攻略がほぼ不可能なゲームのことを指します。
司法試験はその難易度の高さからよく「無理ゲー」と称されます。確かに困難な試験ではありますが、決して不可能ではありません。
詳しくは後述しますが、例えば令和6年の司法試験の合格者数は1,592人、出願者数4,028人、実受験者数は3,779人であり、実受験者ベースの合格率は約42%と決して低すぎる数字ではないことがわかります。
もちろん、きちんとした対策を取り、正しい方向に努力する必要はありますが、全受験者の中で相対的に高い点数を取れれば決して「無理ゲー」ではありません。
出典元:令和6年司法試験の結果|法務省
司法試験の難易度を5つの観点から調査!
司法試験の難易度を、①合格率、②受験資格、③経済面、④勉強時間、⑤独学挑戦した場合から調査してみました。
合格率から見る難易度
まず、司法試験の合格率から難易度を見てみましょう。
直近の司法試験受験者数(出願者数)と合格者数は以下の表のとおりになっています。
| 試験年度 | 受験者数(出願者数) | 合格者数 |
|---|---|---|
| 平成30年 | 5811 | 1525 |
| 令和元年 | 4930 | 1502 |
| 令和2年 | 4226 | 1450 |
| 令和3年 | 3754 | 1421 |
| 令和4年 | 3367 | 1403 |
| 令和5年 | 4165 | 1781 |
| 令和6年 | 4028 | 1592 |
直近の合格率は(小数点以下切り捨て)
- 平成30年:26%
- 令和元年:30%
- 令和2年:34%
- 令和3年:38%
- 令和4年:41%
- 令和5年:43%
- 令和6年:42%
となっており、合格率は近年急激に上がってきていることが分かります。
近年の合格率の高まりからも、受験者の中で相対的に高い点数を取ることができれば合格できる試験だということがわかります。
司法試験の受験資格から見る難易度
もっとも、司法試験には以下の通り受験資格について厳しい要件があるため、合格率から直ちに難易度は低いとはいえません。
そこで、司法試験の受験資格から難易度を見ていきます。
司法試験を受験するルートとしては、①予備試験に合格するという予備試験ルートと、②法科大学院を卒業するという法科大学院ルートがあります。
予備試験ルート
予備試験ルートでは、7月の短答式試験、9月の論文式試験、翌年1月口述試験の3つの試験の合格が必要となります。
これらの試験は、順番にひとつずつ合格しなければ次の試験に進めないという制度になっています。そして、合格による免除の制度がないため、論文式試験、口述試験で不合格になった場合であっても、翌年は短答式試験から受験する必要があるため、難易度が高いと言われる理由の一つとなっています。
一方で、予備試験には受験資格や受験回数制限がなく、誰でも、何回でも受験することが可能になっています。
法科大学院ルート
法科大学院ルートでは、法科大学院を卒業する必要があります(令和5年司法試験からは卒業見込みが出た段階で受験することができます)。
法科大学院は、少人数で、教授と学生間、学生同士の間で議論を行いながら、授業を進めています。また、法曹三者や法律関連業務などの実務研修や体験学習などが行われているという特徴があります。
法科大学院には、修了まで3年間の法学未修者コース、2年間の法学既修者コースがあり、司法試験を受験するまでに時間と費用がかかるため、受験資格を得る点という観点から見て、難易度が高いと言われる理由となっています。
経済面からみる難易度
次に経済面から難易度を見ていきます。
司法試験を受けるためにはかなりの費用を必要とする場合が多く、経済面からみても難易度が高いといわれることがあります。
国立大学の法科大学院の費用は、既修者が総額189万円、未修者が総額269万4000円となっています。
毎年トップクラスの合格率を誇る慶應義塾大学法科大学院の費用は、既修者が総額334万4380円、未修者が総額496万6520円となっています。
予備試験ルートでは費用は抑えられますが、予備校通いが望ましく、予備校の費用は約100万円となっているところが多いです。例えば、アガルートが約69万~124万円、LECが約101万円~132万円、伊藤塾が約112万円以上となっています。
勉強時間から見る難易度
では、勉強時間をどれくらい要するのかを見ていきます。
司法試験では、試験科目数が多く、司法試験自体の難易度が高いため、かなりの勉強時間が必要とされています。
司法試験の合格に必要な時間は3000~8000時間といわれ、中には1万時間という方もいます。
したがって、合格者の多くが複数年に渡る勉強を経ていることがわかります。
一般的な司法試験受験生は、大学を卒業し、法科大学院(既修者コース)を卒業してから司法試験を受験すると、約6年間勉強することになるため、通常であれば6年間の勉強が必要となると想定できます。
勉強時間をあまりとることができない社会人や、法律知識がない法律未修者であれば8~10年の期間を要することもあります。
独学挑戦した場合の難易度
次に独学で司法試験に挑戦した場合の難易度ですが、こちらは相当難易度が高くなると言わざるを得ません。
司法試験に独学で合格するためには、まず予備試験への合格が必要です。
過去5年間の予備試験の合格率は、令和2年から令和6年まで、4.2%、4.0%、3.6%、3.6%、3.6%と推移してきています。したがって、予備試験の合格率は約4%で推移してきており、合格率は非常に低いといえます。
そして、令和6年予備試験の合格者の内訳を見ると、最終合格者449人のうち、法科大学院修了・在学中・中退の人数を除くと、434人となります。最終合格者のうち約9割が法科大学院以外の受験者であったといえます。とはいえ、合格者の6~7割が予備校に通っているとのデータもあり、独学者は少ないと考えられます。
独学での司法試験・予備試験の合格が難しい理由は以下の2点が大きく挙げられます。
- 合格までに長い期間を要する
- 論文式試験問題の添削指導を受ける機会がない
合格までに長い期間を要する
上記の通り、司法試験合格までには長い期間を要します。一人で勉強する精神力を保つことも難しいですが、長期間勉強していると試験に合格するための勉強から離れた勉強をしてしまうリスクがあります。
法律学はそれ自体が学問の対象とされているため、非常に奥が深く、時として司法試験の合格には必ずしも必要とはいえない事項もあります。独学者として、試験に必要な知識かどうかを見抜くことは難しく、司法試験合格に必要な知識を効率よく取得していくためには法科大学院への進学や予備校の利用が望ましいといえます。
論文式試験問題の添削指導を受ける機会がない
司法試験・予備試験には10科目の論文式試験があります。
論文式試験ではインプットした知識を点数を取れる形でアウトプットしていく必要があります。点数がとれる論文を書くためには、自分で書いた論文を司法試験合格者などに見てもらい、何をどのように書いていくべきなのか、添削や指導を受けることが重要です。
独学での挑戦は費用を抑えることはできますが、添削を受ける機会がないことから独学での司法試験・予備試験の合格は難易度がかなり上がるといえます。
あくまで一例ですが、司法試験に独学で挑戦された方の中には10年間の勉強を経て司法試験に合格した方もいます。インプットを浅く広く一通り終わらせ、早くアウトプットに入ることが重要との意見もありました。
司法試験と東大合格、難易度を比較
最難関の資格試験のひとつといわれる司法試験合格と、大学偏差値で国内トップである東京大学合格の難易度を比較します。
司法試験合格と東大合格の難易度を、①合格率、②偏差値、③勉強時間、④試験科目と得点率の4つの観点から調査します。
合格率で比較
直近の令和6年司法試験の合格率は約42%でした。2024年度入試の東大合格率は、約32%(志願者数9559人、合格者数3085人)でした。
合格率の数字だけを見ると司法試験の合格率が高いことがわかります。もっとも、上記の通り司法試験は受験資格を得ることが難しく、特に予備試験の合格率が約4パーセントであるため、合格率の数字のみで判断することは難しいです。
偏差値で比較
東大の入試偏差値は、概ね67.5~72.5とされています。一方、司法試験の偏差値は約75であるといわれています。
この点から、司法試験の偏差値のほうが東大合格よりも若干高いといえます。
勉強時間で比較
では、勉強時間はどうでしょうか。
東京大学に合格するために必要な学習時間は、約3000時間といわれており、司法試験に必要な勉強時間は3000時間~8000時間と言われています。
したがって、勉強時間の観点からは司法試験のほうが難易度が高いことがわかります。
試験科目・得点率で比較
司法試験は、短答式試験と論文式試験があります。
選択式試験の科目は、憲法、民法、刑法の3科目です。論文式試験の科目は、公法系科目(憲法、行政法)、民事系科目(民法、商法、民事訴訟法)、刑事系科目(刑法、刑事訴訟法)、選択科目(経済法、労働法、租税法、倒産法、知的財産法、環境法、国際公法、国際私法のうち1科目)の計8科目があります。
一方で、東大の入試では、大学入学共通テストと2次学力試験を受験する必要があります。
大学入学共通テストでは、理系と文系で違いがありますが、大きくは、数学、国語、理科、社会、外国語を受験する必要があります。2次学力試験では、文系は数学、国語、地歴、外国語を、理系は数学、国語、理科、外国語を受験する必要があります(https://www.yotsuyagakuin.com/b_geneki/u-tokyo/)。
したがって、単純な科目数では司法試験のほうが多いといえます。
では、得点率の観点からはどうでしょうか。
司法試験の合格ラインは、短答式試験が約6割、論文式試験が約5割といわれています。予備試験の合格ラインについても、短答式試験が約6割、論文式試験が約5割といわれています。
一方で、東大の合格ラインは、大学入試共通テストで約8割5分~9割、2次学力試験で約6割となっています。
したがって、得点率の観点からは、東大合格の方が司法試験よりもより高い点数を取る必要があるといえます。
以上より、偏差値や勉強時間、試験科目の観点からは司法試験のほうが若干難易度が高いと見ることができます。
令和5年予備試験では、東大生の予備試験合格率が約22%(受験者数477人、合格者数103人)であり、東大生であっても司法試験に合格できない可能性があるといえ、司法試験の難易度が東大合格よりも高いといえるのではないかと考えられます。
もっとも、得点率の観点からは、東大のほうがより高い点数が求められていることがわかります。
試験自体が異なるため、一概にはいえませんが、試験の性質としては、東大合格のためには、苦手をなくして、さらに高得点を取る必要があり、一方の司法試験では、高得点は求められておらず、苦手科目をなくすことが合格に繋がりやすいといえます。そうだとすると、一概に、司法試験が東大よりも難易度が高いともいえないと考えられます。
無理ゲーと言われる司法試験、意外と簡単という声も
予備試験も最終合格率は約4%ですが、細かく見ていくと、短答式試験の合格率が約20%、短答式試験合格者の論文式試験の合格率が約20%、論文式試験合格者の口述試験の合格率が約98%となっています。
そして、令和6年司法試験では、短答式試験の合格率が約78%、短答式試験合格者の論文式試験の合格率が約54%であり、短答式試験に合格した半数以上が司法試験に合格していることがわかります。
さらに、合格ラインは短答式試験が約6割、論文式試験が約5割となっています。
したがって、それぞれの試験、科目に対し、適切な勉強、対策を取ることができれば、合格が”無理ゲー”とはいえないと思われます。
受験者の中には記念受験の人もいる?
受験者の中には記念受験の人もいます。
特に予備試験は、司法試験と異なり受験資格についての要件がなく、誰でも何回でも受験することが可能です。したがって、将来、法科大学院試験や司法試験を受験する練習として予備試験を受けてみるという人も多くいます。
また、法律について学んできた記念として、予備試験を受験するという人もいます。
したがって、対策をしっかりし、合格を目指して受験している志願者の数は、実際の人数よりも少なく、実質的な合格率はもっと高くなると考えられます。
上位ロースクールでは合格率が50%以上のところも
| ランキング | 法科大学院名 | 合格率 | 受験者数(人) | 最終合格者数(人) |
| 1位 | 慶應義塾大法科大学院 | 59.35% | 246 | 146 |
| 2位 | 愛知大法科大学院 | 55.56% | 9 | 5 |
| 3位 | 京都大法科大学院 | 49.31% | 217 | 107 |
| 4位 | 一橋大法科大学院 | 48.78% | 123 | 60 |
| 5位 | 東京大法科大学院 | 47.45% | 255 | 121 |
| 6位 | 中央大法科大学院 | 45.86% | 181 | 83 |
| 7位 | 早稲田大法科大学院 | 42.12% | 330 | 139 |
| 8位 | 大阪大法科大学院 | 40.68% | 177 | 72 |
| 9位 | 神戸大法科大学院 | 37.50% | 136 | 51 |
| 10位 | 同志社大法科大学院 | 36.94% | 111 | 41 |
令和6年の法科大学院別の合格率を見ると、慶應義塾大学法科大学院が、100名以上の合格者数を輩出し、かつ、50%を超える合格率を出しています。そして、京都大法科大学院や東京大法科大学院、早稲田大法科大学院も100人以上の合格者を出し、40%以上の合格率をキープしています。
法科大学院のメリットは、合格率の低い予備試験とは異なり、法科大学院を終了(修了見込)できれば、3年以内に司法試験の受験資格を得ることができるという点です。そして、上位ロースクールでは、半数以上の受験者が合格しています。
法科大学院に進学することにより確実に受験資格を得ることができ、さらに、上位ロースクールに進学することができれば、40~50%の確率で合格を狙えるということがわかります。
したがって、司法試験は、合格が決して不可能ではなく、必要な勉強ができれば合格することができる試験であるといえます。
司法試験の難易度まとめ
司法試験は最難関の国家資格といわれており、難易度が高いことには変わりありません。
しかし、これまでに述べてきた通り、司法試験の合格率は年々上昇していること、合格ラインで求められている得点率は決して高くはないことなどから、司法試験は決して”無理ゲー”ではなく、必要な対策を着実に取ることで合格できる試験だといえます。
一方で、長い期間に及ぶ勉強量が必要であり、試験科目が多く、論文式試験が中心となっているため、的確な勉強を効率よくやっていくことが重要です。
アガルートは目的に合わせた8つの講座が用意されており、添削や質問制度も充実しています。
アガルートでは、合格に直結する力を磨くことができます。司法試験の合格を目指すうえで不安がある方は、アガルートにご相談ください。
司法試験・予備試験の受験を
検討されている方へ
- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?
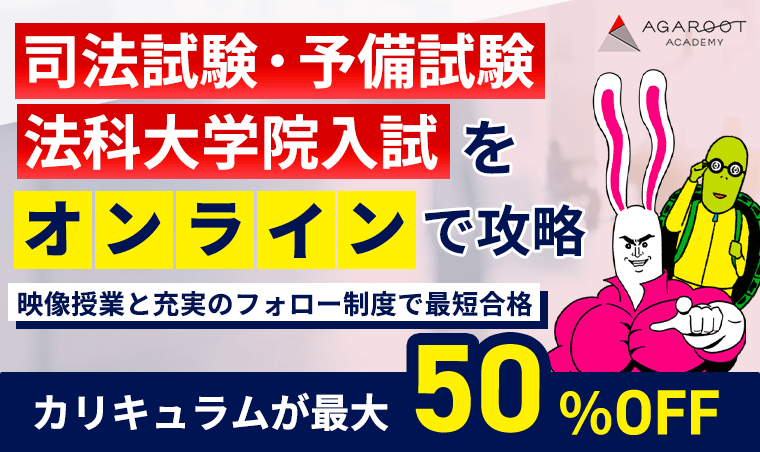
合格者の声の累計981名!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
予備試験合格で全額返金あり!!


サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、
司法試験の勉強についていけるかを試せる!
「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!
300名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!
司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る