【司法試験・予備試験】 演習書おすすめ14冊!効果的な選び方・使い方についても

基本書や判例を読み、いざ答案を書くとなった時に、どのように問題文を読めばいいのか、どのように論述すればよいのかわからない方は多いでしょう。その際に参考になるのが演習書です。
しかし、どの演習書を使えばよいのか、わからず悩んでいる方は少なくありません。
多くの司法試験受験生が悩まれているのが演習書選びだと思われます。
このコラムでは、おすすめの演習書とその特徴、演習書の選び方、使い方を解説します。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変
- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?


約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
迷ったらこれ!司法試験・予備試験勉強でおすすめの演習書
※リンククリックで詳しい説明に飛びます
| 科目 | 書籍名 |
|---|---|
| 民法 | Law Practice民法Ⅰ~Ⅲ|商事法務 |
| 憲法 | 判例から考える憲法|法学書院 |
| 行政法 | 事例研究行政法|日本評論社 |
| 商法 | Law Practice 商法|商事法務 |
| 民事訴訟法 | 事例演習民事訴訟法|有斐閣 |
| 刑事訴訟法 | 事例演習刑事訴訟法|有斐閣 |
| 刑法 | 刑法事例演習教材|有斐閣 |
このコラムでは、各科目2冊ずつ演習書を紹介しますが、どの本を選べばよいのかわからないという方に、上記の表では各科目で最もおすすめする演習書をまとめています。
多くの受験生の間で使用されており、これを読んでおけば間違いないという1冊を厳選しています。
次章からは、ここで挙げた1冊を含む各科目2冊ずつ、おすすめの演習書を紹介します。
各演習書の詳細を知りたいという方はそれらの紹介をご覧ください。
【司法試験・予備試験】民法でおすすめの演習書
民法の演習書としては、多くの受験生が「Law Practice」を使用しています。
債権法については、「事例でおさえる民法 改正債権法」の解説が充実しており、使用する受験生が増えている印象を受けます。
Law Practice民法Ⅰ~Ⅲ|商事法務
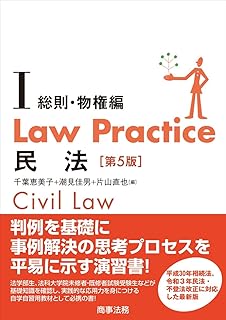 ※引用:amazon |
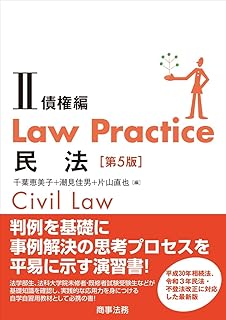 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
多くの受験生が利用している演習書です。
総論から親族・相続法まで司法試験の重要論点を押さえています。
判例事例をもとにしている事例問題が多く、司法試験にも役立ちます。
司法試験のひとつの設問くらいの分量の事例が書かれており、その後、解説がされています。もっとも、本演習書には解答例などは付いておらず、答案を具体的にどのように欠くのかについては別途学習が必要です。
事例でおさえる民法 改正債権法|有斐閣

事例演習を通して、なぜ改正が必要となったのか、改正後の問題点は何かについて解説されています。
今後、生じうる論点への検討もできる点が特徴です。
本書が想定している読者は法学部卒業生や未修1年次の民法科目履修終了者の民法の基本的な知識を備えている者とされています(はしがき)。
したがって、債権法を一通り学習した上で本演習書ができると、より理解が深まると思われます。
【司法試験・予備試験】憲法でおすすめの演習書
憲法は特にいろいろな演習書に手を出してしまいがちですが、絞って集中して学習することが重要です。
判例から考える憲法|法学書院

題名の通り、憲法判例について学べる演習書です。
憲法の判例は、一見判示内容がそう反しそうな判例や、相互の関係性が不明確な判例が多くあります。
複数の判例の結びつきをどのように考えるかを学べる演習書です。また、各章ごとに自らの立場の論拠、それに対する反論として使用できる、重要事項をまとめた部分があり、論述に生かせるメリットもあります。
憲法ガールⅠ~Ⅱ|法律文化社
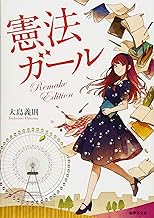 ※引用:amazon |
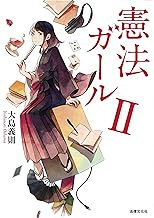 ※引用:amazon |
司法試験の過去問を会話形式で解説している本です。
解答例もついており、論述の参考にすることができます。
もっとも、本自体のレベルが高く、司法試験で上位答案を目指すという観点で読むとよいと思われます。司法試験問題を通して判例の射程が解説されているため、司法試験対策に適した演習書といえます。
【司法試験・予備試験】行政法でおすすめの演習書
行政法では、現在多くの受験生が事例研究行政法を使用しています。
基本シリーズから基本行政法判例演習が出版され、今後、使用する受験生が増えていくと思われます。
事例研究行政法|日本評論社

現在、受験生の中で最も定番となっている演習書のひとつです。
特に第1部では司法試験の頻出論点が扱われているため、行政法の学習を一通り終えた段階で解くことをおすすめします。
第2部では第1部よりもやや難易度の高い問題が、第3部では司法試験に近い形式の問題が掲載されています。
本演習書には解答例がついていないため、具体的にどのような答案を書くのかについては、ほかの学習が必要です。
基本行政法判例演習|日本評論社

2023年1月に出版された演習書で、基本書で受験生から人気のある基本行政法と同一の著者が書いています。
判例の事実、判旨などが紹介され、判例事例をもとにした関連問題が掲載されています。
判旨の紹介では判例の読み方が脇に書かれており、論理の構造を学ぶことができます。判例の考え方を、行政法の答案の流れに組み込めていない受験生に役立つでしょう。
【司法試験・予備試験】商法でおすすめの演習書
商法では、Law practiceを使用している受験生が多いです。
もっとも、授業の教材として、会社法事例演習教材が用いられている大学院もあり、後者の演習書も人気が高い状況になっています。
Law Practice 商法|商事法務
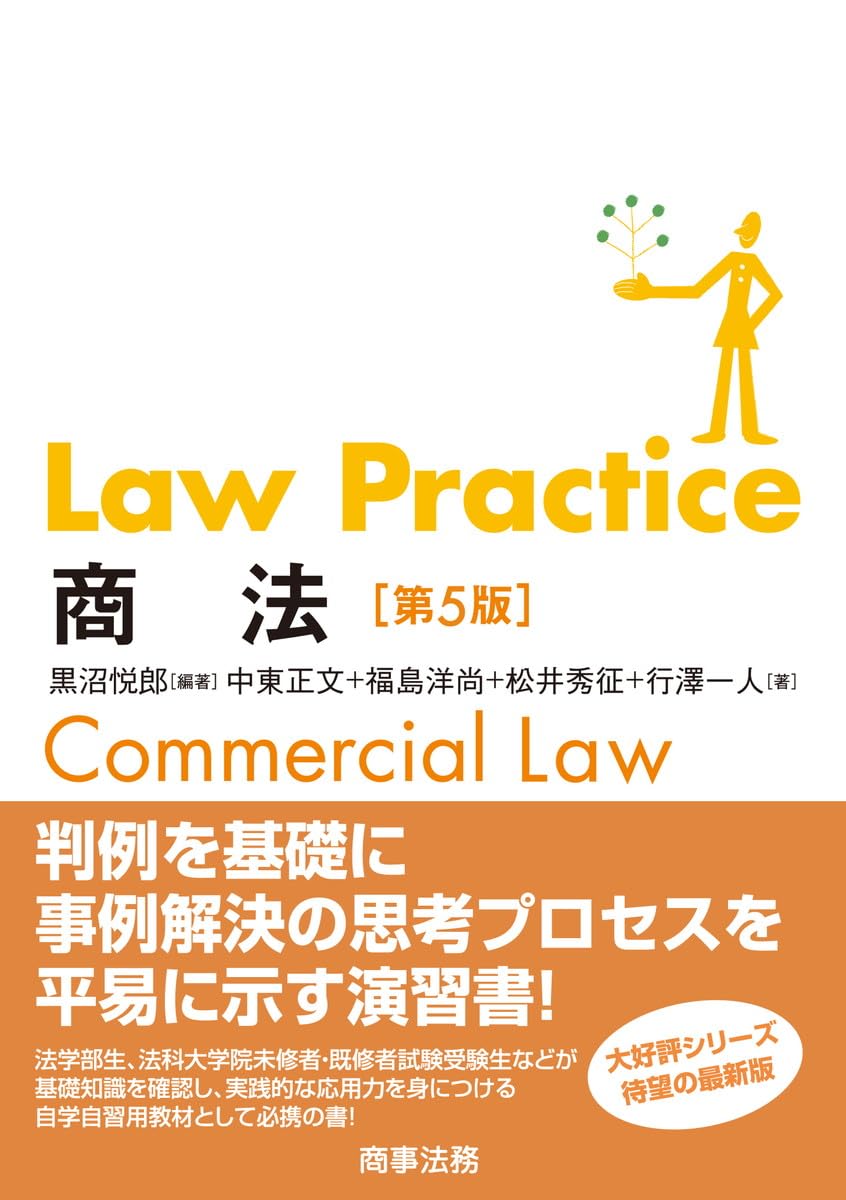
Law Practiceシリーズの商法編です。本演習書は百選に掲載されている事案をもとに作成されています。
司法試験は百選に掲載されている事案をもとに出題されることが多いため、司法試験対策に強くおすすめできる演習書です。
解答例はついていませんが、解説が丁寧で司法試験の論述に活かせる記述が多くあります。
会社法事例演習教材|有斐閣

刑法事例演習教材とともに、受験生に人気となっている演習書です。
京大本とも呼ばれています。もっとも、事例のレベルが高いため、予備試験対策に向いている演習書といえるでしょう。
本演習書には参考文献や参考判例のみが掲載されており、解説や解答例がついていないため、それらの文献を調べながら学習する必要があります。
【司法試験・予備試験】民事訴訟法でおすすめの演習書
民事訴訟法は、理解が難しい点、細かい論点が出題されている点から複数の演習書に手を出してしまいがちですが、1冊の演習書と過去問に絞って、何度も演習することをおすすめします。
事例演習民事訴訟法|有斐閣

本演習書は少しレベルが高めですが、考える力をつけるのに役立ちます。起案例が添付されているため、独学にも役立つ演習書です。
民事訴訟法では、基本原則などの理解を前提として、基本書や演習書ではあまり扱われていない問題が出題されることが多いです。
したがって、そのような未知の問題を解くために、考える力をつけることが重要です。
事例で考える民事訴訟法|有斐閣

近年、人気になってきている演習書です。
予備試験の分量の問題と解説が掲載されています。非常にレベルの高い問題が多いため、民事訴訟法で高い評価を得たいという受験生に向いています。
一方で、どのように答案を書けば良いかという観点から解説されており、初学者に役立つ記述も多くあります。
【司法試験・予備試験】刑事訴訟法でおすすめの演習書
刑事訴訟法では、事例演習刑事訴訟法が人気です。
あてはめ部分については、規範あてはめ刑事訴訟法が司法試験の参考になるでしょう。
事例演習刑事訴訟法|有斐閣

多くの受験生に使用されている演習書です。
解説は、会話文の形式で書かれており、受験生の疑問に沿って論じられている印象を受けます。
判例の規範や法原則が導かれる理由について熱く論じられています。
同シリーズの他科目の教材と同様に、レベルの高い問題が多く出題されています。したがって、刑事訴訟法で高評価を取りたい受験生におすすめの演習書です。
規範あてはめ刑事訴訟法|立花書房
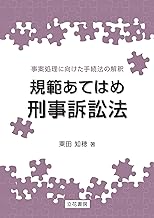
先ほど紹介した事例演習刑事訴訟法が規範定立理由を厚く書くための演習書であるのに対して、規範あてはめ刑事訴訟法は、あてはめ部分に着目した演習書です。
高裁裁判例を素材として規範の使い方を学習できます。具体的には、各重要論点について、規範を解説し、3つの裁判例が紹介されています。
刑事訴訟法の規範に、具体的にどの事実を挙げてどのような評価をすればよいのかを学習でき、全受験生におすすめできる演習書です。
【司法試験・予備試験】刑法でおすすめの演習書
刑法では、以下の2冊を多くの受験生が利用しています。
刑法事例演習教材|有斐閣

刑法では最も定番の演習書となっています。
司法試験・予備試験でも本演習書の事例と類似の問題がよく出題されており、司法試験対策に役立つ演習書です。
複数の論点を含む事例が紹介され、解説されています。もっとも、本演習書の解説は薄く、独学で取り組む場合は、刑法について一通り学習が進んだ時期がよいでしょう。
刑法演習サブノート210問|弘文堂
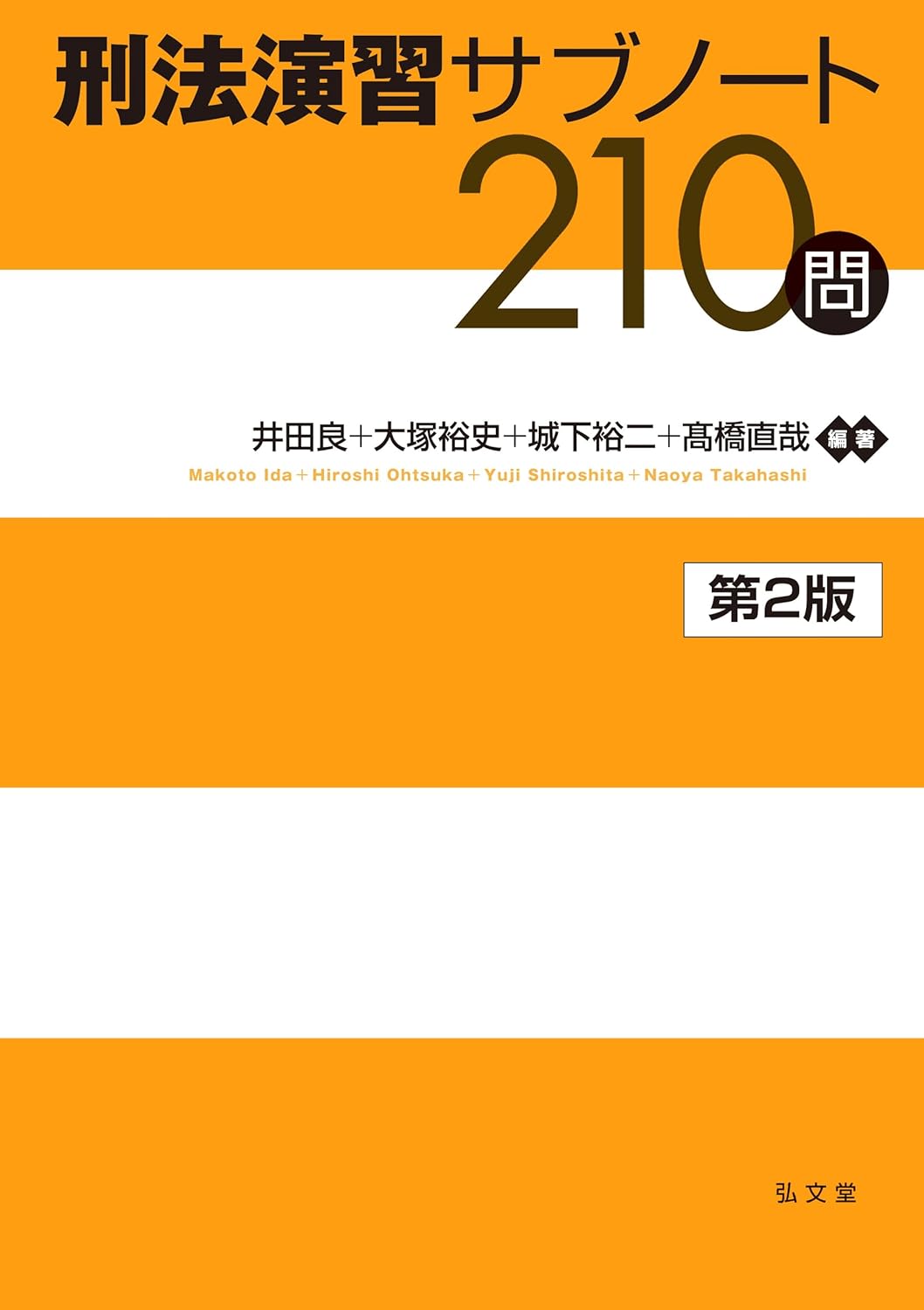
1頁に簡単な事例と設問が書かれており、その裏に解説が書かれている演習書です。
題名の通り、多くの問題で刑法全体を網羅することができます。
論点の網羅性の観点からは最も優れた演習書の中の1冊といえます。初学者から試験直前期の受験生まで、おすすめできる演習書です。
【司法試験・予備試験】演習書の選び方
これまでおすすめの演習書とその特徴について説明してきました。
ここでは、演習書の選び方について説明します。演習書を選ぶ大きな観点として、以下の2点があります。
- 解答例が付いているかついていないか
- 自分のレベルや目的に合ったものを選ぶ
解答例が付いているかついていないか
1点目は、解答例の有無です。
演習書には解答例が付いているものとついていないものがあります。各科目の答案の型や論証が定まっていない方は、解答例が付いているものを選ぶことができると、実際にどのような答案を書けばよいのかがわかり、参考になります。
もっとも、解答例は必ずしも司法試験向きの論述になっていない場合があります。
論述が足りないところがあったり、反対に、司法試験合格に求められている以上のことが書かれたりしている場合があります。そのことを前提に解答例を検討できると、より間違いのない理解に繋がります。
自分のレベルや目的に合ったものを選ぶ
2点目は、演習書のレベルです。演習書には、初学者に適しているものから、司法試験直前期の受験生、その中でも上位合格を目指す方に適しているものまで、それぞれのレベルがあります。
自分の学習のスピードや、目指すレベルに合わせて演習書を選ぶことが重要です。
レベルを確認するうえで参考になるのが演習書のはしがきです。
多くの演習書では、どういう人をターゲットとしているかが書かれていることが多いです。はしがきを読み、自分のレベルにあっているものかどうかを確かめたうえで、中身を確認できるとスムーズです。
【司法試験・予備試験】演習書の効果的な使い方
最後に、演習書の効果的な使い方について以下の3点を説明します。
- 使用する順番(優先順位)を間違えない
- 事案と論述のポイントを理解する
- 典型論点については過去問と演習書で反復する
使用する順番(優先順位)を間違えない
演習書には多種多様なものがあります。そのため、すべての演習書をやりきることは不可能であるため、それらすべてをやる必要もありません。
場合によっては有害になってしまうこともあります。中でも過去問の検討をせずに演習書に飛びついてしまうことは危険です。
司法試験の過去問の出題形式や、出題されている論点、事例の作り方を確認しないまま、演習書を検討したとしても、どの部分に着目し、深める必要があるのかがわからないまま検討することとなります。
特に、典型論点については過去問で出題されている事例と似ている形で出題される可能性が高いです。
また、出題趣旨や採点実感で、どのように書けば点数がより入るかが書かれています。
どの演習書よりも参考にすべき解説であるため、検討は必須です。
最良の演習は過去問であることを頭において、演習書は、過去問で扱われていない論点や、過去問の関連論点を押さえるような形で使用できるとよいです。
事案と論述のポイントを理解する
答案を書くためには、事案を分析し、論点を把握し、条文・規範を定立し、適切な事実をあてはめ、結論を出す必要があります。
したがって、過去問や演習書で押さえるポイントは、事案の分析の仕方と、論述の仕方です。
出題者は、各問題で論じてほしいことを念頭に事例を作成します。したがって、事例から出題者が論じてほしいことを読み取る力が必要です。
過去問であれば出題趣旨や採点実感、演習書であれば解説を読み、出題者がどの事実に着目してほしかったのかを確認することで力がつきます。
また、規範に対してどの事実をあてはめるべきかについても、出題趣旨・採点実感や、演習書の解説で述べられています。
多くの場合、もととなっている判例がどのような事実を考慮して検討しているかです。判例の理解を深めるうえでも過去問・演習書で力をつけることができます。
典型論点については過去問と演習書で反復する
上記でも述べましたが、典型論点で一番参考になる演習は過去問です。
まずは過去問を検討し、どのような論述をすれば点数がとれるのか、合格答案のレベルに立つことができるのかを確認する必要があります。
そのうえで、典型論点がどのような出題のされ方をしても答えられる力をつけるために、演習書が効果的です。
過去問と演習書で反復して学習することによって、他の受験生よりも当該論点について厚い論述を行うことができるようになります。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
予備試験合格で全額返金あり!


約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る