予備試験の一般教養は対策すべき?効率的な勉強法とは?問題内容も解説

司法試験予備試験の短答式試験には、法律基本科目の他に一般教養という、短答式試験の合計得点270点のうち60点を占める科目があります。
他の法律基本科目(7科目)がそれぞれ30点ずつしかないことを考えると、一般教養科目が短答式試験のかなりのウエイトをしめていることがわかります。
とはいえ、予備試験を受験しようとする方の中には、
「一般教養の試験って何が問われるの」
「対策ってどのようにしたらいいの」
「これまで自分なりに勉強して、短答式試験に挑戦しているが、一般教養でなかなか点数を伸ばすことができない」
などの様々な悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このコラムでは、一般教養の試験内容だけでなく、その重要性や合格のために必要な効率的な勉強法について紹介していきます。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変
- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?


約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
司法試験予備試験における一般教養の重要性と難易度!対策はすべき?
予備試験の短答式試験における一般教養科目は、全体の270点中60点という高い配点を持ちながら、その内容は非常に幅広く、難易度も高いと言われています。
人文科学から社会科学、自然科学、さらには英語まで、その範囲は多岐にわたります。一方で、この科目は司法試験には含まれていないため、多くの受験生はこの部分の対策を軽視してしまう傾向があります。
実際、42問の問題群から好きな20問を選ぶ形式のため、得意な分野だけをピックアップして解答するという戦略を取る受験生が少なくありません。
しかし、この一般教養科目には、しっかりと対策を行うことで得点の取りやすい部分も存在します。
特に、社会科学の範囲は学びやすく、過去問を見ると一定の傾向があり、得点源として期待できる部分です。また、大学入試での社会や理科に該当する人文科学も、頻出トピックを中心に学習することで、得点を伸ばすことが可能です。
もちろん、法律の基本科目が最優先ですが、一般教養科目にも適切な対策を施すことで、短答式試験全体の得点を大きく伸ばすことができるのです。
下記より、そんな一般教養科目の効果的な勉強方法について詳しく解説していきます。
司法試験予備試験に合格するために必要な一般教養の勉強法
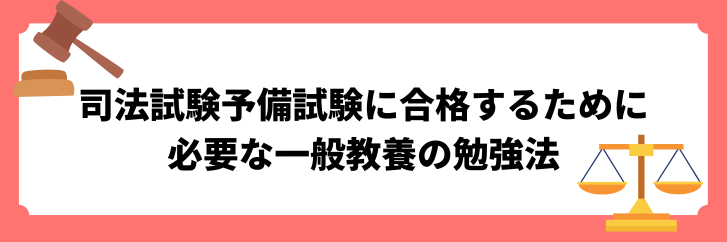
予備試験の短答式試験に合格するためには点数の割合の高い一般教養で得点を稼ぐことが一つの鍵になります。
この章では、そもそも一般教養で問われる問題内容は何か、そして効率よく得点を稼ぐために必要な勉強法は何かということについて紹介します。
問題内容は、①人文科学、②社会科学、③自然科学、④英語の4つの分野から40問程度出題され、特定の分野に偏ることのないよう、バランスよく知識や論理能力などが問われます。
そのような出題内容の一般教養科目ですが、予備試験、しかもその短答式試験でしか出題されません。
そのため、最終的な司法試験合格のためということを考えても、時間のかけすぎにも気をつけなければならず、効率的に勉強することが求められます。
対策の時期によって適した勉強法は少し異なりますが、重要な勉強法は主に三つあります。
まず、全期間に共通して重要な勉強法は過去問を解くことで、一般教養の試験の出題傾向と対策をつかみ、また繰り返し出る問題についての知識を身につけることです。
そして、対策の時期に応じた重要な勉強法は、長期的には、一般教養の択一問題をコツコツ満遍なく継続して解くこと。
直前期には、得意な分野や範囲に絞ってメリハリをつけて知識を身につけることがあげられます。
下記に記載する各勉強法の詳細を把握し、一般教養試験の自信をつけて、得点源にしましょう。
一般教養の試験で問われること
一般教養の試験は全部で40問程度あり、主な出題内容・分野は上記のとおり、①人文科学、②社会科学、③自然科学、④英語です。
ここではそれぞれの内容や特徴について紹介します。
①の人文科学は、日本史・世界史・地理、思想・哲学、文学・芸術の分野からの出題になります。②にも言えることですが、論理問題や英語とは異なり、ある程度の知識がなければ解けない問題が多く、得点を稼ぐには事前の準備が重要な分野です。
②の社会科学は、政治・経済分野や社会学分野から出題されます。4つの中でも比較的範囲が絞られており、対策は立てやすい科目とされています。
③の自然科学は、物理・化学・生物・地学・数学などの理数系から出題されます。
予備試験は文系出身の受験生が多いので全く解けない問題ばかりだと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、中にはよく考えれば解ける問題や大学受験時のセンター試験の理科基礎等の知識を使って解くことができる問題もあります。
④の英語は、全体的に比較的高度な内容が問われます。
法務省が発表したサンプル問題では空欄あてはめのような文法問題がでていますが、近年では適度な量の英語長文をもとにした問題が出題されています。
これら全ての分野の問題を必ず解かなければならないわけではなく、受験者はこの中から自分の得意な問題や解けそうな問題を選択して、40問のうち計20問解けば良いだけなので、そこまで過剰に恐れる必要はありません。
しかし、それぞれの分野の範囲は広いうえ、試験内容自体も簡単ではありませんので、一朝一夕で習得できるほど甘い試験でもありません。
得点を稼ぎにいくのであればきちんとした対策を立てる必要があります。
以下では一般教養の試験で得点を稼ぐのに効率的な勉強法を紹介していきます。
過去問を解いて出題傾向と対策をつかむとともによく出る内容については知識をインプットする
一般教養科目に限らず、過去問と全く同じ問題が試験本番で問われることはほとんどありません。
しかし、他の科目と同様に一般教養科目も出題方法・傾向は過去の試験から把握することができ、よく問われる分野・知識があることに気がつくことができます。
また、過去問をよく解いていくことで、一例ですが、①前提知識がなくともよく問題を読んだり、論理的な思考のみで解ける問題、②前提知識を一定程度要するが、それがあれば問題文や論理的思考を使って解くことができる問題、③知識のみで解くことができる問題というように類型化し、そのうちどのような類型の出題が多いかということも把握できるようになります。
これによって、自分の目標とする得点をとるために、どの分野においてどの程度の知識・量が必要かというゴールまでの道筋をはっきりと見据えることができ、精神的にも物理的にも対策が立てやすくなります。
さらには、過去問を解き、解答解説を参照していく過程で、出題された問題やよく問われる分野についての知識をインプットすることができます。
このように、過去問は試験対策にとって宝の山ですので、ぜひ活用してみてください。
長期的には一般教養の択一問題をコツコツ継続して解く
一般教養の試験範囲は、上述のとおり範囲が膨大です。
中には、予備試験の短答式試験を見据えて、長期的に対策を行おうという方もいらっしゃるかと思います。
膨大な範囲の知識を教科書などでカバーしようとすると時間はいくらあっても足りませんので、よく試験で問われる問題や分野がまとめられた問題集や択一六法などを活用して択一問題を一日何分程度でもいいので時間を決めて、塵も積もれば山となるの精神で毎日解き続けましょう。
もちろん択一問題ですべてをカバーできるわけではないですが、長期の対策で、よく出る分野や基本的な分野においては満遍なく知識を得られるとともに、直前期の対策が非常に楽になります。
直前期は得意分野に絞ったメリハリのあるインプットをする
膨大な範囲の一般教養をすべて直前期にカバーすることは不可能です。
さらにいえば、一つの分野ですら、直前期にすべて対策をすることは難しいので、大学受験などのこれまでの試験等を通してある程度自信を持つことができた分野に絞って対策をすることが重要です。
その分野について、過去問から出題内容を予想したり、絶対に解くことができる問題をつくるという意思をもったりなどによって、さらなる重点的な対策をおこなうことができれば、時間の非常に限られる直前期にあれこれ手を出して満遍なく不十分な知識を得るよりは確実に効率よく得点アップを図ることができます。
直前期はメリハリをつけた知識のインプットに努めましょう。
一般教養の勉強法においてやってはダメなこと
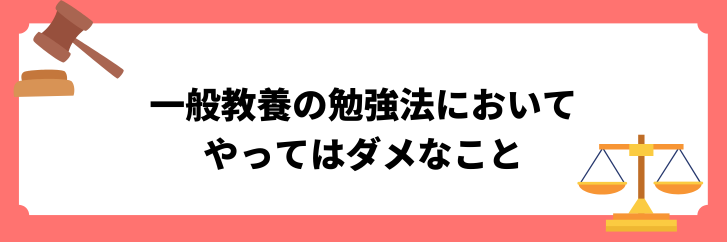
これまで予備試験短答式試験を突破するために必要な勉強法を紹介していきましたが、ここでは、逆にやってはいけない勉強法を紹介します。
まず一つ目は、すべての分野をカバーしようとして手を広げすぎてしまうことです。
法律基本科目と比べて得点の割合は大きいですが、試験範囲が膨大で、出題分野すべてを網羅的に勉強するのに莫大な時間がかかる一方で、それによって得られるものもさほど大きくありません。
得意分野や対策がしやすいとされている社会科学に絞るなどして効率重視の対策を立てましょう。
二つ目は、一つ目と関連しますが、一般教養の勉強に時間をかけすぎて法律基本科目の勉強をおろそかにしてしまうことです。
一般教養の試験は予備試験の短答式試験にしか出題されませんので、予備試験・司法試験合格との関係では、法律基本科目の勉強を差し置いて勉強するほど重要な科目ではないといえます。
そのため、まずは法律基本科目の勉強を優先し、あくまで一般教養の対策は、短答式試験の突破を容易にさせるためのものであるという位置付けで、最短で効率のよい対策にとどめましょう。
三つ目は、時間を測らずに過去問を解くことです。
法律基本科目と比較して一般教養科目の試験は、時間に余裕がありますが、余裕があると言ってもどのくらいのペースで解き進める必要があるのか、論理問題・英語・理数系等の試験本番で考える要素が大きい問題にどの程度時間を使うことができるのかなどについてはあらかじめ時間を測って問題を解くなどして準備をしておくべきです。
まとめ
- 予備試験の一般教養は、短答式試験270点中60点を占める
- 出題分野は、人文科学・社会科学・自然科学・英語の4つで、得意分野を活かした戦略が鍵
- よく試験で問われる問題をおさえておく
一般教養の対策は、法律科目とのバランスが重要です。効率的な学習計画を立て、得点を伸ばす戦略を意識しましょう。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
予備試験合格で全額返金あり!


約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る