【司法試験・予備試験】基本書のおすすめランキング35冊!科目別に紹介!

司法試験を目指す方が最初に悩まれているのが基本書選びだと思われます。
基本書はその法律について学ぶ最初の本になることが多いため、失敗したくありませんよね。
各法律について説明している本はたくさんありますが、どの本が司法試験に適しているのか、多くの受験生に読まれている本はどの本か、迷う方は少なくありません。
このコラムでは、各法律についておススメの基本書を5冊ずつ挙げて説明しています。基本書を選ぶ参考にしてみてください。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変
- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?


約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
- 1 迷ったらこれ!科目別でおすすめの基本書を紹介
- 2 【司法試験・予備試験】民法でおすすめの基本書ランキングTOP5
- 3 【司法試験・予備試験】憲法でおすすめの基本書ランキングTOP5
- 4 【司法試験・予備試験】行政法でおすすめの基本書ランキングTOP5
- 5 【司法試験・予備試験】商法でおすすめの基本書ランキングTOP5
- 6 【司法試験・予備試験】民事訴訟法でおすすめの基本書ランキングTOP5
- 7 【司法試験・予備試験】刑事訴訟法でおすすめの基本書ランキングTOP5
- 8 【司法試験・予備試験】刑法でおすすめの基本書ランキングTOP5
- 9 【司法試験・予備試験】基本書の選び方のポイント
- 10 【司法試験・予備試験】基本書の選び方でよくある質問
迷ったらこれ!科目別でおすすめの基本書を紹介
※リンククリックで書籍の詳しい説明に飛びます
| 科目 | おすすめの基本書 |
|---|---|
| 民法 | 民法(全)|有斐閣 |
| 憲法 | 憲法I 総論・統治、Ⅱ人権|日本評論社 |
| 行政法 | 行政法|弘文堂 |
| 商法 | 会社法LEGAL QUEST|有斐閣 |
| 民事訴訟法 | コンパクト版 基礎からわかる民事訴訟法|商事法務 |
| 刑事訴訟法 | 刑事訴訟法LEGAL QUEST|有斐閣 |
| 刑法 | 基本刑法Ⅰ総論、Ⅱ各論|日本評論社 |
このコラムでは、各科目5冊ずつ基本書を紹介しますが、5冊のうち、どの本を選べばよいのかわからないという方に、上記の表では各科目で最もおススメする基本書をまとめています。
多くの受験生の間で使用されており、これを読んでおけば間違いないという1冊を厳選しています。
次の章からはここで挙げた1冊を含む各科目5冊ずつ、おススメの基本書を紹介しています。各基本書の詳細を知りたいという方はそれらの紹介をご覧ください。
【司法試験・予備試験】民法でおすすめの基本書ランキングTOP5
民法では、総則、物権法、担保物権法、債権総論、債権各論、親族・相続で1冊ずつ基本書がわかれていることが多いです。
ここでは、1冊またはシリーズで民法全体を網羅している基本書を中心に紹介しています。
1位|民法(全)|有斐閣

総則から親族・相続法までを1冊で解説している基本書です。
限られたページ数で民法全体を解説しているため、網羅性は高くなく、通説・判例の立場を簡潔に説明しているという印象を受けます。
そのため、司法試験前にまとめノートのような活用の仕方ができると良いです。
2位|民法Ⅰ~Ⅵ LEGAL QUEST|有斐閣
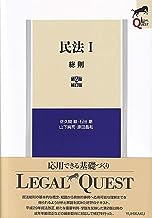
基本的なところから解説されており、初学者でも理解しやすい内容になっています。
もっとも、論述に物足りないところもあり、通読後はアウトプットを通して、足りないと感じたところをほかの基本書で補うという意識を持っておく必要があります。
民法のリーガルクエストシリーズ内では、Ⅳ親族・相続への評価が高く、多くの受験生にも使用されています。
3位|コア・テキスト 民法[エッセンシャル版]|新世社
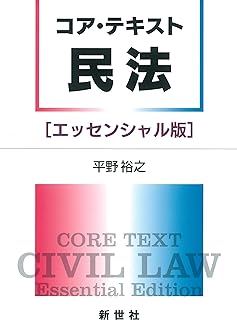
1冊で民法全体を解説しています。
1位に挙げた民法(全)よりも網羅性が高い点が特徴です。
しかし、基礎から丁寧に解説されている本ではなく、一通り民法について学習した人が試験前に読み返すのに適している本といえます。
4位|民法の基礎1総則 民法の基礎2物権|有斐閣
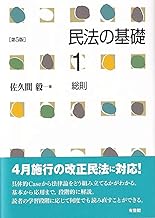 ※引用:amazon |
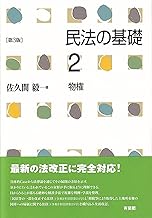 ※引用:amazon |
本の題名通り民法の各制度を基礎から説明しています。
もっとも、司法試験合格に十分な情報・論述がされており、また、挙げられている判例も豊富です。
特に総則は多くの受験生に読まれており、最も定番の基本書のひとつといえます。
5位|基本講義 債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得 基本講義 債権各論Ⅱ不法行為|新世社
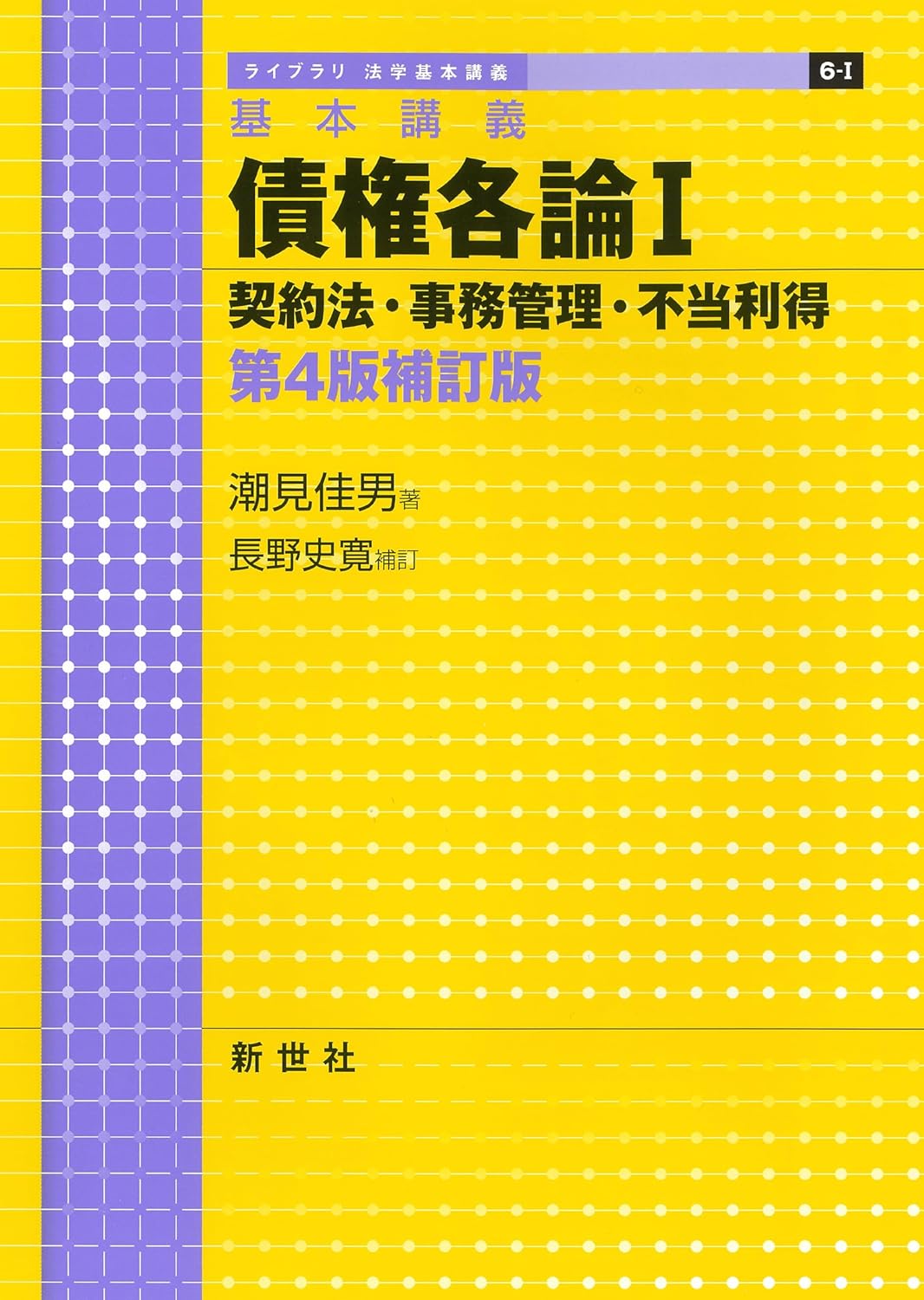 ※引用:amazon |
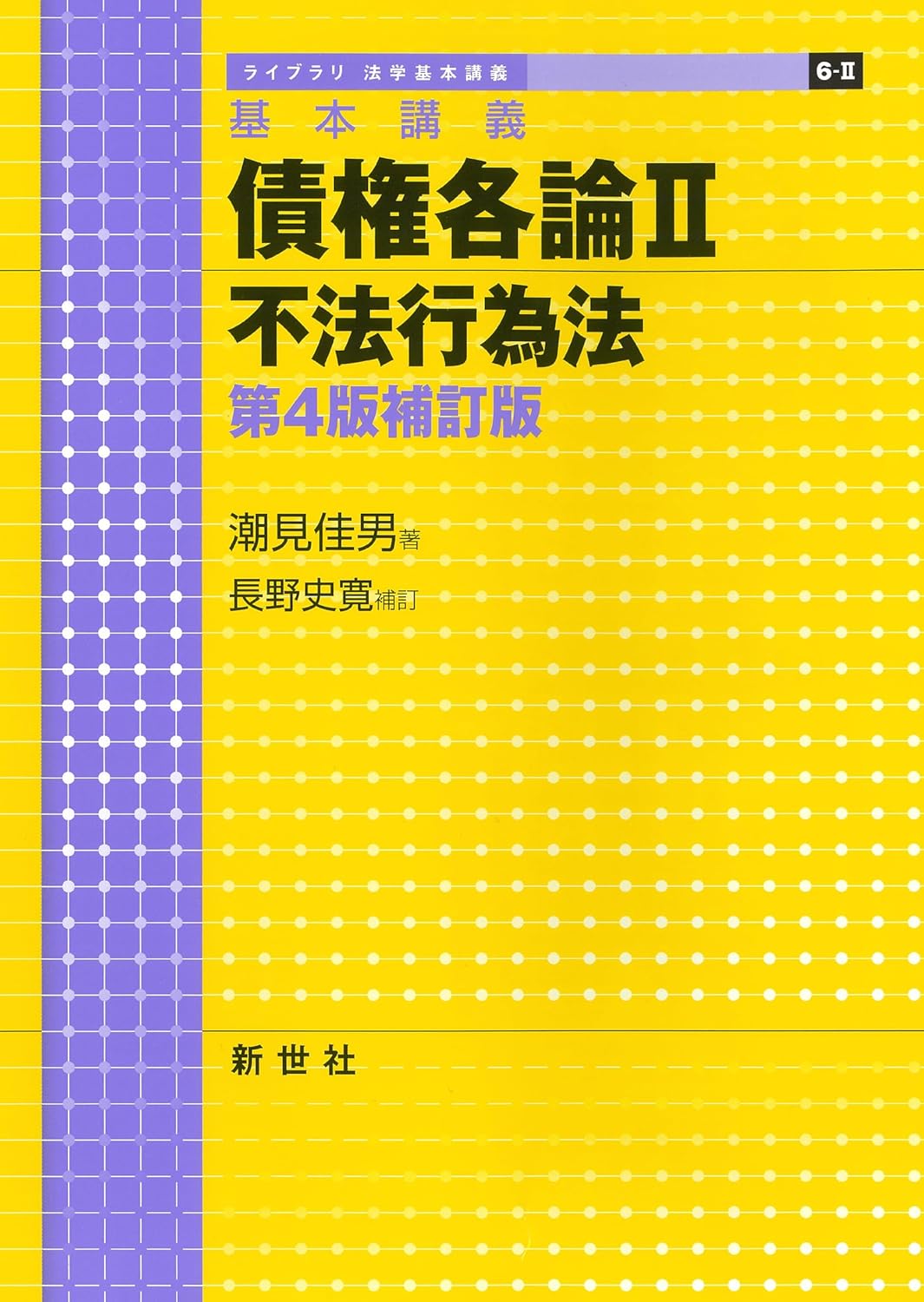 ※引用:amazon |
もっとも、1位で挙げた基本書と著者が同一であり、大部分の記述が重なっています。多くの受験生に読まれており、各論分野では最も定番の基本書のひとつです。
【司法試験・予備試験】憲法でおすすめの基本書ランキングTOP5
憲法は判例をどのように答案に落とし込むかで迷われている方も多いでしょう。
判例の考え方を答案に書けるようにするという観点から、判例の解説をしている基本書を中心に挙げています。
1位|憲法I 総論・統治、Ⅱ人権|日本評論社
 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
憲法の基本から説明されています。
はしがきにも書かれていますが、通説・判例の記載が中心となっており、憲法特有の細かい学説上の議論には立ち入っておらず、司法試験対策にも適しているといえます。
近年、使用する受験生が増えてきている印象です。
2位|基本憲法Ⅰ 基本的人権|日本評論社

基本シリーズの憲法です。
ページ数が372頁とコンパクトであり、内容も判例の見解を中心に書かれています。
判例が示している規範をどのように司法試験の答案に書くかという観点で解説されており、違憲審査基準の定立で迷っている受験生は必読といえます。
3位|憲法|岩波書店
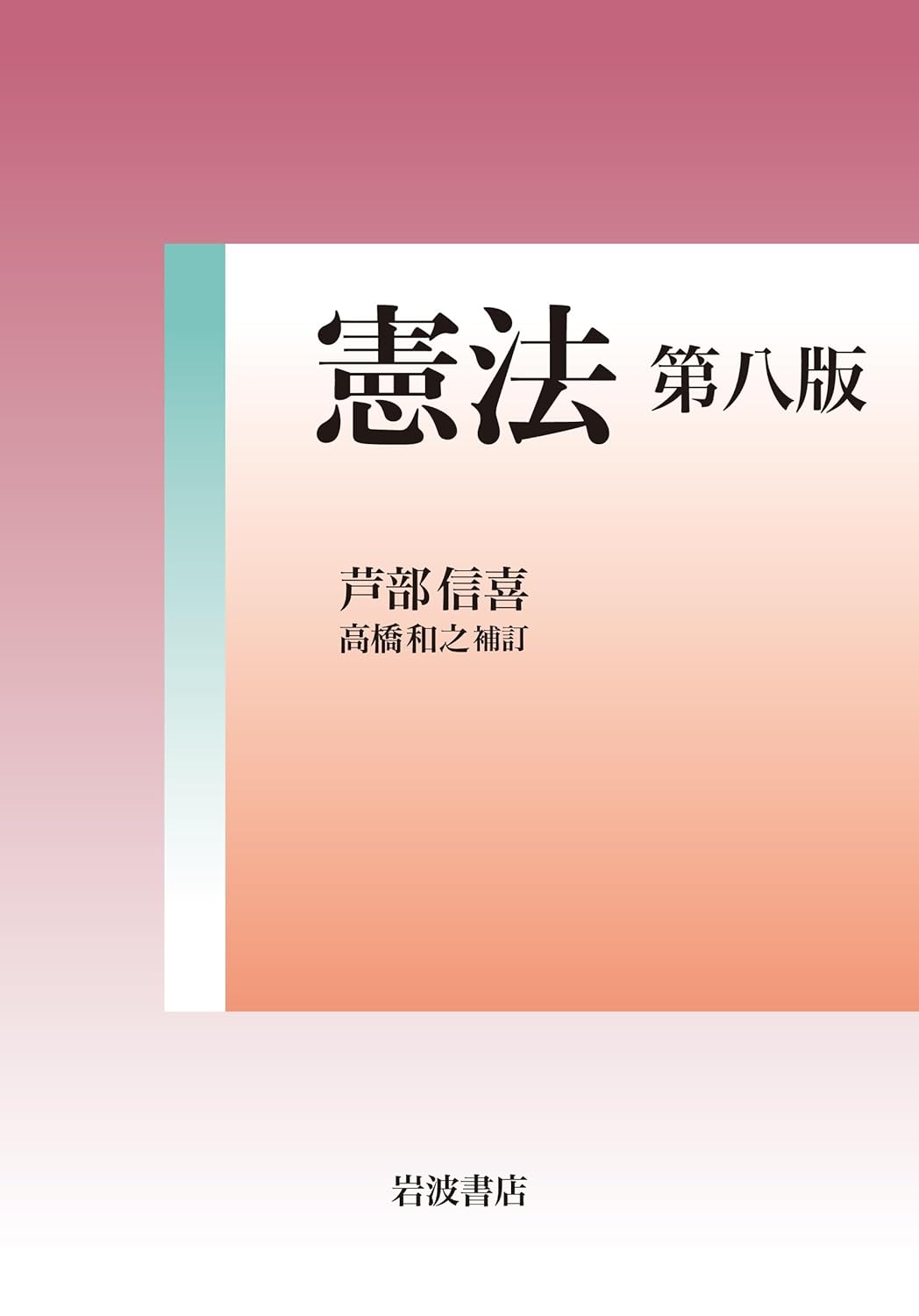
芦部憲法と呼ばれている基本書です。
憲法の通説はほとんどが芦部説であり、司法試験を受験するうえで最も重要な基本書のひとつです。
特に、総論・統治分野については、短答式試験で本書の文章がそのまま出題されることがあり、必読の一書といえます。
4位|憲法Ⅰ基本権、Ⅱ総論・統治|日本評論社
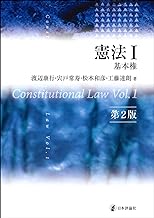 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
判例を重視している基本書です。
受験生には特に憲法Ⅰ基本権が多く使用されています。三段階審査の手法から判例が分析されており、司法試験に役立つ記述も多いです。
ほかの基本書を読む中で疑問に思った点や足りない点を辞書的に活用する受験生も多いです。
5位|憲法学読本|有斐閣
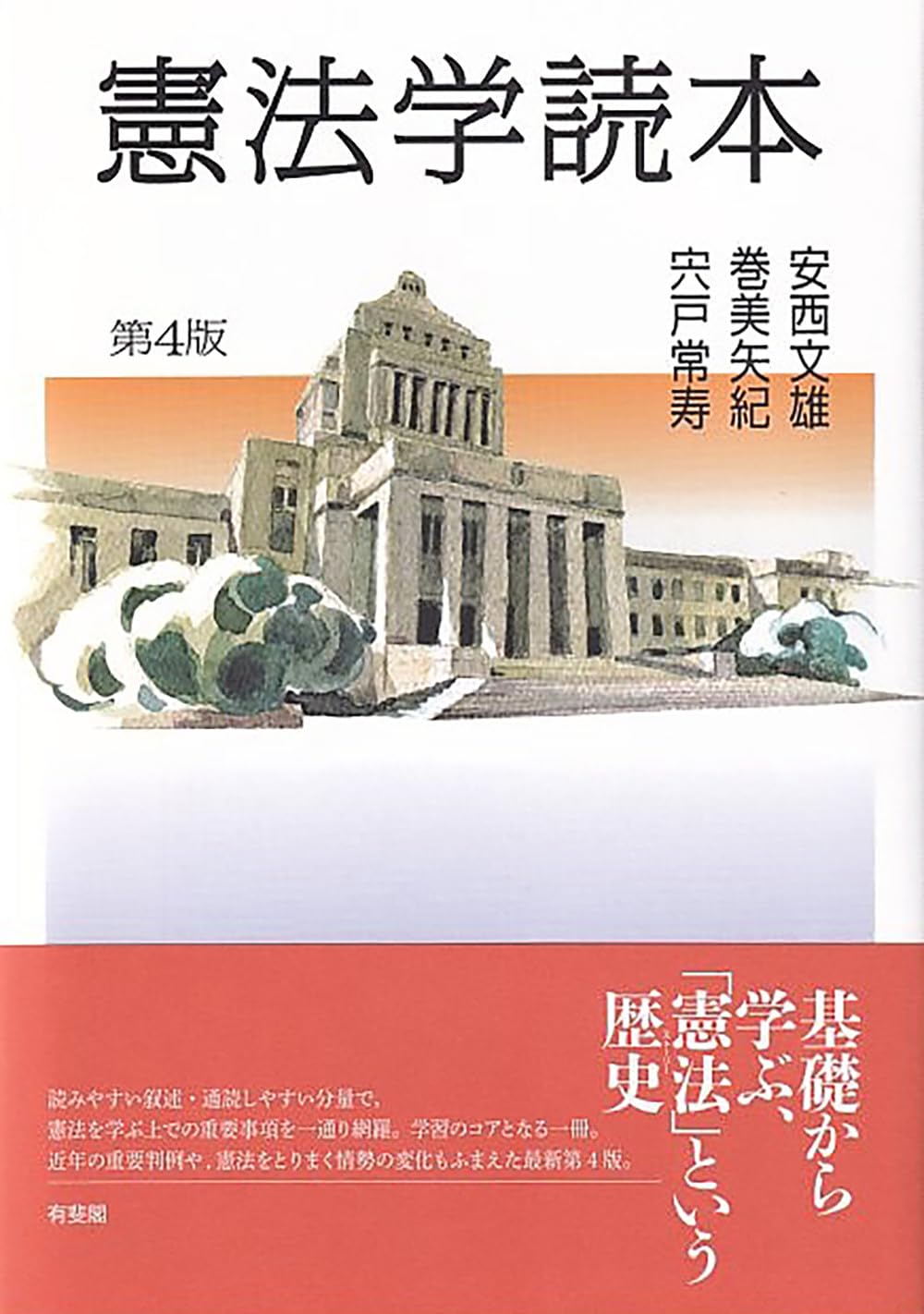
憲法の全体像をつかむために有益な基本書です。
統治と人権を1冊で解説しており、コンパクトでわかりやすい記述になっています。
もっとも、個々の論点について深く学ぶためには足りないこともあり、ほかの基本書などで補う必要があります。
【司法試験・予備試験】行政法でおすすめの基本書ランキングTOP5
行政法の基本書について説明します。受験生の多くが、1位か2位の基本書を使用している印象です。
1位|行政法|弘文堂
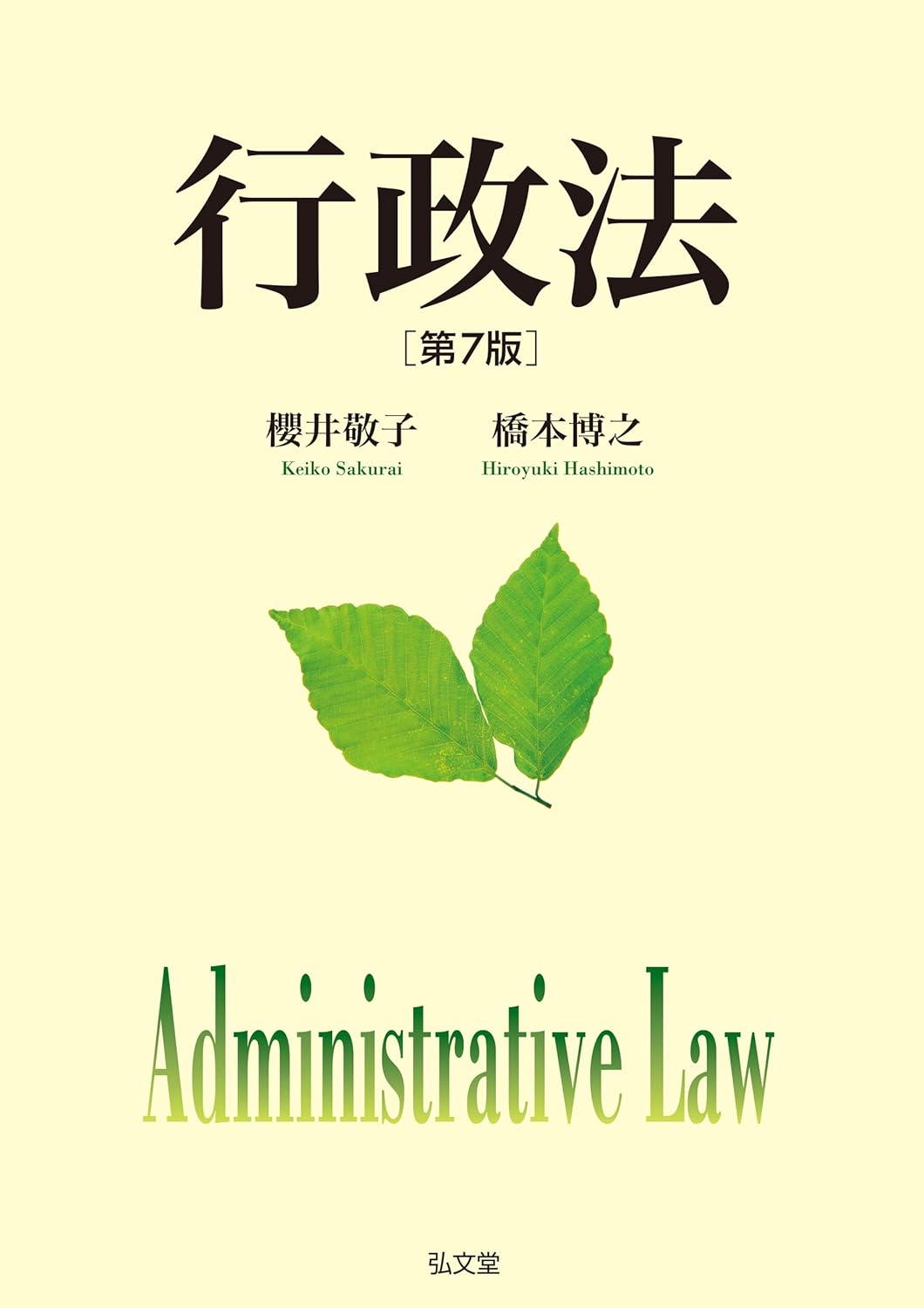
サクハシとよばれている基本書です。判例が多く掲載されている点に特徴があります。
コンパクトな記載にとどまっているため、判例の結論や規範を導く理由については、行政判例ノートで確認しておく必要があります。
2位|基本行政法|日本評論社
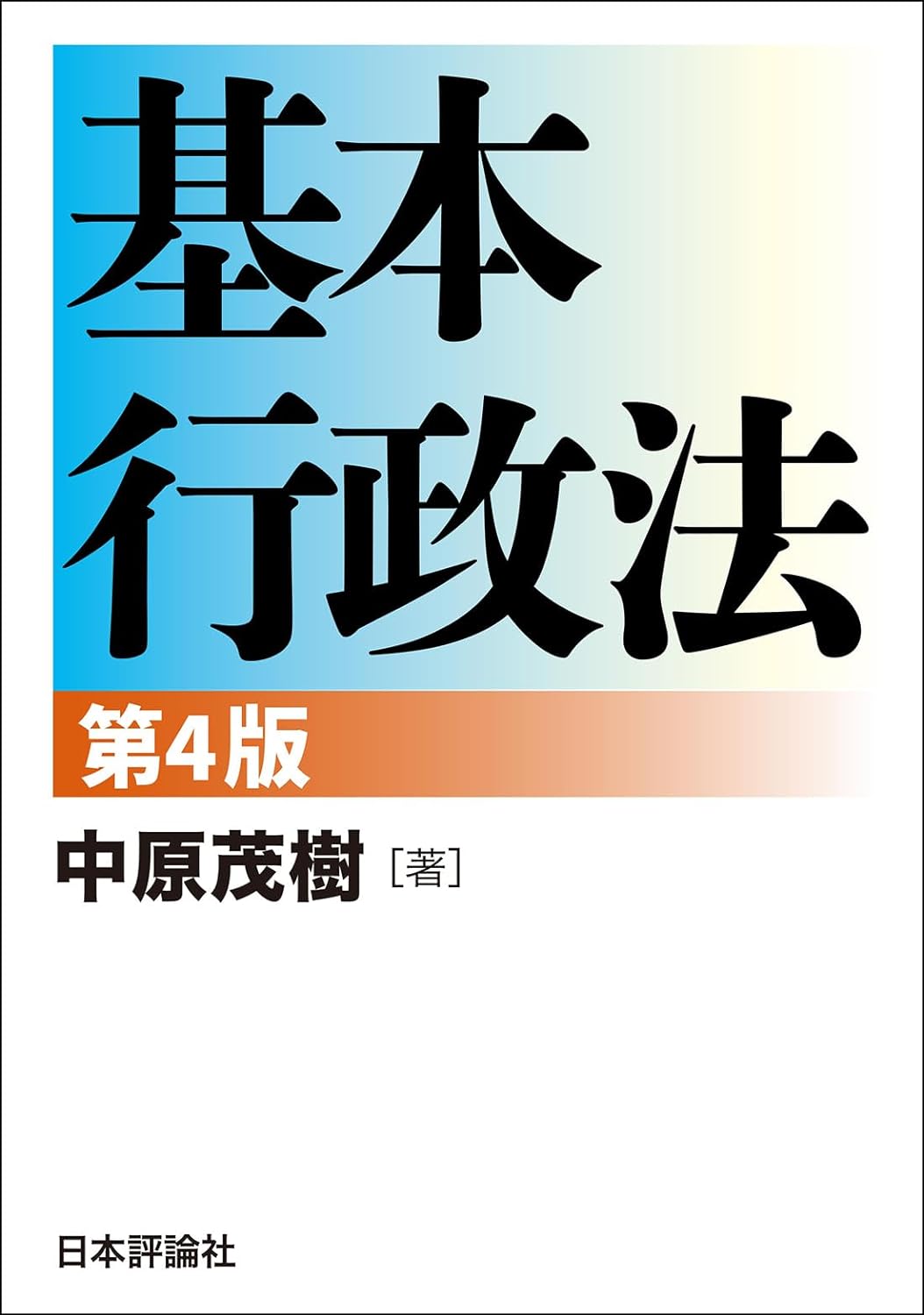
基本シリーズの行政法編です。
それぞれの論点について基本となる重要な判例に対し解説されており、答案作成上も参考にできる記述が多いです。
近年の司法試験の判例の考えを示しながら答案を作成させる問題における対応でも有益です。
3位|スタンダード行政法|有斐閣

行政法の入門書です。
具体例や図表により、通説・判例がわかりやすく説明されています。
また、各章に演習問題とその解答例がつけられており、判例の理解を深めるために有益です。
本書を通読し、行政法全体の理解を深めたあとに、ほかの基本書を読むことによって、よりわかりやすく行政法を学ぶことができる一書です。
4位|行政法概説Ⅰ行政法総論 行政法概説Ⅱ行政救済法 行政法概説 行政概説法Ⅲ行政組織法/公務員法/公物法|有斐閣
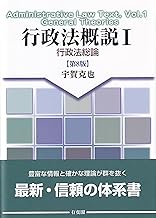 ※引用:amazon |
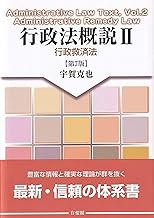 ※引用:amazon |
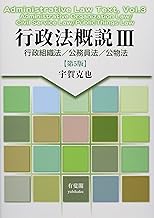 ※引用:amazon |
基礎から実務で使える情報まで、幅広い読者を想定している基本書です。
メジャーな基本書の中では最も情報量が多いと思われます。基本的な内容が大文字で、発展的な内容が小文字で書かれており、メリハリをつけて読むことができます。
5位|行政法Ⅰ行政法総論 行政法Ⅱ行政救済法 行政法Ⅲ行政組織法|有斐閣
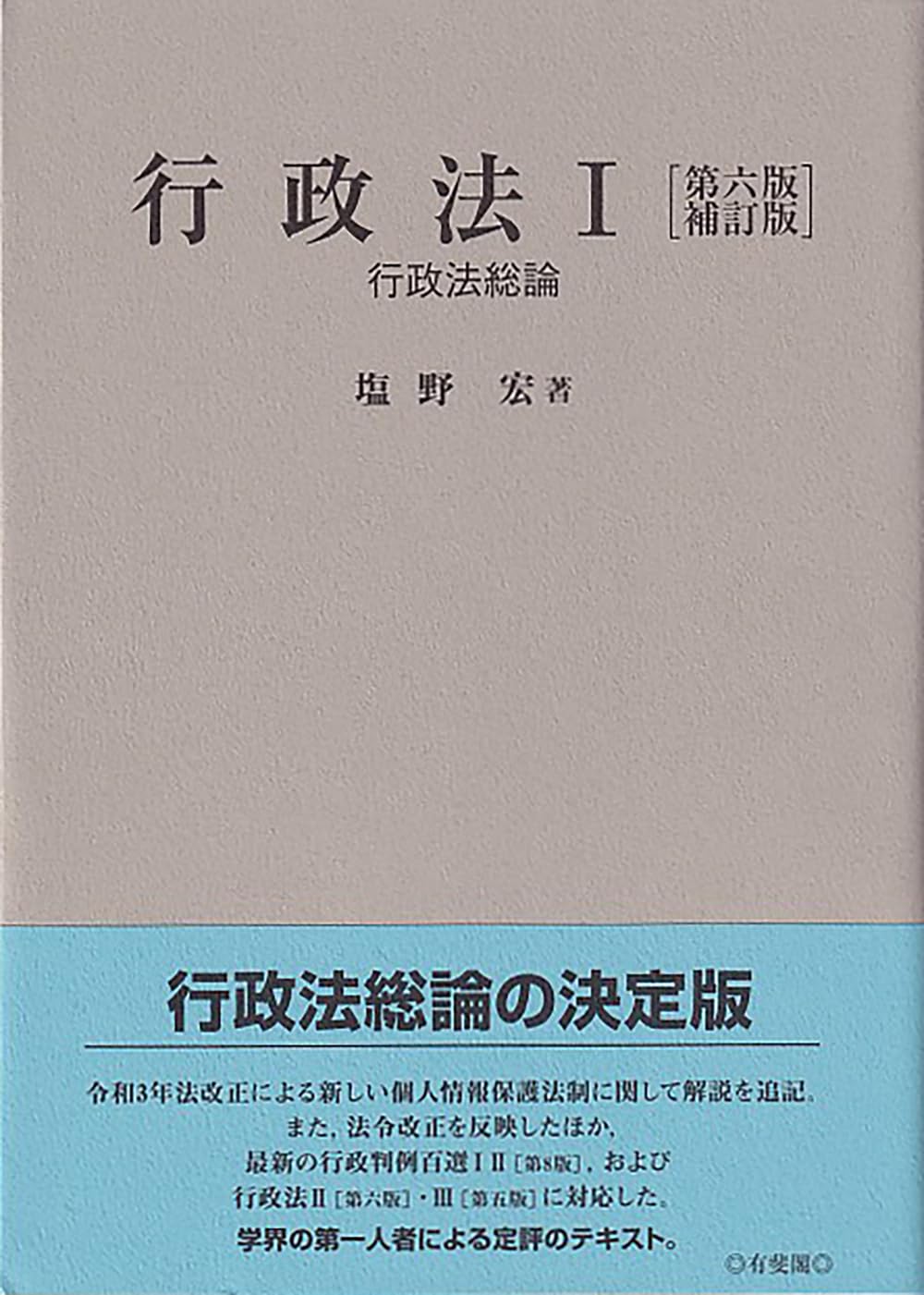 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
行政法における通説は塩野説が多く、ほかの基本書でも参照されることが多い基本書です。3冊本であることから情報量は多く、論述も丁寧です。ほかの基本書を読みながら辞書的に使用するという受験生が多い印象です。
【司法試験・予備試験】商法でおすすめの基本書ランキングTOP5
司法試験の商法はほとんどが会社法からの出題となっています。ここでは、会社法の基本書について説明します。
1位|会社法LEGAL QUEST|有斐閣

司法試験対策に最も適している基本書のひとつです。
コンパクトに判例の立場の解説がされています。
発展的内容について触れているコラムの中にも司法試験に必要な知識があり、一通り通読することが重要です。
2位|会社法|弘文堂
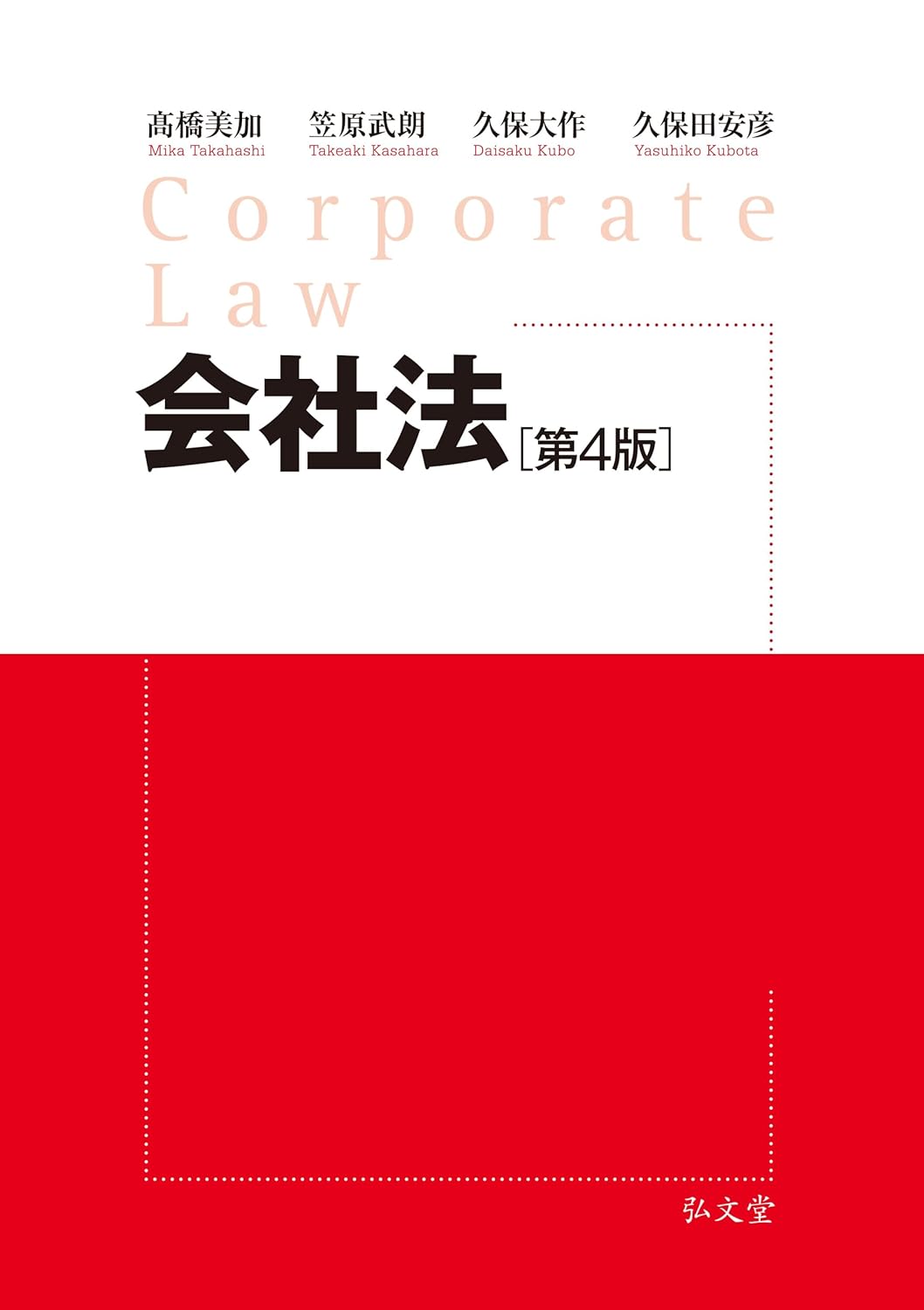
通説・判例の解説が丁寧にされている一方、学説の細かい対立についての記述は少なく、司法試験を意識した基本書といえます。
理解が難しい分野については、絵も使いつつ、わかりやすく説明されています。
3位|会社法|有斐閣

有斐閣ストゥディアシリーズの会社法です。
基本的な会社法の制度・判例について、わかりやすく説明されている入門書です。
基本書としては内容が薄いですが、会社法では判例学習が中心となるため、判例百選などの判例集と併せて利用する受験生も多いです。
4位|会社法|東京大学出版会
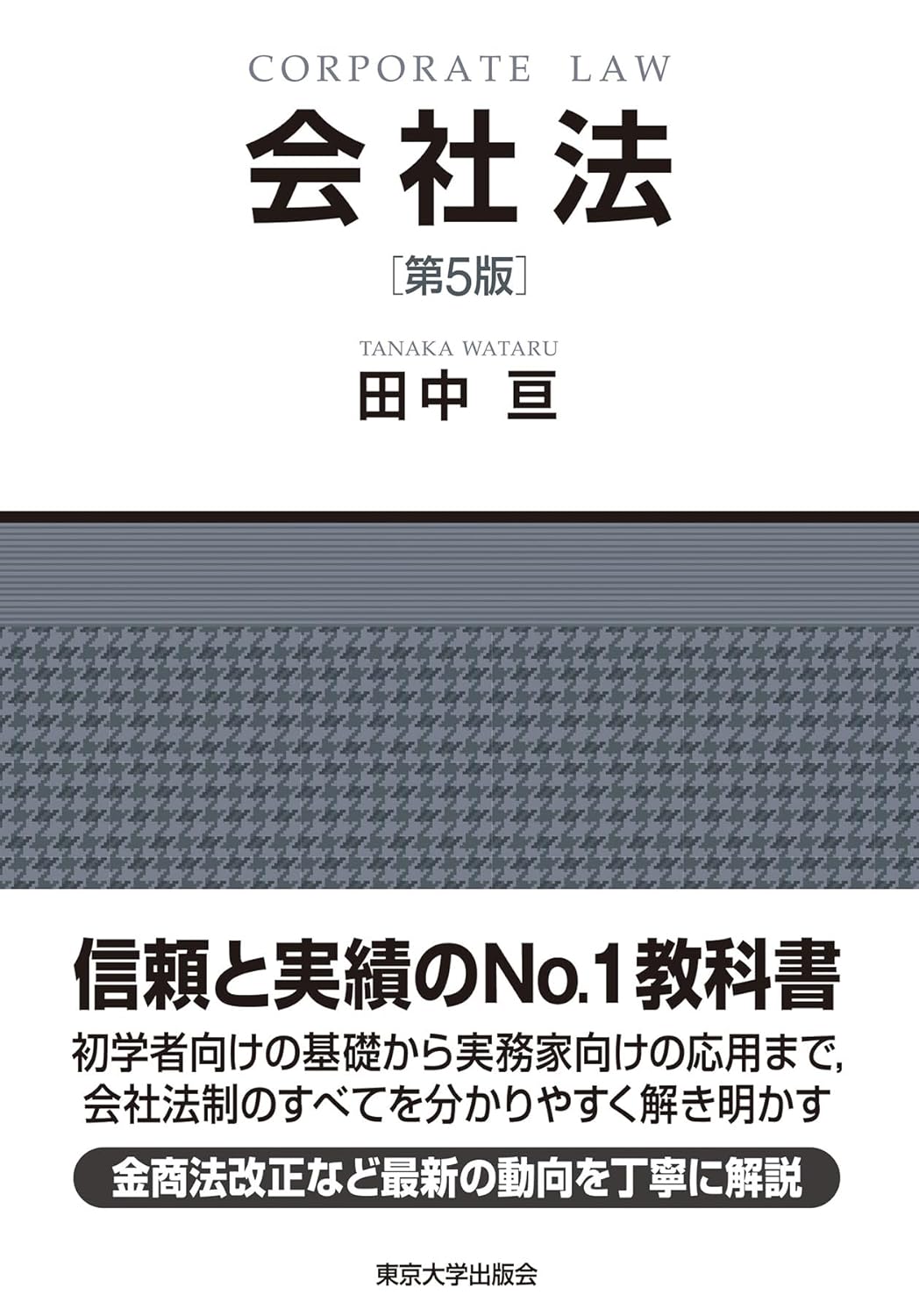
904頁と分厚く、基本的な内容から発展的な内容まで情報量が多いです。
リーガルクエストの著者の一人が書いている基本書であるため、リーガルクエストの辞書としての活用にも資する基本書です。
5位|株式会社法|有斐閣
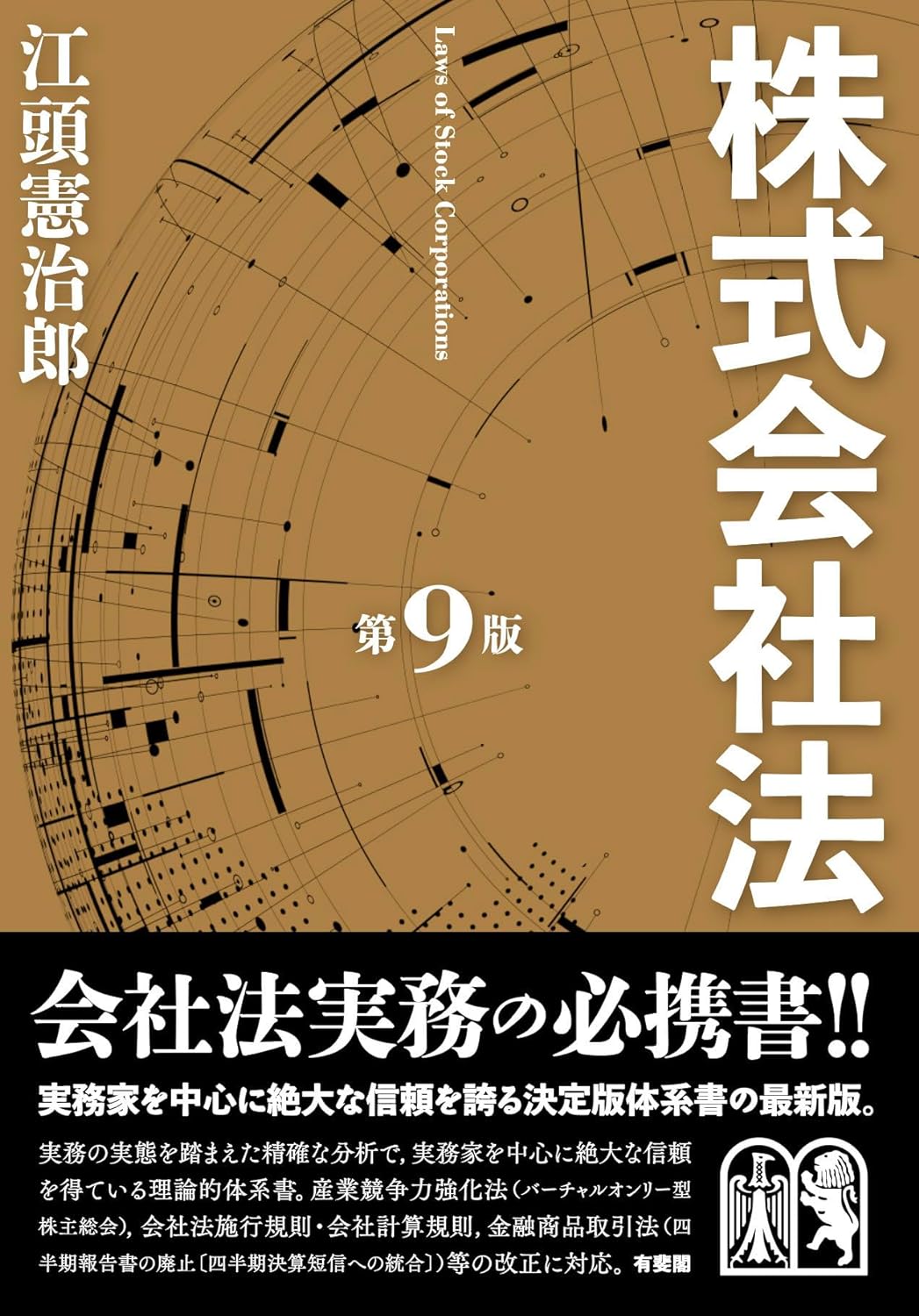
1000頁を超える情報量で、会社法の各制度について制度趣旨から丁寧に説明されています。
もっとも、実務家や研究者を対象にしているため、司法試験には関係ない論点や情報も多いです。辞書として使用できるとよいです。
【司法試験・予備試験】民事訴訟法でおすすめの基本書ランキングTOP5
民事訴訟法は「眠素(みんそ)」と呼ばれるほど、理解が難しい法律のひとつです。
したがって、初めから難しい基本書に手を付けてしまうと、理解ができず、通読が進まないことがあります。
最初はコンパクトな基本書(入門書)を通読し、民事訴訟法全体についての理解を一通りしたうえで、本格的な基本書を読み始めると効率的です。
1位|コンパクト版 基礎からわかる民事訴訟法|商事法務

ページ数が224頁と少なく、民事訴訟法全体を簡単に解説している本です。
基本書を読む前に読んでおくと、民事訴訟法全体についての理解をもって読めるため、入門書として使用できるとよいです。
2位|民事訴訟法|日本評論社

元裁判官が通説・判例の立場を踏まえて書いている本です。
ページ数が862頁と分厚いですが、難しい論点について具体例を用いながら説明がされており、わかりやすい文章で書かれている印象です。
3位|基礎からわかる民事訴訟法|商事法務

1位に挙げた会社法LEGAL QUESTの元となっている本です。
難解で司法試験でも頻出となっている論点については、図を用いて、簡単な言葉で説明されている点が特徴です。
特に、訴訟物論や既判力に関する記述はほかの基本書よりもわかりやすく、多くの受験生が参考にしています。
4位|民事訴訟法 LEGAL QUEST|有斐閣

通説・判例の立場から書かれており、司法試験対策に向いている基本書です。
もっとも、通説・判例の解説がされたうえで、その見解とは異なる立場を採用している記述もあり、そのことを念頭に読んでいく必要があるでしょう。
5位|講義 民事訴訟|東京大学出版会

420頁とコンパクトな基本書ですが、民事訴訟法の全分野について説明があり、網羅性があります。
コンパクトな分、通説・判例についての記述が薄い部分もあり、それらについては判例集などでカバーする必要があります。
【司法試験・予備試験】刑事訴訟法でおすすめの基本書ランキングTOP5
刑事訴訟法では、同じシリーズの中で、ほかの法律の基本書も出ているリーガルクエスト、基本刑事訴訟法が人気となっています。
1位|刑事訴訟法LEGAL QUEST|有斐閣
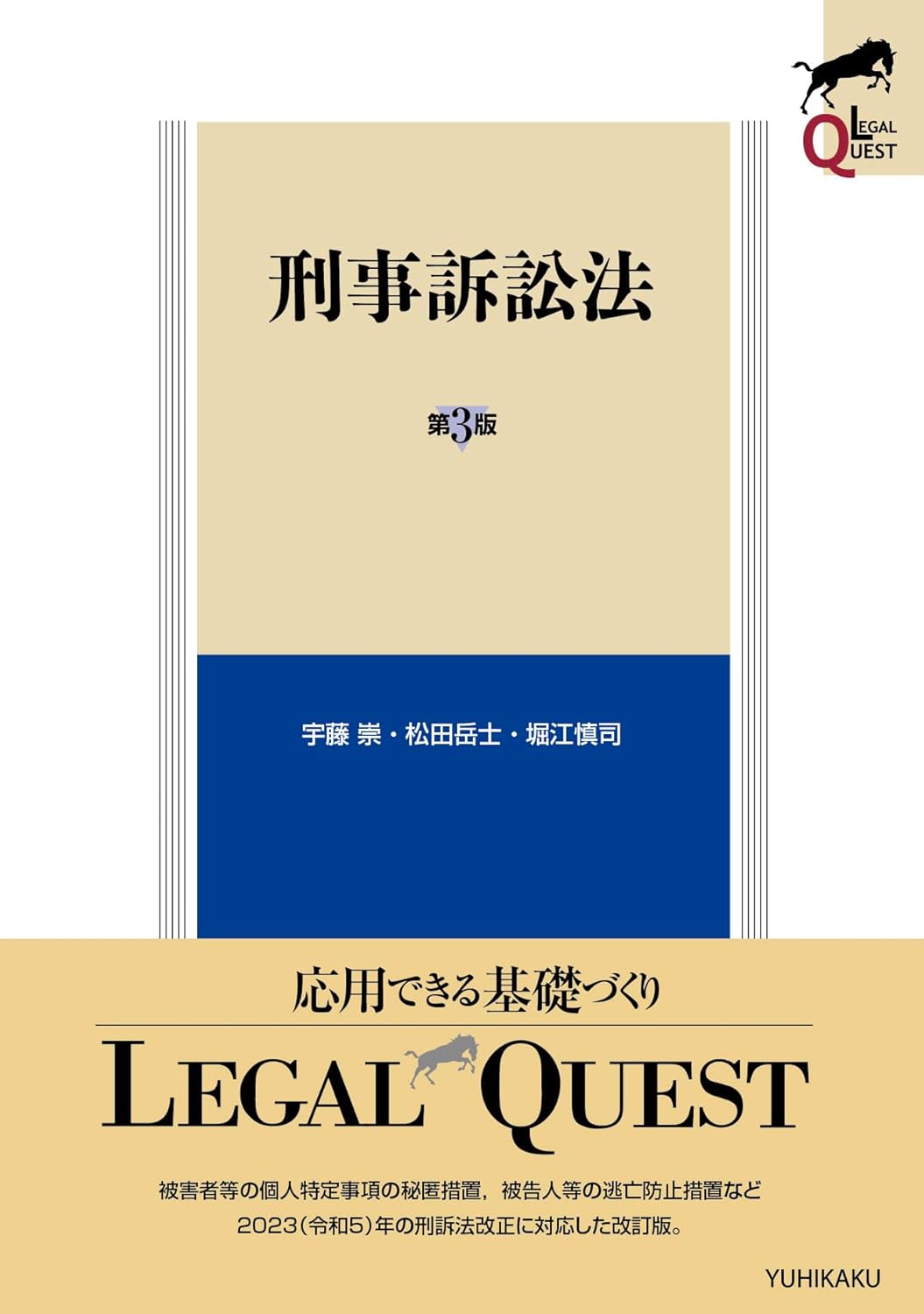
司法試験受験生に必要な情報が詰められている基本書です。
刑事訴訟法の制度や条文の趣旨から丁寧に説明されており、初学者から司法試験受験生まで使えます。判例の解説では、事案と判旨について豊富な情報量で説明されています。
2位|基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編、Ⅱ論点理解編|有斐閣
 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
基本シリーズの刑事訴訟法編です。初学者でも理解しやすい説明がされています。
Ⅰの手続理解編では、具体的な事例を用いて刑事訴訟法の各制度が説明されています。
Ⅱ論点理解編では、多くの判例事例をもとに設問が作成され、司法試験の重要論点について、判例に沿って学習することができます。
3位|刑事訴訟法|有斐閣
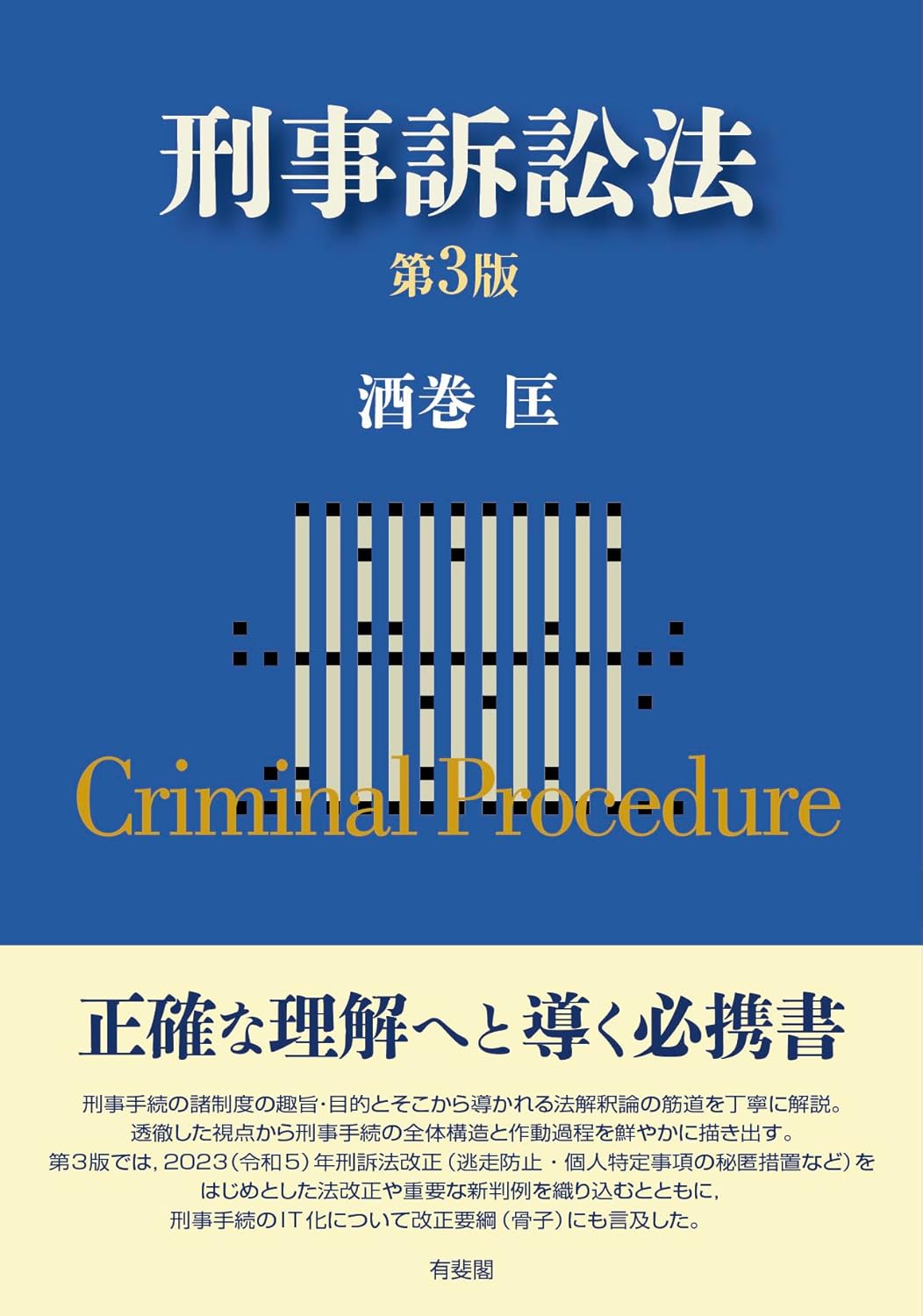
法学教室に連載されていた「刑事手続法を学ぶ」を修正した基本書です。
判例の規範を丁寧に分析できている点に特徴があります。2020年に第2版が発刊され、最新判例についても解説されています。
4位|刑事訴訟法|成文堂

司法試験受験生を念頭に書かれている基本書であり、司法試験対策にも有益です。
司法試験における重要論点について、基礎から丁寧に説明されています。細かい学説の対立に入ることなく、刑事訴訟法についてわかりやすく解説されています。
5位|刑事訴訟法|有斐閣
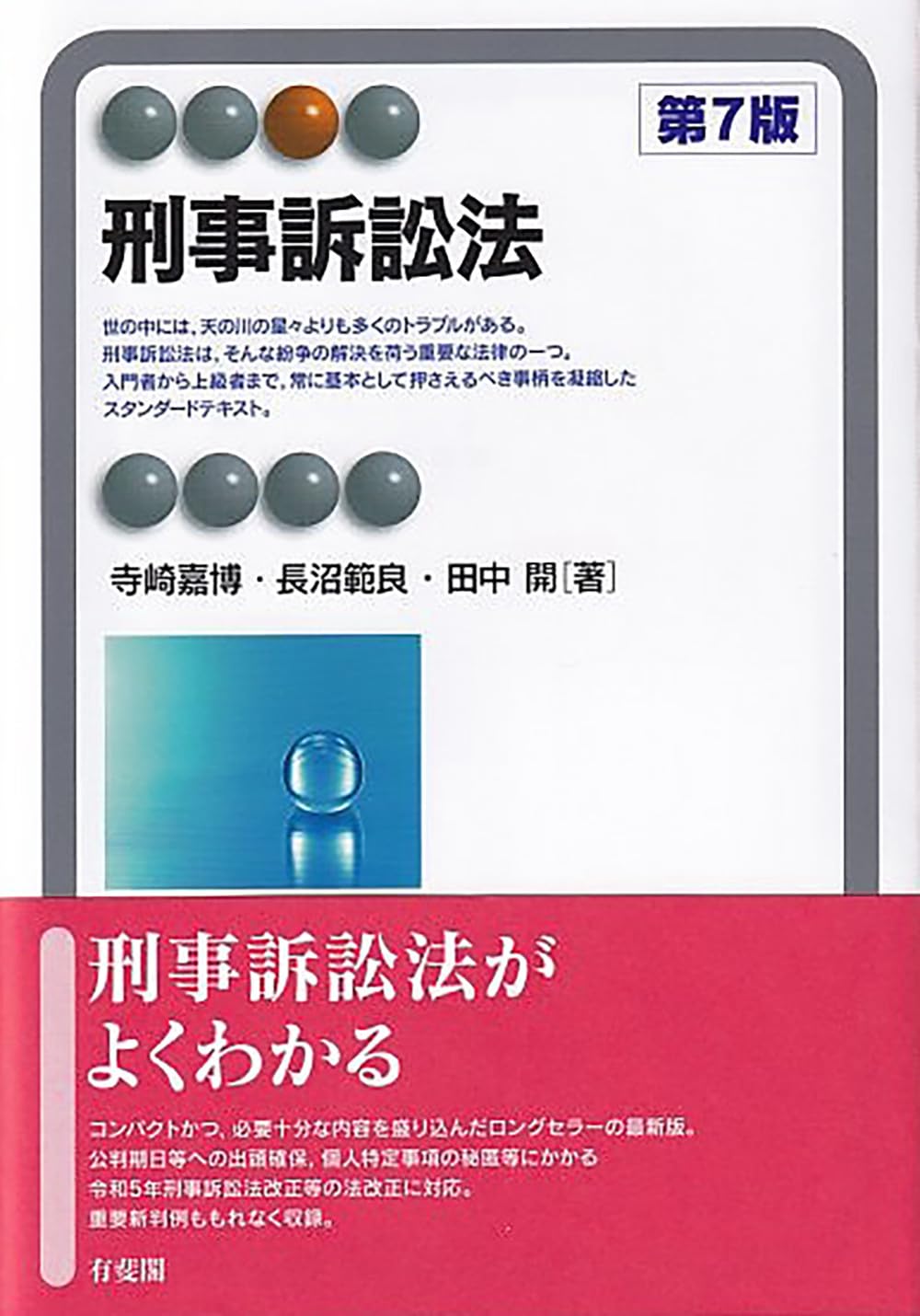
刑事訴訟法の基礎的事項と判例の解説に重点が置かれています。
入門書に近い基本書です。もっとも、刑事訴訟法では、判例学習が中心となるため、判例百選などの判例集と併用できれば、本書も基本書として足りると思われます。
【司法試験・予備試験】刑法でおすすめの基本書ランキングTOP5
刑法には、大本の考え方の違いとして、行為無価値と結果無価値という二つの考え方が対立しています。
基本書がどちらの立場で書かれているのかに注意して読んでいく必要があります。
1位|基本刑法Ⅰ総論、Ⅱ各論|日本評論社
 ※引用:amazon |
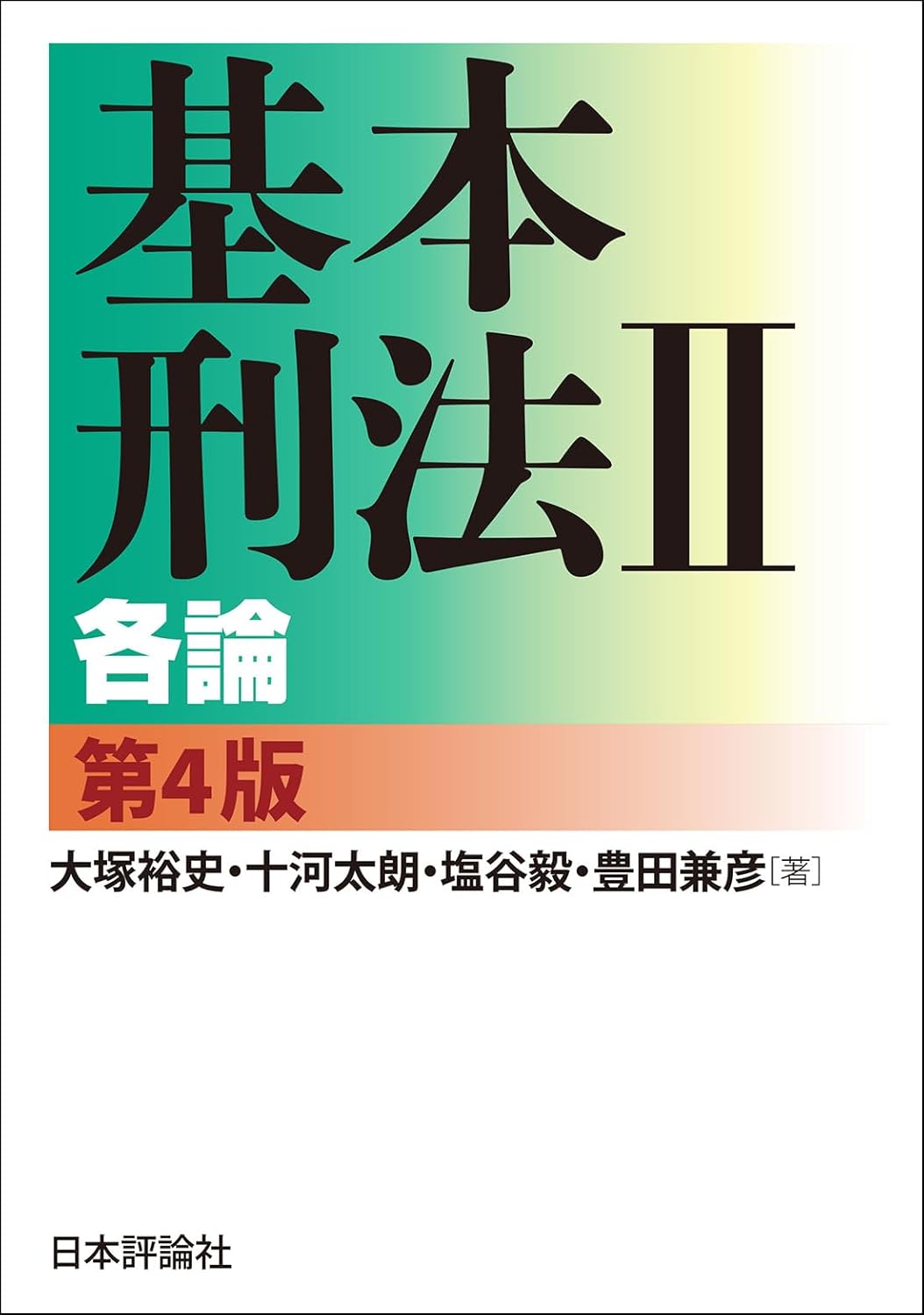 ※引用:amazon |
判例の立場を丁寧に解説している基本書です。
学説の説明は司法試験に必要な範囲にとどめられており、効率的に試験対策を行うことができます。
論文で使用できる論述が多くあり、かつ、細かい点まで解説がされているため、論文式試験にも短答式試験にも必須の1冊といえます。
2位|刑法|有斐閣
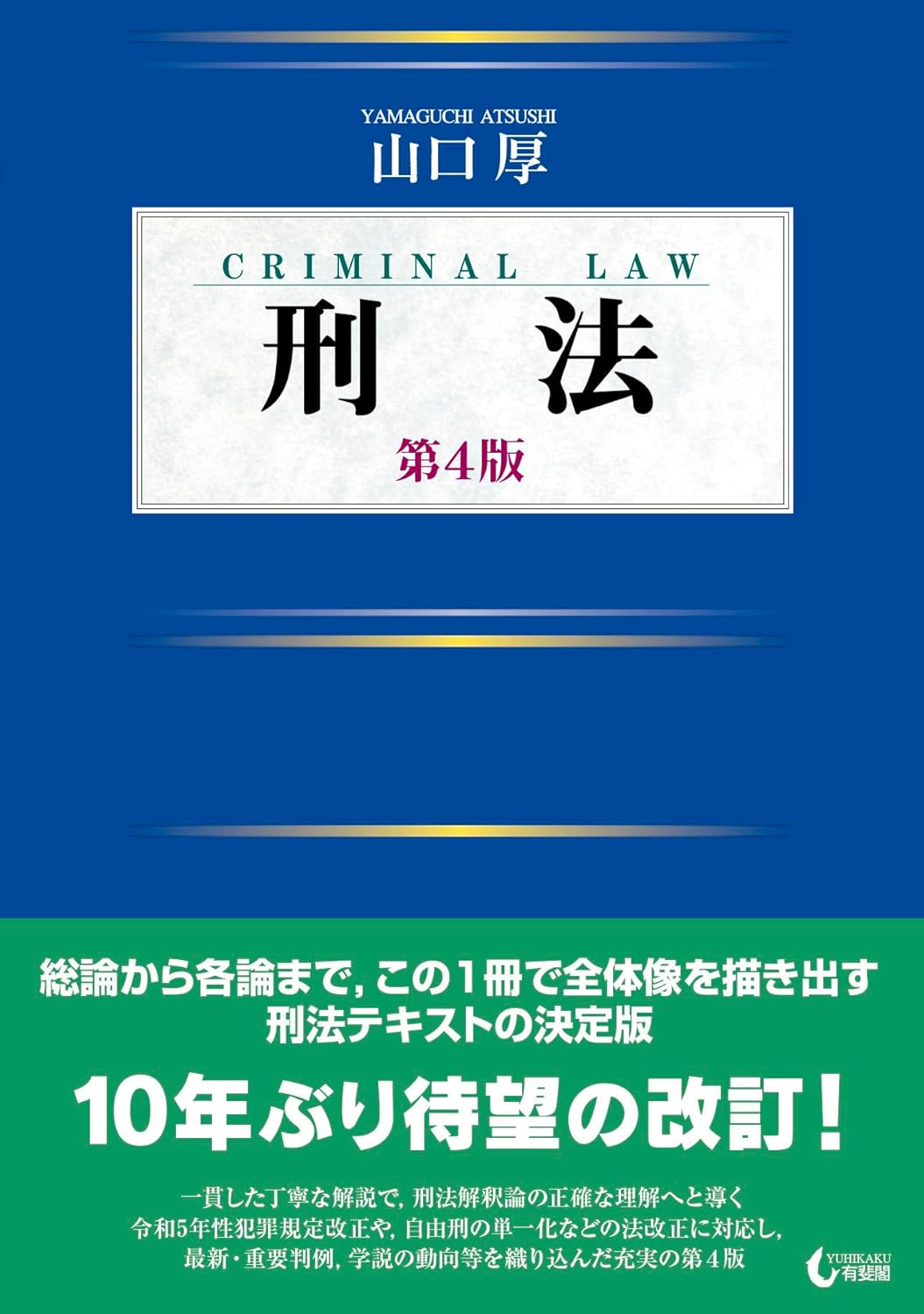
結果無価値の立場から書かれている基本書です。
1冊の中で総論と各論の通説・判例の解説がされており、コンパクトな記述になっているため、刑法を勉強し始めた方や、試験直前の見直しに有用です。
3位|講義刑法学・総論 講義刑法学・各論|有斐閣
 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
行為無価値の立場から書かれている基本書です。
通説・判例の解説がされており、司法試験対策にも有益です。基本刑法が試験対策に特化している一方、各論点について理論的な論述が書かれている印象があります。
4位|刑法総論 刑法各論|有斐閣

結果無価値の立場から書かれている基本書です。
現在の最高裁判事が書いている本であり、論理的一貫性が高いです。
自説の立場を取る記述も多いですが、判例の解説もされており、司法試験対策にも有益です。総論が428頁、各論が690頁と分厚いため、辞書として使用する受験生も多いです。
5位|刑法各論|弘文堂
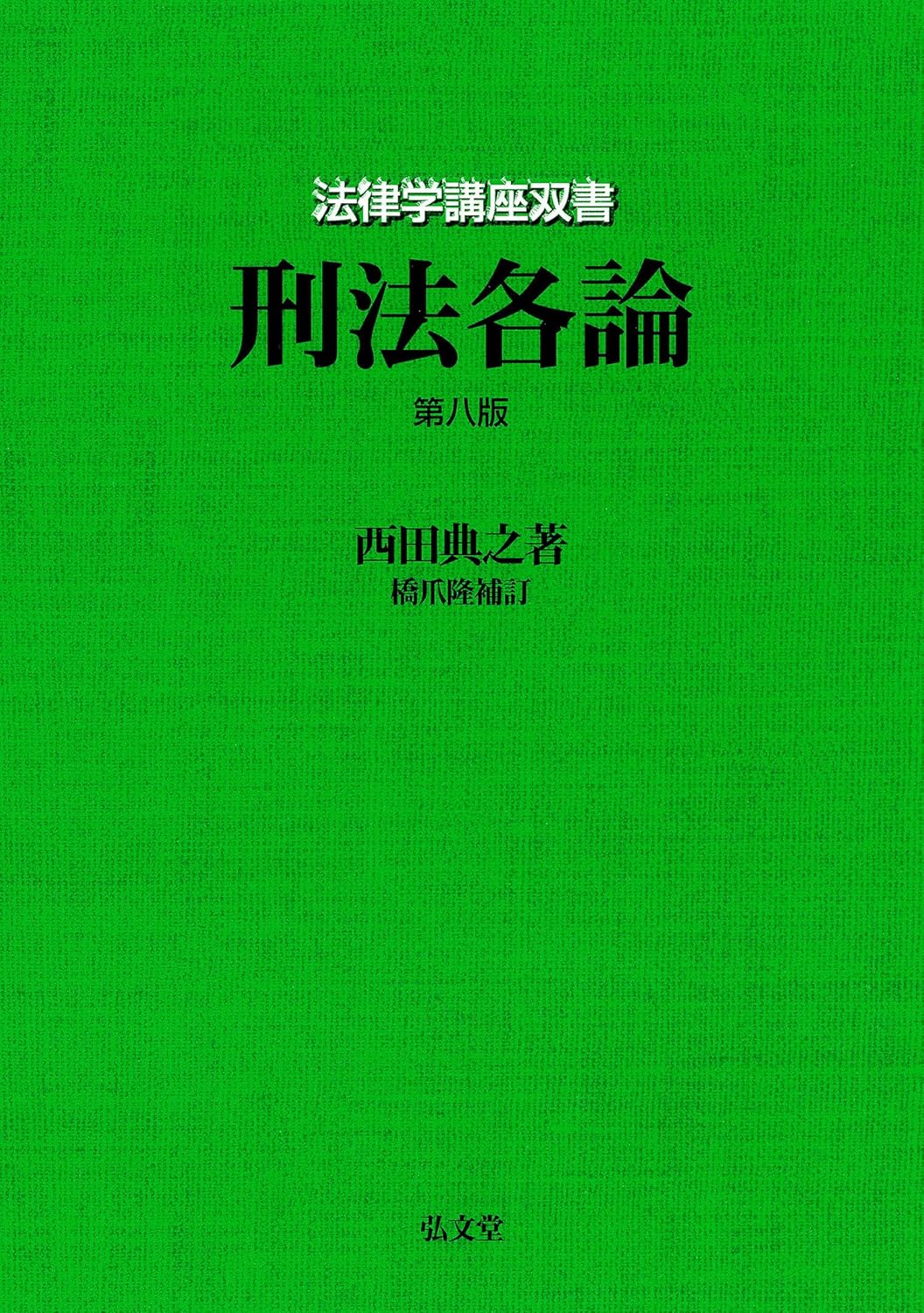
結果無価値の立場から書かれている基本書ですが、行為無価値を採用する受験生も各論の基本書として使用する方が多いです。
多くの文献にも引用されており、刑法各論の基本書の定番と言われています。
【司法試験・予備試験】基本書の選び方のポイント
これまで各法律科目の基本書の特徴について説明してきました。
しかし、どの基本書も定番の基本書となっており、優れた点があるため、どの本を選べばいいのかわからない方に、基本書選びのポイントを解説します。
通読用?それとも辞書用?目的をはっきりさせる
基本書には、通読に適するものと、辞書としての使用に適するものがあります。
通読用は1冊を通して読んで、全体を理解するという点に重きがあります。
辞書用は通読用の本では理解できない論点や、通読用の本には書かれていない分野について調べる際に使用するという点に重きがあります。
基本的には、法律全体について標準的な解説がされている本が通読用、情報量が多いものが辞書用と考えていいでしょう。
これらを混ぜて読み進めてしまうと、ある論点ではAという学者の見解で考え、またある論点ではBという学者の見解で考えるということが生じてしまう可能性があります。
それらの見解が論理的に相反する者であった場合、司法試験でも答案に影響が出てきてしまいます。
各学者の考え方が混ざってしまわないよう、まずは通読用で学習を進め、ひとつの見解を抑えたうえで、足りない分野や論点、異なる考え方を辞書用の基本書で学習できるとよいです。
マイナーなものより定番を選ぶ
司法試験では、相対的に上位の成績を取る必要があるため、大多数の受験生が有している知識を持っている必要があります。
したがって、合格した受験生の多くが使っていたという定番の基本書を使うことが重要です。
また、定番となっている基本書は、それを読んだ受験生が司法試験に合格しているという実績を持っている基本書です。
どれだけ優れている基本書であっても、司法試験に合格するという観点からは、司法試験に適している基本書を使用する必要があります。
したがって、その基本書で合格した人が多いのか、基本書の実績を考慮できるとよいです。
上記のランキングに挙げた基本書は、それぞれの法律科目で定番となっている基本書です。
実際に手に取ってみて使いやすそうなものを選ぶ
基本書の学習において1番重要なことは読み切ることです。
法律はひとつひとつの制度が独立しているものではなく、制度が重なり合って成り立っています。
したがって、一度理解できなかった論点についても、通読することで理解できるようになったり、理解できている論点でもより深く理解できるようになります。
定番の基本書であれば、基本書によって合否に直結するような違いは生じません。
そうだとすると、実際に手に取ってみて、通読できそうな、使いやすそうなものを選ぶことが重要です。
【司法試験・予備試験】基本書の選び方でよくある質問
最後に、基本書の選び方でよくある質問について解説します。
基本書は必要?
そもそも基本書とは、学者がある法律に関して網羅的・体系的に書いた専門書のことをいいます。
独学者にとっては基本書がその法律の教科書となるため、必須となりますが、予備校利用者にとっては予備校のテキストが教科書となるため、必ずしも必要とはいえません。
予備校の教科書は、基本書と比べて、より司法試験対策に特化した本といえるでしょう。
基本書だけで司法試験・予備試験は突破できる?
結論から述べると、基本書だけでは司法試験・予備試験は突破できません。
基本書に書かれている判例知識だけでは足りないところや、基本書の知識をどのように答案に書くかという学習のためには、判例集や演習書などを使用する必要があります。
基本書のほかに何が必要?
多くの受験生が利用しているものとして、基本書のほかに六法、判例集、演習書、過去問などがあります。
六法はポケット六法やデイリー六法、判例六法を使用している受験生が多いです。判例集は判例百選やケースブックが利用されています。
基本書の効果的な使い方を教えてほしい
基本書は以下の3点の使い方が効率的です。
1点目は、知識を網羅的に獲得する「教科書」としての使い方です。上記でも述べた通読用としての使い方です。各法律の論点や全体の体系的理解を目指します。
2点目は、「辞書」としての使い方です。予備校利用者であれば、予備校の教科書で足りない部分を補ったり、通読用の基本書を持っている方であれば、その基本書で足りないところを調べたりします。
3点目は、より理解を深めることに使う「補助教材」としての使い方です。短答式の問題や論文の答案作成などのアウトプットの勉強を行う中で、各演習書の解説では理解が足りない場合に、当該論点の理解を深めるために使います。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
予備試験合格で全額返金あり!


約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る