司法試験・予備試験全過去問集を紹介!問題集のおすすめと選び方のポイントも

司法試験や予備試験の対策に頭を悩ませていませんか?
数ある過去問集から、どれを選べばいいのか迷うこと、多いですよね。一つ一つの問題集を手に取って確認するのは大変な作業です。
このコラムでは、司法試験・予備試験の全過去問集を徹底的に紹介!さらに、問題集のおすすめや選び方のポイントについても詳しく解説します。
最適な問題集を見つけ、試験対策を確実に進めましょう。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変
- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?


約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
予備試験過去問集
短答式試験
論文式試験
| 年度 | 問題 | 出題の趣旨 |
|---|---|---|
| 2011年 (平成23年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2012年 (平成24年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2013年 (平成25年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2014年 (平成26年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2015年 (平成27年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2016年 (平成28年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2017年 (平成29年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2018年 (平成30年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2019年 (令和元年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2020年 (令和2年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2021年 (令和3年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤一般教養科目 | 出題の趣旨 |
| 2022年 (令和4年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2023年 (令和5年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2024年 (令和6年) | ①憲法・行政法②刑法・刑事訴訟法③民法・商法・民事訴訟法④法律実務基礎科目⑤選択科目 | 出題の趣旨 |
口述試験
| 年度 | 問題のテーマ |
|---|---|
| 2011年(平成23年) | 問題のテーマ |
| 2012年(平成24年) | 問題のテーマ |
| 2013年(平成25年) | 問題のテーマ |
| 2014年(平成26年) | 問題のテーマ |
| 2015年(平成27年) | 問題のテーマ |
| 2016年(平成28年) | 問題のテーマ |
| 2017年(平成29年) | 問題のテーマ |
| 2018年(平成30年) | 問題のテーマ |
| 2019年(令和元年) | 問題のテーマ |
| 2020年(令和2年) | 問題のテーマ |
| 2021年(令和3年) | 問題のテーマ |
| 2022年(令和4年) | 問題のテーマ |
| 2023年(令和5年) | 問題のテーマ |
| 2024年(令和6年) | 問題のテーマ |
司法試験過去問集
短答式試験
| 年度 | 問題 | 解答 |
|---|---|---|
| 2006年(平成18年) | ①公法系②民事系③刑事系 | ①公法系②民事系③刑事系 |
| 2007年(平成19年) | ①公法系②民事系③刑事系 | ①公法系②民事系③刑事系 |
| 2008年(平成20年) | ①公法系②民事系③刑事系 | ①公法系②民事系③刑事系 |
| 2009年(平成21年) | ①公法系②民事系③刑事系 | ①公法系②民事系③刑事系 |
| 2010年(平成22年) | ①公法系②民事系③刑事系 | ①公法系②民事系③刑事系 |
| 2011年(平成23年) | ①公法系②民事系③刑事系 | ①公法系②民事系③刑事系 |
| 2012年(平成24年) | ①公法系②民事系③刑事系 | ①公法系②民事系③刑事系 |
| 2013年(平成25年) | ①公法系②民事系③刑事系 | ①公法系②民事系③刑事系 |
| 2014年(平成26年) | ①公法系②民事系③刑事系 | ①公法系②民事系③刑事系 |
| 2015年(平成27年) | ①憲法②民法③刑法 | ①憲法②民法③刑法 |
| 2016年(平成28年) | ①憲法②民法③刑法 | ①憲法②民法③刑法 |
| 2017年(平成29年) | ①憲法②民法③刑法 | ①憲法②民法③刑法 |
| 2018年(平成30年) | ①憲法②民法③刑法 | ①憲法②民法③刑法 |
| 2019年(令和元年) | ①憲法②民法③刑法 | ①憲法②民法③刑法 |
| 2020年(令和2年) | ①憲法②民法③刑法 | ①憲法②民法③刑法 |
| 2021年(令和3年) | ①憲法②民法③刑法 | ①憲法②民法③刑法 |
| 2022年(令和4年) | ①憲法②民法③刑法 | ①憲法②民法③刑法 |
| 2023年(令和5年) | ①憲法②民法③刑法 | ①憲法②民法③刑法 |
| 2024年(令和6年) | ①憲法②民法③刑法 | ①憲法②民法③刑法 |
論文式試験
| 年度 | 問題 | 出題の趣旨 |
|---|---|---|
| 2006年(平成18年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2007年(平成19年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2008年(平成20年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2009年(平成21年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2010年(平成22年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2011年(平成23年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2012年(平成24年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2013年(平成25年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2014年(平成26年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2015年(平成27年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2016年(平成28年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2017年(平成29年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2018年(平成30年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2019年(令和元年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2020年(令和2年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2021年(令和3年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2022年(令和4年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2023年(令和5年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
| 2024年(令和6年) | ①公法系②民事系③刑事系④選択科目 | 出題の趣旨 |
司法試験・予備試験の短答式問題集おすすめ2冊
ここからは短答式試験のおすすめの過去問題集についてご紹介します。
短答過去問パーフェクト|辰巳法律研究所
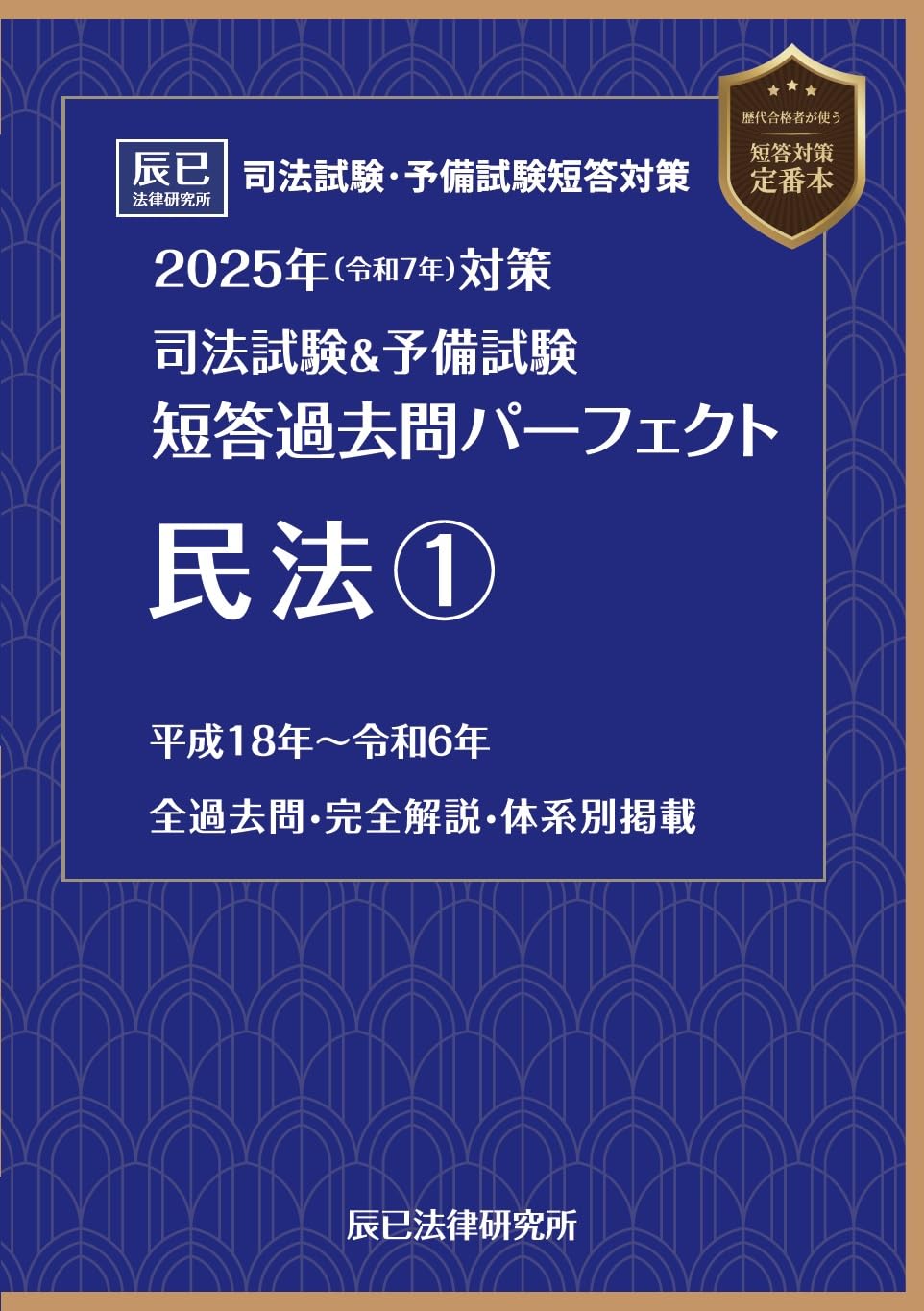 ※引用:amazon |
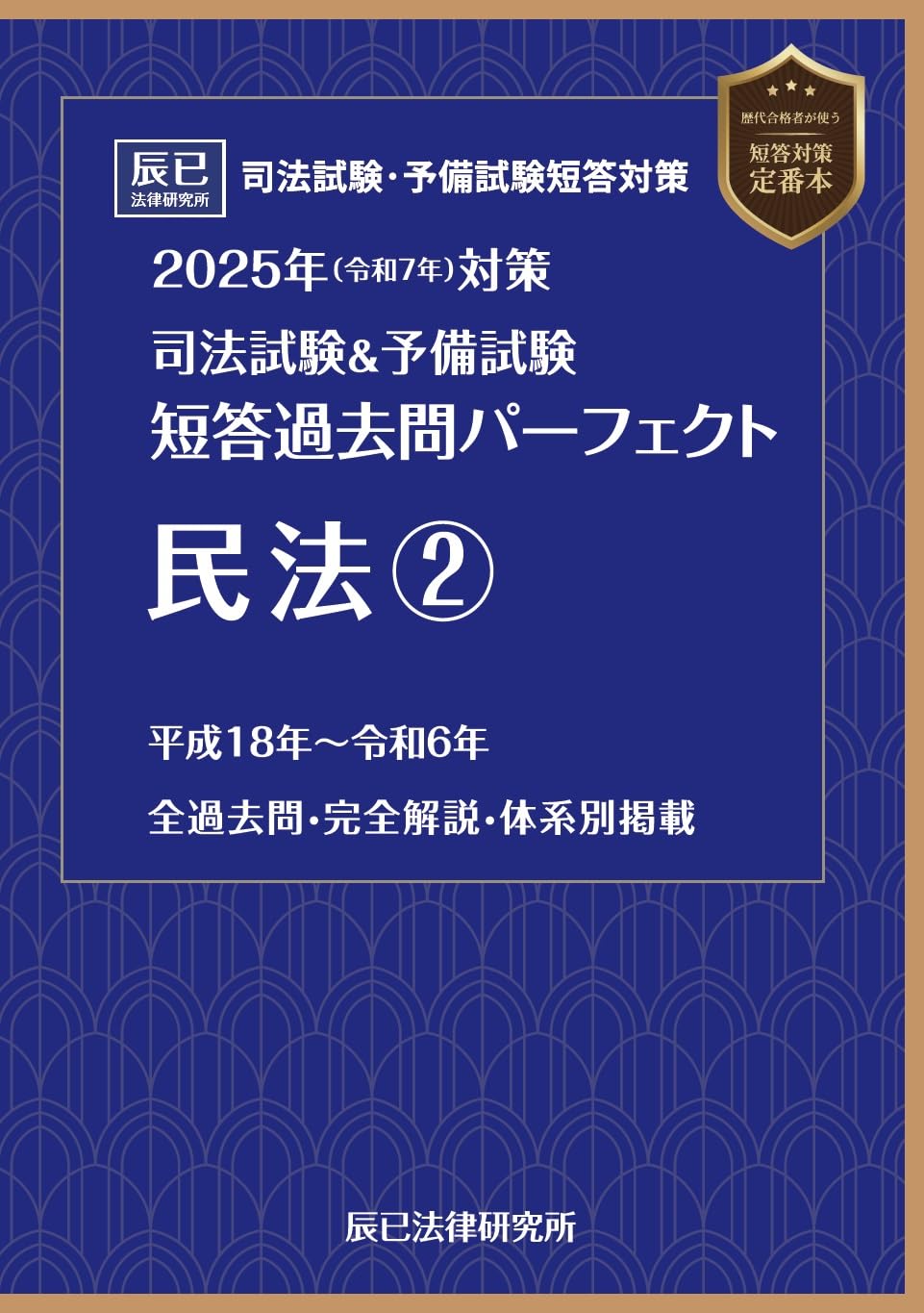 ※引用:amazon |
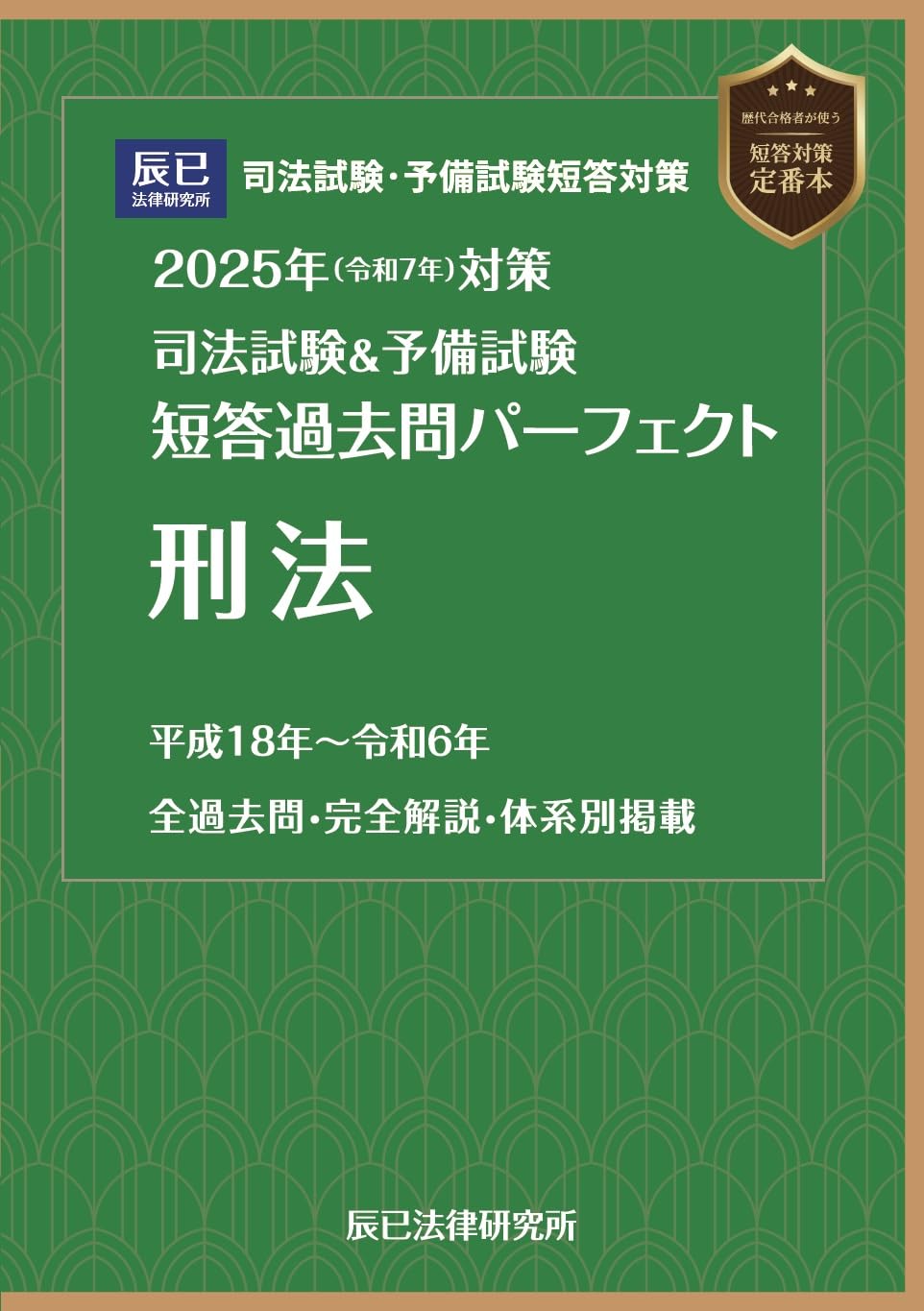 ※引用:amazon |
短答過去問パーフェクトの特徴とおすすめのポイントを紹介します。
特徴
現行の司法試験・予備試験が開始されてからの両試験のすべての過去問が体系別に整理され、掲載されています。
受験生の正答率も掲載されており、問題の難易度・重要度がわかります。
問題の解説も充実しています。
おすすめポイント
基本書や法律の条文の順番で問題が整理されているため、基本書の通読や条文の素読をしながら問題を解いていくことができます。
また、実際の短答式試験の形式で問題を解くことができるため、試験の形式にも慣れることができます。
肢別本|辰巳法律研究所
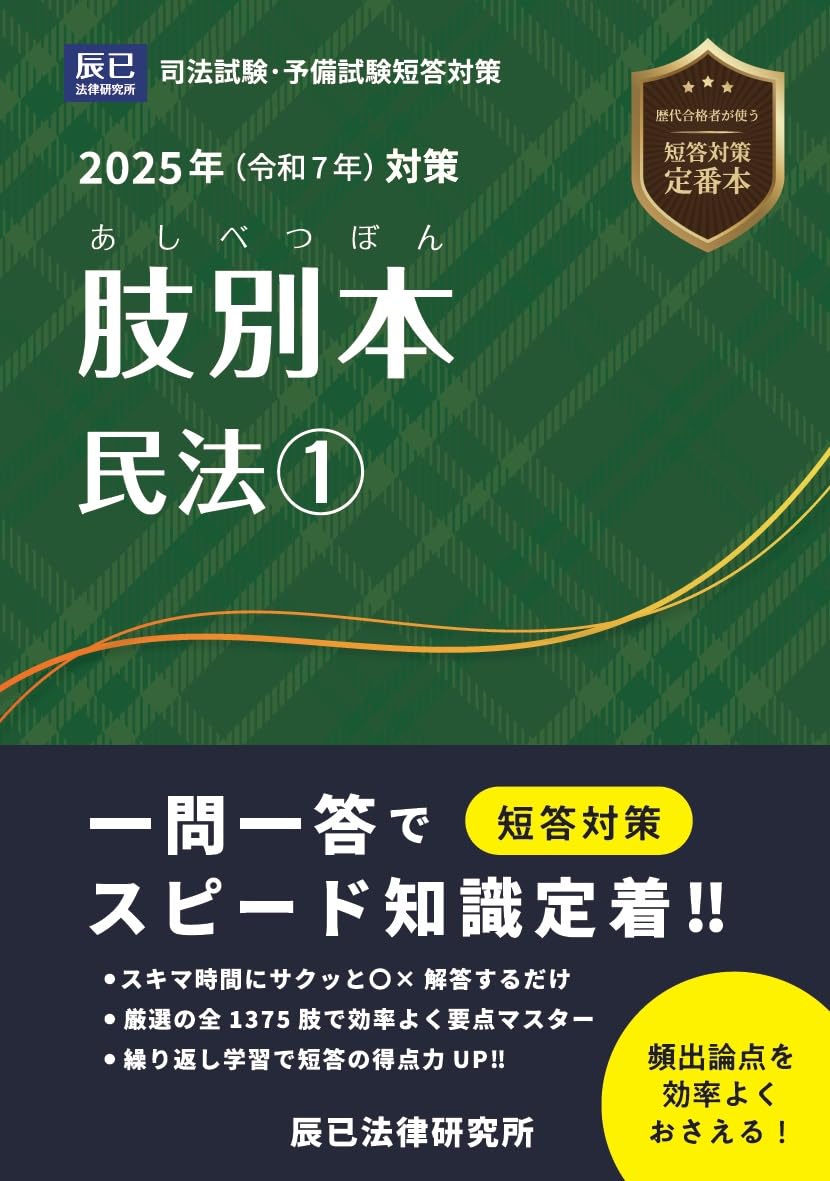 ※引用:amazon |
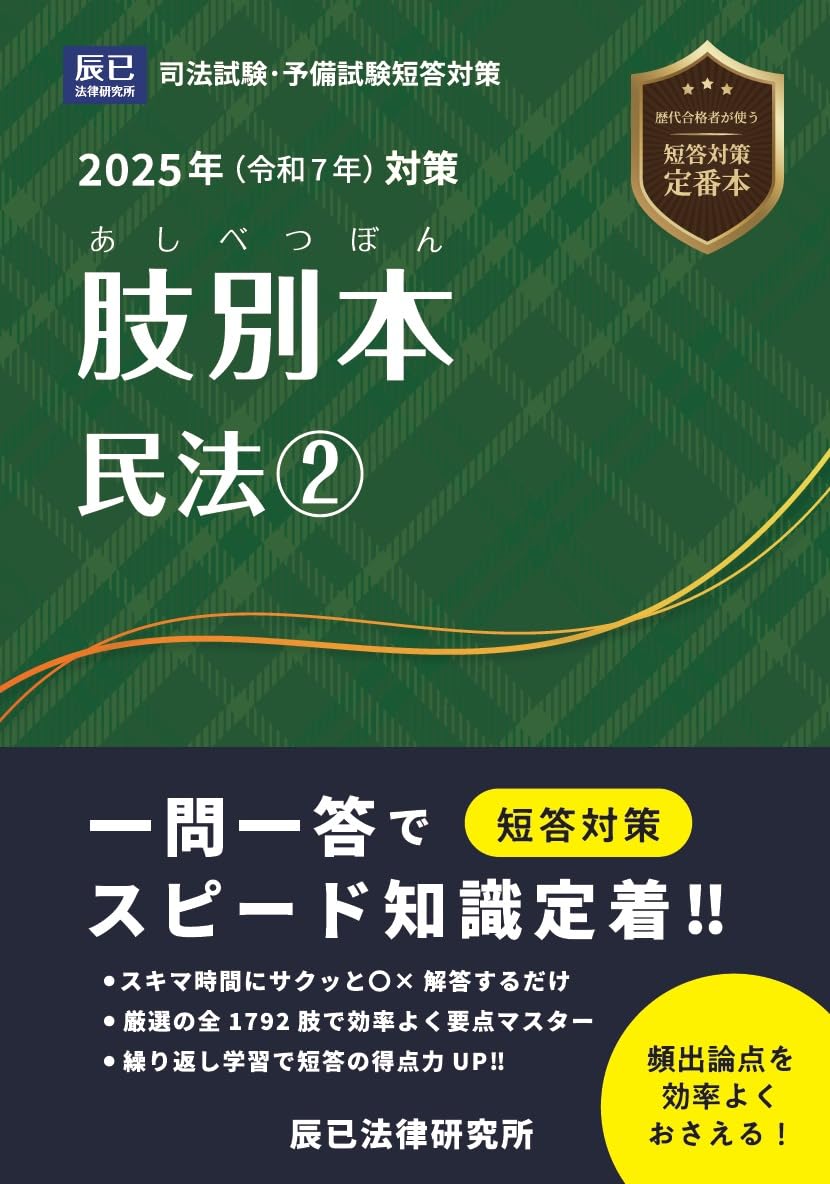 ※引用:amazon |
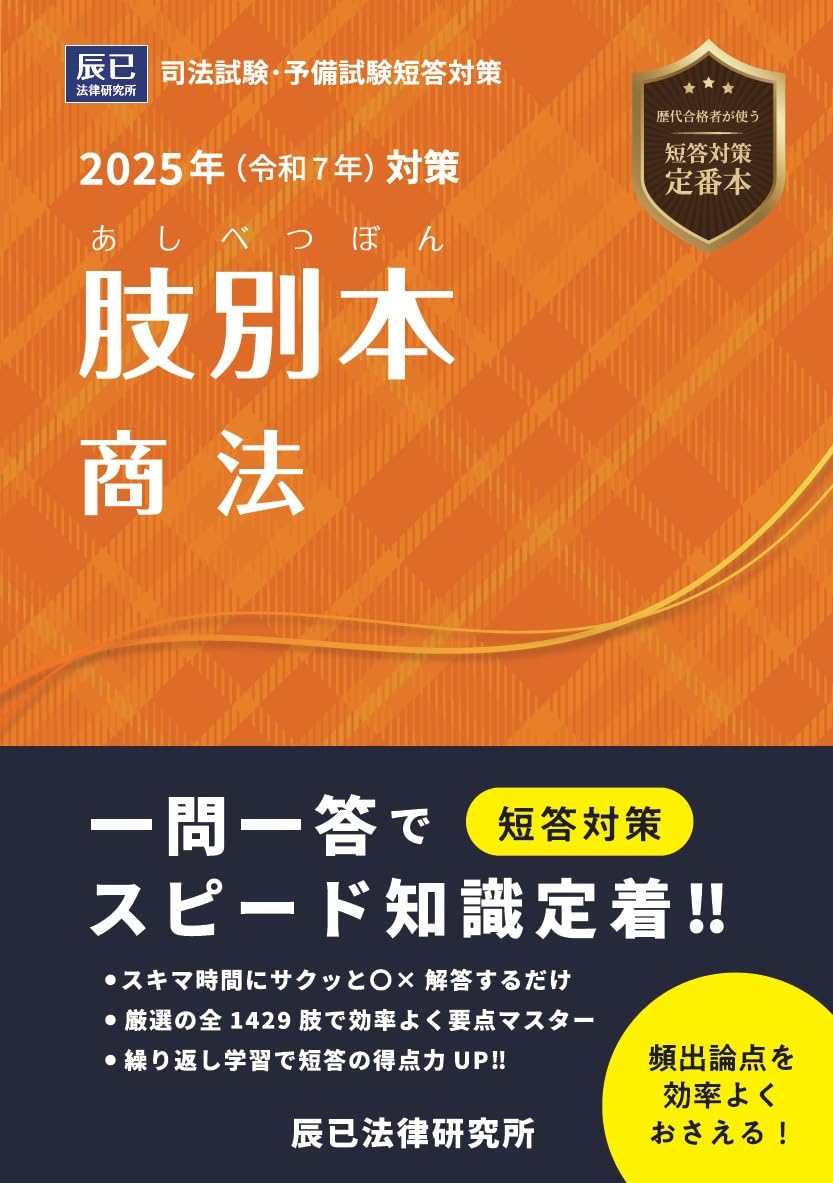 ※引用:amazon |
肢別本の特徴とおすすめのポイントを紹介します。
特徴
肢別本という名前の通り、各肢がバラバラに分解されて掲載されています。
見開きの左のページに、選択肢がひとつずつ記載されており、右のページに、正誤と解説があります。
本の大きさがB6判でほかの問題集よりも小さく、持ち運びやすい点が特徴です。
もっとも、その分解説もコンパクトであることが多く、条文や基本書を見ないと解説だけでは理解できないという問題もあります。
おすすめポイント
旧司法試験の問題や辰巳オリジナルの問題も掲載されているため、ほかの短答試験の過去問題集よりもより細かい知識をつけることができます。
苦手分野を克服する時に、当該分野の問題を解くという使い方がおすすめです。
司法試験・予備試験の論文式問題集おすすめ2冊
次に、論文式試験おすすめ過去問題集をご紹介します。
アガルートの司法試験・予備試験 総合講義1問1答|アガルートアカデミー
 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
アガルート総合講義1問1答の特徴とおすすめのポイントを紹介します。
特徴
本書は、論文式試験で問われる知識を一問一答形式で整理されている問題集です。
基本原則・条文の要件の意義や条文の趣旨が問われ、それに解答します。解説はコンパクトにまとめられており、コンパクトな論述に役立ちます。
おすすめポイント
基本的な知識が定着しているかを確かめられる教材で、その意味では初学者から使用できる教材となっています。
もっとも、試験直前期の受験生にとっても、原理原則からさかのぼって知識の確認を行うことができるため、有益な教材です。
感覚ではわかっているけれど、正確な文言で答えられないという問題も多く、論文式試験に向けての基礎体力をつけることができます。
新伊藤塾試験対策問題集ー論文|弘文堂
 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
伊藤塾の試験対策問題集の紹介をします。
特徴
本書の特徴は、法的三段論法を意識した答案例が掲載されていることです。答案例の右側脚注には、答案の流れがわかりやすいように、何を論じているかが書かれています。
おすすめポイント
司法試験では各科目、答案の型があります。それに沿って論じることで、採点官に伝わりやすい答案になり、また、論点漏れを防ぐことができます。
本書では、答案例が掲載されており、その解説が書かれています。
本書の演習を繰り返すことで、各科目の答案の型を身に着けることができます。
問題のレベルとしては、法科大学院入試レベルかと思われるため、初学者の方にもおすすめできる問題集です。もっとも、答案の型が身についていない法科大学院生にも有益な問題集です。
【司法試験・予備試験】問題集の選び方のポイント
ここでは問題集を選ぶ際のポイントを、①解答例・解説のわかりやすさ、②目的にあった問題集、③シェアの3つの観点から説明します。
解答例や解説のわかりやすさ
1点目は解答例や解説のわかりやすさです。
問題集はひとつひとつの問題だけでなく、全体の演習を通して目的を達成しようとしていることが多いです。
したがって、問題集を通してやることによって得られるものが大きいため、どの問題集も「やり切る」ということが重要です。
そのため、自分が使いやすいものを選ぶということが何よりも大切ですので、本屋などで実際に手に取って中身を見て、使いやすそうなものを選べるとよいです。
問題集の選び方ですが、自分が難しいと感じている論点について、複数の問題集を見て、一番わかりやすい解答例・解説が書かれていた問題集を選ぶということもおすすめです。
自分の目的に合ったものを選ぶ
2点目は自分の目的に合ったものを選ぶということです。
問題集には、それぞれ目指している目的があります。
例えば、解説が細かく載っている問題集であれば知識を深めることには役立ちますが、その分、問題集が分厚くなるため、情報の取捨選択を行う必要があります。
反対に、解説が少ない問題集は、何周も回すことができるというメリットがあります。
規範定立やあてはめに不安がある方は、解説が細かく記載されている問題集で、規範定立理由、事実の摘示の方法、評価の仕方を学べるとよいでしょう。
一方で、事案から論点を抽出することに不安がある方は、多くの問題を何周も解けるという問題集がおすすめです。
問題集の「はしがき」などで、その問題集の目的が書かれていることが多いため、はしがきに着目することもおすすめです。
シェアの広いほうを選ぶ
3点目はシェアの広いほうを選ぶということです。
司法試験は相対評価で合否が決定されているため、ごく一部の受験生しか知らない高度な論点に解答できることよりも、大部分の受験生が書けている内容を充実して答案に示すことが合格に繋がります。
したがって、まずは、大部分の受験生が知っている論点を充実して書ける力をつけることが重要です。
そのためには、合格した受験生の多くが使用していた問題集を使用することが効率的です。
上記で紹介した問題集はいずれも受験生の評判が高く、また、多くの受験生が利用していた問題集です。
迷っている方は、紹介した問題集の中から自分の目的に合っているものを選べるとよいでしょう。
【司法試験・予備試験】問題集の効果的な使い方を短答・論文別に解説
次に、問題集の効率的な使い方を説明します。
短答式問題集の効果的な使い方
まずは、短答式問題集の効率的な使い方です。
知識の維持や定着、再確認に使用する
短答式問題集は試験までに少なくとも3周は繰り返せるとよいです。
短答式問題集は、基本書や条文、テキストなどの体系順で構成されていることが多いです。
したがって、1周目は基本書や条文の素読をしたあとに、その該当箇所の問題集を解けると、知識の定着に役立ちます。
2周目は、冒頭から最後まで問題を解いていき、間違えた問題をあぶりだしていく作業ができるとよいです。
3周目以降は間違えたところだけを解きながら間違いをなくしていくという方法がおすすめです。
また、その際は、理由まで答えられて正解とできるとよいです。司法試験・予備試験では、過去問では結論のみで正誤を導けた問題が、理由まで見たうえで正誤を導く必要がある問題として再度出題されることが多いです。
したがって、各肢の結論だけで正誤を導けた問題であっても正解とせず、理由まであっているかどうかで判断できるとよいです。
同じ問題集を繰り返すこと(あれもこれもと手を広げすぎない)
論文式問題集でも共通しますが、同じ問題集を繰り返しすることで知識が定着します。
したがって、複数の問題集に手を出してしまうことは効率的ではありません。
多くても2冊にできるとよいです。
その使い方としては、基本の問題集を決め、その問題集を終えて不安が残る部分があれば、そのポイントについて+1冊にできるとよいでしょう。
論文式問題集の効果的な使い方
次に、論文式問題集の効率的な使い方について説明します。
入門書を読み終わったら、まずは問題集を読み込んでみる
問題集に取り組むのはインプットが終わってからと考えている方も多くいらっしゃると思われますが、入門書を読み終えて、その科目の一通りの全体像をつかめたら、問題集を読んでみることをおすすめします。
問題集には、質の高い答案例が掲載されており、司法試験で、何をどのように論じることが求められているかをつかむことができます。
初期から答案の書き方に触れることによって、基本書や判例集を読む際にも、何を意識して読めば、知識を答案に落とし込めるかがわかります。
答案に直結する形で、インプットができるようになるため、効率的です。
答案の型を叩き込む
司法試験では、答案の型をつかむことが重要です。
採点官に読みやすい答案を書くという観点からも、論点漏れを防ぐという観点からも役に立ちます。
まずは、法的三段論法を習得することが大切です。「問題提起→規範定立→あてはめ」という流れで書かれている答案を読み、自分のものとして習得することを心掛けられるとよいでしょう。
法的三段論法を意識できるようになったら、各科目の答案の書き方の習得を目指します。
例えば、憲法であれば、「権利保障の有無→違憲審査基準の定立→個別具体的検討」、刑法であれば、「客観的構成要件→主観的構成要件→違法性→有責性」といった流れです。
各科目で点数を効率よくとりやすい答案の流れがあります。解答例や解説を読み、それをつかめるようになることが合格答案に近づきます。
まとめ
このコラムでは過去問題集について、①短答式・論文式それぞれのおすすめ問題集、②問題集の選び方、③問題集の使い方という3つの観点から解説しました。
過去問題集の演習では、短答式問題集でも、論文式問題集でも、まずは1冊の問題集を一通りやってみるということが重要です。
そうすることによって、問題集があっているかあっていないか、どの部分があっていないか、それを克服している問題集はどの問題集かを把握することができます。
反対に、複数の問題集に手を出してしまうと、ひとつの論点に対して複数の解答例・解説を読むことになってしまうため、結局どのように論じればよいか困惑してしまうことも少なくありません。
さらに、どの問題集の検討も不十分で論点を網羅できずに試験を迎えてしまうことにもなりかねません。
まずは、問題集を1冊決めて取り組めるとよいです。
問題集選びに迷っている方は、上記の問題集を選ぶ観点を参考に、本コラムで紹介した問題集から選ぶことをおすすめします。