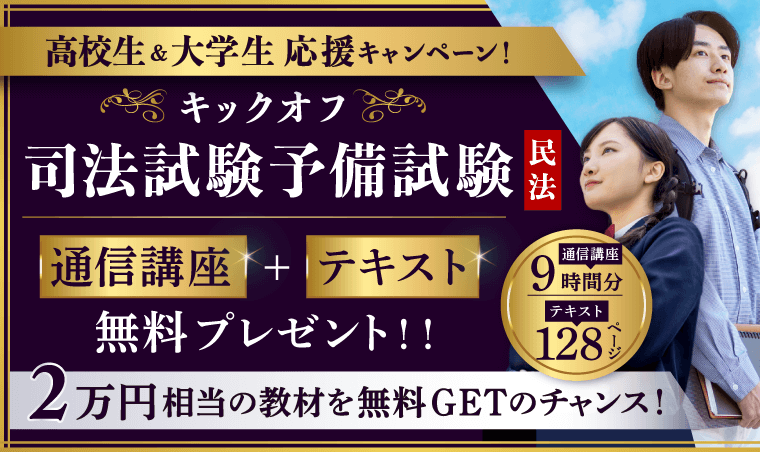司法試験に独学で合格した人はいる?本当に無理?おすすめのテキストや勉強法も

「司法試験に挑戦したいけど、仕事があって法科大学院に通うのは時間的にも難しい……」
「できるだけ費用をかけずに司法試験に合格したい……」
これから司法試験の勉強を始めようと思っている方の中には、このような悩みを抱いている方も多いのではないでしょうか?
こうした悩みを解決する一つの方法として、「独学」があります。
「司法試験に独学で合格」と聞くと、なかなか難しそうに聞こえるかもしれません。
そこで、当コラムでは、実際に独学で司法試験に合格することは可能なのか?独学で司法試験に挑戦する際に気を付ける点は何か?といった点について解説していきます。
司法試験・予備試験の受験を
検討されている方へ
- 司法試験の勉強についていけるか不安
- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい
- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい
このような悩みをお持ちでしたら
アガルートの無料体験を
ご活用ください


サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、
司法試験の勉強についていけるかを試せる!
「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、
司法試験のすべてがわかる!
300名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!
司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
【結論】司法試験に独学で合格した人はいる!その共通点とは
正直なところ、司法試験に独学で合格する人はかなり少数なのですが、ゼロではありません。
独学合格者の正確な人数のデータはありませんが、独学で受験する場合に必ず必要となる予備試験の合格率は直近の5年間で約4%で推移しており、その合格者のうち約40%が法科大学院出身者(中退者含む)でした。
残り60%の中には予備校利用者が相当数いることが考えられるため、独学受験での合格数はかなり低いと考えられるでしょう。
しかし、インターネットで情報収集してみると「不可能ではない」ことがわかります。
中には10年間の勉強を経て独学合格を果たした方もいました。
そこで、この章では、司法試験に独学で合格する人の共通点について説明していきます。
司法試験に独学で合格する人の共通点は、大きく3つあります。
- 一人でもモチベーションを高く保って勉強できること
- 計画的に勉強できること
- 周囲に頼れる人がいること
以下では、それぞれの点について解説します。
共通点① 一人でもモチベーションを高く保って勉強できること
やはり、司法試験の勉強をするうえでもっとも重要なことは、「モチベーションを高く保つこと」だといえるでしょう。
司法試験は、最難関試験と言われるだけあって、合格するために必要な勉強時間や勉強量は膨大です。特に、法科大学院に通わず独学で勉強する場合には、予備試験を突破する必要があり、予備試験の合格率の低さを考えると、相当な長期間にわたる勉強を覚悟しなければなりません。
法科大学院や予備校に通って勉強をする場合、司法試験の勉強に嫌気が差してしまったときでも、同じ目標に向かって勉強する仲間と励ましあったり、信頼できる先生に相談したりすることができるので、勉強に対するモチベーションは比較的保ちやすいはずです。
一方、独学の場合、基本的には一人で勉強を続けることになるため、その中でモチベーションを高く保ち続けるのは簡単ではありません。
そのため、途中で挫折せず司法試験合格を勝ち取るためには、一人でもモチベーションを高く保って勉強できることが重要であるといえるでしょう。
共通点② 計画的に勉強できること
2つ目は、「計画を立てて勉強を行うこと」です。
先でも説明したとおり、司法試験の勉強は長期戦になることが多い上、幅広い科目の勉強をしなければなりません。特に、予備試験の場合、短答試験8科目(基本7科目+一般教養)、論文試験9科目(基本7科目+実務基礎科目、選択科目)、口述試験2科目(民事、刑事)といったように、膨大な試験範囲の勉強をこなしていく必要があります。
そのため、司法試験や予備試験に合格するためには、多くの試験科目をバランス良く勉強しなければなりません。したがって、計画を立てて勉強を行うことは、司法試験においては特に重要です。
実際、合格者の多くはスケジュールを立てて勉強しています。
そのため、独学の場合であっても、スケジュールを立て、それに従いコツコツと勉強を行うことは、とても重要なことだといえるでしょう。
共通点③ 周囲に頼れる人がいること
3つ目は、「周囲に頼れる人がいること」です。
独学の場合、一番気を付けなければならないのは、自分の勉強のやり方が正しい方向をむいているのか、という点です。
いくら長い時間勉強したとしても、その方向性が間違っていると、なかなか合格まで辿り着くことはできません。しかし、独学の場合には、間違った勉強をしていたとしても、それを指摘してくれる人がいないため、一人ではなかなか気付きにくいといえるでしょう。
そのため、周囲に頼れる人がいることが重要です。近くに司法試験合格者がいる場合などには、その人に定期的に勉強方法や進捗をチェックしてもらうのが良いでしょう。
司法試験に独学で挑戦するメリット・デメリット
司法試験に独学で挑戦することには、メリットもあればデメリットもあります。
独学で挑戦するメリットとしては、「費用を安く抑えることができること」が挙げられます。
反対に、デメリットとしては、「勉強のやり方によっては合格までに時間がかかってしまうこと」が挙げられます。
以下では、それぞれについて詳しく解説していきます。
独学のメリット
独学のメリットとしては、「費用を安く抑えることができること」が挙げられるでしょう。
法科大学院ルートで司法試験を目指す場合、国立でも2年間で200万円弱程度はかかるといわれています。また、予備校に通う場合であっても100万円以上は費用がかかるのが一般的です。
一方、独学で勉強する場合には、基本書や参考書代くらいしか費用がかからないので、法科大学院や予備校を利用する場合と比べると、大幅に出費を抑えることが可能です。
そのため、司法試験の勉強にあまり費用をかけられない人にとっては、独学はおすすめの勉強方法だといえるでしょう。
独学のデメリット
独学のデメリットとしては「勉強のやり方によっては合格までに時間がかかってしまうこと」が挙げられます。
前の章でも説明したとおり、司法試験に合格するためには、正しい方向性で適切な勉強を行うことがとても重要です。
しかし、独学の場合、仮に間違った方法で勉強を行なっていたとしても、それを指摘してくれる人がいないため、なかなか勉強の方向性を修正しにくいのも事実です。
そのため、法科大学院や予備校を利用する場合に比べると、合格までに時間がかかってしまうことがあります。
もっとも、こうしたデメリットは、身近な司法試験合格者などに定期的にアドバイスを受けることで解決可能です。近くに司法試験合格者がいない場合には、SNSなどを利用してアドバイスを受けるというのも一つの方法でしょう。
司法試験の独学が難しい理由
司法試験の独学が難しい理由としては、法律範囲の広さ、複雑な問題形式、学習の方向性の不正確さ、モチベーションの維持が難しいことが挙げられます。
法律範囲の広さ
司法試験の合格のためには民法、刑法、憲法、行政法など、非常に多くの法分野をカバーしなくてはいけません。さらに、判例や法律改正に常に目を光らせる必要があり、自分自身で最新の情報を追い続けなくてはならないという難しさがあります。
複雑な問題形式
司法試験では、知識を問うだけでなく、与えられた事例に対して論理的に考え、分析する力が求められます。問題の内容が抽象的であり、予備校などの指導なしで、短期間で適切な解答方法を身につけるのは困難です。
学習の方向性の不明確さ
司法試験の準備は多岐にわたるため、どの科目にどれだけの時間を割くべきか、どこに重点を置くべきかを独学で見極めるのは難しいと言えます。過去問や実績のあるカリキュラムに基づいた指導を受けた方が効率的に学習できるケースが多いと言えるでしょう。
モチベーションの維持
司法試験の勉強は長期戦であるため、自己管理が非常に重要です。独学では、仲間との交流が少なく、孤独感が強まることがあります。そのため、モチベーションを維持し続けることが難しく、途中で挫折しがちです。
【何から始めればいい?】司法試験に独学で挑戦するときの勉強法
やっぱり独学で合格したい!という場合、実際に司法試験に独学で挑戦するためには、どのような順番で勉強を行なえばよいのでしょうか?
おすすめの勉強方法は下記の3ステップを辿ることです。
- 基本書を通読して各科目の基本的な事項についてインプットを行う
- 実際に過去問や演習書を解いて答案構成を行なう
- 過去問を解いて答案を書く
勉強法①基本書を通読して各科目の基本的な事項についてインプットを行う
独学での勉強法の1ステップ目は、「基本書を通読して各科目の基本的な事項についてインプットを行うこと」です。
司法試験は、最難関といわれる試験ではあるものの、やはり一番重要なのは基礎を固めることです。そのため、まずは各科目の基本書を通読して、基本的な事項についてインプットを行うことが必要になります。
ただし、この際に注意してほしいことは、あまり細部にこだわりすぎないことです。
基本書は、当該法律の専門家である学者などが執筆していることが多く、その内容は非常に高度で難解です。そのため、基本書の通読を行う際には、細部にこだわりすぎず、全体の大枠を掴むことを意識して読み進めていくのが良いでしょう。
勉強法②実際に過去問や演習書を解いて答案構成を行なう
独学での勉強法の2ステップ目は、「実際に過去問や演習書を解いて答案構成を行うこと」です。
基本書を通読してインプットが一通り終了したら、できるだけ早くアウトプットに切り替え、過去問や演習書を解いてみましょう。
最初は難しくてなかなか思うように解けないかもしれませんが、そこで諦めてはいけません。
司法試験の合格者であっても、最初から過去問などを完璧に解けていた人などほとんどいないので、そこは割り切って、どんどん問題を解き進めていくことが重要です。
まずは、答案構成だけでかまわないので、同じ問題を何度も繰り返し解くことで、知識を定着させていきましょう。
勉強法③過去問を解いて答案を書く
独学での勉強法の3ステップ目は、「過去問を解いて答案を書くこと」です。
答案構成を繰り返してある程度知識が定着してきたら、今度は実際に過去問を解いて答案を書いてみましょう。
最初はなかなか上手く答案が書けず苦労するかもしれませんが、合格答案を書けるようになるためには、実際に手を動かして何度も答案を書いてみるのが一番です。
答案を書き終わったら、自分の答案と模範解答例を見比べて、自分の答案に何が足りていなかったのか復習しましょう。
また、身近に司法試験合格者がいる場合には、答案を見てもらい、添削してもらうというのもおすすめです。他の人に添削してもらうことで、自分一人では気づけなかった書き方の癖などに気づくことができるでしょう。
司法試験に独学で挑戦する際におすすめのテキスト
司法試験に独学で挑戦する際、どのようなテキストを使えばよいのか気になる方も多いのではないでしょうか?
この章では、独学におすすめのテキストを3つ紹介します。1つ目は日本評論社の「基本○○法」シリーズ、2つ目は「アガルートの司法試験・予備試験合格論証集」、3つ目は伊藤塾の「試験対策問題集」シリーズです。以下では、それぞれのテキストについて、詳しく説明していきます。
おすすめテキスト①日本評論社の「基本○○法」シリーズ
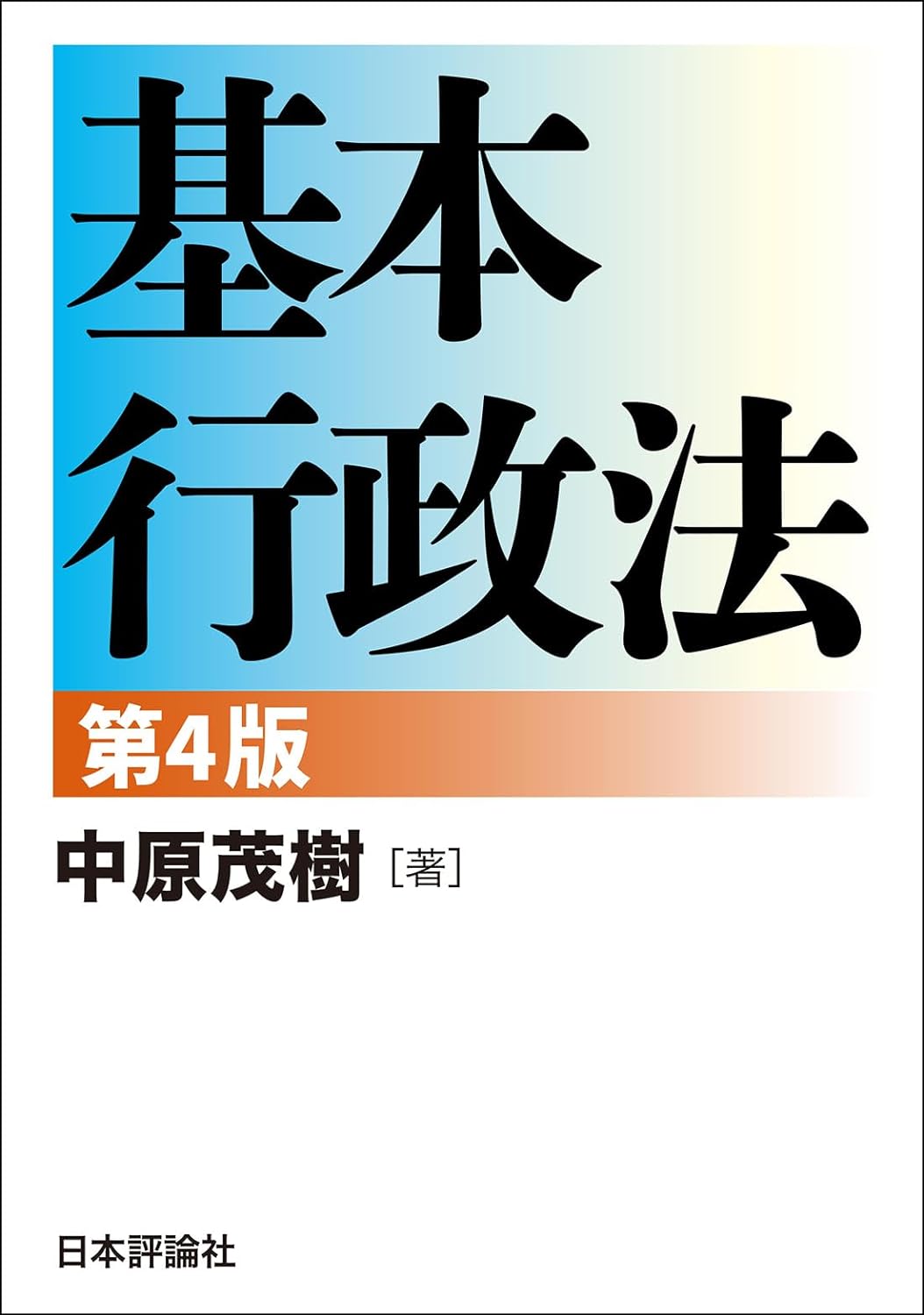 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
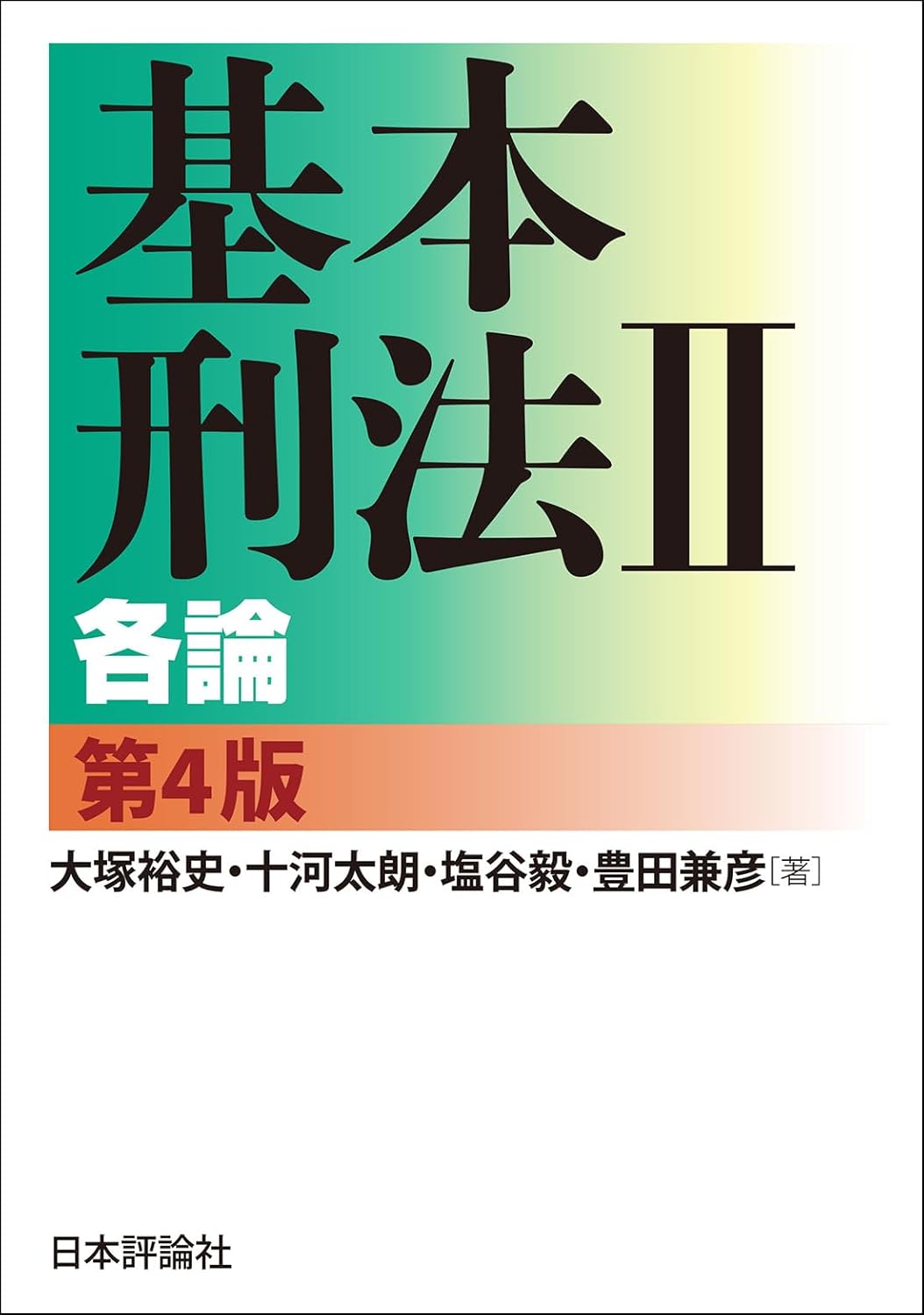 ※引用:amazon |
1つ目は、日本評論社の「基本○○法」シリーズです。このシリーズは「基本シリーズ」と呼ばれる基本書で、各科目の基本事項が非常に分かりやすくまとまっています。
このシリーズの一番の特長は、重要な項目ごとに設問や事例が載っており、それに対応する形で解説がなされている点にあります。
基本書と聞くと、法律についての難解な説明が延々と続いているようなイメージを持つ人も多いかもしれませんが、この基本シリーズは設問や事例ごとに解説がなされているため、飽きずに読み進めることができます。
解説自体も非常に分かりやすく書かれているため、初学者の方でも使いやすいシリーズだといえるでしょう。そのため、最初のインプットを行うための教材としては、うってつけの教材です。
おすすめテキスト②アガルートの司法試験・予備試験合格論証集
 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
 ※引用:amazon |
2つ目は、「アガルートの司法試験・予備試験合格論証集」です。
このテキストは、いわゆる論証集と呼ばれるものであり、司法試験合格に必要な定義や規範が網羅的に記載されています。
司法試験に合格するためには、最低限、重要な定義や規範を暗記する必要があります。このような定義や規範は、自分でノートにまとめるなどして暗記するのも不可能ではないのですが、やはり一からまとめノートを作成するとなると相当な時間と手間がかかってしまいます。
そこで、このような時間と手間を省きたい人にとって、論証集はとても役に立つ教材だといえるでしょう。「アガルートの司法試験・予備試験合格論証集」には、充分な書き込みスペースもとられているため、論証集に書き込みをして、自分なりにカスタマイズすることも可能です。
おすすめテキスト③伊藤塾の「試験対策問題集」シリーズ
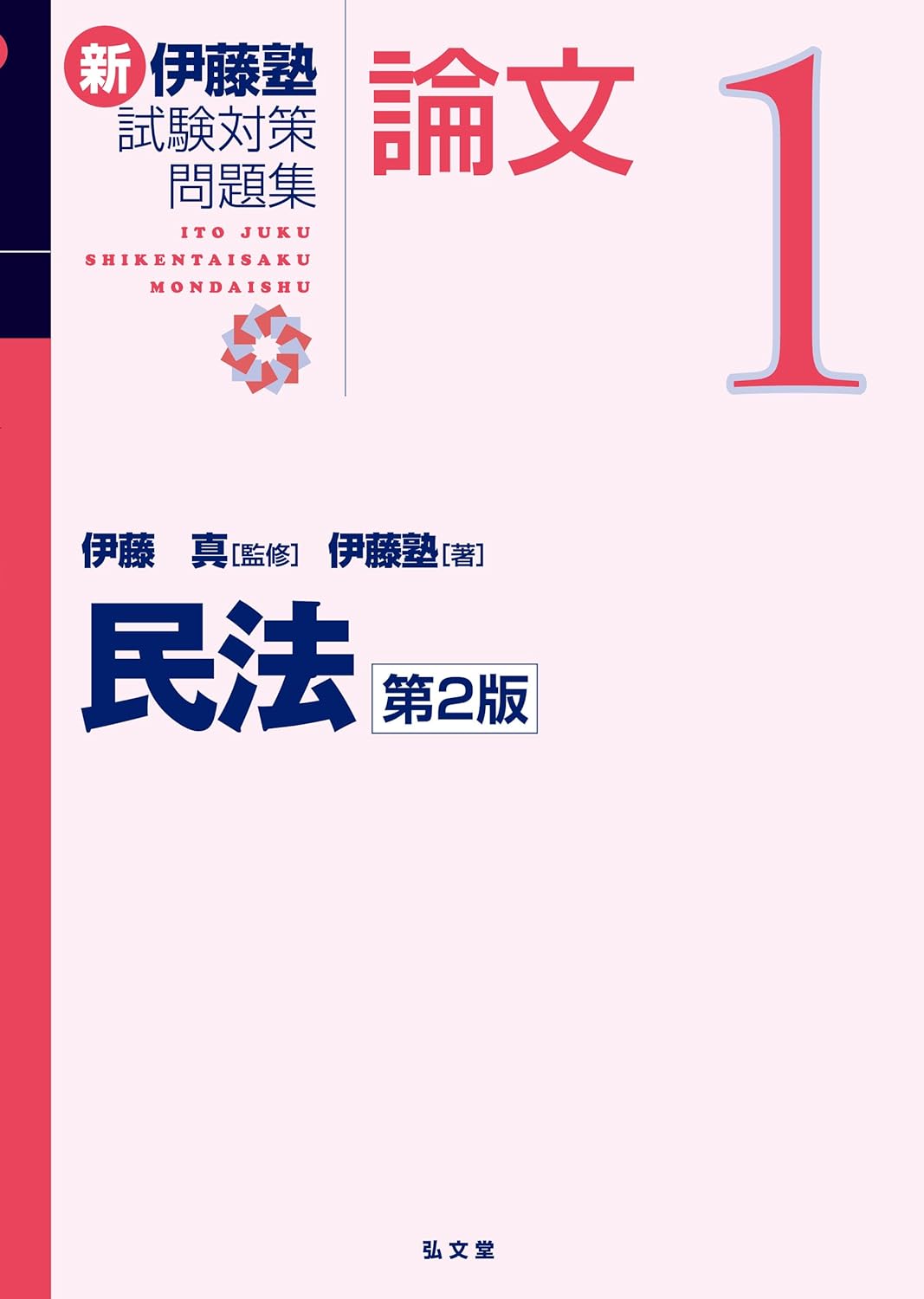 ※引用:amazon |
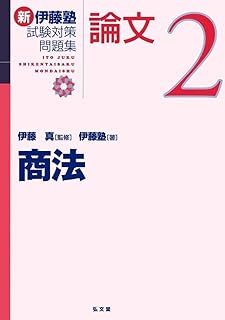 ※引用:amazon |
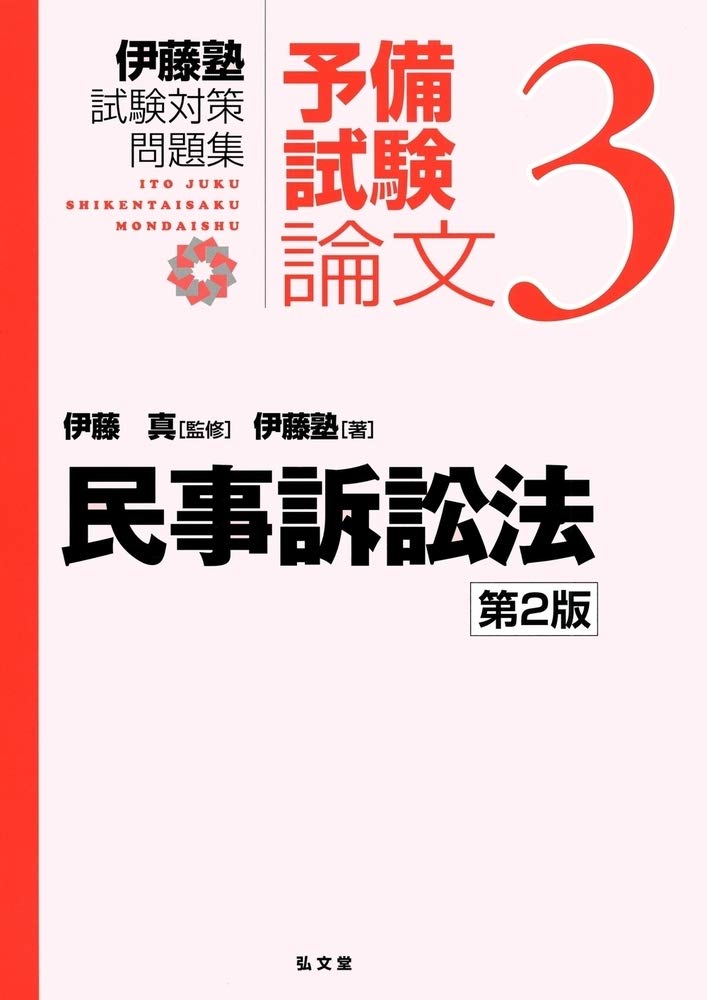 ※引用:amazon |
3つ目は、伊藤塾の「試験対策問題集」シリーズです。このテキストは、「赤本」とも呼ばれている演習書で、予備試験の過去問を初めとした事例問題とその解答・解説が載っています。
先ほどの勉強法の項目でも説明した通り、司法試験の勉強において重要なことは、実際に問題を解いて繰り返し答案を書くことです。そのようなアウトプットを行う段階で、このテキストは大きな価値を発揮します。
このテキストには、問題ごとに模範解答例がついているため、自分が書いた答案と見比べてみて、どこが足りていないのか確認することができます。
また、このテキストには、模範解答例の他に、司法試験合格者が書いた再現答案も載っているため、合格答案の相場観を知ることも可能です。そのため、アウトプットを行う段階では非常におすすめの教材だといえます。
司法試験の独学に関するよくある質問
社会人でも司法試験に独学合格できる?
社会人が司法試験を目指す場合、まず予備試験に挑戦するケースがほどんどですが、社会人の予備試験合格率は、例年1.3%~1.7%と非常に低くなっています。
そのため、独学での合格は不可能ではないものの、極めて困難ということができます。
効率的に勉強するためにも、社会人の方には特に予備校での学習をおすすめします。
司法試験の独学期間の目安は?何年?
個人差が大きいため、独学期間の目安を計算するのは難しいですが、最短でも数年単位の勉強が必要であるといえます。
司法試験の合格な勉強時間の目安は、3000~8000時間であり、1日8時間勉強したとしても、1年~3年かかる計算になります。
独学か予備校に通うか迷ったら?
独学で勉強するべきか予備校を活用するべきか、迷った場合は、予備校の無料体験を受けてみることをおすすめします。
体験してみて、予備校の授業の質や市販の教材との違いを実際に見てから、予備校なしでも勉強を続けていけそうか、検討するとわかりやすいです。
アガルートでも無料体験を実施していますので、ぜひ活用してみてください。
まとめ
これまで、司法試験に独学で挑戦する方法について解説してきましたがいかがだったでしょうか?
独学で司法試験に合格するのはなかなか難しいことですが、適切なやり方で勉強をすれば、独学で合格することも決して不可能ではありません。
それでも、やはり最難関といわれる司法試験に独学で挑戦するというのは不安が大きくなるものですし、合格するまでの時間もそれなりにかかることを覚悟する必要はあります。
そこで、そのような不安のある方は、ぜひ一度、アガルートに相談してみてください。アガルートには司法試験受験のプロが揃っているため、各々にあった勉強スタイルを見つけることができるはずです。
司法試験・予備試験の受験を
検討されている方へ
- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?
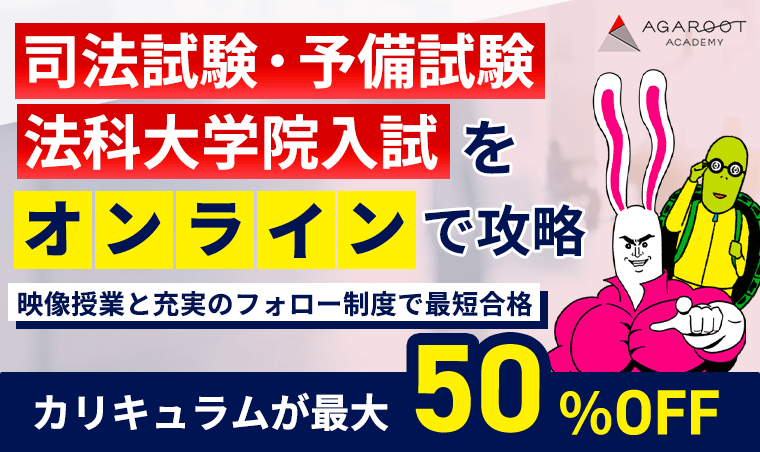
合格者の声の累計981名!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
予備試験合格で全額返金あり!!


サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、
司法試験の勉強についていけるかを試せる!
「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!
300名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!
司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る