【司法試験・予備試験】論文式の対策と勉強方法!科目別の対策法も

「論文式試験の勉強を始めたけど、なかなか論文が書けるようにならない…」
「これから論文式試験の勉強を始めるに当たって注意する点は何?」
司法試験・予備試験の受験生の中には、このような疑問や悩みを抱いている方も多いのではないでしょうか。
特に予備試験においては、論文式試験が一番の山場とされており、論文式試験を突破することができれば最終合格に大きく近づくことになります。
そこで、本コラムでは、司法試験・予備試験における論文式試験の対策と勉強法について紹介していきます。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変
- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?


約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る目次
【司法試験 予備試験】これを見れば全てがわかる!鉄板の論文勉強法を5つのフェーズで解説!
論文式試験の問題の押さえておくべき特徴とは
近年の予備試験・司法試験の論文式試験においては、問題文中の事例が詳細かつ長文になっている傾向にあります。
そのため、従前よりも、問題文中の事実をできるだけ多く拾い、制限時間内に処理する力が求められるようになっています。
この際に、重要となるのは問題文中の事実を使って適切なあてはめを行うことです。
したがって、論文式試験の勉強においては、このあてはめの練習をしっかりと行う必要があります(もちろん、あてはめの前提となる規範の学習も必須です)。
論文式試験の基本的な勉強法と対策
この章では、論文式試験の基本的な勉強法と対策のポイントについて説明します。
重要なのは下記の3点です。
- 法的三段論法の理解
- インプットよりアウトプット重視
- 予備校の論文添削を徹底活用し答案の書き方を身につける
法的三段論法の理解
1つ目は、法的三段論法を理解することです。
法的三段論法とは、「規範」「あてはめ」「結論」の3ステップのことを意味します。
「規範」とは、法律の条文及びその解釈によって定立された定義や規範などを意味し、「あてはめ」の段階ではその規範に、問題文中に書かれている具体的事実を適用します。
そして、「結論」では、あてはめにおいて定義や規範に具体的事実を適用した結果を示すことになります。
例えば、以下のような問題を見てみましょう。
_________________________
問題文
Aは、友人から近いうちに甲土地の地価が大幅に上がるとの情報を聞いたため、そのことを甲土地の所有者Bにも伝えた上で、時価より相当高額を支払って甲土地をBから購入し、登記も自己に移転した。しかし、後にこの情報は虚偽であったことが判明した。
当該情報が虚偽であることは甲土地の付近ではある程度知られており、Bもそれを知っていた場合、AはBに対して代金の返還を請求することができるか。
※アガルート|「論文答案の書き方講座 民法第1回[2]」より
_______________________________
本問では、まず、民応95条2項の要件該当性が問題となります。
「法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」(民法95条2項)とは、①法律行為の基礎とした事情(事実)に関する表意者の「認識」が相手方に示され、②相手方に了解されて、③「法律行為の内容」となっていたとの意味であると解されます。これが、「規範」に当たります。
そして、本問では、①「近いうちに甲土地の地価が大幅に上がる」とのAの認識がBに示され、②Bにもこのことが了解されて③本件売買契約が締結されているから、「法律行為の内容」となっていたといえます。これが「あてはめ」の段階です。
最後に、95条2項の要件を充足する、ということを「結論」において示します。
司法試験・予備試験の論文式試験では、このような三段論法の流れに沿って答案を書くことがとても重要です。
関連コラム:【司法試験】論文・答案の正しい書き方とは?法的三段論法を身に着けよう!
インプットよりアウトプット重視
2つ目は、インプットよりもアウトプットを重視することです。
前述のとおり、論文式試験においては、法的三段論法に従い答案を書く必要があるため、まずは規範を理解し、暗記することが重要になります。
しかしながら、司法試験・予備試験において学習すべき規範の量は膨大であり、これらのインプットに時間を割きすぎるとなかなか答案を書く練習をすることができません。
そこで、おすすめなのが、アウトプットを行う中で、規範などを理解・暗記する方法です。
先ほども述べたとおり、近年の論文式試験ではあてはめの力が特に重要視されるようになっているため、アウトプット重視の勉強方法であれば、あてはめの練習もしつつ、規範を理解・暗記することが可能です。
最初はなかなか論文を書くのが難しいかもしれませんが、実際に書いているうちにだんだんできるようになってくるものなので、とにかく早めにアウトプットを開始しましょう。
予備校の論文添削を徹底活用し答案の書き方を身につける
3つ目は、予備校の論文添削を徹底的に活用し答案の書き方を身につけることです。
論文式試験の勉強においては、アウトプットが重要であることを説明しましたが、実際に答案を書いても、それを自分ひとりで添削するのはなかなか難しいですよね。
そこで、おすすめなのが、予備校の論文添削を活用することです。
予備校の論文添削を活用することで、第三者の目から自分の答案がどのように評価されるのかを知ることができます。
また、自分ひとりでは気付けなかった弱点などにも気付くことができるはずです。
論文式試験の科目別の勉強法と対策
この章では、論文式試験の科目別の勉強法と対策方法について解説していきます。
民法
民法の論文式試験では、土地やお金などの財産をめぐって争っている人たちの法的な立場を説明したり、どちらの主張が認められるかを説明したりする問題が出題されます。
したがって、問題を解く際には、争っている人たちが、まず何を望んでいるか、その法的根拠は何か、相手の反論には何があるか、反論の法的根拠は何かといったことを考えることが必要です。
その際に重要なのは、民法の条文を基礎としてその要件と効果を考えることです。
条文学習はどの科目においても重要ですが、民法においては特にこの条文学習が重視されるべきといえるでしょう。
そのため、過去問の演習等に加え、条文を素読する勉強もおすすめです。
関連コラム:司法試験・予備試験に受かる民法の勉強法!短答と論文それぞれ解説
商法
商法の論文式試験では、会社法に関する事例をもとに、判例知識や条文知識を問う問題が出題されます。
会社法は条文が多く複雑であることもあって、商法の論文式試験においては、会社法の条文操作が特に重要になります。そのため、日頃の論文式試験対策においても、条文を引くことは特に意識しましょう。
また、商法の論文式試験においては、取締役の責任や株主総会の取消事由といった頻出論点が存在します。
これらの分野は過去の司法試験・予備試験においても繰り返し、出題されているため、特に重点的に対策を行う必要があります。
そのため、短文の事例問題集などを用いて繰り返し練習し、これらの処理手順をマスターするのがおすすめです。
関連コラム:司法試験・予備試験に受かる商法の勉強法!短答と論文それぞれ解説
民事訴訟法
民事訴訟法の論文式試験では、弁論主義や処分権主義、既判力及び複雑訴訟などについての深い理解が問われる問題が出題されます。
短答式試験と異なり、細かい訴訟手続きなどの細かい知識が問われることは少ないのですが、代わりに深い知識や理解が問われることになるため、これに合わせた勉強を行う必要があります。
そのため、まずは、基本的な概念についての趣旨や定義の理解・暗記を徹底するようにしましょう。
民事訴訟法の論文式試験においては、単なる判例の理解や暗記のみでは対応することができない発展的な問題が出題されることが多々あります。
しかしながら、このような問題であっても、基本的な概念についての趣旨や定義をしっかりと理解していれば、なんとか太刀打ちすることができます。
そのため、まずはこれらの理解・暗記を徹底したうえで、過去問演習等により答案練習を重ねるのがおすすめです。
関連コラム:司法試験・予備試験に受かる民事訴訟法の勉強法!短答と論文それぞれ解説
憲法
憲法の論文式試験には、①主張反論型、②リーガルオピニオン型の2つの出題形式があります。
①の主張反論型とは、一方当事者の立場に立って主張を論じ、そのあと、他方当事者からの反論を想定しつつ、私見を述べるという出題形式です。
一方、②のリーガルオピニオン型とは、反論を交えつつ法律家の立場で私見を論じるという出題形式です。
出題形式は異なるものの、いずれの形式でも、問題となる法令の合憲性を論じること、私見に対する反論を論じることが求められています。
このように、憲法の論文式試験ではある程度出題形式が決まっているため、まずは答案の型を抑えることが重要です。
基本的には、保障の有無→制約の有無→正当化の順に検討していくことになります。
また、憲法の論文式試験の問題においては、参考とすべき判例に言及するよう指示がある場合も多いため、判例集等を用いた判例学習が特に有用だといえます。
関連コラム:司法試験・予備試験に受かる憲法の勉強法!短答と論文それぞれ解説
行政法
行政法の論文式試験では、ある事例をもとにそれに関する個別法を解釈し、訴訟要件や実体法上の要件について検討する問題が出題されます。
訴訟要件については、ほぼ毎年のように出題されており、処分性・原告適格・訴えの利益のいずれか(あるいは複数)が出題されています。
そのため、特に処分性・原告適格・訴えの利益の3つの分野については特に重点的に対策を行うことが必要です。
これらの分野には、いわゆる答案の型のようなものが存在しているため、それらの型を抑えることが、非常に重要になります。
また、行政法においては、出題趣旨や採点実感の汎用性が高く、それらを読み込むことも試験対策に直結します。
関連コラム:司法試験・予備試験に受かる行政法の勉強法!短答と論文それぞれ解説
刑法
刑法の論文式試験では、事例に基づき、一人あるいは複数人について、その罪責を検討する問題が出題されます。
また、近年では、特定の論点について、複数の学説を比較するような問題が出題されることも多いです。
罪責の検討においては、まずは答案の型を身に付けることが重要です。
刑法の答案では、基本的に、構成要件該当性→違法性→有責性の順で検討することになるため、問題演習を通じてこの型をマスターしましょう。
答案の型を身に付けた後は、構成要件や条文の文言の定義などをしっかりと暗記し、それに問題文中の事実をあてはめる練習を行う必要があります。
また、学説問題に対応するためには、基本書やテキストなどを読んで、判例・通説以外の学説についても理解を深めることが重要です。
関連コラム:司法試験・予備試験に受かる刑法の勉強法!短答と論文それぞれ解説
刑事訴訟法
刑事訴訟法においては、事例をもとに捜査や公判手続の違法性・問題点等を論じる問題が出題されます。また、刑法と同様、複数の学説を比較させる問題が出題されることもあります。
刑事訴訟法においては、歴史的に見ても、判例が重要な役割を担ってきました。そのため、刑事訴訟法の論文対策においても判例学習は欠かせません。
問題によっては、判例の射程を意識した論述が必要になるものもあるため、日頃から判例集を読み込み、その考え方や射程を理解することを心がけましょう。
また、他の科目と同様、出題趣旨や採点実感を読んだり、繰り返し過去問を解いたりすることも重要です。
関連コラム:司法試験・予備試験に受かる刑事訴訟法の勉強法!短答と論文それぞれ解説
法律実務基礎科目
法律実務基礎科目は、民事実務基礎と刑事実務基礎の2つに分かれています。
民事
民事実務基礎では、主に、要件事実に関する問題、事実認定問題、法曹倫理問題、民事訴訟手続や執行・保全に関する問題が出題されます。
基本的には、どの分野に関しても、過去問を繰り返し解くことが一番重要です。
民事実務基礎は他の法律科目と比べると出題範囲が狭く、過去問と似たような問題が再度出題されることも多いため、過去問演習が最良の対策だといえるでしょう。
もっとも、要件事実に関しては、過去問だけでは対応できない可能性があるため、要件事実に特化したテキストや参考書を一読することをおすすめします。
刑事
刑事実務基礎では、主に、身柄拘束に関する問題、事実認定問題、法曹倫理問題、刑事訴訟手続や証拠法に関する問題が出題されます。
刑事実務基礎も、民事実務基礎と同様、基本的には過去問を繰り返し解くことが最も有用な対策方法です。
また、刑事実務基礎においては、刑法や刑事訴訟法の基礎知識について問われることもあるため、刑法や刑事訴訟法の勉強が、刑事実務基礎の対策にも直結します。
関連コラム:予備試験に受かる民事・刑事実務基礎の勉強法!
論文式試験の受験直前にやっておくべき対策
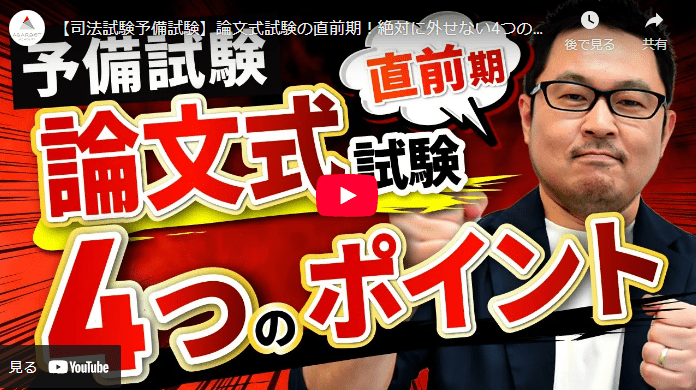
この章では、論文式試験の受験直前にやっておくべき対策4つについて下記を解説します。
- 短文事例問題集と過去問の演習見直し
- 実務基礎のインプット
- 公開模試の受験に目的を持つ!
- 体調管理
短文事例問題集と過去問の演習見直し
1つ目は、短文事例問題集と過去問の演習見直しです。
直前期にやってしまいがちな失敗として、自分の知識不足ばかりに目が行ってしまい、新しいテキストや問題集に手を広げてしまうということが挙げられます。
もっとも、論文式試験において合否を分けるのは、直前期に新しく入れた知識ではなく、これまで培って反復してきた知識を本番できちんと発揮できるかどうかです。
したがって、直前期には新たな知識を入れようとするのではなく、これまでやってきた短文事例問題集と過去問の演習を徹底的に見直すことが非常に重要になります。
この際、問題のポイントなどをテキストやノートに一元化しておくと、試験直前でも復習しやすいのでおすすめです。
実務基礎のインプット
2つ目は、実務基礎のインプットです。
実務基礎科目は、多くの受験生がなかなかそこまで手が回らないということもあり、相対評価の予備試験においては、勉強すればするほど点数が伸びやすい科目です。
そのため、本番直前まで諦めずに実務基礎のインプットを行うことが重要です。
また、実務基礎科目は、出題範囲が狭く、過去問と類似の問題が繰り返し出題されているため、比較的短期間でも点数を伸ばすことが可能です。
公開模試の受験に目的を持つ!
3つ目は、公開模試の受験に目的を持つことです。
予備試験の公開模試は、基本的に本番と同様丸2日かけて行なわれることが多いのですが、わざわざ時間をかけて模試を受験する以上は、目的意識を持つことが重要です。
公開模試の目的としては、大きく、本番のシュミレーションや時間配分の確認といったことが挙げられます。
一方で、公開模試を出題予想に特化して利用することはおすすめできません。
出題予想に意識がいくと、これまでやってきた短文事例問題集や過去問演習の復習が疎かになりがちだからです。
そのため、出題予想はあくまで副次的な目的として位置づけるようにしましょう。
体調管理
4つ目は体調管理です。
体調管理については、フィジカル面とメンタル面の両方に気を配るようにしましょう。
フィジカル面については、睡眠時間の確保が特に重要です。
直前期はつい睡眠時間を削って勉強をしてしまうこともあるかもしれませんが、本番で最大限のパフォーマンスを発揮するためには、しっかりと睡眠をとるようにしましょう。
また、メンタル面については、「もう間に合わない」「あれもやらないと」などとマイナス思考に陥ってしまいがちですが、試験対策を100%に出来た合格者は存在しません。
そのため、日々の「できた」を積み重ねることで、自信に繋げるようにしましょう。
まとめ
本コラムのポイントは以下の通りです。
- 司法試験・予備試験の論文式試験では、法的三段論法の理解が必須
- アウトプット重視の勉強法で、答案を書く練習を早めに開始する
- 予備校の論文添削を活用し、客観的なフィードバックを受ける
- 各科目ごとに答案の型を身につけ、条文や判例を活用する
- 直前期は新しい知識の詰め込みより、過去問や短文事例問題集の復習が重要
司法試験や予備試験の論文式試験では、論理的な答案を書く力が問われます。法的三段論法を軸に、実践的な勉強を重視し、答案作成力を鍛えましょう。
司法試験・予備試験の合格を
目指している方へ
- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を
無料体験してみませんか?

合格者の声の累計981名!
追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
予備試験合格で全額返金あり!


約13.5時間分の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る