法科大学院入試の難易度は?試験科目・倍率・合格実績から解説!【2025年最新版】

「司法試験に興味があるけど、法科大学院に入るのって難しいの?」
「法科大学院の入試内容について詳しく知りたい!」
司法試験に合格したい場合、予備試験ルートを除くと、まずは法科大学院(ロースクール)を修了して、司法試験の受験資格を得ることが必要です。
そのため、司法試験を目指す人の中には、法科大学院について上記のような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本コラムでは、法科大学院の入試難易度について、試験科目・入試倍率・司法試験合格実績から解説していきます。
法科大学院の合格を
目指している方へ
- 法科大学院に合格できるか
不安&勉強をどう進めて良いかわからない - 法科大学院の合格に特化した
効率的な勉強がしたい - 志望校別の過去問対策など、
自分に合った学習をしたい
アガルートの法科大学院講座を
体験してみませんか?
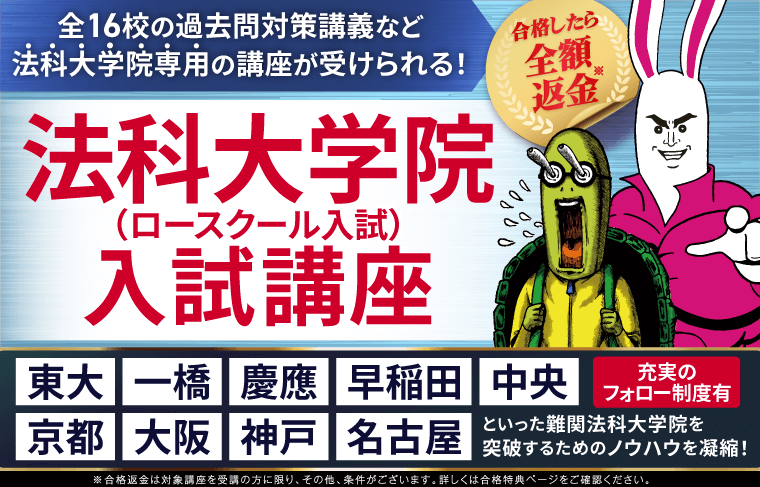
法律知識がゼロの方でも、1年で
難関法科大学院入試突破に必要な
学力が身につくカリキュラムあり!
最短合格できるカリキュラム&
講座で効率的に勉強できる!
法科大学院別過去問対策からステートメント作成まで!自分に合った講座が選択可能◎
【無料体験】約14時間10分の
動画講義をプレゼント中♪
(豪華特典付き)
\1分で簡単!無料/
▶まずは無料体験したい方はこちら
目次
【結論】法科大学院の難易度は総じて高い!入試内容に合わせしっかりとした対策を取るのがベスト
結論から言うと、近年の法科大学院の入試難易度は高くなってきているのが事実です。
理由としては下記の5つです。
- 制度改革により今後需要が高まる可能性があるため
- 司法試験も見据えた対策を入試の時点で行う必要があるため
- 法科大学院入試の中でも上位ローは受験者層のレベルが高いので難易度も高いため
- 受験する法科大学院によって対策方法が異なるため
- 法律の知識だけではなく論理的思考力も問われるため
以下で詳しく説明していきます。
制度改革により今後需要が高まる可能性があるため
まず、法科大学院の入試難易度が高まっている理由としては、近年の制度改革に伴う法曹コースの設置・在学中受験の開始により、以前よりも法曹を目指しやすくなったということが挙げられます。
法曹コースとは、法学部等を設置する大学が、法科大学院と連携して法科大学院の既修者コースの教育課程と一貫的に接続する体系的な教育課程を編成し、法曹志望者や法律の学修に関心を有する学生に対して、学部段階からより効果的な教育を行うものです。
法曹コースの授業は法科大学院未修者コース1年目の内容を代替するものであり、法曹コースを修了し、早期卒業をした者は、法科大学院未修者コースの2年目(既修者コース1年目)に進学し、法曹を目指すことが想定されています。
引用:法曹コースとは|文部科学省
そのため、法曹コースの場合、大学の法学部に3年間、法科大学院に2年間通い、在学中受験で司法試験に合格することができれば、最短5年間で司法修習に行くことが可能です。
法曹コース設置前は、予備試験合格者を除いては、司法修習まで7年弱かかるのが一般的であったため、今回の制度改革によって、かなり法曹を目指しやすくなったといえるでしょう。
そのため、法科大学院の人気も今後一層高まってくるものと考えられます。
司法試験も見据えた対策を入試の時点で行う必要があるため
また、法科大学院の入試内容は、一定程度の法律知識が問われることになるため、簡単ではありません。
そもそも法科大学院は、法曹を養成するための大学院であり、修了すると司法試験の受験資格を得ることができるため、入学者の多くは司法試験合格を目標に学習を行なっています。
そのため、法科大学院入試においても、司法試験受験のベースとなるような、法律知識が問われることが多いです。
たしかに、司法試験と比べれば、より基礎的な内容が出題されることにはなりますが、それでもやはり最難関と言われる司法試験を見据えたものである以上、簡単であるとはいえないでしょう。
したがって、法律の基礎的な内容については、法科大学院入試対策においてもしっかりと学習しておく必要があります。
法科大学院入試の中でも上位ローは受験者層のレベルが高いので難易度も高い
さらに、法科大学院入試の中でも、上位ローと言われる人気の高いロースクールを目指す場合には、より難易度が高くなります。
例えば、国立では、東京大学法科大学院や京都大学法科大学院などが、私立では、慶應義塾大学法科大学院や早稲田大学法科大学院などが上位ローと呼ばれており、人気の高いロースクールとなっています。
もっとも、これらのロースクールは受験者のレベルも高い場合が多く、ロースクール在学中に予備試験に合格する人も少なくありません。
そのため、ロースクール入試であっても、かなり高いレベルの法律知識が求められることになり、それに向けた対策が必要になります。
受験する法科大学院によって対策方法が異なる
法科大学院ごとに対策方法が異なるというのも、法科大学院入試の難しさの一つといえます。
法科大学院入試においては、2~3校を併願するのが一般的であるため、それぞれの入試傾向に合わせて試験対策を行う必要があります。
たしかに、基本的な出題範囲は、どの法科大学院入試でもほとんど差はありません。もっとも、法科大学院によっては、科目数が違ったり、試験時間が違ったりと、多少の違いはあります。
そのため、ある程度は入試の過去問などを解いて、入試形式に慣れる必要があり、複数の法科大学院を受験する場合は、大変だといえるでしょう。
法律の知識だけではなく論理的思考力も問われるため
法科大学院入試においては、法律知識だけでなく論理的思考力も問われることが多いです。
司法試験が論述式試験メインであることから、法科大学院入試においても、論述式試験を課せられる場合がほとんどです。
そのため、いくら法律知識をたくさん有していたとしても、それらを使って論理的な文章の形で答案を書くことができないと、法科大学院入試においては得点することができません。
そのため、法科大学院に合格するためには、法律知識の学習のみならず、文章として答案を書く練習も必要になります。
以上のように、法科大学院の入試難易度は高いため、志望する法科大学院の入試内容に合わせた対策を行うことが非常に重要です。
法科大学院入試の難易度について倍率・科目・司法試験合格実績から
この章では、法科大学院入試の難易度について、倍率・科目・司法試験合格実績から解説していきます。
入試倍率(合格率)
| 倍率順位 | 法科大学院名 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学 | 480 | 92 | 5.22 |
| 2 | 筑波大学 | 179 | 40 | 4.48 |
| 3 | 専修大学 | 194 | 44 | 4.41 |
| 4 | 日本大学 | 250 | 59 | 4.24 |
| 5 | 上智大学 | 138 | 41 | 3.37 |
| 6 | 東京都立大学 | 121 | 41 | 2.95 |
| 7 | 琉球大学 | 49 | 17 | 2.88 |
| 8 | 慶應義塾大学 | 1065 | 382 | 2.79 |
| 9 | 神戸大学 | 418 | 161 | 2.60 |
| 10 | 東京大学 | 626 | 244 | 2.57 |
| 11 | 早稲田大学 | 951 | 373 | 2.55 |
| 12 | 愛知大学 | 38 | 15 | 2.53 |
| 13 | 九州大学 | 141 | 58 | 2.43 |
| 14 | 関西大学 | 194 | 80 | 2.43 |
| 15 | 明治大学 | 357 | 148 | 2.41 |
| 16 | 学習院大学 | 90 | 38 | 2.37 |
| 17 | 京都大学 | 438 | 188 | 2.33 |
| 18 | 大阪大学 | 443 | 192 | 2.31 |
| 19 | 法政大学 | 147 | 64 | 2.30 |
| 20 | 千葉大学 | 124 | 54 | 2.30 |
| 21 | 関西学院大学 | 229 | 101 | 2.27 |
| 22 | 中央大学 | 1041 | 467 | 2.23 |
| 23 | 創価大学 | 80 | 36 | 2.22 |
| 24 | 金沢大学 | 51 | 23 | 2.22 |
| 25 | 名古屋大学 | 232 | 106 | 2.19 |
| 26 | 同志社大学 | 301 | 138 | 2.18 |
| 27 | 北海道大学 | 137 | 64 | 2.14 |
| 28 | 岡山大学 | 55 | 26 | 2.12 |
| 29 | 福岡大学 | 57 | 27 | 2.11 |
| 30 | 東北大学 | 223 | 106 | 2.10 |
| 31 | 立命館大学 | 308 | 148 | 2.08 |
| 32 | 広島大学 | 89 | 43 | 2.07 |
| 33 | 駒澤大学 | 83 | 43 | 1.93 |
| 34 | 南山大学 | 27 | 14 | 1.93 |
| 35 | 大阪公立大学 | 75 | 44 | 1.70 |
令和4年度の法科大学院の入試倍率ランキングは、上の表のとおりです。
入試倍率が一番高かったのは一橋大学法科大学院で、その倍率は5.22倍となっています。
それ以外の法科大学院でも、ほとんどが倍率2倍を超えており、やはりそれなりに難しいといえるでしょう。
もっとも、このランキングは、未修コースと既修コースを合計したものになっているため、自分の志望するコースの倍率については、別途ホームページなどで確認しておく必要があります。
試験科目数
法科大学院入試の試験科目については、基本的に、司法試験と同様、憲法・行政法・民法・商法・民訴法・刑法・刑訴法の7科目が出題されることが多いです。
東京大学法科大学院や京都大学法科大学院などのロースクールでは、上記の7科目が出題範囲となっています。
もっとも、ロースクールによっては、一部の科目が試験範囲から除外される場合もあります。
例えば、慶應義塾大学法科大学院や早稲田大学法科大学院、一橋大学法科大学院などでは、行政法を除いた6科目が出題範囲です。
また、同志社大学法科大学院では、行政法・商法受験型と、民訴法・刑訴法受験型が用意されており、受験者はどちらかの方式を選択して受験することが可能です(参照:入学試験要項(2024年度))。
このように、法科大学院によって試験科目が異なるため、自分の志望する法科大学院のホームページなどであらかじめ確認しておくようにしましょう。
どのロースクールであっても、基礎的な事項が問われる点は共通しているものの、やはり試験科目数の多いロースクールは、その分必要な対策が増えるため、難易度が高いといえるでしょう。
司法試験の合格実績
また、司法試験の合格実績も、法科大学院の難易度を測る上で重要な指標といえるでしょう。
法科大学院入試の受験者は、基本的に司法試験合格を目標にしているため、やはり司法試験合格実績の高い法科大学院は受験生からも人気があり、難易度も高い傾向にあります。
令和4年度司法試験における、法科大学院ごとの合格率ランキングにおいては、1位が京都大学、2位が東京大学、3位が一橋大学となっており、これらのロースクールは非常に学生のレベルも高く、入学難易度の高いロースクールとなっています。
このように、司法試験の合格実績とロースクールの難易度との間には相関関係があるため、司法試験合格実績も、法科大学院の難易度を測る上では重要な指標となります。
法科大学院ごとの司法試験合格率ランキングについては、以下の関連コラムも参照してみてください。
参考コラム:【最新】法科大学院の合格率ランキング!おすすめは?
まとめ
このコラムでは、法科大学院の入試難易度について、入試倍率・試験科目・司法試験合格実績の面から解説してきました。
やはり、司法試験合格を目指すための大学院ということもあり、ロースクールの入試はそれなりに難易度が高いということが分かりましたね。
もっとも、そのようなロースクールであっても、事前にしっかりと入試対策を行なえば、心配する必要はありません。
アガルートでは法科大学院入試(ロースクール入試)専願カリキュラムを用意しています。
本カリキュラムは、1年間の学習で難関ロースクール入試を突破することを目的として設計されています。法律の基礎知識から、論文試験問題対策まで、難関ロースクール突破に必要な学習をすることができます。
受講相談も用意しているので、ロースクールに入りたいが、どのように勉強を進めればよいかわからないという方は、ぜひ一度アガルートにご相談ください。
法科大学院の合格を
目指している方へ
- 法科大学院に合格できるか
不安&勉強をどう進めて良いかわからない - 法科大学院の合格に特化した
効率的な勉強がしたい - 志望校別の過去問対策など、
自分に合った学習をしたい
アガルートの法科大学院講座を
体験してみませんか?
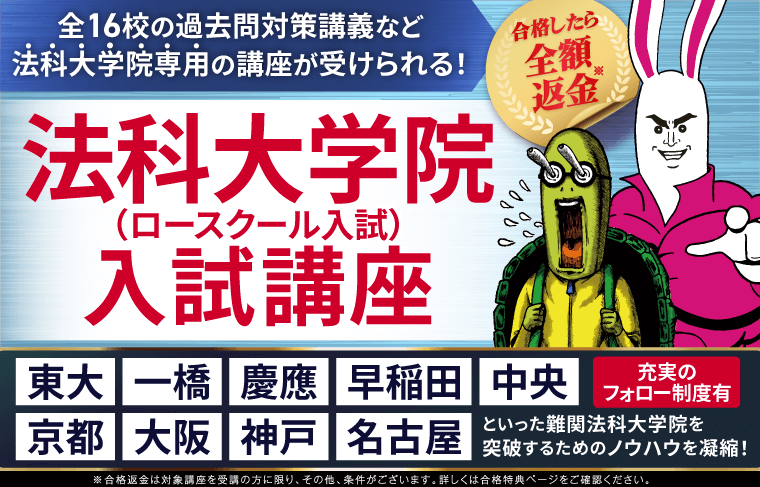
法律知識がゼロの方でも、1年で
難関法科大学院入試突破に必要な
学力が身につくカリキュラムあり!
最短合格できるカリキュラム&
講座で効率的に勉強できる!
法科大学院別過去問対策からステートメント作成まで!自分に合った講座が選択可能◎
【無料体験】約14時間10分の
動画講義をプレゼント中♪
(豪華特典付き)
専願カリキュラムの講座を見る
まずは無料体験したい方はこちら


約13.5時間の動画講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記!
司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!
司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック
合格の近道!司法試験のテクニック動画(約40分)
『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)
割引クーポンやsale情報が届く
\1分で簡単!無料/
▶資料請求して特典を受け取る